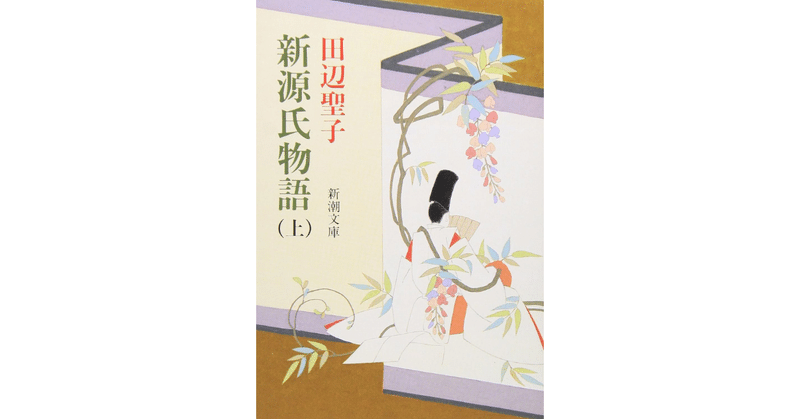
情操教育としての「源氏物語」
『新源氏物語(上) 』田辺聖子(新潮文庫)
現代のヒーローとして甦った“光る君”。平安の宮廷で華麗に繰り広げられた光源氏の愛と葛藤の物語を、新鮮な感覚で“現代”のよみものとして描いた大ロマン長編―比類ない美貌と知性、そして高貴な身分を持つ源氏は、至福の愛を求めて、許されぬ恋、苦しい恋を重ねる…。上巻には、「眠られぬ夏の夜の空蝉の巻」より「佗びぬればはかなき恋に澪標の巻」までを収める
。
『源氏物語』は以前読んでいたので記憶を呼び覚ます読書。最初に読んだときよりも『源氏物語』に出てくる女たちの特徴に惹かれててゆく。田辺聖子はそのへんの書き方が上手いのかもしれない。
「夕顔」はこんなに悲劇のヒロインだったのかと改めて関心したり、紫の君は源氏が須磨に行っている間に大人の女性になったとか(北の方としての使命を果たす)、それにしても須磨に行くまでの光源氏のやりたい放題なのは女は欲望を満たすものとしか考えていないのだ。その挫折が藤壺だった。藤壺が理想の女としてただ一人女神として君臨す。
田辺聖子『新源氏物語』は桐壷が無くて「空蝉」から始まる。光源氏の最初の遍歴は、失敗談を見せてから「帚木」になっていく、そこで「雨夜の品定め」という流れになっている。そこで先輩ナンパ師たちの成功談を聞くのだが、田辺聖子はそのへんの書き方が上手いのかもしれない。
最初の左馬頭(身分が低い)女の話(下品な感じがする)、次が頭中将(雅な恋の話)で、途中で加わる紀伊守が空蝉の夫の子供で、その夫が伊予助で光源氏の侍従、さらに空蝉の弟小君も登場して、このへんは注意深く読まないと混乱する。わざと混乱させるように書いているのか?
光源氏は藤壺という契りたい女性がいるので、その他の女は藤壺との欲望を満たす為の代役にしかならない。多くの女と交わることがこの時代勲章なのか?そこは面倒を見るということもあるのだが、若いうちは女はアクセサリーのようなものなのかもしれない。花の名前がそのアクセサリーのような気がする(花ではなく空蝉のような人もいるけど)。
そうして夕顔との逢瀬がある。
「夕顔」はこんなに悲劇のヒロインだったのかと改めて関心したり、館のホラーチックな話は、まだ六条御息所の物の怪ではないけど、夕顔のヒロインの話は緊迫感のある話でこの話だけでもいいと思った。源氏は夕顔との失敗談でかなり学ぶことがあったのだと思う。そういう失敗談は若さゆえで、みんな若いのだ。今だったら渋谷あたりでたむろしている十代の御曹司か有名タレントかというところだろう。その光源氏がハメを外して取り返しのつかないことになるけど、付き人が優秀でスキャンダルの始末をする。惟光は源氏の付き人ですけど優秀なマネージャーのような感じ。また「夕顔」から派生していく物語の伏線が控えている。そういう細部にも二回目になると気が付き、読み返すほど面白い物語なのだ。
紫の君は最初はねんねで、幼女を連れてきてしまった源氏は犯罪者のようで、最初の関係も痛ましい出来事とし、紫式部は丁寧に描いている。その紫の上が須磨に行っている間に大人の女性になっていく(北の方としての使命を果たす)。そういう女性の成長物語としても読める。須磨で光源氏は明石の姫君に子供を産ませ、京に連れて帰る。ここは明石の君も紫の上も両方耐え難い事件だが、それに耐えてあの時代の理想の女になってゆく。
その反対なのが、葵と六条御息所の争いで、まざまざと女の嫌な部分を見せている。その後に光源氏が業平のように都落ちして、須磨は黄泉がえりの話に通じていると思う。そこが光源氏の神々しい力としての神話になっていくので、それまでのやんちゃな餓鬼とは違って、女たちの面倒見がいいマメ男(せっせと手紙やら和歌を送る)になる。その変化が須磨(明石)の黄泉がえりの話になっている。
光源氏の女としての理想は藤壺でそれは禁じられた恋だった。その代わりの女を求めるのだが、理想の女ではない女にもそれぞれ良いところがあると発見していく。そこが『源氏物語』の多様性の女たちの物語になっている。
それは女官として中宮の教育係に抜擢された紫式部の書いた『源氏物語』がそれ以後の女の教科書として読まれ続けたのではないかと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
