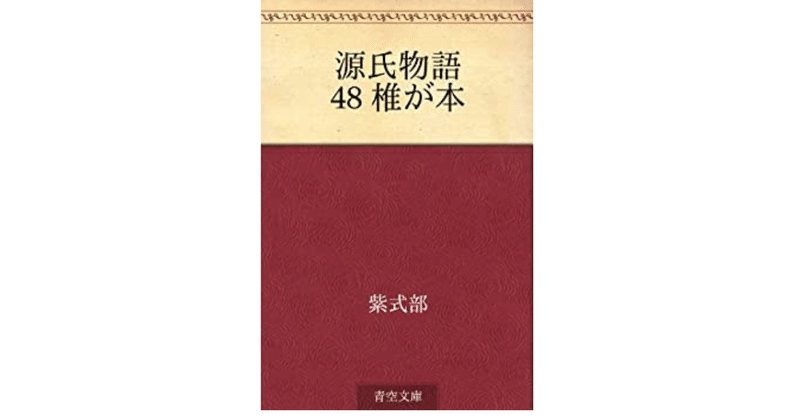
薫は「燃あがる緑の木」だった
『源氏物語 48 椎が本』(翻訳)与謝野晶子( Kindle版)
平安時代中期に紫式部によって創作された最古の長編小説を、与謝野晶子が生き生きと大胆に現代語に訳した決定版。全54帖の第46帖「椎が本」。薫から宇治に住む美しい姉妹の話を聞いた匂宮は興味を持つ。余命が少ないことを感じた八の宮は姫君達に軽率な結婚をするなと諭し、薫に後見を頼んで山寺で亡くなった。薫は大君を訪れ、匂宮が中の君との縁談を望んでいる事、そして大君は私が京に迎えたいと打ち明けるが、取り合わない大君だった。平安時代中期に紫式部によって創作された最古の長編古典小説を、与謝野晶子が生き生きと大胆に現代語に訳した決定版。
「椎本(しいがもと)」の題名の由来は、薫(中納言)が八の宮を偲んで詠った歌から来ている。
立ち寄らむ陰とたのみし椎が本むなしき床になりにけるかな
椎の木は大木になるので、その根本で休みながら回想するのだが、これは八の宮だけではなく、「柏木」も回想したものと思われる。『源氏物語』は姫たちは花の名前が多いが、男君は木の名前なのかと思ったが、「柏木」ぐらいしか思いつかないが「薫」が「柏木」の姿を受け継いだ「椎本」ではないかと考えた。この情景どこかで想い出すな、と思ったら今同時進行中の大江健三郎の作品だった。四国の森の大木の根本の窪みに身を潜めて瞑想するのだ。その木はナラかクヌギだと思ったが、椎の木でもいいのかなと思った。
大江健三郎で思い出したことは、もう一つ人物再登場法でこれはバルザックやフォークナーの影響があると考えられているが、『源氏物語』も人物再登場法の物語であると思う。大江健三郎は『源氏物語』を読み込んでいたことを告白していた(『新しい文学のために』)。それは『源氏物語』を要約しても意味がなく、その物語の中に入って一つ一つの言葉の意味を辿っていくことによって物語が開かれると言っているのだ。それは大江健三郎が後年の作品で詩を読む時に用いられる方法だ。イェーツにしても、ブレイクにしても一つの言葉のイメージから詩的言語の言の葉を開示していく。その年輪(枯れた木が再び再生する樹木というイメージ)を重ねて樹木が成長するように、大江健三郎の樹木としての文学は四季の巡回を物語的語りながら成長していく『源氏物語』のイメージと重なる。
「異化」という方法は、そうした言葉を探っていき新たな言葉を引き出して繋げていくことだとすれば、『源氏物語』から世界文学へという「異化作用」がなされてもいいのではないかと思う。
それと『源氏物語』に出てくる信仰の形が、例えばここでは初瀬詣りとして、物語に影響を与える。それは末法思想もあるが、その先に浄土信仰があったことが伺えるだろう。それこそ大江健三郎が描きたかった『燃あがる緑の木』の祈りの形でもあるかもしれないのだ。ここで燃あがるのは薫の欲望だが『源氏物語』を世界文学として開いてみるのも面白いのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
