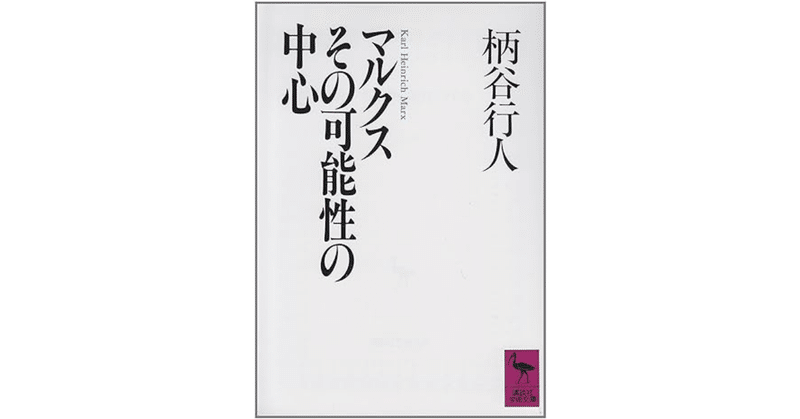
マルクスから漱石へその可能性の中心
『マルクスその可能性の中心』柄谷行人 (講談社学術文庫)
マルクス=ヘーゲル主義の終焉において、われわれは始めてマルクスを読みうる時代に入った。マルクスは、まさにヘーゲルのいう「歴史の終焉」のあとの思想家だったからだ。マルクスの「可能性の中心」を支配的な中心を解体する差異性・外部性に見出す本痛は、今後読まれるべきマルクスを先駆的に提示している。価値形態論において「まだ思惟されていないもの」を読み思想界に新たな地平を拓いた衝撃の書。亀井勝一郎賞受賞。
目次
1 マルクスその可能性の中心
2 歴史について―武田泰淳
3 階級について―漱石試論1
4 文学について―漱石試論2
なんでこんな本を読もうと思ったのか?マルクス『ブリュゲール18日』の解説がわかりやすいと思ったのだ。この本もあとがきと解説を読めばいいのではないか?と身も蓋もないことを言ってしまう。
柄谷の思索はポストモダンの構造主義のようで、本人は構造主義ではないというのはポスト・ポストモダンということで、ヴァレリー=小林秀雄が来るのである。それは哲学ではプラトンの問題から始まっているので、そこにニーチェの批評があるのだと思う。等価価値というのは言葉だけのもので、それがヘーゲルの弁証法の誤りとかそんなところか?とりあえずマルクスはヘーゲルから出発したのでその思考方法もヘーゲルのシステムから出発せねばならないのだが、そうした言葉のまやかし、それは人工に作られたもので自然ではないというような。ここではズバリ言葉のことを言っているのだった。
言葉と自然状態にある人間の乖離かな。神や英雄を好むとか、そこで言葉の平等性はそもそも崩れるのだ。ニーチェが「すべての概念は、等しからずものを等価にする」と言っていていて、概念が哲学=言葉という感じで、それは自然ではないということだった。
資本論の等価価値というのもまやかしということなのだが、システム論なのかと思った。言語システムが西欧の一神教に委ねられていくというような。だからニーチェが出てくるのだろう。近代はマルクスの言う革命ではなく保守主義的なナポレオン登場の権威主義的・反動的な運動が起きたのか?ということ。
マルクスの等価価値を言葉の問題として、そこから始まるヘーゲルの弁証法の詭弁を言っているのだが、哲学というものはキリスト教的一神教から始まっているのでそこを崩してしまうと論理が破綻していく。せいぜいネオプラトン主義(グノーシス)を夢見るだけなのかもしれない。貨幣の平等性というのはありえず階級闘争の中で一つの止揚させると神の問題が出てくるということなのか?そこに神に委ねてしまう奴隷根性(ニーチェ)があるというような。
文芸批評も日本の近代という問いで漢文という中国の言葉でもない日本的翻訳の問題として問うたもの。武田泰淳が読む歴史本が司馬遷『史記』でありそれは中国語で読むのではなく日本の翻訳として文字が中心である書き下し文という文字言葉なのである。そこに中国語の声の文化は失われていく。武田泰淳が中国の研究室で日本と中国の橋渡しをしようと思っていたのだが、それは中国人の声を無視した司馬遷『史記』から得た歴史だったのだ。
漱石も英語を日本語化された漢文文化のように対処できると思っていたのだが、それは三角関係のような、日本、西欧、漢文化(アジア主義)という中でストレスからヒステリー問題になっていくのだが、そのヒステリー問題を直視しないという。自然主義文学との優位性の問題として、有島武郎『或る女』のほうがよく捉えているとうのは、そういうヒステリーのあり方だろうか?そこはフロイントを援用する精神分析批評のように感じた。
漱石の中にある「英文学」と「漢文学」と「日本」という立場に於いて選んだのが「漢文学」の日本精神というものだった。それは「漢文学」の日本回帰という声よりも文字だけの世界だった。そこに「英文学」の心理描写に惹かれていきながら拒絶せねばならないという個人主義の内面の問題があった。それは日本の近代思想と重ねっていくのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
