
シン・短歌レッス43
江ノ電。鉄オタではないのでスマホ写真だが俳句を作れる。本当か?鉄オタの俳人っているのか?その人には負けるだろうが。鉄道への愛が足りないと思う。今日の一句。
江ノ電を待つ鉄オタに春の風
月並みすぎるか?季語だけなんだよな。考える余地があるのは。「新緑」の方がいいかも。
新緑の江ノ電待つ春の風
どうしても春の風から抜けられない。今日は風が強い日だったから。
『源氏物語』和歌
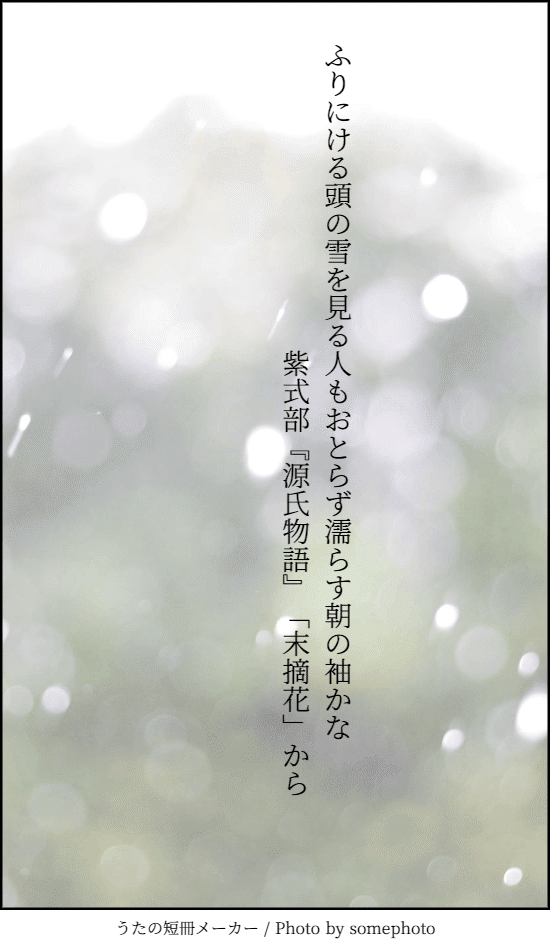
掲載歌は、光源氏が末摘花との後朝の朝に門番の老人に同情した歌であるという。これも本歌取りなのだろう。
春の日の光のあたる我なれどかしらの雪となるぞわびしき 文屋康秀
を連想させる。袖を濡らしたのは別の意味なのだが。
『源氏物語の和歌』十首
今日も高野晴代『源氏物語の和歌』から。
(藤壺の中宮)
唐人の袖ふることは遠けれど立ち居につけてあはれとは見き
光源氏が「青海波」を舞う有名な帖で、その後に妊娠した中宮を見舞うシーンの後に光源氏が贈った歌の返歌。
(光源氏)
物思ふに立ち舞いべくもあらぬ身の袖うち振りし心知りきや
(朧月夜)
憂き身世にやがて消えなば尋ねても草の原をば問はじとや思ふ
藤壺の中宮に会いたいと思って尋ねたが朧月夜と出会い関係を持った後の名前を尋ねたが名乗らずに歌を返した。「草の原」は墓場ということを塚本邦雄が書いていたっけ。源氏の返歌。
(光源氏)
いづれぞと露の宿りを分かむ間に小篠(こざさ)が原に風もこそ吹け
右大臣の六の君であることが後から知れて光源氏の都落ちの原因となるのであった。
(六条御息所)
袖ぬるる泥(こひぢ)とかつは知りながら下(お)り立つ田子のみづからぞ憂き
賀茂祭(葵祭)での車争いで有名な帖です。その怨念から六条御息所の物の怪が葵に祟るのですが、光源氏は六条御息所を訪ねる。その時の光源氏への怨念の歌というより自分の境遇に自己嫌悪する歌です。「田子」は田んぼを耕す農夫。そして古歌を引用する。
くやしくぞ汲みそめける浅ければ袖のみ濡るる山の井の水
これは浅い水を汲もうとして袖が濡れるのを恋愛に譬えた恋歌です。六条御息所の教養の高さも伺われます。その歌の光源氏の返歌は、
(光源氏)
浅みにや人は下り立つわが方は身もそばつまで深き泥(こひじ)を
この返しは、自己中と言われても仕方がない。自分の方は泥水に浸かるような恋の深みにハマっているというのだから。光源氏は自己中だからこそ女を変えて恋するのだから、もう何も言えない。物の怪になるしかないのかもしれない。
でも葵の上もとんだとばっちりを受けたもので光源氏にこの頃は愛されていない。ただ光源氏の子供を身籠っている。そして後年はその六序御息所の屋敷を桃源郷のような四季の館に変えてしまうのだ。バブルの地上げ屋みたいなこともする。
(六条御息所)
神垣はしるしの杉もなきものをいかに紛(まが)へて折れる榊ぞ
六条御息所は光源氏と別れる決心をして娘(伊勢の斎宮となる)と共に伊勢へ去っていこうとする。光源氏が六条御息所の処に来て榊を投げるのは、古歌(『後撰集』と『伊勢物語』)の歌をかけている。謎歌のようなものですか?榊は年中緑で変わらぬ木で、
ちはやぶる神垣山の榊葉は時雨に色も変わらざりき 詠み人知らず
『伊勢物語』では
ちはやぶる神の斎垣も超えぬべし大宮人の見まくほしきに
その引き歌の榊投入で歌で返すのだから、六条御息所とはそういう文学的なやり取りが面白かったのかもしれない。六条御息所の和歌も『古今集』の「しるし杉」を踏まえているのだという。もう言葉の文学ゲームですね。
わが庵(いほ)は三輪の山もと恋しく訪(とぶら)ひ来ませ杉立てる門 詠み人知らず
光源氏の六条御息所への返歌も『拾遺集』の和歌を踏まえていた。
(光源氏)
少女子(をとめご)が辺りと思へば榊葉の香を懐かしみ留めこそ折れ
これはちょっとヤバい歌で少女子(をとめご)は伊勢の斎宮(秋好中宮)でその娘を折ろうとしているのです。それは、すでに紫の上で経験済みだった。
(光源氏)
橘の香をなつかしみほととぎす花散る里をたづねてぞ訪(と)ふ
前の帖と同じ頃の話で、『榊』では父の桐壺院の崩御と藤壺が出家してしまい光源氏は恋の相手を地方に求めるのです。これも桐壺院の女御(この人も光源氏の愛人)だった妹に手をだす。この歌はその女御に宛てたもので、まだこの時は姉目当てだったという。これに対して女御は光源氏の返歌する。
(女御)
人目なく荒れたる宿は橘の花こそ軒のつまとなりけれ
俳句レッスン
今日は正津勉『忘れられた俳人 河東碧梧桐』から十首。ほんとに忘れられたのか図書館にも手頃な本がないのだった。これは良書。
一息に三里はきたりせみのこえ
面白う聞けば蜩夕日かな
狼や炬燵火きつき旅の宿
行水を捨てゝ湖水のさゝ濁り
春寒し水田の上根なし雲
赤い椿白い椿と落ちにけり
白足袋にいと薄き紺のゆかりかな
痒かろう寒かろう人に会ひたかろう
能登へ渡るすずしき月の船路かな
夜に入りて蕃椒(とうがらし)煮る台処
松尾芭蕉の「せみのこえ」を感じさせる山歩きの句だが、それは芭蕉の静寂とは対照的にずんずん山奥に入るごとに蝉の合唱が響いてくるようでもある。山人なのかと思ってしまう。碧梧桐が定住の俳人虚子との違いは漂流のノマド性だったのだと思う。その脈が自由律の山頭火にも受け継がれてゆく。
次の二句は子規に認められた句。けっして子規の写生句とはいえずに子規も奇想だと評する。碧梧桐の俳号は、碧は真っ青、梧桐は青銅。青銅のようにまっすぐ真っ青という俳号だという。そのへんの豪快さ。
これも子規が「思想に於いて奇抜なる」と評している。すでに老成しているとも(わずか子規と出会って三年だった)
「根なし雲」にノマド性が出ている。田んぼを上から眺めている雲に思いを馳せるのだ。定住の俳人ではない漂白の俳人性が出ている。またそれが世間の評価のように「春寒し」なのだ。滝井孝作評。
元禄の続猿蓑の惟然(いぜん・芭蕉門下の俳人)の句「更け行くや水田の上の天の川」に似ているが惟然の句は凄艶(せいえん)。春寒しの句は少女のように美しい 滝井孝作
この頃子規に虚子と双璧と評されるのだがそれは絵画的写生句を見ていた。
白足袋の句は、「紺のゆかり」がもともとある模様なのか?青い花を踏みつけた色を現しているようにも思える。
「痒かろう」は入院した碧梧桐への見舞いの子規の句。ただ子規の思いとは違っていたのだと思う。また旅に出るのだから。それは碧梧桐の恋人を虚子に奪われたということだった。奪われたというより定住の人を彼女が選んだのだろう。
子規によって激烈なる感情から淡泊な俳句とされたがそれは一時的なことにしか過ぎなかった。
映画短歌
今日は『ザ・ホエール』から。
鯨魚(いさな)取り海や死にする山や死にする
これは「海は死にますか山はしにますか」の歌の元歌のようだ。これを参考に作ろう。
トリトンよ我はクジラ
浮上する
海は死にする山は死にする
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
