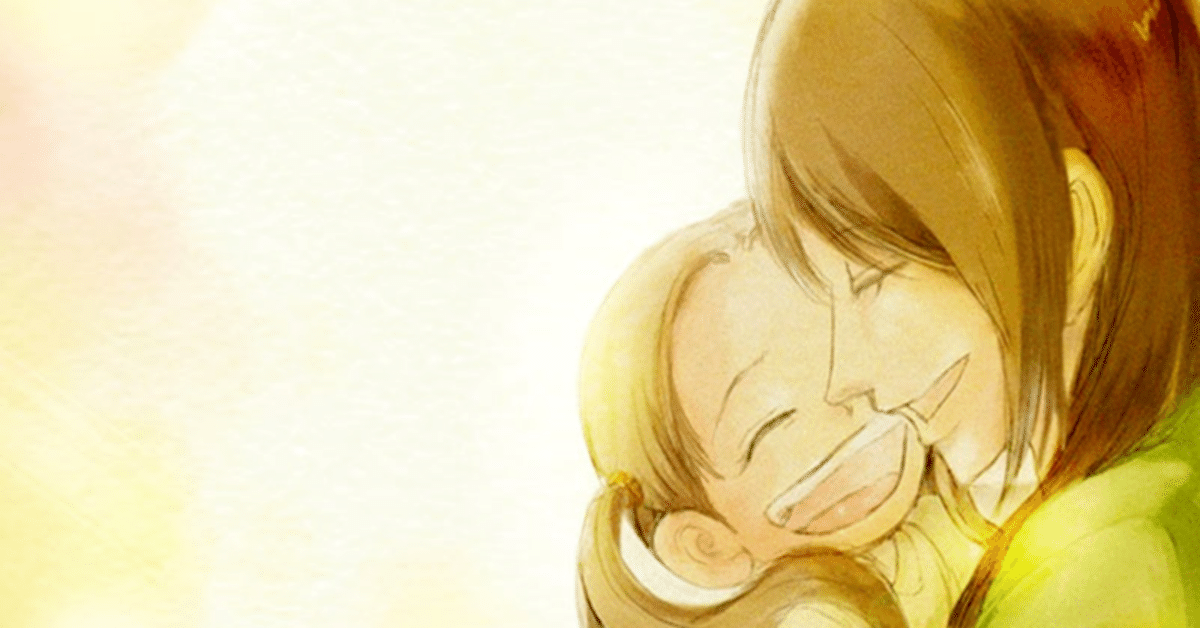
母が守ったもの 〔ショートストーリー〕
母が守ったもの
「あーーー疲れたぁぁーー」
ふーーっと長く息を吐いて湯に体を沈める。
体内に溜まって身体を重くしていた『疲労』が、ゆっくりと湯船の底に降りていく。
社会人になってまだ一ヶ月が経っていないなんて信じられない。なのに、こんなにも疲労を感じているだなんて。
「若いのに」
思わず、そう自分でつぶやいてしまう。
我が家の湯船はとても小さい。昔から思っていたけれど、今ではなおのこと。
私は身体を折りたたみ、ゆっくりと天井を見上げるように、顔だけをぽっかりとだして、後頭部から頭も湯に沈める。
我が家には、最後に湯に浸かる人は潜っても良いというルールがある。
と言っても、母と私の二人暮らしで、潜りたいのは私だけ。
私が考えた、マイルールだ。
私には母しかいない。この世でたった一人の大切な母。
母の愛に包まれていたから、父がいないことを嘆いたことはないが、不思議に思って尋ねたことはある。
母からの回答はいつも曖昧で、これと言った答えは未だに見つかっていない。
「まぁ、男と女のことだもの。色々あって然るべきよ」
湯船に浸かりながら、また独り、つぶやく。
お湯に両耳が浸かると、湯の中のくぐもった音がやすらぎをくれる。コポコポと気泡が連なり湯の中を移動していく音を聞きながら、ゆっくりと目を閉じる。
いつしかうっすら眠気に襲われ始めた頃、気泡の音はやがて心地よい雑音と、一定のリズムを刻むトクトクという音に変わっていた。
なんだかとても安心できる音。温かい、優しい誰かに守られているような。
母の顔が浮かんだ。
頭がふわふわする。身体の重さはすでに感じなくなった。それなのに瞼は重く、自力で開けることができない。そのとき、遠く、何かを隔てたところから、男の話し声を聞いた。
「おまえが望んだことなんだから勝手にしろ。おれは一切責任を取らない。」
不明瞭でも、わずかに聞き取れた。
何もかもおまえ一人でやれ。おそらく男がそう言い放った直後、強い衝撃が伝わった。と同時に、私は呼吸が苦しくなる。
私以外の “誰か” の、強い悲しみを感じる。
苦しい。そしてとても寂しい…。
目を開けたとき、私を覗きこむ母と目があった。
寝てないでしょうね〜?と心配しているような、面白がっているような母の表情。
「お風呂で寝たら溺れるよ〜」そう言って立ち去った母の後ろ姿を見た。
何だったんだろう、さっきは。夢だったのか。どちらにしろ、これまでもずっと母が私を守ってくれていたのは間違いない。今だって。
「お母さんを幸せにしよう」
声に力がこもる。
疲れはいつの間にか消えていて、母への想いと共に涙が溢れた。
【完】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
