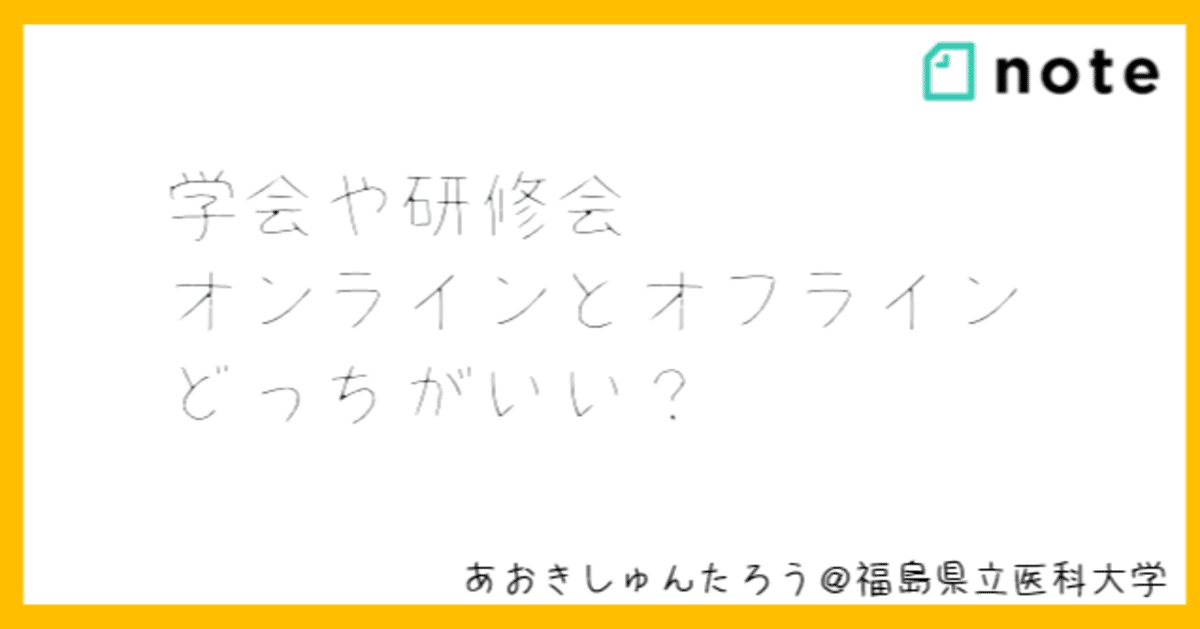
学会や研修会はオンラインとオフラインどっちがいい?
今年もコロナの影響は収まらず、学会や研修会は軒並みオンラインの開催になってます。オンラインの学会ももちろんいいのですが、オフラインの学会もやっぱり良いよなあと思ったりもします(早く収束して、オフラインの学会や研修会にも参加したいですね~)。
今年はオフラインの学会もオンラインの学会もどちらも参加させてもらいました。参加させてもらった雑感とともに、それぞれのどんなところが良いのか?について考えてみたいと思います。
オフラインは”参加感”が体験価値だったっぽい。
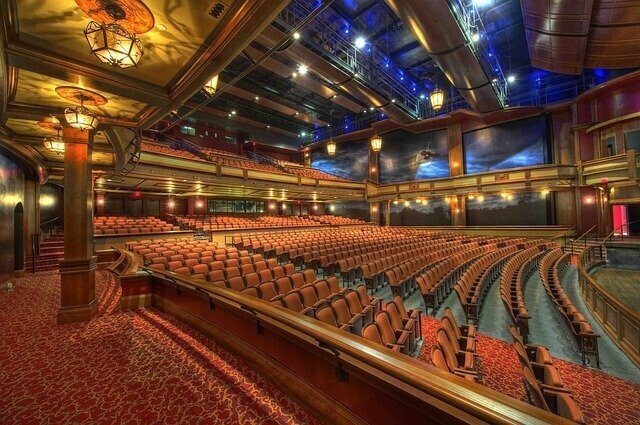
そもそも、学会やワークショップ会場に行って、国際会議場なんかのふかふかのソファに座って、著名な先生方のお話を大型のスクリーンで聴くこと自体にどうやら体験価値がありそうです。
人によるのでしょうが、映画も大型スクリーンで、大音量スピーカーで、ふかふかの椅子に座って、ポップコーン食べながら的なものに価値はありますよね。ホームシアターもいいですが、そもそもに映画館とホームシアターは別の体験です。
ミュージシャンのライブだって、家のテレビで見るのと、ライブ会場で見るのは全然異なるわけです。
オフラインで実施すること自体が、体験価値を生んでいて、いつもと違う体験をするってことがポジティブな体験になることがあるのでしょう。これが学習効果を促進したり、集中持続させていて、学会やワークショップにまた来たいなあという体験を生んでいるのかもしれません。
戦う相手がYouTubeやネットフリックスになってしまう。生涯学習として認識されるならいいが、その競合意識にはなかなかなれない。
オフラインは知り合いと話せる機能、新しい繋がりができる機能が強め

講演が終わった後に、講演者のもとに行列ができて、ご挨拶、お話ししたいというのが、学会ではよく見る光景でした。オフラインの学会ですとそれが容易にできるわけですが、オンラインだとなかなか難しいですね。
また学会は数日間で開催されるので宿泊が必要になるのですが、そうすると昔なじみの仲間でご飯を食べたりとか、お酒を飲んだりしてというのがよくある光景でした。そんななかで、新しいアイデアが出てきたり、次回の学会で出したい企画なんかが出てくるわけです。もちろん会場にいるときも、仲間とディスカッションしたりできる年に数回の貴重な機会だったりします。
オンラインでZOOMでもいいんじゃない?みたいな話もありますが、自分の体験としては、ZOOMでずっと話をしていた中で、対面で同じ人に会うと、おおリアルだ!と思って毎度感動します(笑)体験価値としては人と対面で会うことは強めなようです。
オンラインでも媒体によっては参加者間交流できるプラットフォームもありますが、現状では、主催者の意図の通りにしかグルーピングするのもなかなか難しいので、この人とお話ししたい!となってもなかなかお話しするのは難しいです。ここはオフラインにはなかなか勝てないですよね。
オンラインは情報格差を是正する

オンラインの学会やワークショップは、これから1つの選択肢として残り続けます。去年や今年は、はじめての経験だったということもあるので、運営が大変でしたが、ノウハウが積まれていくと、その大変さは薄らいでいくと思います。
参加者や実施者も、移動することがなくなるので、学習機会の地域格差や所得格差は減っていくのではないかと思います。この辺りはおおきいアドバンテージですよね。
仕事の合間とかでさっと参加するなんかもできるので、話が面白い先生の話を遠隔で聴けるというメリットも出てきそうです。個人的にはわたしが資料作って話すより、話が面白い先生に話してもらったほうがよっぽどいいなとか思っています。
各地域でおこなわれることで、その地方の宿泊業や飲食業、観光業にはプラスになりますので、地方創生の観点からは各地域での学会やワークショップは続けてもらいたいなと思いますが、同時にオンラインでの参加もできるようにとしてもらえるのが良いかなあと思います(運営は大変ですがね…)。
オンラインで”参加感”を増す工夫

正直に言うと、私は集中力がないので、シンポジウム90分聞く持久力がありません。なので、最初から視聴しないという選択をしがちです(ごめんなさい)。画面で見るなら、せっかくならコンテンツとして見たいものを見たいなあと思ってしまい、YouTubeとかNetflixのほうを見る時間に割いてしまいます。
オンラインで実施している以上、画面を見るという行動自体は、学会の動画を見るのも、YouTubeを見るのも同じなのではないかなと思います。そうすると、学会のほうに参加してもらうには、映像コンテンツとして面白くする工夫が今後必要になるのですが、これはなかなか難しいです。
私としては、オンラインでも”参加感”を増す工夫をする必要があるのではないかなと思います。YouTubeライブ配信を参考にしてみましょう。YouTubeライブ配信は、配信者と視聴者がチャットを介してやりとりをします。
学会でも、チャットを使うなどして、講演する人が即時的にチャットを拾っていって、視聴者とやり取りをすることで参加感が増すのではないかと思います(そもそもオフラインでも相互作用を生み出す工夫をしたいですが)。
あるいはメンチメーターを使うなどもあるかもしれません。皆さんの意見を眺めながら解説を加えていく仕組みなんかも、体験価値を生み出せる可能性がありそうです(メンチメーターはこちらの記事をご覧ください)。
ということで、オンラインもオフラインもどっちも良い面もあると思います。せっかくオンラインでの学会や研修が普及したので、これからもどちらの良さも使いながらやっていければいいなあと思います。
オンラインで研修を行う時の工夫などは、過去の記事でも書かせてもらってます。良かったらご覧になってください。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
筆者 あおきしゅんたろうは福島県立医科大学で大学教員をしています。大学では医療コミュニケーションについての医学教育を担当しており、臨床心理士・公認心理師として認知行動療法を専門に活動しています。この記事は、所属機関を代表する意見ではなく、あくまで僕自身の考えや研究エビデンスを基に書いています。
フォローやチャンネル登録してもらえたら泣いて喜びます!
Twitter @airibugfri note以外のあおき発信情報について更新してます。
Instagram @aokishuntaro あおきのメンタルヘルスの保ち方を紹介します(福島暮らしをたまーに紹介してます)。
YouTube ばっちこい心理学 心理学おたくの岩野とあおきがみなさんにわかりやすく心理学とメンタルヘルスについてのお話を伝えてます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
