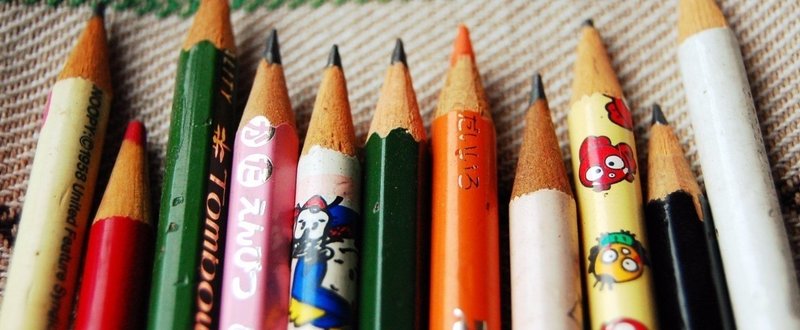
多様性のある世界の中身
今回は「多様性/ダイバーシティ(Diversity)」についてのちょっとしたお話。
0、
昨今よく耳にすることが多くなった。
割と、これからの社会が目指すべき理想めいた風に使われている気がする。
しかし、自分はどこかその使われ方に違和感をぬぐえない。
要は「色々なものを受け入れられるようになりましょう」ということなのだろうが、何かが足りてないと感じている。
ーーーーー
最近、多様性の価値を認めている企業の一つと言えるGoogleでこんな事件があった。
Googleの多様性を否定したエンジニア、即刻解雇される(GIZMODE 2017/8/9)
ものすごく簡単に説明すると、男女差別的文書を公表した社員を「きみ会社の和を乱しているから首ね」と即行で解雇してしまったというもの。
それに対して元社員は、「やっぱり俺を首にするとか、多様性なんて認めてないやんけww!」と辞めた後、堂々と顔まで晒して自分のやったことは正しかったと主張。
多様性を否定して解雇されたGoogle元社員「後悔はしていない」(GIZMODE 2017/8/14)
多分まだまだこの問題は続くと思われる。
1、
そんな中、下記のツイートに以前から自分が感じていたことと同じことが書いてあった。
追記※表示されなくなったので消えてしまったと思われる。
書いてあった文を要約すると、虫(ここではゴキブリ)も人も「生物としては同価値」だから、片一方を好きで、もう片方を嫌う人が多様性を主張しても説得力が無いよ?という意味。
多様とは、生きとし生けるものすべてがありのままの状態のことを指す。
それはとてもカオスな状態だ。
みんなが好き勝手わちゃわちゃやって、まぁ多様だからそれでもいいよねというのが多様性を受け入れるということの本質だろう。
ーーーーー
多様性を受け入れる考え方そのものには反対しないし、同質性を求めることも秩序ある社会にとって必要だと思う。
結局のところ、これは個人の価値観や生き方に関する問題である。
多様で無いことを訴えるものを受け入れることも、また多様性の受容に繋がると思う。
しかし実際な話、あなたは自分が嫌いな人間の存在を許容できるだろうか?
2、
とある小説の一部分で、後々いじめにつながるだろうと思ったケースがあったので例に出してみる。
ーーーーー
登場人物にAさんとB君がいる。
二人は同じ中学のクラスメートで、Aさんは明るくちょっとおしゃれに興味を持ちだした、クラスでも目立つ中心的存在。
対して、B君は暗く友達はおらず、目立たない存在である。
B君はいわゆるアスペルガーの傾向があり、一部の認知能力が高いものの、対人関係ではコミュニケーションが苦手としている、というふうに描かれている。
ーーーーー
物語の場面は、朝の登校してきた生徒が集まっている教室である。
Aさんが、ちょっとした目立ちたがりと冒険心から香水を付けて登校してきた。クラスメートはその匂いを嗅いで良い匂いだねと褒める。
Aさんはクラスの中心的存在なので、あっと言う間にクラス全体がAさんの香水やそれを付けてきたAさんを褒め出し、Aさんは凄いという空気が生まれ出した。
そこにB君が登校してくる。
B君は思ったことをすぐ口にしてしまう人なので、その香水の匂いを嗅いだ瞬間
「うわっ、臭ぇ!」と言葉を発する。
その声は教室に響き渡り、クラスの中に冷や水を掛けたような瞬間が訪れる。
ーーーーー
さてあなたはこの後どうするだろうか?
Aさんだったら、ショックを受けその後馬鹿にされたと怒るだろうか?
B君だったら、なぜクラスの雰囲気が冷え固まったのか理解できなくてとまどうかもしれない。
その他の周りの人間でも、Aさんに近い人なら怒ってB君を批判するだろうし、そんな仲良くない人なら「あら~やっちまったよ」とその後の推移を見守るかもしれない。
その時、どの立場を取っているかによって感じ方は異なるだろう。
ーーーーー
小説ではその後当然の如く、B君はいじめ→無視の展開へと続くが、
多様性を受け入れるということは、こういうケースを数多く経験して、どんなことが起こったとしても、それも普通だよなと考えを改めていくことでしか学べないと思う。
3、
じゃあ空気の読めない人間はそのままで、読める人間だけ我慢すればいいのだろうか?
それって読める人だけが損じゃないか!?
いや、そうではない。
そもそも、初めから自分のことが他者に100%受け入れられるわけではないと知っておくべきなのだ。(人間がお互いの存在を100%受け入れ合えていたら、とうの昔に社会は一つに統一されていただろう。)
だから、相手のことを受け入れられなければ別にそれでいいじゃないかと思う。
受け入れるのが無理ならさーっと離れて行くだけである。
徒党を組んで、集団で個人をいたぶるような趣向よりはよほど健全ではないかと思う。
結局のところ、個人の価値観をもっとはっきりさせることが重要であろう。
4、
私の好きな方に、楠木建さんという経営学者がいる。(著書には大変お世話になった)
彼の主張の中に
物事を判断する上で重要なのは「好きか?嫌いか?」であり
真実か嘘か、正義か悪かではない
というものがある。
とても同意できる言葉だ。
混沌の中で生きられる自分の価値観を生み出していきたい。
追記
自分がGoogleの社長だったら、問題を起こした社員をどう扱っただろうか?
やはり首にすると思う(苦笑)
というより、差別をする人間とはそもそも一緒に仕事はしたくないし。
それに差別する人間は、自らもまた差別される可能性があることは認識するべきだろう。
何らかのアクションをいただけると、一人で記事を書いてるわけではないのだと感じられ、嬉しくて小躍りしちゃいます。
