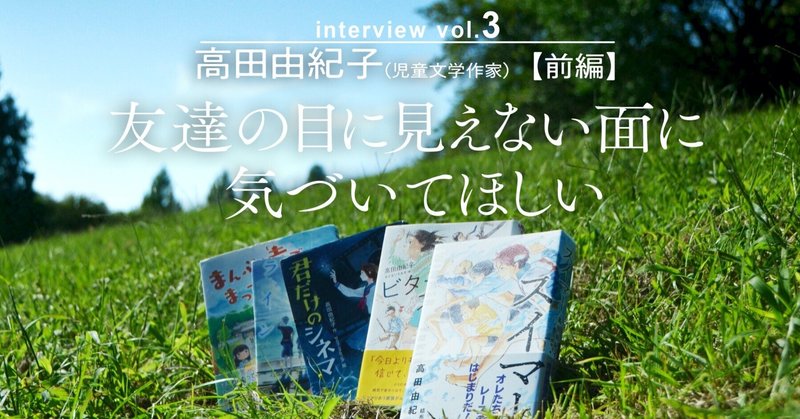
友達の目に見えない面に 気づいてほしい|高田由紀子(児童文学作家) 【前編】子どもの本インタビューvol.3
オチャノマート(OCHANOMART)
「子どもの本のインタビュー」vol.3
子どもの本に関わる方々のインタビュー第3回目は
児童文学作家の高田由紀子さんです。
佐渡島が舞台の作品が多い高田さんの作品は、モチーフが多彩です。
競泳や遠泳などのスポーツ、介護、ミニシアターなど様々。
その中で、友情を育んだり、挫折したり、不登校だったり、
子ども達の心の動きを繊細に見つめています。
どのような思いで作品に向き合ってきたのか、お話をうかがいました。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
佐渡島は子どもが自信を取り戻す舞台として最適
●コロナの影響はどうでしたか?
休校の影響が大きかったです。ずっと家族と一緒に家にいなきゃいけないので、お互いストレスを溜めないように心がけました。今の子どもはオンラインゲームなどで友達と繋がっているので、そこで会話していたみたいです。また今回コロナで大変な思いをされている方も多いと思いますが、家にいるのが向いている子にとっては価値観を見直せる機会になったんじゃないかなと思います。

●高田さんの作品のほとんどが佐渡が舞台ですが、どんなところが魅力なのでしょうか?
デビュー作の『まんぷく寺でまってます』高田由紀子・著/木村 いこ ・絵(ポプラ社)の時は単純に実家があったので舞台にしました。その時は佐渡を舞台にした児童文学があまり無かったので私が最初に書くぞという気持ちで。自然がとても豊かなところが魅力です。自然は自分の力ではどうにもできないものなので、逆に子どもが自分の存在の小ささを知ることにもつながるはずです。
また、二作目、三作目と書く中で人とのつながりが今住んでいる千葉よりも密だと感じました。近所のおばちゃん達が声をかけてくれたり。都会にないおおらかさが田舎にはあるんです。都会で自分らしさを見失った子が自信を取り戻していく舞台として最適だなと思っています。
また逆の意味で、佐渡は都会にあるものが無いんです。例えば『君だけのシネマ』で取り上げたような映画館が今まで無かったんです。『スイマー』に出てくるような温水プールも無かったですし、電車も無いし、デパートも無いし。私が小さい頃はコンビニも無かった。
だからこそ都会から来た子ども達には当たり前の施設が無いことに、大きな意味があると思うんです。無いからこそ一つでもあることのありがたさを伝えられるんじゃなかと思っています。舞台としては面白いのでいくらでも書けますね。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

『スイマー』高田由紀子・著/結布・絵(ポプラ社)について
小六の向井航は東京のスイミングクラブで活躍してがんばっていましたが、友達とトラブルになり挫折してしまいました。そんな時、おばあちゃんと暮らすために佐渡に引っ越してきます。そこで新たな仲間と出会い友情を深め、ふたたびスイミングを通して再生していくというお話です。
水泳はチームワークだと知ったんです
●主人公の航は、都会では仲間たちとうまくいかず試合でも失敗して挫折します。挫折してしまう子どもが立ち直るために必要な事はどんなことだと思いますか?
親が大らかに見守ることは大事ですね。それと友達の影響は大きいですよね。航は都会のスイミングにいた時は、友達はライバルだと思っていました。でも佐渡に来てからの友達とは、スイミング以外に生活や家族とも深く関わる事ができて友情が深まりました。
表面的に見えていたものとは違う面がある事を知るんです。それが泳ぎやチームワークにいい影響を与える過程を描きたかったんです。
●航と、龍之介、信司、海人の個性的なキャラクターがいいですよね。
いろんな友達がいることは、価値観の幅につながりますよね。気の合う友達ってどうしても性格も似てくると思うので、物語の中だけでもいろんな子に出会ってほしいという思いを込めて書いてます。
●スイミングをテーマにしたのはどうしてでしょうか?
私も小学生の頃、水泳の大会に選手で出ていました。最初は一人でやれるスポーツだから、気楽でいいなと思っていました。水泳だと勝つのも負けるのも一人だと思っていたんです。
でも大人になって水泳はチームワークだと知ったんです。ある時、競泳の日本代表選手の本をいくつか読んだんです。北島選手が活躍した時代はクラブの垣根を超えてチームワークを高めていた時期だったらしいんです。
たとえば、オリンピックで初日にメダルを取ったのが自分の所属クラブと違う選手でも、チーム全体がいっきに盛り上がっていい結果を残せた。だから水泳はチームワークだということに納得しました。孤独とチームワークを描くのに水泳は面白い題材だなと思いました。
泳いでいるときは一人なんですが、仲間がいることが力になる。もともとチームプレーのスポーツより、それが表現しやすいかなと思ったんです。
生活に触れることで友達のいろんな面が見えてくる
●その中で海人のキャラクターはチームの中でも我が道を行くというところがありますね。
海人は頭がよくて、リーダーシップがあって、優れている部分が多いんです。でも、完璧そうに見えて心にもろい部分があったりして、完璧じゃない海人をみんなが知ることになる。だから海人は目に見えない部分に気づかせてくれる存在として描きたかったんです。
●例えばSNSなどで他人の素敵な生活が流れてきますよね。でも裏にはその人の別の面があることに、大人でもなかなか気づけないですよね。
航があえて友達の家に行くシーンを設定したんです。龍之介の家に行ったらいつも元気で勝気な龍之介が、妹にホットケーキを焼いてお兄ちゃんとしてがんばっている。
海人は学校では完璧そうに振る舞っているけど、部屋に図鑑がたくさんあったりして、家では一人の時間が長いんだなって思わせる。生活に触れることで友達のいろんな面が見えてくると思うんです。学校だけで見ている姿が全てじゃ無いことを、4人の関わりをとおして伝えたかった。
●そういう価値観の幅という意味では、海人の両親が離婚していたりとか、龍之介のお母さんがシングルマザーだったり、いろんな家族の形が出てくると思うんですけど、それは意識的なのでしょうか。
やはり自分の家族以外にいろんな家庭があると知ることもすごく大事だと思っていて。いろんな家族の形があることを知っていると、その子が大人になる上で根っこの太い人間になれると思っています。将来自分が大人になった時にいわゆる普通の家族の形態になるとは限らないですよね。
そうなった時に自分や周りの人を受け入れていける、太い人間になってほしい。そこは自分がひとつゆずれない、大事にしていきたい部分だと思っています。
私のお話は学校があまり出てこないんです。実はそこも意識してるんですよね。学校も長い時間を過ごす大事な場所だと思うんですが、そうじゃない場面にも子どもの良さや、学ぶことがたくさんあると思っているので、私はそこをできるだけ書いていきたいです。
●学校以外の方が子どもの本質が出ているかもしれないですよね。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

『ビター・ステップ』高田由紀子・著/おとないちあき・絵
(ポプラ社)について
元気でおしゃれだったおばあちゃんが、ある日脳梗塞で倒れて、後遺症が残ってしまいます。一緒に暮らすことになった小5のあかり。変わってしまったおばあちゃんにとまどい、怒ったり、悲しんだりしながら少しづつおばあちゃんの気持ちもわかってきてきます。そんな家族が次の一歩を踏み出していく姿を描いた物語です。
義母の介護の時、その状態を客観的に受け止めることができなかった
●介護という少し重いテーマかもしれませんが、児童文学の題材にしたのはどうしてでしょうか?
義理の母が脳梗塞で倒れて、同居していた時期があったんです。麻痺が残る以外に感情のコントロールが難しくなりました。私も自分の引っ越しや子育てと重なって、義母の状態を客観的に受け止めることができませんでした。
義母に対して主人公のあかりと同じように、なんでもっと前向きになってくれないんだろう、なんでもっとリハビリがんばらないんだろうって思っていました。
でも10年以上たって客観的に考えたり、いろいろ調べたりしてみると、ただわがままを言っていたのではなく、感情のコントロールができない状態だったのかもしれないし、そういう後遺症もあるとわかったんです。だから、認知症以外にもいろいろな症状があると知って欲しかった。
その時は長男が年少くらいで、私もつらくて厳しくあたってしまいました。もし子どもが小学生、中学生だったらどのように受け止めてたかな、ということを考えました。その中で私自身の心の整理として一度書いてみようと思ったんですよね。
●介護をしているあかりのお母さんの立場だったんですね。
子ども達におじいちゃん、おばあちゃんがこういう風になることもあるということを伝えたいなというのはありました。いま同居していない子がすごく多いので、もしかしたらおじいちゃん、おばあちゃんが年をとっていく様子がわからない子もいっぱいいるかもしれないですよね。
●知っているだけでも、受け入れる時の気持ちが違いますよね。
介護のことって人になかなか言えないし、相談できないんですよね。義母が倒れたころ、まだ長男は幼稚園の年少で、まわりのお母さんは子育てで忙しい時期でした。どこにでかけたとか、習い事でこうだったとか、そういう話題が多い中でおばあちゃんの介護のことなんてとても話しづらくて。介護すること自体よりそれがつらかった。だからこんな家庭もあると思ってもらえたらいいですよね。
●性格が変わってしまうのも本人が悪いわけではなく、病気の症状だと思えると少し違いますよね。
わかっていても受け止めきれない部分も多いんですが、物語を読むことで自分一人だけじゃないと思ってもらえればいいかな。私の作品の中でも書いていて、一番つらかったですね。
どんな時でも家族として一緒にいる意味は大きい
●このお話に限らず高田さんの作品は、おじいちゃん、おばあちゃんが、たくさん登場して、主人公を導いたり癒したりしてくれます。
おじいちゃんや、おばあちゃんを頻繁に登場させるのはどうしてでしょうか?
私は夫の仕事の都合で千葉に来て、夫の実家とも、私の実家とも離れてしまって、二人っきりで子育てしている感覚が強いんです。それはとても心細いんですよね。おじいちゃん、おばあちゃんは子ども達にリアルな縦の人生を見せてくれる存在として、私達のような母親世代も見守ってくれるような存在として、登場させたいといつも思っています。
●あかりの家族ではお父さんが大事なときに飲みに行っていたりなど、頼りなく描かれていますが。男女の役割などは昭和から平成、令和では変化を感じますか?
周りをみていると若いお父さん達は昔よりは、育児などに関わって変化しているとは思います。リモートワークで仕事と家事の男女の分担もどんどん変化して、お互いに気づくこともあると思います。
ただやはり社会全体のしくみが変わらないと、女性に負担がまだまだ多いんじゃないかな。とくに介護はまだまだかなと正直なところ思います。昔みたいに家でお世話をするのは女性にかなりの負担がかかります。
介護施設や様々な支援を利用して家族だけの負担にならないようにすることが大事だと思っています。
あかりのおばあちゃんはお裁縫して洋服を直したりするんですが、どんな状態になっても人の役に立って感謝されるのが大事だと思いこんでいます。そういう役にたちたいという気持ちは、障害があるなしに関係なく人間の根本として変わらないと思います。
でも、あかりが物語の中で「おばあちゃんが役に立つとか立たないとか、そんなこと……もうどっちだっていい」と気づくシーンがありますが、大切な人はそこにいてくれるだけでいいんですよね、本当は。
●ビター・ステップというタイトルはどういう思いでつけられましたか?
これは担当の編集者さんがアイディアを出してくれて決めたんですけど。ビターという言葉を使ってるだけあって、家族ってきれいなだけじゃなくて、みんな元気とかみんな仲良くとか、そうじゃなくなる部分もいっぱいあると思うんですよね。
最近では核家族が多くて、なるべくきれいなところを見せたい意識がお母さん達も強いかもしれません。子育て世代が読む雑誌だと、きれいですっきりした暮らしとか、素敵な家族とか、そういう特集が多くて。でもキラキラしたものばかりが生活や家族じゃないんですよね。それに憧れるとか書かれると、そうじゃないといけないのかなと落ち込んでしまうこともあります。
私も義母と暮らしていたときは、隣の人が出かけているだけで羨ましくなったりしていました。でもそういう家でもちゃんと前をむいてやっていけることを伝えたかったんです。
どんな時でも家族として一緒にいる意味って大きいと思います。にがくてもきれいじゃなくても一緒にいることの大切さ、そしてちょっとだけでいいからステップを踏んで前を向いていくことの大事さ。そんな思いが込められています。
【後編へつづく】

高田由紀子
千葉県在住、新潟県佐渡市出身。故郷への思いが深く、佐渡ののびやかな自然のなかで、葛藤し成長する子どもたちの姿をみずみずしく描いた物語が多い。主な作品として『まんぷく寺でまってます』『青いスタートライン』『ビター・ステップ』『スイマー』(以上ポプラ社)など。『君だけのシネマ』(PHP研究所)で第5回児童ペン賞少年小説賞受賞。「季節風」同人。日本児童文学者協会会員。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
