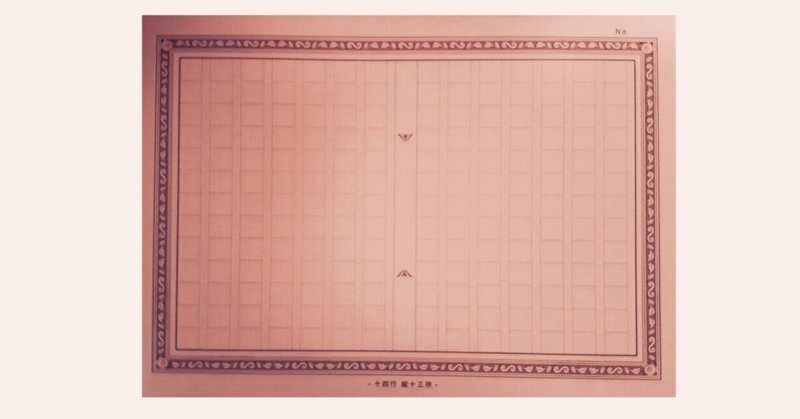
ひととせ⑥【連続短編小説】
※前回の「ひととせ⑤」はこちらから
サキがいない。
その日だけかと思ったけれど、そうではなかった。明日は来るかも、明後日か、1週間後とか。いろいろ思ったが、ついぞ姿を見せることは無かった。入院してからまもなく10日が経とうとしているのに連絡の一つもない。
コンコンと部屋のドアを誰かがノックし、どうぞと言うとゆっくりとドアが開いた。
「川崎さん、お加減はどうですか」
僕の通う勤務先のメンタルクリニックの主治医である。
「先生、わざわざ来てくださったんですか」
僕は驚きつつも、彼がサキではないことに落胆していた。けれどそれもこの数日で何度も経験しているせいか、わずかな落胆である。
「あなたの許可をもらって、という前提でこちらの病院の担当医に連絡をもらったんです。体の後遺症などもなさそうだと聞いています。お顔を見る限り、元気もあるようですね、安心しました」
そう言って、彼は何か白い包みの箱を僕に渡した。
「お見舞いです。確か以前にミルクティがお好きだと伺っていたので、専用のティーバッグを探してみたのですが・・・・・・」
どこか照れた様子で笑って見せた。そしてすぐに何かに気づいたらしく、眉間に薄くしわを寄せた。
「すみません、病室で手軽に飲めるものにすればよかった。申し訳ないです」
「ああ、そんな気を使わずに。ありがとうございます」
いただいた包みを開き、パッケージを見て驚いた。
「好きな、店のものです」
そう言って、思わず胸から喉元が急速に熱くなる。この店の紅茶を使って入れるミルクティを、サキはとても気に入っていたのだ。
「『サキ』さんの、好きなお店ですか」
僕が言うよりも先に彼が言った。彼の顔を見る。柔らかな微笑みで、僕を見据えていた。まるで、いつもの診療室である。全ての何かから解放されてその空間には自分と自分を許してくれる存在しかいないのだという強烈な安心感。僕は思わず口元が緩んだのだった。
「そう、そうです。よくご存じですね。ああ、僕が以前に言ったんだっけ。いつだったろう、覚えていないなぁ。うん、でもそう、先生の元に通うようになって割と早い時かもしれない。そうだ!その当時に1度だけ、診療室にサキを連れて行ったことがありましたね。そのときかもしれないな。ちょうど休職したばかりの時にサキと出会ったので、ああ、この店のミルクティはたまたま通りがかった時に買ったものなんだけど、それを彼女に出したら大喜び。それ以来、僕はよくお土産に買って帰ったりしたんです。そんな話も先生にしたのかもしれない。ああ、ありがとうございます。1日も早く退院してサキと一緒にいただきますね」
一息に言いながら、僕は涙が出ていることに気づいた。
「川崎さん」
彼は近くのティッシュペーパーを僕に1枚よこすと、そのまま穏やかな表情で続けた。
「『サキ』さんなどと言う人はおそらく存在しません」
彼のその言い方が、例えば『結婚おめでとう』と言うよりも幸福に満ちた柔らかな笑顔だったので、僕はいったいなにを言われているのか理解ができない。
「いいですか、サキさんはいません」
「いや、なにを言っているんですか。先生にも僕はちゃんと話していたでしょう。それに、1度だったか2度だったか、僕は先生に会わせたはずです」
僕はいつの間にか握っていた梅の花の折り紙を強く握りしめていた。
「そうですね、サキさんと来院されたことがありました」
「ほら、やっぱり!それなのになぜおかしなことを言うのですか」
もう一方の手で別の梅の花をとってはくしゃりと握りしめる。入院期間中にも、折り紙で梅の花を切っては折り続けていたので今では手の届く範囲にいくらでもある。
「けれどそこにいたのはあなた一人でした」
穏やかな表情は緩やかに崩れ、僕を哀れんで見えた。
仕方がないので僕は、また別の梅の花を握りつぶした。
続 ひととせ⑦【連続短編小説】- 2月13日 12時 更新
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
