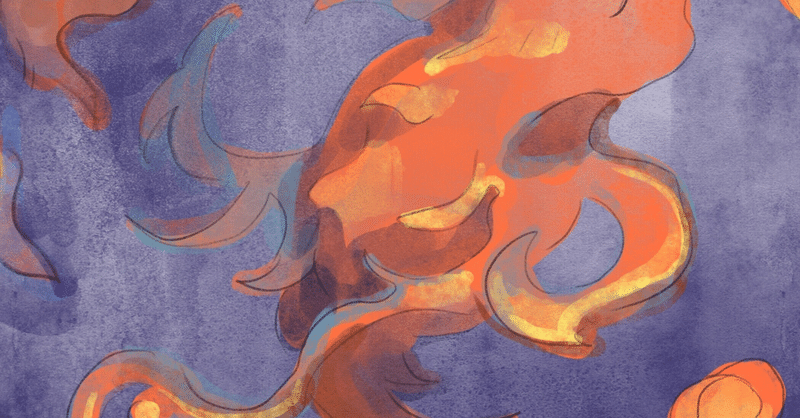
超短編小説|火の玉があらわれた。
今日は、『火の玉』というお話をお届けします。
2分くらいで読めると思います。
やせいの火の玉が、あらわれた!
暗い夜道に、とびだしてきた!
僕が火の玉を見たのは、閉店時間ギリギリのスーパーまで歩く道中だった。草むらで新種のモンスターに遭遇したときのように、なんの前触れもなく出し抜けにそれは出現した。
小さな火の玉は、しだいに多くなっていった。電光石火の如く、上下左右に揺れていた。不思議と音は聞こえなかった。そのことが僕を余計に混乱させた。
もちろん、正面から猛スピードで走ってくる車なら避けられるかもしらない。けれどそれが火の玉なら、話は別だ。僕は特別な訓練を受けているわけではないのだ。
僕は火の玉の前にして、言葉を失った。人間は火を前にすると、無力になる。その場に立ちすくむことしかできなくなる。
それは、僕の家の近所で火事が起こったときも例外ではなかった。
僕はソファーに横になり、読みかけの本のつづきを読んでいた。小説が最後の章に入ったところで、とつぜん焦げたような匂いがした。僕は即座に窓を開けると、強烈な匂いが部屋中に蔓延した。僕は窓を閉めて、ベランダの方へ進んだ。
遠くの方で、建物から真っ赤な大きな火が立ちのぼり、黒い煙がもくもくと立ち込めていた。ビルの上空を、黒い灰が鳥のように羽ばたいていた。遠くの方で燃えているはずなのに、黒い灰は僕の住んでいるアパートにまで届いていた。
周囲には、燃え盛る炎を見ようとする数人の野次馬がいた。マンションのベランダから身を乗り出している者もいた。
それからまもなくして、消防車が来た。数台の消防車が消火活動をしている間、僕は黙って火事を見ていた。まるで僕たちの声が燃え尽きてしまったかのように、火は人間から言葉を奪った。そのあいだ、真っ黒の灰は雪のように、ひらひらと舞い降りていた。
火の玉は、ついに僕の目の前にまで接近していた。僕は、足の親指にギュッと力を入れて踏ん張った。それから、いつ来ても避けられるように膝を曲げた。次の瞬間、火の玉が正体をあらわした。
それは、自転車に跨ったおじさんのタバコの火だった。僕は言葉を失った。おじさんは、タバコをくわえな
がら、何事もなかったように、僕の横を通っていった。
僕は胸をなで下ろして、閉店間際のスーパーへと急いだ。
サポートして頂いたお金で、好きなコーヒー豆を買います。応援があれば、日々の創作のやる気が出ます。
