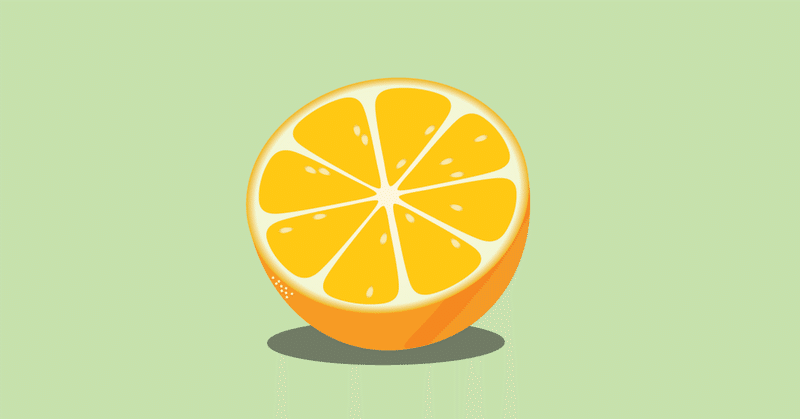
Photo by
air_mezzanine
「待つ」ことと「待たぬ」ことのあわい
私たちの学校がテレビ局から取材を受け、その様子が全国放送された。
その時のタイトルが「待てば育つ」だった。
待つことが難しい世の中になったとよく聞くし、よく言う。
LINEを送ればすぐにメッセージが返ってくる。
検索ワードを打ち込めば分からないこともすぐに分かる。
頼んだ商品はすぐ手元に届く。
自分が「やりたい」と思ったことが、即時に満たされる時代になった。
欲求が満たされるまでの時差を、人は待つ。
サービスは即応的に、人々の果てしないフローを一瞬も遮ることなく、欲求を満たし続ける。
鷲田がいう通り、今やわが子の誕生ですらおそるおそる待つことはない。
超音波をあてれば、生まれる前に性別が分かる。
ほのかに顔が分かる。
遺伝子が分かり、出生をじりじりと待つこともなく、いろいろ手を打てる。
教育にもその波は押し寄せている。
子どもが自分で試し、失敗し、落ち込み、気を取り直し、紆余曲折の果てに気づいたら成長していたというような時間のかかることはできなくなった。
焦りがある。
未来に向けて、前のめりで進まなければいけない強迫観念がいつからか生まれた。
人間をふくむ自然は、どこまでいっても意のままにならないものである。
偶然を待つ。
時が来るのを待つ。
流れを待つ。
そうした感性を失ってしまえば、人間の重要なことを見逃してしまう。
では、教育におけるあらゆる介入を中止し、牧歌的な自然に戻れば良いのかというと、それも叶わない夢だろう。
私たちにできるのは、「待つ」ことと「待たぬ」ことの無限のあわいの中で何ができるのかを考え、実践し続けることだけだ。
「結局はバランスだ」なんて分かったようなことを言ってみる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
