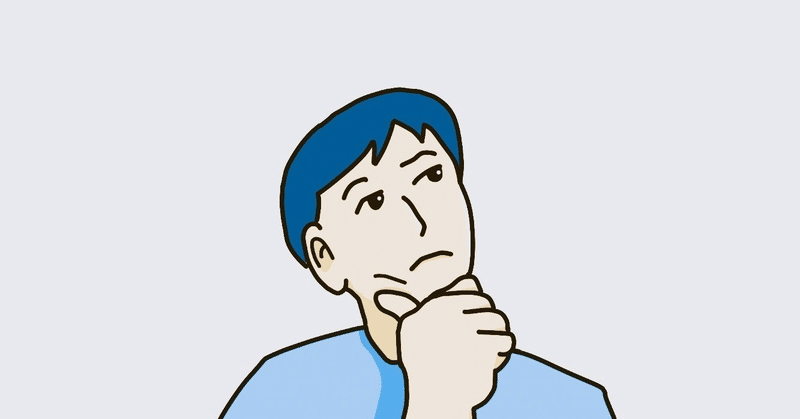
エピステーメーと不登校
フーコーの代表作に『言葉と物』があります。
副題は「人文科学の考古学」とあり、膨大な資料の研究と精緻な分析によって〈主体哲学〉の起源と来歴を明らかにし、打破しようとする野心的な作品です。
難解でありつつも、その分析の量と質は凄まじいレベルで、名著です。
さて、フーコーは〈エピステーメー〉という概念を提唱しました。
エピステーメーとは、時代ごとに存在する、あらゆる知の成立条件を規定する認識体系のことです。
例えば、17〜18世紀(古典主義時代)のあらゆる知を成立させていたのは、“表象”であるとフーコーは言います。
この世界をなるべく客観的に記述しようとする営みが古典主義時代の知であり、そこではどのように世界を記述すれば、正確な記述となるのかが主な問題意識でした。
つまり、「世界の観察」です。
しかし、カント以降、人間は世界そのもの(物自体)を認識することが不可能だと判明します。
私たちが客観的な世界を認識できないとなれば、世界の客観的な記述ということも不可能なので、知の構造が変わらざるを得ません。
ここに、「世界を観察する人間を観察する学」が生まれます。
19世紀以降(近代)においては、“人間”が諸学の成立条件を規定するようになりました。
こうして、古典主義時代のエピステーメーを構成する3つの領域(一般文法、富の分析、博物学)が、19世紀になると知の格子である他の3分野(文献学、経済学、生物学)へと変化していくことを明らかにし、人間が知の対象となったのはたかだか19世紀になってからに過ぎないということをフーコーは主張しました。
さて、フーコーほど偉大で雄大な対局的歴史観を打ち出すことはできないけれど、教育においても前提条件が時代ごとにあり、どれだけオリジナルな思想だと思っていても、その影響からは逃れ得ないということを自覚することは大切です。
例えば、不登校。
学校に行けない(行かない)子どもたちの呼称ですが、そもそも不登校という呼び方が生まれたのはここ30年くらいです。
その前を見てみると、怠学、学校恐怖症、登校拒否など、様々な呼び方が存在していたことがわかります。
そして、それぞれの呼び方に、各時代がどのように学校に行けない(行かない)子達を捉えていたのかということが表れています。
「怠学」という言葉には、文字通り「怠けている」という意味が込められており、学校に行けないのは本人の性格上の問題であるとされました。
「学校恐怖症」には、学校に行けないことを病理であると捉え、治療対象とする意味が込められています。
実際、この時代に「学校恐怖症」を扱ったのは精神科医で、母子分離不安が原因であると考えられていました。
「登校拒否」の時代には、学校に行けない(行かない)のは本人の問題であるとする派(戸塚ヨットスクール)と、学校側に問題があるのであって学校に行けない(行かない)のはむしろ正常な生理的反応なのだという派(東京シューレ)に別れて、大激論が起こりました。
そして、現在は学校に行けない(行かない)現象をなるべくそのまま記述しようとする「不登校」という呼び方になりました。
70年あまりの変遷を乱暴にまとめると、学校に行けない(行かない)のは本人の性格的問題、病理、そして学校側の環境的問題とする、原因の所在を人間の内から外へと置き換える認識上の旋回がくるりとあったと考えることができます。
そして、この旋回を規定する知の枠組みとは何か。
それこそが、フーコーの問題とするエピステーメーの次元なのでしょう。
もちろん、フーコーレベルで分析するなんて僕にはできないので、エピステーメーの位置にあるものをぼんやりと意識しながら、または誰かの発見の恩恵に預かりながら、目の前の現実に向き合っていくということしかできませんが、しかしそれでも意識するのは重要だと考えています。
理由は、僕たちの知の枠組みを構成するエピステーメーを意識し、変化していく物だと知ることで、一つのあり方だけを絶対視する姿勢を遠ざけることができるからです。
『言葉と物』のラストはこの言葉で結ばれています。
「もしもこうした配置が…18世紀の曲がり角で古典主義的思考の地盤がそうなったようにくつがえされるとすれば、そのときにこそ賭けてもいい、人間は波打ちぎわの砂の表情のように消滅するであろうと。」
旧来の学校制度を乗りこえるために、これからの教育の実践や理論がたくさん生まれています。
それらもまた、来るべき未来には「波打ちぎわの砂」のように消えていくものだと頭の隅で思いながら、固執することなく、冷静に選びとっていくことが重要なのだと感じています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
