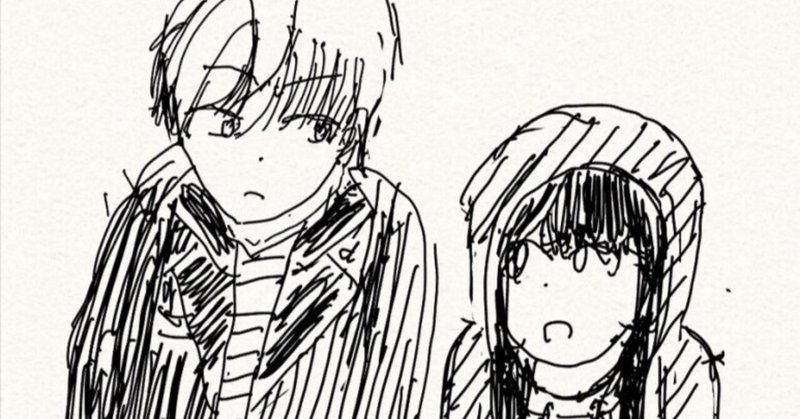
「CANON 11」 EP.1 人工知能評論家 (1)
Synopsis
富士歌音(ふじ・かのん)は車椅子で移動する高校生・音楽評論家。友達とふと立ち上げたマガジンに続々と同僚が加わる。自動評価演算システムを持つバーチャルAIストリーマーや、異世界から聴いたことない音楽を持ち込んでくる亡命皇族、匿名希望のライター応募者は憧れの現役○○○○⁈ キテレツなメンツ揃いで、今日も世界を採点採点! 認められない価値を掘り出し、本日も10点満点の11点に至る《CANON(古典)》を見つけ出せるのか⁈
Characters
富士歌音(ふじ・かのん):高校生にして文才を発揮する作家兼音楽評論家。電動車椅子が欲しくて公募に参加。ネット浸りの毎日を送る中であらゆる大衆文化(と毒舌)を習得した。今はWEBマガジン《CANON》の収益化と拡張に向けて動いている。弟の歌織(かおる)が主に付き添い介助。
N:歌音とは施設絡みの幼馴染。高校中退後、歌音の介護補助、レコード屋職員、バリスタ、自主制作系SSW(シンガーソングライター)、社会運動などに取り繕っている。賢くて神経質、歌音にだけデリカシーが効く。
夜行星(やこうせい):人造人格プログラム。バーチャル・ストリーマーで、音楽/映画レビューチャンネルを運営。冷たい性格(性格?)だが、よく他人のコンピューターを勝手にハックして飛び出る。作品データを一瞬で読み取り、評価を小数点以下まで出せる。
セヤン・ケーネン:異世界から亡命してきた皇族で、幼い頃に兄・セオン、姉・セヨンと共に地球に移った。中学校に通い、夢は映画監督。全国各地のインディー/ローカル・ミュージックを探し回るのが趣味。アマチュアメタルバンド“Hosanna Moshpit”のドラム。ある教会の裏小屋に住んでいる。
(匿名希望):業界の裏事情にやけに詳しい。
Ch.1 人工知能評論家
「正直、人間の評論家はもう要らないかなって」
夜行星が長い髪を後ろにめくりながら冷たく言った。
その30分前。
歌音は床に横になって音楽を浴びるように聴いた。何も思い浮かばない時や、動機が湧かない時のために作っておいた、5000曲に至るプレイリストをランダムに再生する習慣がある。これらはあらゆる時代や地域からの音楽の中で、歌音が直々に「CANON(古典)」として厳選した、本人曰く、「世界最強のプレイリスト」である。
脚には元から力が入らないので自力で起きるのは難しい。スピーカーで鳴るマスタリングされた音波に紛れて窓をうつ雨粒の音がかすかに混じって聞こえる。
よし、今日はサボり確定だ。
「学校行け」
頭上から不機嫌そうな男の顔が視野に入ってきた。友人のNだ。本名は久保縁(くぼ・えん)。
「喧嘩で退学したやつに言われたかねぇよ」
「退学じゃなくて中退な? 俺はやること多すぎて学校を諦めざるを得なかったんだよ。あと喧嘩は別件だ」
「そんな優秀さんが女の子の部屋にノコノコと入ってくんなよ、暇そうじゃん」
「そこ、〈キモいから〉とかじゃないんだ。で、なんでそんなだらっとしてたの」
「それがね、この前に期待してるっていったラップ・チームの新譜が…」
「いまいちだった?」
「クソダサかったのよ」
それは格の違う評価だった。「いまいち」と「ダサい」は明らかに違う基準だ。一方、「良い」・「すごい」・「素晴らしい」の使い方も異なり、普段よく用いられる「名盤/名作」という言葉も一定基準以上でなければ〈許されない〉。
「だからそんな(しょーもない)〈名曲セラピー〉を…」
「なんか心の声がしたぞ」
「うおっ、なんでわかった」
「合ってるのかよクソが。音楽評論家だからだ」
「すごいな、評論家!」
「ねぇ、それより聞けよぉ〜。なんかいきなり808にモジュレーションぶちこんでるけどドリルかレイジかはっきりしてほしいしいや別にジャンルを包括できてんのならそれで構わんけどよぉレファに追いつけてすらないじゃんかあとバックダブリングはもう何あれって耳を疑ったしそれとそれと—」
歌音は脚は動かねど元気いっぱいに毒舌喰らわす女の子。電動車椅子が欲しくて応募した青少年文芸賞で入賞はしなかったものの、関係者に目をつけられてとりあえず(?)作家になった。小説集の在庫は処分に困ったと聞くものの、障害の経験を編んだエッセイ集が大衆的な反応を得た。
その成功のおかげでやむなく断らざるを得ない事案ができるくらい執筆依頼が次々と届く中、独特な提案が訪れた。アニソンのレビュー集に共に参加してほしいとのことだった。歌音の小説内容がサブカルと緊密な関係を結んでいること、実際に歌音自身もあらゆる通路でアニメ愛・音楽愛を語ってきたことから十分ありえる依頼で、深く悩まず快く受け入れた。
「君は作家である同時に評論家になろうとしてるんだ。できる?」
その時、Nは注意深い口調で助言した。彼はアマチュアのSSW(シンガーソングライター)でもあって、音楽に関してもだいぶ詳しい。しかし歌音だってネットで人生を浸かっているうちに、YouTubeやショートフォームの大半を占有する音楽をある程度掘り下げているつもりでもあった。昔から大作家たちが音楽について語る著作もよく読んでいるし、自らの感覚としては一切の抵抗感もなかった。それに、文化産業を上から目線で見下すスノビズムはネット人間の基本素養だ。難しいことはない。
「別に構わんくね?」
「創作と批評に同時に携わることそのものは原則的に全然ありうると僕も思うよ。でも各領域においての責任の類は全く別物で、それらを同時に背負えるかって問いたいだけ」
「ふーん」
歌音が目を瞑って考えるジェスチャーをした。
「でもやるっきゃねぇだろ」
今となって考えてみると、正直あの時、何も考えてなかった。
そして高校生文才、富士歌音の著作目録には小説『黄泉国公務員日記』・『ミックス・マスター・カリーナ』、エッセイ集『人生二輪車』に加えて批評書『アニソン名曲ガイドブック』(共著)が加わった。ちなみに今は『ポストラップ時代のリテラシー』の刊行に向けて絶賛執筆中。そんな感じで、割と学校のサボりがいがある作業効率を見せる中、歌音は音楽評論家の経歴に踏み出したのだった。
その後、個人ブログサイトを改造し、本格的に音楽について語るレビュー専門のWEBマガジン《CANON》を立ち上げ、編集長という肩書きもプロフィールに揃え始めた。実際は無料コードレスWEBページをマガジンと自称しているだけなのだが、時々そのルートを通じたメールや連絡をもらうと、この制度なき文化の脆さをついつい知らされる。
「—で、なんで来たのよ」
「落差すごいな。まあ、あれだ。《CANON》のことで相談がある」
「えっ、ボクのことで? ドキッ」
「マガジンの方な」
「おおっ、そりゃあ学校どころじゃねぇな! ドキドキッ」
《CANON》のスタッフは歌音とNの二人。《CANON》は現在、収益化と拡張に向けての段階を進めている。その際に登場した案が、YouTubeなど、ソーシャルメディアの活用方針である。
「そのベンチマーク対象としてこの前送った動画、見たか?」
「ああ、V-Tuberの夜行星な? キャラ可愛くてチャンネルの全動画見て寝過ごしたわー」
「だから今朝ああだったのかい。今日、その人と遠隔会議することになったから、準備しとけよ」
「なっ! お前、編集長のことわりもなくそんな…!」
「お前が任命した〈マネージャー〉だろ? 文句あるなら自分に…」
「そんな… まだファンとして出会う心の準備が…!」
かわいいな、おい。
夜行星は3D動作再現技術のアニメ風キャラクターを用いて活動するバーチャル・ストリーマーで、音楽と映画のレビューを専門にするチャンネルを運営している。機械的な冷たい口調で加減せず作品をきちんと丁寧に貶す仕草が、なんか、こう、モえる(⁈)との評判だ。
歌音たちはさっそくリビングに移った。
「正直、人間の評論家はもう要らないかなって」
夜行星が長い髪を後ろにめくりながら冷たく言った。
その発言の前まではすごい技術だなと頭の理解が目の前の自然すぎるモーションとハッキングに追いつかなかった。
夜行星は割とクローズドな会議の場でもアバターで登場した。というか、会議はzoomやせめてSkype、Discordなどのような会議・連絡ツールではなく、彼女(おそらく)の主要な活動空間である、YouTubeのプライベート・リンクで行われた。かと言ってチャットを通じたものでもなく、きちんと歌音たちの様子の音声と動作を即座に捉えられている様子だった。頭の追いつけない技術の連続だったが、IT超大企業のGoogleなだけに(?)なんらかの裏技があるんだなぁと現実逃避していた。
そしてその発言に至ると、やっと違和感が理解できるようになった。
「そうですよね! すべておっしゃる通り!」
「おい」
このバカはまだ追いついてないみたいだ、とN。
「つまりあんたはその、なんだ、人工知能とか言い出すわけか?」
Nがイラついて喧嘩腰に訊いてきた。
「そんなしょぼいものと比べないでくださる? ただのデータ網で暮らす人格よ」
「いや、〈ただの〉って言われても… まあいい。(いいんだ、と正気を取り戻した歌音が思った。)でもさっきの発言は聞き捨てられねぇな」
「よいしょ」
夜行星が映像のフレームから這い出てきた。
「じっくり聞かせてもらいますか?」
「どこの貞子だよ」
「あいにく液状画面越しまでには出られませんけれどね」
「よかったじゃねぇか」
「でも今の時代、」
違うところから声がした。Nのふところのようだった。携帯電話を取り出すと、そこにお馴染みのロングヘアのアバターがいた。
「モニター・トゥー・モニターで移れば大抵いけるでしょう?」
「ごめんな編集長、ことわりもなくこんなん会わせちゃって」
「わかればよろしい。それはそれとしてえええすごい! どうやったの今の⁈」
歌音が騒いだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
