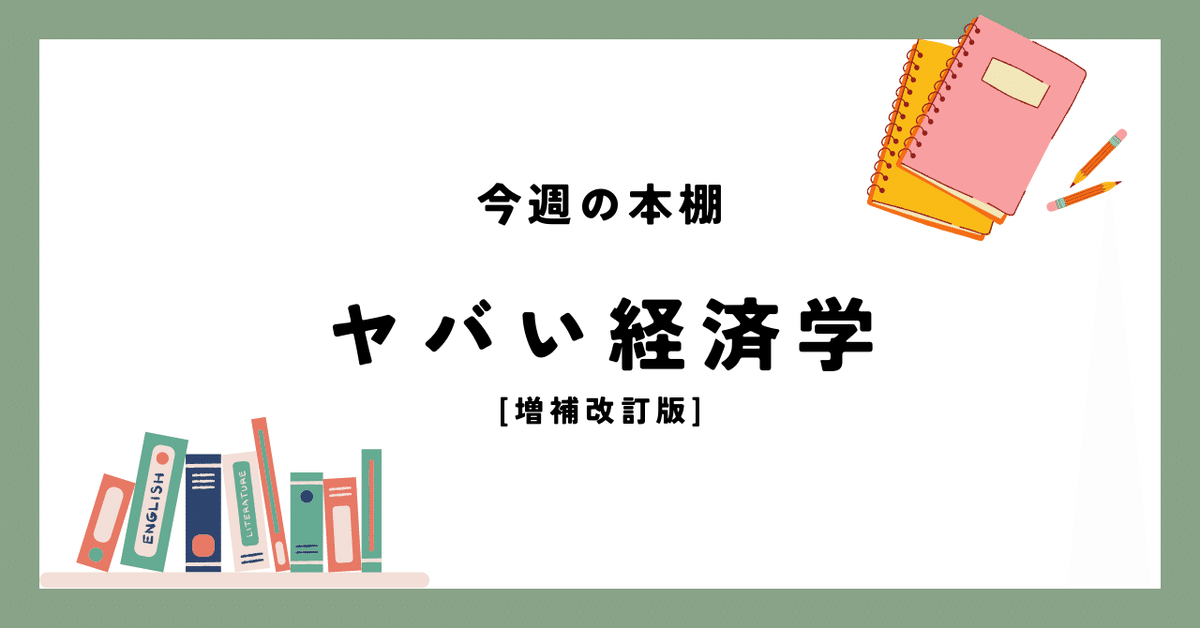
【今週の本棚】ヤバい経済学
昨年の夏ごろ、こんなジレンマが話題になった。コロナ感染対策として、東京都がPCR検査をするため民間クリニックにキット代金や送料に加えて、1回あたり3000円の「諸経費」を支払う制度を作った。領収書もいらないから、とにかく多くの人に検査してもらおうと。果たして、検査数は急増した。
だが、一部のクリニックは商品券を配って「集客」し、それを目当てに同じ人が1日に何回も検査を受けるようになった。「予防効果なしの、唾液と商品券の交換じゃないかッ!」とメディアは騒いだが、本書を読んでいる人は誰もがこうなると推測していたはずだ。
人間はインセンティブ(動機付け)に敏感だ。これは、経済学の基本中の基本。僕も大学の授業で習った…つもりだったが、この本を読むまでその意味があまりしっくりきていなかった。しかしここに記されて実社会からの例とちょっぴり皮肉った解説を通すと、ドライな学問がとても面白くなり、教訓もしっかり身に付くのだ。気に入っているのは僕だけではない。世界で400万部も売り上げたベストセラーだ。
日本人にとっても身近なトピックがある。それも「ズル」を取り上げた第1章に関する相撲の話だ。
過去のデータを洗い直し、相撲は本当に「ガチンコ勝負」なのかどうかを調べたものだ。スポットを当てたのが、勝ち越しがかかっている7勝7敗の力士と、既に勝ち越している8勝6敗の力士の千秋楽の取り組み。成績を考えると8勝している方がより強くてだいたい勝つはずだが、実際には7勝の力士の方が8割もの勝率を見せていた。八百長の直接的証拠はないが、はっきりした「取引」がなくても、8勝の力士が「今回負けてあげると、自分の勝ち越しがかかっているときに空気を読んでもらえるだろう」と「忖度」していることが十分に考えられる。
PCR検査問題に近いのが、(これとは異なる本に載っている)中国の化石発掘の話。アメリカの恐竜博士が「化石1個にいくら」というご褒美制度で地元の方に発掘を促進しようとした。もう結果はわかるはず(笑)。数で儲かる制度だからと、せっかく大きな化石を見つけても、みんなはそれを砕いて複数として提出していたのだ。恐竜よりも先に人間性を掘り起こしたようだ。

スティーヴン・D・レヴィット/スティーヴン・J・ダブナー 著
望月衛 訳
東洋経済新報社/2,200円(税込)
『ヤバい経済学』を読むと、やばい制度、やばい政策を見出すのが本当に楽しくなる。商品券でもあげるから、ぜひ読んでみてくださいッ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
