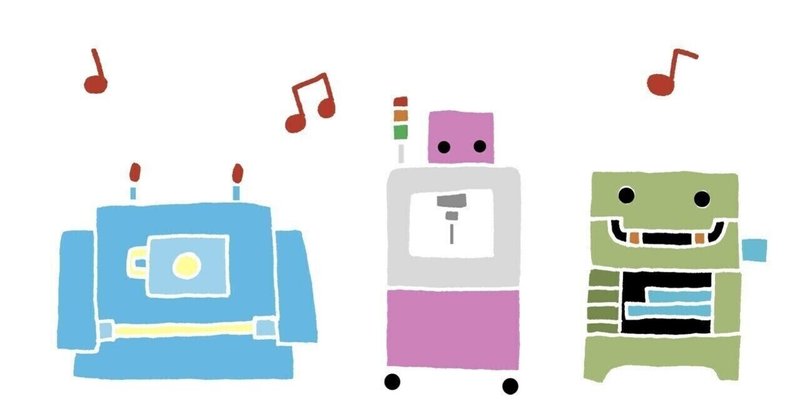
でき太くん三澤のひとりごと その54
投稿 その54
先日でき太くんに入会したばかりのご父兄から、「うちの子は小学3年生ですが、小学3年生だとどのくらいのことができるようになっていれば良いのでしょうか」というご質問がありました。
今の私にとっては、この質問が一番答えづらい質問です。
私の中には「3年生だから」という基準がないからです。
将来的に中学受験を視野に入れているお子さんに対しては「3年生のいつくらいまでに、ここまでの単元を終わらせる」というような目標は設定しますが、昔からある「学年枠」という基準で子どもを見るという視点がもう私にはないのです。
この「学年枠」という基準。
私にとっては邪魔で仕方がありません。
この基準を満たすことができているときには、さほど問題はないのですが、ちょっとでもその基準を満たすことができなくなると、さまざまな問題が起きてきます。
もし3年生のお子さんが、2年生のかけ算九九がスラスラ暗唱できず、1年生のくり上がりのあるたし算に指を使っていたら、学校の先生や、親御さんはその子をどのように見るでしょうか。
たいてい「問題あり」と見るようになります。
3年生では九九だけでなく、わり算もスラスラできて、4ケタのたし算やひき算がスラスラできることが「基準」だからです。
この「問題あり」という意識で接することが、その子の成長を阻害していくのですが、そのことに気づかずに、なんとか3年生の「基準」を満たそうと努力すればするほど、その子は傷ついていきます。
3年生でも、1年生くらいに感じるほどおさない子もいます。
数の発達がゆっくりで、くり上がりがスラスラとできるまでに半年かかってしまうというケースもあります。
人の顔がすべて違うように、子どもの成長のスピードも様々です。
みんな成長の仕方が違うのです。
ひとり一人「自分のスタートライン」から学習を進めて、ひとり一人のステップで成長をしていけば良いのです。
このようなお話をすると、多くの人が「その通りだと思います!」と言ってくれます。
これはとてもうれしいことです。
ただ、学年枠という「基準」を自分の意識の中から取り除くのは、なかなか大変な作業です。
いわゆる「頭ではわかっているのですが、なかなか。。。」という世界です。
私もこれには本当に時間がかかりました。
もしご自分のお子さんが、3年生で、九九がスラスラ言えず、くり上がりにも指を使っている。
このときに「基準」を完全に度外視できるか。
それでも、「この子ならだいじょうぶ。必ずできるようになっていく!」と疑いもなく信じることができるか。
他のお子さんがスラスラ3年生の問題を解いているときに、わが子が指を使っている。
このときに「基準」を度外視して、わが子だけを見つめることができるか。
それでも、「私の子ならだいじょうぶ。この子のステップで成長していけば必ずできるようになる」と、疑いもなく信じることができるか。
まわりの大人がどのような意識で子どもを見守っているか。
これが子どもの能力伸長を左右する重要なポイントなのです。
深く疑いもない肯定的な意識。
この意識で子どもたちを見守っていきたいですね。
ちなみに、冒頭の質問をされてきたご父兄には、ぜひお子さんを「できる!できる!きっとできる!」という意識で常に学習をサポートしていってくださいとアドバイスさせていただきました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
