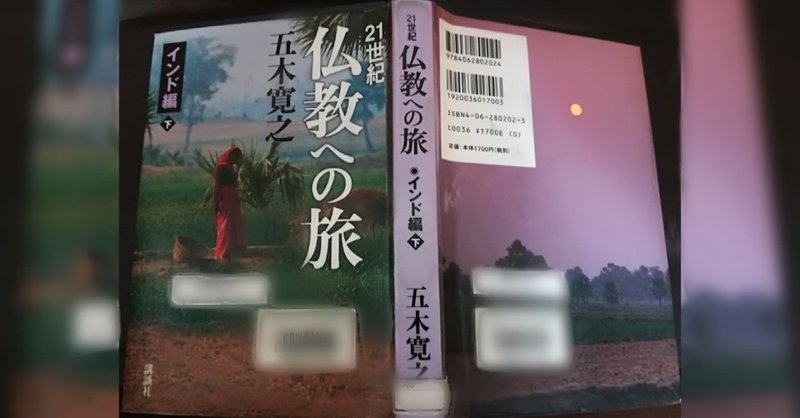
「21世紀 仏教への旅・インド編〈下〉」五木寛之
ブッダの死とその前後の事件の数々
遊女との約束
いかに高等な遊女とはいえ、…いくら財産があり、上流のよう人びとと関係をもっていても、娼婦はインドの身分制度のなかでは、差別される階層に属していた。
いくら絶世の美女と謳われようとも、いくら大金を積まれても、彼女のこころにはいつも、満たされない虚しさがあったのではなかろうか。それを埋めようとして、彼女は仏教に帰依したのにちがいない。
当時はブッダを食事に招待することは、とても大事な供養だと考えられていたそうです。その日の遊女アンバパーリーとの約束を守り、ブッダは貴族からの招待を断ったとのこと。差別なんてしません。損得も考えません。
教師
つまり、たよるべきはそれぞれの自己であって、指導者ではない。指導者の言葉にたよらず、あくまで普遍的な法にたよるように自己を律していかなければならない、とブッダはいいたかったのだろう。
自分に何を期待するのか、とアーナンダや修行僧たちに語ったブッダの気持ちと、自分は弟子をひとりももたない、といった親鸞の思いのなかには、重なるものがあるにちがいない。
私には現在師匠とかいう人は居ませんが、もし居たらそうはいっても「あなたが居なくなったらどうしたらいいのでしょう?」と言いたくなる気持ちはわかります。師匠のお世話をする人は、そういった意味でも大変かもしれませんね。
老い
アーナンダよ。わたしはもう老い朽ち、齢をかさね老衰し、人生の旅路を通り過ぎ、老齢に達した。わが齢は八十となった。譬(たと)えば古ぼけた車が革紐の助けによってやっと動いて行くように、恐らくわたしの身体も革紐の助けによってもっているのだ。
(中村元訳「ブッダ最後の旅」六二頁)
このくだりを読むまで、私は晩年のブッダが、みずから老いの実感というものを、ここまではっきり述べているとは、想像もしていなかった。それだけに驚きもしたのだが、同時にブッダという人にますます共感せずにはいられなかった。
ブッダがもたらしたこの言葉は、一見、弱音にも聞こえる。だが、これは弱音ではない、と私は思う。
むしろ、人生の現実をしっかり見定めて、自分の「老い」のすがたを、弟子の前で包み隠さず示している。そのブッダの勇気というものを物語るエピソードなのではあるまいか。
それにしても、最近は、年をとることをマイナスの現象だと受けとめる風潮がもっぱらだ。
「老化」という言葉を避けて、わざわざ「加齢」などという変な言いかたをしたりもする。あるいは、カタカナで「エイジング」といいかえたりもする。
満開の花や瑞々(みずみず)しい若葉はたしかに美しい。けれども、紅葉も、落葉も、そして枯れた枝が灰色の空に手をさしのべているような風景も、それはそれで魅力的ではないだろうか。
晩年のブッダが達した静かな境地を知ると、秋や冬の魅力というものを発見しなおしたい、とつくづく考えずにはいられない。
目指したい境地です。それには、それまでの季節を精一杯生きることですかね…。
この世は美しい:願望?
ブッダの教えの第一歩は「人生は苦である」という、徹底したネガティブ・シンキングからはじまっている。
それでも、最後の旅の終わりには、「この世は美しい。人間のいのちは甘美なものだ」とブッダにつぶやいてほしい、と切に願った人が多かったのではないか。
白か黒か、肯定か否定か、というのではなく、暗闇のなかでこそ、ひと筋の光明が輝いてこころにしみる。その意味で「この世は美しい」という言葉も、後世の付加だといって単純には片づけられないのではないか。
解脱とか涅槃とか老病死苦とかなにかと面白くないネガティブキャンペーン満載な中、救いが欲しいという願いですかね。私個人は仏教美術が好きですが。奈良のお寺も縁あって大まかには巡りました。でもちょっと華やかすぎかも。信仰を大切にしたいものです。
三ヵ月後の死の予言
私の余命はもう残り少ない、弟子であるお前たちを捨てて私は去っていくだろう、とブッダはきっぱりと告げている。
ヴェーサーリーの人びとは、涙ながらにブッダを見送り、ケッサリアに巨大なストゥーパ(32m)を建てたという。
毅然と去っていったのだそうです。いずれ我々に出来るでしょうか…。頑張りましょう。
鍛治工の子チュンダ
ブッダは食中毒がもとで亡くなったのは知られているところです。粥を提供したのは鍛治工の子チュンダでした。
遊女と同じように、下層の者として差別を受けていた鍛治工の子チュンダも、その教えを聞いてブッダに帰依したのだろう。
当時、鍛治工に食事の供養を受けるということは、遊女の家で食事の供養を受けるのと同じくらい驚くべきことだったらしい。インドでは、カーストを異にする人びとは、いっしょに食事をしないのがふつうだからだ。
だが、ブッダは社会で差別されている人たちの供養を喜んで受け、そういう人にも教えを説いている。
チュンダが用意した「きのこ料理」を見てブッダは、自分だけにください、とたのみ、残りを穴に埋めなさい、と命じた。きのこ料理が悪いことを知っていたからです。
当時食うや食わずの世の中で、食事を提供すること自体、とても価値があったようです。
ブッダは一貫してチュンダをかばい、下痢をしながらも入滅の地クシナガラへ向かいます。
奇蹟
奇蹟1:「水が飲みたい」と言ったブッダに、ひどく濁った川の水が、近づくと澄んで透明になった。
奇蹟2:寄進された金色の衣が色あせた。(それほど臨終を迎えるブッダの体が神々しく輝いて見えた。→後世の神格化?)
奇蹟3:沙羅双樹(さらそうじゅ)が時ならぬ花を咲かせ、虚空から曼陀羅華(まんだらげ)や栴檀(せんだん)の粉がブッダの体にふりそそいだ。また虚空で天の楽器が奏でられ合唱が起こった。
これらは、神格化であり、ブッダは修行完成者が尊敬されるのは奇蹟によってではないと否定。
日本でみられる涅槃図は、インドには見られないそうです。
アーナンダ号泣
四苦八苦の一つ「愛別離苦」。いくら学んでも、修行しても、悲しいものは悲しい。
最後の直弟子
スバッダという行者が、亡くなる前にブッダの教えを聞きたいと訪ねてくる。教えを聞いたスバッダは感激して、ブッダに帰依します。
こうしてブッダはクシナガラで八十年の生涯を終えました。
けれども、ブッダは豪華な宮殿のなかでもなければ、大都市のにぎやかな場所でもなく、旅の途中、さびしい寒村で亡くなった。
そういうブッダのすがたに、こころから共感し、あこがれ、尊敬の念を感じずにはいられないのだった。
たぶん、私も(もちろんブッダとは違いますが、)最期は野垂れ死に、かしら。
ここでブッダのお話は一旦終了。
「ブッダの教え」と現代の「仏教」
現代のインドは、ヒンドゥー教とカースト制の国であって、ブッダの教えは見る影もない。
ただ、ヒンドゥー教は懐が深いというか、ブッダを取り入れヴィシュヌ神の九番目の化身としている。それを楯にして、大菩提寺をヒンドゥー教のものと主張し、インドで活動している日本人佐々井師が、抗議している。
佐々井師は辛辣な口調で語る。とくに、話題が日本や日本の仏教界のことになると、おのずと口調きびしくなる。
「日本人は、中層階級より上のインド人とだけつきあって、そこから見えてくるインドをインド人と呼んでいます。けれども、実際には下層の人びとが過半数いるわけで、その最下層の世界から見たインドは全然ちがいます。」
それはそうかと。日本人がお付き合いするインド人とは、ビジネスがらみの場合が大部分ではないでしょうか。IT とか紅茶とかのトップクラスのかたとかかと想像します。
それにしては、日本での佐々井師の知名度は低い。
佐々井師に対しては毀誉褒貶(きよほうへん)もさまざまで、その活動にも賛否両論がある。きわめて高く評価される一方で、批判も多い。インドの仏教界での評価とちがって、日本の仏教界からは、ずいぶんきびしい言葉も聞こえてくる。それは、佐々井師が歯に衣を着せずに発言するためでもあるだろう。
利害損得からすれば、それは新しいなにかを主張してもそれがなにか?ということになるでしょう。
日本でも法然、親鸞は流罪。日蓮宗も迫害と受難。蓮如は批判家や学者に人気がなく、民衆には慕われている。
評価の低さこそが改革者の栄光なのだ、
と五木氏。
隠れ仏教徒
だが、佐々井師が語るインド最下層の人びとが受けている差別の実態は、私の想像をはるかに超えて衝撃的だった。
だが、彼らは現実に今日食べる米がない、学校へ行くお金がない、という悲惨な生活をしている。政府は、ヒンドゥー教徒に対してはさまざまな補助金をだすものの、仏教徒にはださないのだそうだ。それは仏教徒を増やしたくないからだ、と佐々井師は怒りを隠さない。
こうした背景で、インドには、実際には仏教徒でもヒンドゥー教信者だと称する人びとが存在するようです。
マハトマ・ガンジー
だが、佐々井師はガンジーについて、「あの人は、非常に博愛的なことをいいましたが、ヒンドゥー教に関しては、最高の宗教であるというようにいって、カーストを認めていました」と指摘する。
あまり深く学んだことはありませんが、インドの思想や宗教もなかなか複雑そうです。
農民の自殺
佐々井師によれば、インドでも日本と同様に自殺が増えているらしい。しかも、農村地帯の自殺者の増加が目立つという。
農村たちは、暑くても雨がふってもひたすら働く。それほど必死に働いても、自分で食べる米がない。地主は借金を取り立てる。その借金を返済できないので、みずから死を選ぶというのだ。
どこかでも聞くようなお話ですね。
佐々井師も、インドの将来については決して楽観していない。
「世界では中国とインドが大きく躍進するといわれています。でも、私たちは、このカーストの矛盾性を解決しないかぎり、インドの向上と発展はないと思うのです。」
闘争仏教
たしかに、アンベードカル博士の仏教には、平和仏教という言葉はふさわしくない。まさに闘争仏教であり、社会的仏教といえるものだった。社会を変革するために、仏教に改宗し、布教したのだから。
いいかえれば、坐禅を組んだり、瞑想をするような平和的な仏教では、差別を解消するというインドの大改革は進められない、ということだろう。
自分のためである「自利」と他者のためである「利他」の二つを二利という。二利を兼ね備えることが、大乗仏教の理想のすがただ。
佐々井師の生きかたは、さらにそれを推しすすめ、自らのいのちは捨てても他者のいのちを救う、何も見返りは求めない、つまり、自利を捨てた一利のみ、ということになる。
佐々井師は「インドに呼ばれた」方のようですが、険しく厳しい道ですね。
ブッダ再び
ブッダの教えは、決して神秘的でも神がかり的でもない。徹底的に考えぬかれた論理と方法論の結晶である。合理的でプラグマチックな人間の思想だ。
そして同時に、どこかやさしい。苦労して生きた人間ほど、そんなやさしさに惹かれるものなのである。
ブッダの教えは徹底して論理的で現実的とは上座部仏教のアルボムッレ・スマナサーラ長老(←微妙にマイブーム?)のお話でもありました。
そんな中でも、どこか複雑であいまいなところがあり、合理と不合理のあいだを揺れながら進んでいく思想、絶えずスイングしながら進路はブレない論理が、仏教が生きた知性の証とのこと。
これから
では、私の中での仏教とは?
インドに行くこともなさそうで、日本国内でも仏像を眺めるくらいしか接点がない気はします。
ただ、無常と中庸を意識してこれから心を整えて生きていければ良いかとは思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
