
ミトコンドリアのメンテナンス:アンチエイジング -エピソード4-
ミトコンドリアは老化や病気など、生きていく上で避けることのできない問題と深い繋がりがあること、更に言えばそれらの根本にある原因ではないかとされている。
そういわれる所以の一つに、ミトコンドリアの老朽化が関係しているようだ。
ミトコンドリアはミクロだが強力な発電所であり、日々稼働し続ける中でだんだんと老朽化していく。小さな老朽化も、次の世代のミトコンドリアへと受け継がれ、塵も積もれば山となる。もしそのダメージを常時取り除けるのなら、私たちは歳をとらずに済むのかもしれない。しかし徐々に、そして確実に老朽化は進んで行くのが現実だ。
今回はミトコンドリアストーリーの第四弾として、このミトコンドリアの老朽化に注目した。そして運動によるメンテナンスによって、老朽化の進行を緩めることができることをご紹介していこう。
ミトコンドリアを知ることが、アンチエイジングの第一歩だ。
1. 日本人が長寿な理由
今回のリードストーリーとして、日本人が長寿な理由の一端がミトコンドリアにあることをご紹介していこう。
ご存知の通り、我々日本人は長生きである。
2022年のWHO(世界保健機構)の統計によれば、日本人が84.3歳で一位、二位はスイスの83.4歳、三位は韓国の83.3歳、四位はシンガポール&スペインが同率83.2歳と、二位以下に大きく差をつけている。その要因の一つとして、ミトコンドリアDNAに日本人特有の変異があることを、日本人の研究者が1998年に発表した。(参考1)
この論文は当時話題になったようで、ご存知の方もいるかもしれない。
発表された論文によれば、ミトコンドリアDNAに発見された変異があると、病気にかかりにくく、かつ長寿になる可能性が高い。日本人全員にそのような変異がある訳ではないが、他国に比べ圧倒的に変異割合が高く、そのため長寿になる人が多い、ということらしい。
それは何故なのか?詳しくみていこう。
まずミトコンドリアDNAというものは、DNAの保管場所である核ではなく、ミトコンドリア自身が保有しているDNAだ。

この長寿に関係しているミトコンドリアDNAの変異は、どうやらATP(体内共通のエネルギー)を作るたんぱく質装置に関係している。ざっくり説明すると、ミトコンドリアの内側には幾重にも電線が張り巡らされていて、その電線に電気が流れることで、最終的にATPを作り出す。(下図)

日本人特有のミトコンドリアDNAの変異は、この電線の中継ポイントにあたる「呼吸鎖」と呼ばれるたんぱく質の構造物に関係がある。呼吸鎖は有酸素能力を左右するミクロな構造物だ。詳しく知りたい方はエピソード2を読んでもらいたいが、今回の記事では上図のイメージでOKだ。
この電子の中継ポイントとなる呼吸鎖では、一定の割合で電子が規定ルートから漏洩してしまうことが避けられない。そして規定ルートから外れた電子は、いわゆる活性酸素と呼ばれる壊し屋の素材になってしまうのだ。

さて、先ほどご紹介したミトコンドリアDNAは、常にこの活性酸素の攻撃に晒されている。その攻撃によって、呼吸鎖の構造をコードしているDNAにダメージを受けた場合、次に呼吸鎖の部品を作るときに不良品を製造してしまう可能性が高まってしまう。
そうなると電子の漏洩は加速され、活性酸素が生まれやすくなる、という悪循環が発生してしまうのだ。

もちろん体は悪循環をなされるがままに受け入れている訳ではない。ミトコンドリアDNAにダメージを負ったとしても、メンテナンス機能による防御態勢が敷かれているので、多くの場合問題とならないようにはなっている。
しかし、防御態勢もパーフェクトではない。ダメージを受ける頻度が高ければ、小さなほころびがミトコンドリアDNAに定着してしまう。そうなってくると部品の一部に留まらず、ミトコンドリア自身、それどころかミトコンドリアネットワーク全体の老朽化という問題に発展してくる。
ここでミトコンドリアの大切な役割を思い出してほしい。それは、細胞の活動に必須のATPを生み出すことである。筋肉の収縮、免疫機能、お肌の更新、その他体の全ての営みが、ATPを必要としている。
ミトコンドリアの老朽化によってATPの生産が間に合わなくなると、これら種々の営みは当然活動を縮小せざるを得ないであろう。
お気づきかもしれない。そう、これが老化である。
ミトコンドリアのATP産生能力の低下は体の機能低下につながるため、ミトコンドリアは老化と密接に関係しているのだ。
さて、日本人の長寿に話を戻そう。日本人は電子の中継ポイントである呼吸鎖で、電子が漏洩しにくいタイプの変異を持っている人が多い。それによってミトコンドリアが老朽化の悪循環に陥る可能性が小さくなって、長寿につながっているのではないか、というのが研究で発表された内容だ。
ちなみにDNAの変異はほとんどの場合、機能低下につながることが多く、活性酸素による老朽化もその一つである。それなのに、私たち日本人は千載一遇の素晴らしい変異を受け継いだ。
何てラッキーなんだ!!ご先祖様、ありがとうございます。
2. アンチエイジング戦略
ここまでの話から、電子の漏洩を防ぐと活性酸素の発生を抑えることができ、ミトコンドリアDNAが攻撃に晒される頻度が減って、アンチエイジングにつながることをご理解いただけただろう。
日本人の多くが生まれ持ったアンチエイジングな特質を持っている訳であるが、それだけでミトコンドリアの老朽化問題全てが丸く収まるわけではもちろんない。遺伝という確率的な問題ではなく、日々の行動で何とかできる方法はないものか?そう考えた研究者たちが辿り着いたベストオプションは、カロリー制限と運動だ。
なぜこの2つなのか?抗酸化物質が増えるからなのか?肥満や糖尿病になりにくいからなのか?
もちろんそういった理由もあるが、ここでは私の記事らしく、呼吸鎖という構造から問題に迫っていこう。
◆カロリー制限
人に限らず、様々な動物においてカロリーを制限することで寿命が延びることが知られている(参考2)。逆を言えば、過食は寿命を縮めることになる。その興味深い理由として、参考3の筆者は呼吸鎖上の電子の渋滞を挙げている。
例えば過剰にエネルギー摂取している場合をイメージしてみよう。
ミトコンドリアは運ばれてきた過剰な糖質や脂質をそのまま放置することができないため、ATP生産ラインを稼働しなければならなくなる。しかし一方で、最終産物であるATPの需要は増えている訳ではない。そうなると生産ラインは供給過多になり、必然的に電子の流れに渋滞が発生する。

電子はお利口にきちんと列に並んで待つような性格ではない。所構わず動き回るので、渋滞が発生すると規定ラインから外れる輩が沢山出てきて、結果として活性酸素が多く作られてしまう。こうして発生した活性酸素は、先ほどご紹介したようにミトコンドリアDNAにダメージを与えてしまい、DNAの変異を起こしかねない。

日本人のミトコンドリアDNAの変異はポジティブに作用するという稀有な変異であったが、多くの場合、DNAの変異は機能劣化につながることの方が圧倒的に多い。そのため過食による電子の渋滞は、機能劣化に作用する確率が圧倒的だ。
そこでカロリー摂取を適度に(ときにはやや少なく)することで、電子の渋滞を発生させないこと。これがミトコンドリアの劣化を遅らせる、アンチエイジングの一つ目の戦略だ。
◆運動
運動を行うことは、体の種々の機能を動員することである。汗を出す、心拍を早める、筋肉を収縮する、全てにATPが必要だ。ATPの需要が高まれば、ATP生産ラインはフル稼働する。そうすれば電子は渋滞することなくスムーズに流れていく。
電子はスムーズに流れさえすれば、規定ラインを逸れてしまう可能性は低くなるので、無駄に活性酸素を発生させなくて済むようになる。

ただ、運動によってATPの需要が増せば多くの電子が流れるため、電子の漏洩が増えるとする説もある。このあたりはTip①でご紹介しよう。ここでは運動が「電子の渋滞を緩和する」ことに注目してほしい。
現代においてカロリー摂取は過剰なことが多いため、電子の流れは停滞しがちだ。これを運動によって緩和し、活性酸素の発生を抑えることで、ミトコンドリアの劣化を遅らせることが期待できる。これがアンチエイジングの二つ目の戦略だ。
もう少し運動の効果を強調するため、ミトコンドリアの新陳代謝についてもご紹介しておこう。
いかに老朽化したミトコンドリアを取り除き、良質なミトコンドリアを維持し続けられるかは、体に備わっているミトコンドリアのメンテナンスサイクルにも依存している。
下のイメージ図では古い、ダメージのあるミトコンドリアを排して、新しいものと入れ替え、次のサイクルへと進んでいく様子を示している。

運動を行うことでオレンジで示した「増殖」、「融合」が活性化され、健康なミトコンドリアをより多く確保できる。なお、この図の1サイクルはただちに完了するものではなく、時間がかかるものである。半数のミトコンドリアが新しいものに刷新される場合でも、1週間はかかる。(参考5)
よって良質なミトコンドリアネットワークを確立するためには、運動を習慣化して良好な循環を繰り返していきたい。運動は積極的なアンチエイジング戦略だ。
継続は力なり。是非、運動しよう。
3. 理解を深めるTips
以上がこの記事のメインとなる部分であるが、理解を深めてもらうために二つ小ネタとなる話題をご紹介しておこう。
Tips①:運動のパラドックス
運動を行うと酸素消費は20倍以上にもなる。
激しい運動をすれば沢山酸素を消費するし、前述の呼吸鎖を流れる電子は多くなる。そうなると、漏れ出す電子が増えて、活性酸素が増えるのでは?と考えるのは自然だ。研究者もそう考え、「なぜ運動で老化を緩和できるのか?」は悩みの種であり、運動のパラドックスとも呼ばれていた。
しかしその後、研究によって運動時に酸素消費が20倍になったからといって、活性酸素も同様に20倍になる訳ではなく、通常の2-3倍程度で済むことが明らかになっている。(参考6)
活性酸素の産生は確かに増えているものの、それと並行して前述のミトコンドリアの新陳代謝サイクルが活性化される。そのことが長い目で見た場合に、良質なミトコンドリアを維持するための環境として優れているようだ。
ちなみにさんざん活性酸素を悪者扱いしてきたが、ミトコンドリアの品質維持には活性酸素がある程度必要なことも分かっていて、活性酸素が0な状態は、かえってミトコンドリアにとっては不健康にもなり得る。トレーニングによってミトコンドリアが増えるのも、活性酸素が起点となったシグナルの伝達経路が貢献している。
壊し屋の活性酸素も、上手く付き合えれば見方となってくれる、とまとめておこう。ということで、「激しい運動はしない方がいいのでは?」と心配する必要はない。
Tips②:運動は万能なのか?
ただし、何事もやりすぎは禁物だ。
私の記事を読んでくださる方の中には、かなりストイックに日々トレーニングに励まれている方も多いと思われるので、注意喚起もしておこう。
Tips①でご紹介したように、運動によって少なからず活性酸素は増えてくる。この活性酸素はミトコンドリアDNAだけではなく、あらゆる構造に攻撃を仕掛けるため、ミトコンドリア自身へのダメージも無視できない。適度なダメージは前述したメンテナンスサイクルに回収され、良い循環を生み出せる。
しかし過度に激しいトレーニングが続けば、メンテナンスサイクルが追い付かなくなることもあり得るのだ。
実際、VO2maxトレーニングの実施回数を週ごとに変え、ミトコンドリアの機能を検証した研究では、週3回までの頻度では順調に機能が向上していたものの、週5回の実施によって呼吸鎖の機能が著しく低下し、次の週にも回復しきっていないことが観察されている。

もちろんトレーニング歴や年齢などにも左右されるので、週5回の高強度トレーニングがダメだと言っている訳ではない。ポイントは、誰しもミトコンドリアにダメージを蓄積してしまう境界線があるということである。
ミトコンドリアにも、キャパがある。やり過ぎはオーバートレーニングを招く事態にもなりかねないことを、ここでお伝えしておこう。
Tips③:鼠 vs 雀
皆さんは鼠(ネズミ)と雀(スズメ)の寿命をご存知だろうか?
鼠の寿命はおおよそ4年である。一方で雀は35年も生き、長寿である。雀に限らず鳥類は哺乳類に比べると寿命が長い。
ところで、動物の寿命は代謝の速さと関係していると言われ、代謝の速さは体の大きさで決まる。つまり、体の大きさからすれば鼠と雀は同等の寿命と考えられるのに、30年ほどの寿命差があるのだ。(参考6)
その理由も、ミトコンドリアの呼吸鎖に関係がある。
鳥類は哺乳類に比べて呼吸鎖が多いことが知られていて、呼吸鎖が多いことで処理できる電子が増える。それによって電子の流れに渋滞が発生しにくくなり、結果として活性酸素が発生するリスクが減るようだ(参考3)。実際、鼠と雀の活性酸素の漏出を比較した研究では、鼠では酸素消費のうち4%が活性酸素になったのに対して、雀は2%と半分で済んでいる。
たった2%?
いやいや、この差が積み重なると鼠と雀のように寿命が全く異なってくると考えると、大変大きな違いである。ちなみに鳥類の飛ぶための筋肉は、ミトコンドリアが筋線維内の30%を占める(人は10%前後)という驚くべき特徴を持っている。(詳しくはエピソード1)
つまり人の3倍ミトコンドリアを配備していて、かつそれぞれのミトコンドリアの呼吸鎖も多いという、有酸素能力に超特化した素晴らしい筋線維を備えている。
この記事では呼吸鎖の役割として、「電子を流すこと」に注目しているが、電子をたくさん流せる=ATPをたくさん作れる、ということなので、呼吸鎖は有酸素能力にとって要の構造だ。
鳥類は飛ぶ際に90%VO2maxほどの出力を常に保つ必要があるのだが、そのためにミトコンドリアを発達させ、副次効果として寿命が延びたのであれば、何ともお得な進化である。(参考8)
なお鳥類を見習って我々が呼吸鎖を増やす有力な手段は、HIITなどのVO2max系のインターバルトレーニングだ。
キツいが高いアンチエイジング効果が見込める。是非試してみよう。
おわりに
今回の記事ではミトコンドリアの持つ呼吸鎖という構造を中心に、アンチエイジングについて話を展開してきた。もちろんこれは一つの観点に過ぎず、抗酸化能やその他数々の事柄がアンチエイジングに影響していることが研究されている。そういったことを知りたい方も多いかもしれない。
この記事でまだまだ物足りない方は、他の方が書かれた記事を読んでみて欲しい。素晴らしい記事がたくさんある。
また、まだ1から3のストーリーを読まれていない方は、是非そちらにも目を通してもらいたい(下にリンクを張っておく)。
既に読んでくれている方も、前回の記事を投稿してから少し時間が経っているので、是非もう一度読んでもらいたい。この記事が下地となって、理解をより深めていけるはずだ。
最後に、「アンチエイジングのために運動を行おうと思うのだが、何がいい?」というご質問にお答えしておこう。
トレーナーとしての私の答えは、「好きな運動を」だ。筋トレでもいいし、ウォーキングだっていい。仲間と何かのスポーツを行うことも最高だ。
なお個人的な私の答えは、「自転車はいいぞ」だ。関節に優しく、1時間ほどならあっと言う間だ。色んな景色を楽しむこともできる(但し、交通事情には要注意)。さらにスマートトレーナーがあれば…..
あまりに自転車熱を押し付けすぎると嫌がられるので、このあたりでやめておこう。
ミトコンドリアを元気にし、豊かなスポーツライフをお送りください!
今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました。
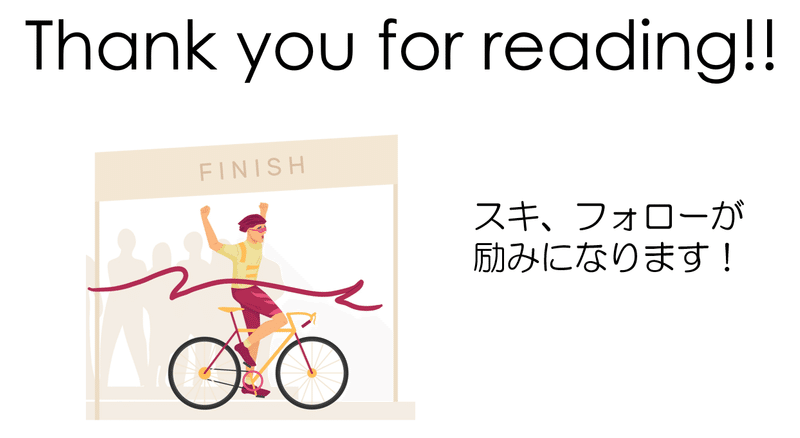
<記事を気に入ってくれた皆様へ>
ページ下にスクロールをしてもらうと「気に入ったらサポート」というものがあります。そちらからご支援いただけると大変光栄です。
参考文献
Tanaka, M. (1998). Mitochondrial genotype associated with longevity. The Lancet, 351(17), 185.
Ló Pez-Lluch, G. (2005). Calorie restriction induces mitochondrial biogenesis and bioenergetic efficiency. PNAS, 103(6).
ミトコンドリアが進化を決めた. ニック・レーン. みすず書房. 2007
Twig, G. (2011). The interplay between mitochondrial dynamics and mitophagy. Antioxidants and Redox Signaling, 14(10), 1939–1951.
Menzies, R. (1971). The turnover of mitochondria in a variety of tissues of young adult and aged rats. Journal of Biological Chemistry, 246(8), 2425–2429.
Herrero, A.(1997). ADP regulation of mitochondrial free radical production is different with complex Ⅰ or complex Ⅱ linked substrates: implications for the exercise paradox and brain hypermetabolism. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 29(3), 241–249.
Flockhart, M.(2021). Excessive exercise training causes mitochondrial functional impairment and decreases glucose tolerance in healthy volunteers. Cell Metabolism, 33(5), 957-970.
Pierce, B. J. (2014). The fat of the matter: how dietary fatty acids can affect exercise performance. Integrative and comparative biology, 54(5), 903–912.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
