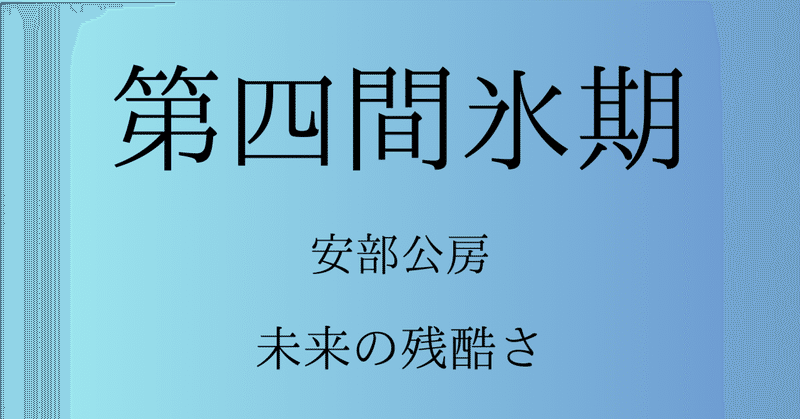
【小説】未来の残酷さ〜『第四間氷期』#2
「第四間氷期」は安部公房による、日本で最初の本格長編SF小説と言われています。間氷期とは、氷河時代のうち、寒冷な氷期と氷期の間にある断続的な温暖期のことです。現代も氷河時代と整理されており、現在のこの時代の間氷期を、本書では<第四>間氷期と呼んでいます。
あらすじ
ソ連が世界で初めて予言機械「モスクワ1号」を作り様々な予言を的中させます。そこで、日本も対抗して、中央計算技術研究所の勝見博士(主人公)が予言機械「KEIGI-1」を完成させました。
しかし、その後、ソ連が「モスクワ2号」を開発し、未来は資本主義が没落し、共産主義の社会になると予想します。これに対し、アメリカが、予言を政治利用するソ連に対して抗議を行います。
このアメリカの抗議を受けて、日本も計画変更を余儀なくされ、政治的な予言ではないもので、予言機械の性能を証明しなければならなくなりました。そこで、研究所はある男の私的な未来の予言をすることを決めます。勝見博士と助手の頼木は、街中で見つけたある男を予言の対象とする候補に決め、尾行を始めました。
しかし、事態はその男が殺害されるという急展開となり予言機械で捜査を行うことになりますが、さらに予想外の出来事が起こっていきます。そして、予言機械から衝撃の人類の未来が語られることになります。
見どころ〜未来は残酷で
この物語は、序盤に殺人事件に巻き込まれたり、主人公の身の回りに奇怪なことが起こるなど、予言機械で想像していたことと一見あまり関係なさそうな話が進んでいき、最初はミステリー小説のようなストーリーとなっています。そして、最終的に予言機械へと全てがつながり、第四間氷期というタイトルの意味するものがわかるとトリハダものの結末になります。
予言機械が示す人類の未来を、希望と捉えるか、絶望と捉えるかは読んだ人次第かもしれませんが、これはわたしたちが想像していない未来であることは断言できます。
あとがきで、作者の安部公房は本作のテーマを現在と未来の断絶としています。
おそらく、残酷な未来、というものがあるのではない。未来は、それが未来だということで、すでに本来的に残酷なのである。その残酷さの責任は、未来にあるのではなく、むしろ断絶を肯んじようとしない現在の側にあるのだろう。(〜中略〜)
この小説は、一つの日常的連続感の死でおわる。だが、それはなんらの納得も、またなんらの解決をも、もたらしはしない。(〜中略〜)
だが、読者に、未来の残酷さとの対決をせまり、苦悩と緊張をよびさまし、内部の対話を誘発することが出来れば、それでこの小説の目的は一応はたされたのだ。
さて、本から目をあげれば、そこにあなたの現実がひろがっている……勝見博士の言葉を借りれば、この世で一番おそろしいものは、もっとも身近なものの中にあらわれる、異常なものの発見らしいのである。
未来の残酷さとは何なのか。もし、自分が勝見博士の立場なら、どのような決断をするのか。読後のモヤモヤ感はトップクラスです。
未来への想像を一変させる小説になること必至の作品です。
関連作品
安部公房『R62号の発明・鉛の卵』(新潮文庫,1974年)
安部公房の短編集。表題になっている「鉛の卵」は、80万年後の未来が舞台で、その時代の人類(未来人)が、炭鉱から冬眠装置を発見し、そこから人間(古代人)が目覚めてしまうお話。未来人が古代人と全く違いすぎて、断絶した未来を感じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
