
暦のお話〜夏至〈乃東枯(ないとうかるる〉
2020年6月21日、本日は二十四節気『夏至』。
七十二候 初候2020年6/21〜25
「乃東枯(ないとうかるる)」
「乃東」というのは「夏枯草(なつかれくさ、かごそう)」、「うつぼ草」の異名で、冬至の頃に芽を出して、夏至の頃に紫色の花穂が黒ずみ、枯れたように見えます。この花穂は、昔から洋の東西を問わず生薬として利用されていたそうです。

二十四節気の『夏至』は、「立夏」と「立秋」のちょうど真ん中です。
一年でもっとも昼が長く夜が短い日。
太陽の通り道が地軸に対して90度、
北半球では正午の太陽がほぼ真上に近いところを通ります。
今日を境に、昼の時間は、
12月の冬至に向けて
徐々に短くなっていきます。

そして、
今日は新月、しかも金冠日蝕が
重なっているという特別な日となりました。
新月は、
太陽と地球と月が
ほぼ一直線に並びます。

太陽─月─地球の順に並び、従って、
地球から月の光(陽光を反射した光)が
見えない日となるのです。
この日から徐々に月は
満月に向かって満ちてゆきます。

ですから、夏至と新月が重なる今日は、
満ちていくものとひいていくものがちょうど交わり転換する時、いくつもの陰陽が交わり転換する日とも取れますね。

ちなみに
日蝕は
新月に起こります。
太陽の黄道と
月の白道が
ちょうど交わり、
太陽の一部(もしくは全部)が
月に隠れる現象が日食です。

直接見ると肉眼には危険なので避けましょうね。

古代より、
太陽は、生命の根源、生命力の象徴とされることが多く、主神として祀られることも多くありました。
黄金や富のシンボルとされることも多いです。


ですから、
夏至の日は、太陽の力が最高潮に達する日として各地で祀られていることが多く、現在でもその風潮を残すところは多いでしょう。

ですが、
この時期、不調を訴える方は少なくありません。
そしてお祭りの雰囲気があるため、飲食や活動を増加させることにより打開しようとする風潮が強いため、対処を間違え、結果長引く不調を味わってしまうというケースを毎年、そしていくつも見かけます。
なんか元気でないなあ
⇩
よし!焼き肉いくか〜
⇩
キンキンに冷えたビールと焼き肉食べ放題!
⇩
翌日、ますますぐったり
これ、当たり前なんです。
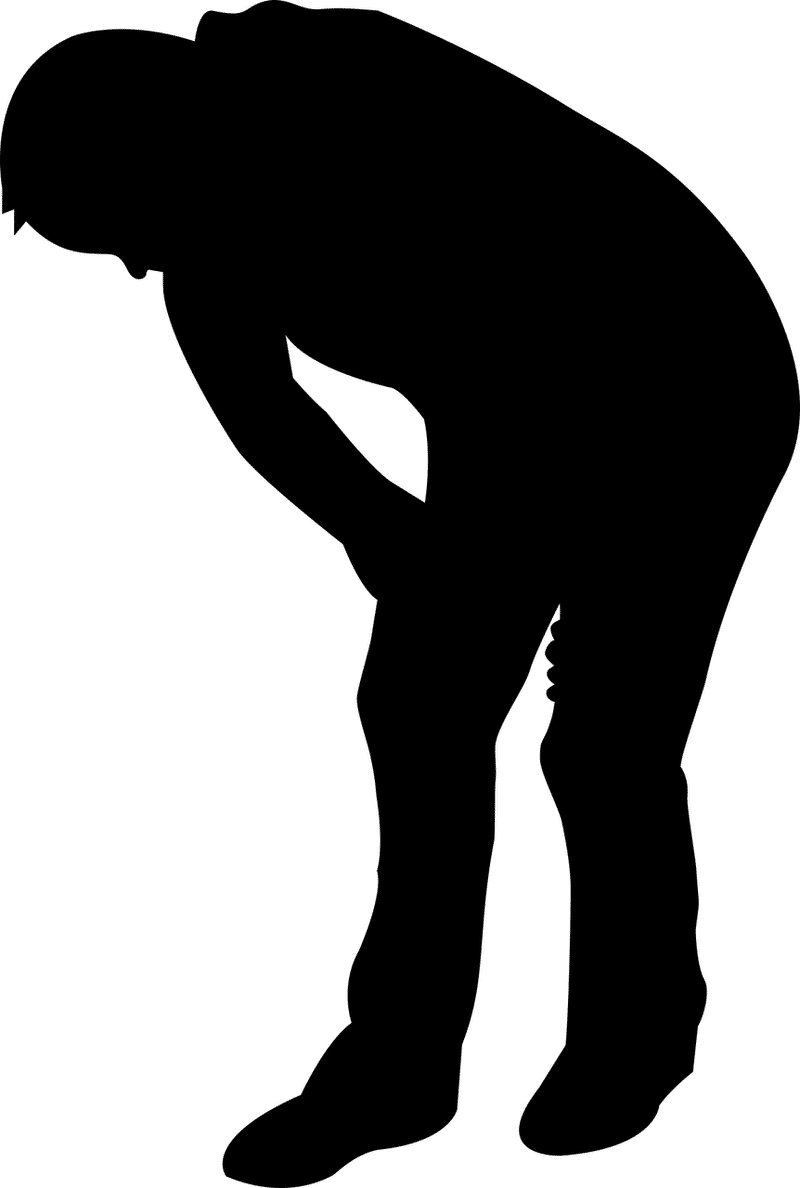
このようにまちがった対処を続け、梅雨が終われば酷暑にさらされ、まさに負の連鎖です。
夏は楽しみも多いですから、そのままなんとなくやり過ごし、冬になってしまうとかなりやっかい、溜めていた『疲労負債』に悩まされることになります。
こうして考えていくと、ある時期突然起こったように思えた不調も、長年の累積であることが多くあります。
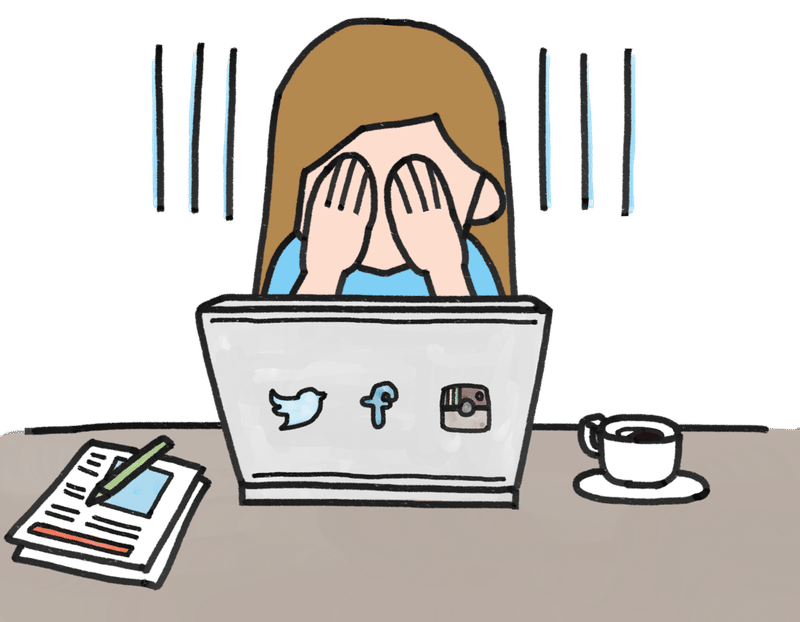
さて、
それでは何故、この対処は間違っているのでしょうか?
そして、適切な処置とは、一体どういったものでしょうか?

この答えは、
アーユルヴェーダから開示されています。
古代インドより続く伝承医療アーユルヴェーダでは、
夏至の前後は最もオージャス(日本でいうところの『精』や『元気の素』)が減る時とされています。
アーユルヴェーダでは、多くの信仰と違い、
・太陽の光は精を衰えさせ
・月の光が精を養生し、回復させる
と捉えられています。
苛烈な日光にさらされるインドならではとも言えるかもしれませんが、
日本の本州で長年生活してきたわたしにも、体感として納得するものがありましたから、あながち風土の由来だけではなさそうです。
この考えを知って、わたしは始めて、これまでの疑問がほどけていくように感じました。
この考えで言うと、
最も太陽の時間が長い夏至は、最も精が落ちる時というのは当たり前です。
また、気候という点からも腑に落ちるものがありました。
各地でそれぞれありますが、
この時期雨季真っ只中という地は広くあります。日本本州もそのひとつですね。
長引く雨、湿度は、肉体を水滞(巡りを落とす)させ、消化力を減退させます。漢方ではこの時期に溜まる悪いものを『水邪』と言い表します。言葉があるくらいですから多くの凡例があったということですね。
ですからやはり『元気の素』である『精』が作られにくいときということになるようです。
この時期の過ごし方としては、

●できる限り、日光が明るくなる6時頃には起床し、遅くても22時頃には眠りにつくように心掛ける。早く起きても睡眠不足は避けたいところ。そうすると早めの就寝が必要になります。夜の時間帯に休息時間を確保することで『月の癒し』を存分に受け取るイメージです。月が出ていなくても癒しは受け取れます。
睡眠時間は時間数だけでなく時間帯も大切です。夜が短く朝起きやすいとも言えるこの時期、早めの就寝を心掛けるのは体力を養う秘訣です。

●身体、特に内臓を冷やさない。冷たいものを取りすぎない。冷えは気づく前に取ることがコツです。

●水分の不足に気をつけるが、冷たい飲み物は要注意。体温・気温のバランスを考慮し、身体に馴染むよう水分を摂ることで巡らせていく。

●運動や労働で肉体を使ったあとは、しっかり休む。後回しにしない。
・食事は消化に良いものを、無理に食べるより、食欲が無ければむしろ食事の量を減らして様子をみるのも秘訣です。
アーユルヴェーダでは、薬として使われるハーブや生薬がいくつもありますが、こういうものを取り入れてみるのも手ですね。
こういうときも頼りになるのはトリファラ。万能選手と言われるトリファラの記事はこちら

また、今は梅のシーズン。
梅も消化力が落ちているときには強い味方。
梅についてはこちらから

夏日があるとはいえ、まだ涼しい日もある今のうちからよく養生して、疲れを残さず夏に挑んでいきましょう。
2020.6/21
『透明な栄養』をテーマに有形無形の造形活動をしています。ホリスティック~全体観~という捉え方を活動の基盤にしています。この捉え方は、いのちの息苦しさが紐解かれたり、改善される可能性をかんじます。noteでは日々の思考研究も兼ねて、この考えをもとに書いたものをシェアしています。
