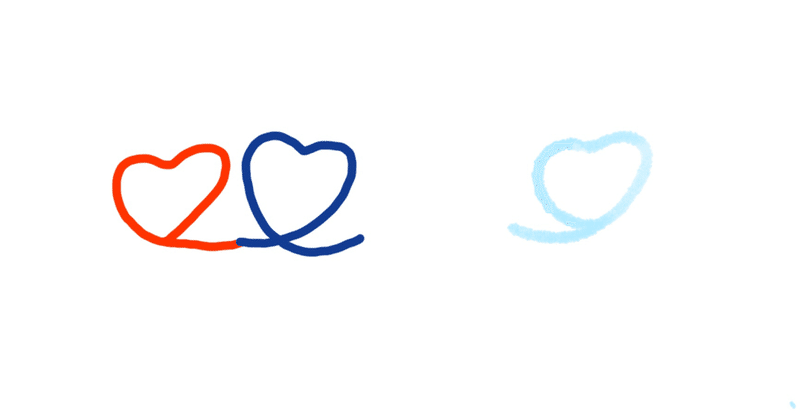
【短編小説】ラスト・デート
ラムネ色のワンピースを着た。クローゼットの中にある夏服の中で、これが一番のお気に入りだ。ひざ下くらいのちょうどいい丈感で、歩くとふわりと揺れる裾がいい感じ。年相応のオシャレができるこの一枚は、特別な日にだけ着ようと決めていたもの。つまり、これを着ているわたしは、今日という日をとても大事にしているということなのだけれど、その乙女心は果たして伝わるのでしょうか。
足元は、クリーム色の履きなれたローヒール。考え事をすると歩くのが速くなる彼といる時は、高いヒールを履かないのが賢い選択なのだ。わたしも別にヒールが好きというわけではないし、むしろローヒールを履けば彼と頭一つ分の身長差ができて、心地良い。そうそう、この身長差は横顔を盗み見るのに、ちょうどいい角度なのだ。左目の涙袋のすぐ横に小さなほくろがあって、それをこっそりとチラ見するのがたまらなく好きなのだけど、わたしの目線に気づくとちょっとだけ眉をしかめたりしちゃって。その表情が、なんともたまらない。困っているような、でも嫌がっていなくて、でもなんだかこう、むず痒そうな。知らなかった表情を知るたびに、胸の奥がギュっとする。我ながら、乙女だ。
マンションのエントランスから、見慣れた影が現れた。今日は普段と比べてキッチリとした服装をしている。いつもは大きめのティーシャツにデニムといったキング・オブ・ラフな服装のくせに、今日は清潔感のある白いシャツに、細身で上品なスキニーなんて履いちゃってる。そのギャップにまたもや胸がどきどきしてしまって、なんだか悔しい。そんな大人っぽい格好、今までしてこなかったじゃないのよ。ああ、好き!
人もまばらな最寄り駅に到着すると、彼はICカードのチャージをするべく券売機へと向かった。わたしはおとなしく、改札前で待つ。ピッと音を立ててすり抜けた先にあるホームには、日差しを避けられる屋根があって安心した。ひとまずこの待ち時間で、彼の肌が日焼けする心配はない。
電車を待つ間、彼は片手でスマホをいじっている。どうやら、これから向かう先へ行くためのルートを調べているらしい。表示されている駅名を覗き見しようとしたら、タイミングよく電車が来てしまい叶わなかった。こちらには見向きもせずにスマホをポケットにしまう。これっぽっちもわたしのペースに合わせてくれなくて、ちょっとだけむっとする。
10分もしないで電車を降りた。土曜日の正午、混雑のピークを迎えている駅の構内を、誰にぶつかることなく進んでいく。こういう変なところだけ器用なのは変わっていない。さっきよりもちょっとだけスピードが速まった両足は、乗り換えの途中にあったコンビニの前でぴたりと止まる。彼はそこで、ハイネケン2缶と焼きプリンをひとつ買った。昔から、両手は空いていないと気が済まないそうで、今も店員さんから受け取ったビニール袋をそのまま無造作にリュックに突っ込んだ。……そうやって何もかもをカバンに詰め込むから、いつも中がぐちゃぐちゃなんだよ!なんて言ったってどうせ聞いてくれないから、もう言ってあげない。そういえば高校生の頃、ぐちゃぐちゃなリュックを勝手に漁って怒られたっけ。ときたま底の方からお菓子とかでてきたりして、あとで内緒で食べたりしたっけ。ちゃんと賞味期限は確認していたし、大丈夫。
乗り換えた電車は、駅構内とはうってかわって乗客が少ない。彼は迷いなく一番後ろの列車に乗り、一番端の座列の、一番端に座った。そのままスマホをいじり始めたのでその画面を今度こそ覗くと、なんともまあ。ここにわたしという存在がいるというのに、違う女とメッセージのやり取りをしている。誰なの、それは。ちょっと、お兄さん。恨めしそうに横顔を見つめると、気まずそうにポリポリと頬をかいて、投げやりにスマホをポケットにしまって眠りだしてしまった。どうやら目的地はまだ先らしい。
ガタンゴトンと規則正しく呼吸をする電車。よく効いた冷房の風が、頬を撫でる。窓から差し込む7月の強い日差しが、容赦なく彼の肌を攻撃していて、インドア派の彼の白い肌を焼いたりしないもんか心配になってくる。彼のポケットに入っていたスマホがブブッと振動した気がしたけれど、浮気男は反応しない。眠ってしまったんだろうか。疲れているのかもしれない。ちゃんと毎日寝ているんだろうか。そういえばどことなく痩せた気がする。夜型の彼のことだから、きっと飲みすぎて二日酔いのまま仕事に行ったりしてるんだろうな。
一時間くらい経っただろうか。もしかしたら、もっと短かったかもしれない。窓から見える街の空がだんだんと広くなり、並ぶ建物の屋根は低く、緑色が増えてきた。とぎれとぎれに現れるトンネルを抜けるたびに、また違う世界に移動している気がして、不思議な感覚がする。ひときわ長いトンネルを抜けようとするその間際、電車がガコンと大きく揺れて、眠っていた彼がもぞもぞと動いた。そのままひとつ大きなあくびをして、ぼんやりと目を開ける。「次は~……」停車駅を告げる電車のアナウンスを聞くと、縮こまった全身に酸素を行き渡らせるかのように伸び、深く深呼吸をした。停車する電車のスピードに合わせてゆっくりと立ち上がる背中は、少し猫背だ。
駅から続くまっすぐな道を、すこしだけ速足で進んでいく。わたしはいつもの通り、ちょっとだけ後ろを歩く。視界の両側には、畑に畑、また畑。たまに現れる一戸建ての住宅に、個人で経営していそうな何かのお店。ビニールハウスでお行儀よく並んでいる緑の野菜に、遠くで聞こえるかすれたセミの鳴き声。都会よりもどことなく優しく、それでもまだ暑い9月の日差しの中、ふたりで速足で前へ進む。
*
高校生の時からずっと追いかけ続けた、大好きな背中が目の前にある。彼が転校してきた高校2年生のあの夏を、今でも思い出す。黒板の前で自己紹介をするその顔は、見るからにぶっきらぼうで、見たまんまいつも不機嫌で、どちらかといえば苦手なタイプだった。なのに、馬鹿な私は怖いもの見たさなのかなんなのか、見事に惚れてしまった。席替えで隣になれたときには、心の中で鼓舞をした。挨拶をするまで1カ月、メアドを聞くまでに2カ月、一緒に帰ろうと誘うのに3カ月もかかった。好きだと伝えたくても伝えられなくて、速足な背中をいつも必死に追いかけた。あまりに速いその足取りに追いつけなくて、思いっきり転んだわたしを見て噴き出す意地悪さ。はじめてみた全力の笑顔が、頭に焼き付いてはなれない。足をひねって動けないわたしを無理やり自転車にのせて、そのまま家まで送ってくれたっけ。彼の自転車の後ろは、たまらなく甘い匂いがした。今も変わらず、彼からはあの頃と同じ匂いがする。
ずっとずっと好きで、同じ大学に行きたくて必死に勉強して、追いかけて追いかけて、社会人になってやっと手が届いた、恋。そこから私と彼は、いわゆる「恋人」ってやつになったようで、名前のつくその関係性にどうしようもなく嬉しくなった。
制服を着ていた彼の後ろを追いかけた青春。よれよれのTシャツをきてバイトに行く彼をベッドの中から見届けた夕方。きなれないリクルートスーツに身を包むシルエットがやけに頼りなかった春。そのどれにも勝る今の彼が持つ大きな広い背中が、やけに眩しい。ちょっとだけ猫背で恰好がつけきれないところにさえも、彼が歩んできた人生が詰まっている気がして、とても尊いもののように感じる。手を伸ばせば触れられそうだけれど、もういっそ抱きついてしまいたいけれど、今日はなんだか気が引けるのでやめておく。
伸ばしかけた手が宙に浮いてしまい、ごまかすように空気を握りしめた。
草地を越え、現れた高い階段。どこかから、心地よい自然の音がする。階段を登り切った彼の横に並ぶと、視界いっぱいに青い海が現れた。
「うわあ」
穏やかに揺れる水面に、キラキラと輝く宝石みたいな地平線。地球が何年もかけて作った鏡がこんなにも尊いなんて、誰が想像しただろう。その感動に声をださずにはいられない。頬をくすぐる湿った潮風が、とても気持ちがいい。ぺろっと舌をだして口の周りをなめると、潮が張り付いていてすでにしょっぱい。
見渡すと、ここにはわたしたちしかいない。こんな絶景を貸し切りだなんて、贅沢すぎる。
目の前にある大海原をどんな顔で見ているかが知りたくて横目で彼をチラ見してみたけれど、風でなびく髪に隠れて表情が見えない。ちょっとだけうつむいたあと、彼は石でできた不安定な階段をつたって砂浜に着地した。サク、サク、と音をたてて、海辺を歩く。さっきよりも歩くスピードは遅い。わたしもその後ろを同じスピードで歩く。時々立ち止まって、海の向こうを見つめる横顔をみていると、身体の中心が絞られるような切なさを感じる。この海を前にして喜んでいるわたしとは大違いだ。
ある程度歩いた後、ちょうどよくあったこれまた脆そうな階段で道に戻った。彼は、まるでそこに階段があることを前から知っていたようにも見える。来た道とは逆側に続く、コンクリートの道をゆっくりと、次第に速く歩く。背中にじんわりと汗をかいていて、シャツが湿っている。
*
それからわたしたちは、いろいろなところをまわった。
まずは、バス停のすぐそばにある駄菓子屋さん。古いせいか小さく唸っているアイスのショーケースの前で、小学校低学年くらいの男の子と女の子がどれを買うか悩んでいる。店内の奥で、だいぶ古ぼけた扇風機で涼んでいたおばあちゃんが「いらっしゃい」と言って笑ってくれた。ほかの商品には目もくれずに彼が頼んだのは、赤いお化粧をしたふわふわのかき氷。すぐに溶けてしまいそうな炎天下の中、シャクシャクと音をたてて急いで食べる。歩きながら食べるなんて、ちょっと行儀悪い。わたしもよくやるけどさ。
歩くこともう間もなく。視界の先に、小さなひまわり畑が見えた。女の子なら憧れちゃうであろう黄色い楽園に、とくに浸る様子もなくズンズンと突き進む。なんてロマンがないんだ。ちょっとは待ってくれてもいいじゃないの。ひまわりへの名残惜しさを残しつつ、駆け足で彼を追いかける。
次なる目的地は、小さな公園。滑り台とブランコと砂場が、出番を待つようにこちらを見つめている。またしても速足で公園へと歩を進め、真っ先に滑り台に登った。成人男性がとるとは思えないあまりに奇抜な行動に、開いた口が塞がらない。子供のように縮こまり、つっかかりながら滑り台をすべる姿に、こらえきれなくなって爆笑してしまう。なにやってんの、間抜け。
次はブランコ。やけに必死になってブランコを漕ぐもんだから、なんだか負けたくなくてわたしも横で漕ぎ始める。久しぶりに乗ったそれは、ジェットコースターよりも勢いがあるように感じて、むきになりすぎるとふっ飛んでしまいそうだ。夢中で漕ぎ続けている中でふと横をみると、頭を抱えたままうつむいている。
「…気持ちわりい」
ぼそっと聞こえた声に、また笑ってしまった。
なにやってんの、かっこ悪。
さすがに砂場に用はないかと思ったら、今度は山をつくりだした。まるで典型的な砂の遊び方で、また笑ってしまう。ほんと、なにやってんの。
ひとしきり遊んで満足したのだろう。近くの水場で手を洗って、わたしたちは公園を出た。
路地を進んで右に曲がったすぐそばに、小さな神社がある。彼は赤い鳥居の前立ち止まって、ひとつお辞儀をした。わたしもそれに合わせて、ペコリ。一歩境内に入ると、まるでここだけ夏を忘れているかのようにひんやりとしている。木々に囲まれ、鳥と虫の生きの根を感じる。酸素が濃くて気持ちがいい。お賽銭をいれてお祈りをする彼の横で、わたしもひとつ願い事を。手を合わせて、神様にたったひとつだけのお願いをする。
神様、いるんでしょ。
どうかお願いね。
神社を出てすぐそばにあるバス停前で立ち止まり、時刻表を指でなぞった。さすがに疲れたのか、「ふう」と息を吐きながら彼がベンチに腰かける。ちょっとだけ距離を空けて、わたしも隣に座る。
じりじりと照り付ける太陽が、遠くの景色をゆらゆらと揺さぶっている。頭の中で響くセミの鳴き声。
わたしたちは、まだこないバスをじっと、じっと、待ち続けた。椅子に手をつく彼の右手に、おそるおそる左の小指だけをくっつけてみた。とくに反応はないけれど、拒否されていないみたいだからそのまま手を絡めてみる。彼の手はいつも冷たいから、ひんやりとして気持ちがいい。
やがてやってきたガラガラのバス。迷わずに、またしても一番後ろの席に座る。エアコンがついているにも関わらず少しだけ開けられた窓からは、生ぬるくて湿った海風が侵入してくる。窓の桟に頬杖をついて、ぼんやりと景色を流し見する瞳は、本当は何を見ているのだろう。彼の顔の右側にだけ日差しがあたっていて、日焼けしないか心配だ。山道のカーブがつくる遠心力に便乗して、その肩にもたれかかる。
*
だいぶ日が暮れて、空がオレンジ色を帯びてきた頃、わたしたちはバスを降りた。あたり一面たんぼだらけだ。カナカナやらツクツクやら、虫たちの歌声が聴こえる。古いガードレールの向こう側で、青い稲穂がサラリと揺れる。わたしと彼は一列になって道を歩く。速くなったかと思えば遅くなる歩調に、彼が意識的にゆっくりと歩いていることがわかる。
わたしは、なんだか苦しい。
歩くたびに、苦しい。
歩きたくない。
このまま歩いてしまうと、身がさけてしまうんじゃないかと、不気味な不安でいっぱいだ。それでも、目の前を歩く大きな背中に導かれるように、この道を進むことが正解であることを信じて歩いていく。わたしの迷いを知ってか知らずか定かではないけれど、彼がときどきちらりと後ろをふりかえる。目線は合わないが、目の前にある大好きな背中を見ると安心できた。
やがて現れた小山の入り口。
決して高くない階段を、ゆっくり、ゆっくり登っていく。
そこにあったのは、お墓だった。
*
PM18時半。都会にある港町。ネオン街にそびえる海は、さっきわたしたちが見た海とは別物みたいだ。駅前に着いた彼は、少し緊張した面持ちである。どうやら、これから誰かに会うらしい。一度だけスマホを確認して何かをうち、すぐにポケットにしまった。身を落ち着かせるためか軽く息を吐き、駅の近くの喫煙所に入っていく。たばこ、やめたんじゃなかったの、と心の中で軽くつっこみをいれて、離れたところから彼を見守る。一服し終えると、神妙な面持ちでまた戻ってきた。
「おまたせ」
19時をまわる少し前、彼女はやってきた。つやっとした肩くらいまである黒髪を揺らし、ノースリーブにデニムと言うシンプルな服装。それは、彼女のスタイルの良さを一層際立てているように見えた。
「いまきたとこ、全然待ってない」
「うそ、絶対早くきて待機してたでしょ」
「あ、ばれた?さすが」
ふたりは自然にほほ笑んで、そのまま自然に手を繋いだ。
「ちょっと歩かない?」
「うん」
海に向かって歩き出した恋人たち。わたしは、歩き出すふたりの邪魔にならないように、そっとうしろを歩く。足音は、たたない。
誰かの残業でつくられる都会の夜景が広がる。生きている人間のぬくもりをネオンから感じたところで、ぬくもりのない自分を実感するだけだから、どうしようもないやるせなさに襲われる。ふたりの他にもカップルは何組かいたけれど、そのどれもがそれぞれの世界にいるみたいで、ここにひとりでいるのはわたしだけのようだ。
たわいもない話を繰り返し、肩を寄せてゆっくりと歩くふたり。
やがて、彼が足を止めた。
「あのさ」
わたしが見たことのない表情をしている。彼女の手をとって、ひとつ深呼吸。ここから先に訪れるであろうすべての出来事を、本当は、わたしは、見たくもないし聞きたくもない。だけど、わたしが今ここにいるのは、ここにきたのは。この時を迎えるためなのだ。
「俺と、結婚してください」
その瞬間、欲しいものが手に入った時の感動を全面に出したように彼女の顔が綻び、そのまま彼の胸に飛び込んで泣き出した。広い背中にまわる細い腕。その頭を撫でるたくましい手。ふたりのシルエットに重なるようにして、いつかの「わたしたち」がダブって見えた気がしたけれど、すぐに消えてなくなった。
「待たせてごめん」
「うん」
「結婚しよう」
*
その石の前で座った彼は、リュックからハイネケンをとりだした。プシュッと開けた途端あふれてくる泡にちょっとだけ慌てて、ゆっくりと「わたし」の前に置いた。続けて焼きプリンの蓋をめくり、コンビニで貰ったプラスチックのスプーンも開封して、プリンの上に供える。わたしが世界で一番に好きなお酒と、わたしが世界で一番に好きな食べ物。
「かんぱい」
カツンと軽くわたしの缶にぶつけて、もうだいぶぬるいはずのそれをぐびっと飲む。昔から一口が多い彼のことだ、今だってきっとたくさん飲んだんだろう。案の定、んっ、とむせそうになり、無造作に口を腕で拭った。
「もう、5年だな」
聞こえる虫たちの大合唱にかき消されることなく、彼の声が頭に入ってくる。
「お前がいなくなってからさ、俺、ばかみたいだったよ。毎日、死んだみたいに生きててさ、死んじゃいたいくらいでさ、死んだらお前に会えるのかなって何度も思った」
まるでなんてことのないように笑いながら、供えたはずのプリンをひとくち食べる。ちょっと、それわたしの。
「それでもなんとかやってきたんだ。仕事も落ち着いたし、ちゃんと大人になったよ。あれからもう5年だろ。お前も、もういい歳なんだから、酒なんて飲みすぎるなよ」
そう言ったくせに、彼自身がまたお酒を飲む。
「出会った頃は高校生で…あの頃の俺らってなんでもできる気がしてたよな。俺は…なんかいつもお前の前ではかっこわるくて、情けなかったな。なんもできなくて、だっせーのなんのって」
指で飲み口をそっとなぞる。
「お前が俺のことを、必死に追いかけてくるのが、可愛くて仕方なかったんだよ。いつも速く歩いて、ごめん」
石をまっすぐに、見て話す。
「逃げてたんだ、自分から。追いかけられると怖くなって、逃げて楽になりたかったんだ。いつも真っ直ぐなお前と向き合うのが怖かったんだ、だから置いていくように、速足になって。しょうもない自分を、見たくなかったんだ。そんな、そんなくだらないプライドで俺は…」
心なしか、鼻声だ。
「もう、だいぶまえからずっと好きだったんだよ、…お前が転んだあの日よりもずっと前から、好きだったんだ。付き合っても、一度も言えなかったけど…ちゃんと、好きだったんだ」
さあっ…と流れる風。草木を揺らす音はきこえるのに、その風を身体で感じることができない。
あったはずの体感が、ない。手のひらが、かすかに透けている。彼が話すたびに頭に流れてくる、確かにあったわたしたちの過去。
「…ごめん」
静かな声で呟いて、うつむく愛しい人。
今日巡った場所はすべて、わたしが事故で死んだあの日に訪れたところだ。彼はあの日を再現していたんだ。あの海も、あのかき氷も、あの公園も、神社も、なにもかも。彼は、あの日をなぞっていたんだ。
「…ごめん、守れなくてごめん」
ハイネケンの缶が、彼からこぼれる水滴によってポンッと音を立てる。にぎりすぎて、ひしゃげる音がする。わたしもつられて泣くけれど、その涙が地面に染みをつくることはない。わたしが存在していないことの、何よりの証拠だ。
「…ごめん、ごめんな、だけど、おれ」
震える背中にそっと近づく。
「もう…前に進みたいんだ」
後ろからその背中に手をまわしても、大好きな温もりが伝わってこなくて、愛しい人の熱を感じ取れない事実にただ悲しくて堪らなくなる。それでもなんとか彼を受け止めたくて、せめてもの思いで輪郭をなぞるように腕をまわす。
どうか、どうか。神様。
わたしが神社で必死に祈ったことはただひとつ。
「彼の記憶からわたしが消えますように」
あの日以来毎日泣いて、濃度の高い絶望でいっぱいの彼の記憶から、すっかりさっぱりわたしを消してください。彼が前に進む選択をこの先もできるように、どうか。わたしは、彼の後ろでしかないから、もう後ろにしかいれないから。
一際大きな風が吹いたその一瞬、甘い匂いがした。それが彼のものなのか、そばでゆれている彼岸花のものなのかはわからない。ただ、わたしが大好きだった匂いを、終わりを迎えるこの時に感じ取れたことが嬉しい。
むせび泣き震える背中。すっかり夕日に染まったわたしのお墓の前で、ふたりで泣いた。
5年前の今日、この時間にわたしは事故で死んだ。
海、駄菓子屋、ひまわり畑、公園、神社。楽しくて楽しくて、このまま時がとまればいいだなんて思っていた矢先に、突っ込んできた居眠り運転のトラックに轢かれて、わたしはこの世を去ったのだ。
その5年後。
幸せを選ぼうとして、今やっと前へ歩み出す彼と、
最後にもう一度あの日をなぞるために。
今、会いに来たのだ。
*
もう一度強く、強く抱きしめ合うふたり。見つめあって、柔らかく笑う彼。わたしは自分の身体が消えていくのを感じながら、もう何粒目かわからない涙を流す。幸せでたまらないのに、どうしてだか同じくらい悲しくて、全身がくまなく痛い。行き場のない気持ちをどこかにぶつけたくて、後ろ手でラムネ色のワンピースをギュッと握った。
またゆっくりと歩き出す夫婦を、立ち止まったまま見送る。もう、追いかけない。その背中を追いかけることは、もう2度とない。ただ彼が、選んだ幸せに向けて前へ進んでいくのを見届ける。
「彼の記憶からわたしを消してください」
最後のデートで願ったことが、叶おうとしている。
事故で死んだあの日、わたしの前で泣く彼をみて、今日と同じ願いをした自分がいる。死んだその直後、全く同じことを願ったのだ。
今の今までそれが叶わなかったのは、99%の願いに抗うように強く立っていた、心の真ん中にいる1%の本心のせいなのだろう。彼が泣くたびに、彼が後ろを向くたびに、今は亡き自分の存在を認めてくれている気がしてしまって、消えなくてもいいんだって勘違いしてしまった。悲しむ彼を見ることで、わたしはどこか喜んでしまっていたのかもしれない。わたしを忘れないでと、彼の記憶にすがろうとしていたんだ。彼の本当の幸せを心から、願えていなかった。
今だって本当は、1%が叫んでいる。どうしようもなく、大きな声で叫んでいる。そばに行きたいと、瞳に映りたいと、その背中に抱き着いてしまいたいと、隠しきれない思いと消えてくれない思い出が、消えようとしているわたしのなかで確かに動いている。歩くのが速くなるたびに、わたしのことを思い出してくれているのがわかってしまって、その癖がどうしようもなく愛おしくてたまらなかった。
彼の記憶にいられることが、嬉しくて、嬉しくて、嬉しくて。
でも、同じくらいに、悲しかった。
悲しくて、たまらなかったんだ。
やっと、消えれる。
わたしが消えれば、この頼りなくて悲しい1%も、消えて無くなる。願いが叶った瞬間、彼がわたしを思い出して泣くことも、もうなくなるだろう。
最後のデートは、とても楽しかった。わたしの99%の願いを叶えるために、神様が与えてくれた2回目の「あの日」。彼と一緒に手を合わせた神社で祈りながらも、この世に神様がいることをわたしはとうに知っていた。わたしを今日形作ってくれたのは、神様なのだ。彼の記憶をかき集めてわたしを形にしてくれたのは、神様なのだ。最後に彼とデートをすることと引き換えに、わたしの魂は完全に消えることになっている。生まれ変わることは、2度とないだろう。来世で彼と会うこともできなくなった。わたしの輪廻転生は、ここで打ち切られる。それが約束だ。
でも、それでいい。それでいいんだ。
やっと、心の底から彼の幸せだけを願えた。彼の未来だけを願えた。最後に、彼の恋人らしいことができた。
この世からわたしの魂が消えれば、わたしの中にあった1%の本心も、消えてなくなる。
願いが叶うのは、もうすぐだ。
大好きだった背中。
いつだって、そこにあった背中。
消えるその瞬間に見ていられるものが選べるのなら、わたしは最後まであなたを見ていたい。
どうか最後まで、その背中を見ていたい。
わたしの恋人だった彼。
愛しい人。大好きなあなた。
どうか。どうか。
もう2度と、振り返らないで。
「結婚 」
おめでとう。
いつも応援ありがとうございます。
