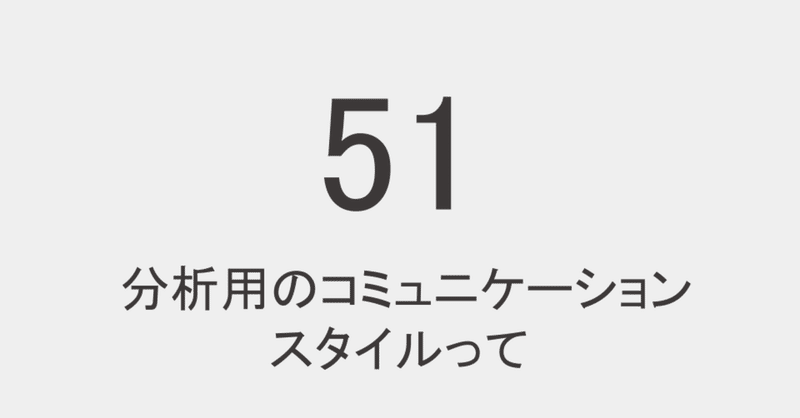
翻訳としてのデータ分析#51 分析用のコミュニケーションスタイルって
原文抜粋 : 翻訳スタイルって
もともと自分が持っているスタイルをそれに押しつけるんじゃなくて、書いているうちにその文章そのもののスタイルがだんだんと立ち上がってくるみたいなふうになるのが理想だと思うんですよ。
『ぼくは翻訳についてこう考えています -柴田元幸の意見100-』より
データ分析に置き換えて考える
「分析を進めるための、自分のコミュニケーションスタイルを身につけておくと便利」と後輩にたまに言っていた。
分析をする上では、関係者とコミュニーションをとり、情報を集める必要がある。その情報収集速度が、仕事の速さを左右する。
人それぞれに、情報を円滑に収集するためのコミュニケーションスタイルは異なる。対面が得意な人もいれば、テキストが得意な人もいる。口数少なく一目置かれる人もいれば、先に情報を発信する人もいる。全てを仕組み化するタイプもいれば、最低限のフォーマットだけ用意するタイプもいる。
もちろん相手あってのことだから、1つのスタイルさえあれば万事解決というわけでもない。ただ、「基本こうやってコミュニケーションを取れば、得たい情報を早急に得られる」というスタイルを確立しておくと、分析を進めやすくなる。
どうすればそのスタイルを確立できるか、について言うと、後進的な根性論だが「溢れるくらいの仕事を受け持つ」のが手っ取り早いと思っている。
そうした状況に置かれると、自分のキャラクターを活かして、最速で情報収集するための、コミュニケーションスタイルが磨かれやすい。
もっとスマートな方法を提示できればいいのだけど、対人術は、実践の中でしか磨かれないというのが今のところの僕の結論だ。だから、その機会を増やすといいと考えている。
量が質に転化する、とよく言う。データ分析という仕事の場合、作業工程と同等に、コミュニケーション部分においても、その効能があると思っている。
たくさんトライして、いろんな人に迷惑をかけたり褒められたりして、分析のコミュニケーションスタイルというのは、段々立ち上がってくるものだと思う。
かくいう自分も会社の中では幅広く立ち回る方だと思うけど、SNSを活用したり社外の人との交流が多いわけではない。だから、もっと洗練されたコミュニケーションスタイルの磨き方や、そもそも全く別のコミュニケーションの在り方の概念があるかもしれない。
が、とりあえずの考えとして記しておく。
サポートされた者たちから受け継いだものはさらに『先』に進めなくてはならない!!
