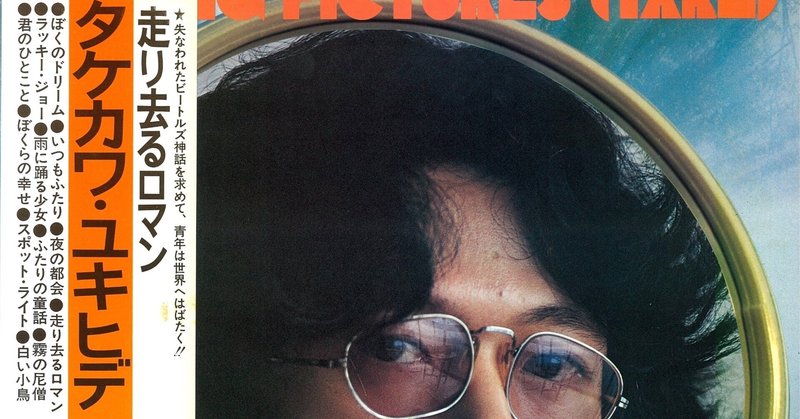
『走り去るロマン』に賭けた夢(ロマン)連載04 <第2章>高校生編 1968~71年 ①
<“浦高” 入学>
1968年4月、タケカワは埼玉県下でも屈指の進学校、埼玉県立浦和高等学校に入学する。“浦高” は男子校で、校訓は “尚文昌武”(しょうぶんしょうぶ)。「文を尚(たっと)び 武を昌(さか)んにす」、すなわち「文武両道」の精神が同校の理念である。毎年春に新入生歓迎マラソン(10km)、11月には隣県の茨城県古河市までの“強歩大会”という名称のマラソン大会(50km)という過酷な恒例行事もありながら、生徒の自主性を尊重した自由な校風の高校である。タケカワはそんな「自由な校風」の中、時には校内で、そして時には校外へ逸脱して音楽活動を展開することとなる。
<部活はいずれも短期間で退部>
中学以来の親友、小山條二も浦高に入学し、タケカワと同じクラスとなる。タケカワは中学まで続けてきた野球は入部せず、小山と共に放送部に入部する。昼休みの校内放送でにビートルズの曲を流し、二人でギャグの応酬のような原稿を作って放送していたという。タケカワは他のクラスメイトに放送の反応を聞き出そうとするが、「そんなのやってた?」との返事。ひょっとしてボリュームが小さかったのでは、と次の放送でボリュームを倍にしてみたら、放送室に3年生が怒鳴り込んできた。「こっちは昼休みも勉強しているんだ!」。それがきっかけで放送部を辞めさせられる。
それからしばらく経ち、1年生の後半には同級生の坂下辰夫(元・埼玉県ラグビーフットボール協会理事長)に勧誘されて、再び小山と共にラグビー部に入部。ラグビーはまったく初心者だったため、ポジションはバックスと聞かされていた。しかし、中学まで野球部で鍛えられた足の速さを買われて、フォワード担当の先輩に「オレがバックスに行くから、お前達はフォワードをやってくれ」と言われ。そのため連日スクラムとタックルの練習ばかりすることになる。その後、バンドで新しいアルバイト先が見つかったため、小山を残して3か月で退部。現在のタケカワはラグビー部時代を振り返り、「いい先輩ばっかりだったので辞めるのが申し訳なかった」と話す。
<サラリーマンコンパの箱バンに>
音楽活動に話を戻そう。中学時代に結成したコピーバンドのメンバーは、それぞれが別の高校に進学していた。中学の卒業謝恩会でのあの感激が忘れられず、それでも人前で演奏する機会や場所もなく、毎週日曜にメンバー宅の倉庫の部屋に集まって練習をするだけのバンド活動を続けていた。
当時の彼らは秋葉原の朝日無線電機(現・LAOX)にある、アサヒ楽器店へ頻繁に出入りしていた。高校生バンドということもあり、店員にも顔を覚えられるようになった2学期のある日、店員から知り合いのミュージシャンを紹介される。彼から告げられたのは、「俺、今度グループサウンズでデビューすることになったんだ。だから今まで俺らが演奏してた店を辞めるんだけど、代わりに新しいバンドを探しているんだ。どう?」という、アルバイトの誘い。タケカワ達は見学を兼ねて、そのミュージシャンに店へ連れて行ってもらうことになった。
店は地元の浦和から電車で乗り継ぎしなければ行けないような、葛飾区金町にあるサラリーマンコンパ(パブ)。店の中には酒瓶が並んだカウンターがあり、どう見ても “酒場” だった。初めて見る “夜の店” にたじろぐタケカワ達だったが、小さくて粗末ながらも店の端にあるステージを見るやいなや、「このステージで演奏したい!」となり、サラコンのマスターも「僕は、君たちのこと19歳と聞いてるから」と年齢を黙認して採用が決まった。いわゆる“箱バン”(店の専属バンド)である。
条件は土・日曜の週2日出勤で、演奏は一晩4回。1回30分の演奏で、演奏と演奏の間に30分の休憩あり。そしてギャラはバンド単位で日給7,000円と提示された。週2回で4週出勤すればバンド単位で月56,000円! メンバーたちはその金額に興奮し、そのギャラをあてにしてアサヒ楽器店で新しいアンプを2台購入してしまった。
<父と子>
そして迎えたサラコン初出勤の土曜。タケカワは派手なシャツとカラージーンズを着込んで、家を出発する際に「今晩は演奏だから帰り遅くなるからね!」と大声で告げて家を出た。駅に行く途中、肝心のエレキベースをうっかり忘れたのに気付いて家に戻ると、さっき家を出た時は布団で寝ていたはずの父・寛海が居間に座っている。ベースを持っていこうとすると「座れ!」と止められた。
「お前、さっき演奏で遅くなるって言ったな? 演奏っていうことは店なのか? 遅くまで演奏する店ってことは、酒を出す店じゃないのか? ということは、未成年は入っちゃいけないんじゃないのか! 親として、未成年をそんな店に出す訳にはいかないな…」
父はすべてお見通し。矢継ぎ早に詰問する父に圧倒されたタケカワだが、「僕らはただ、演奏したいだけなんで…。急いでいるからとにかく行くよ!」と逃げるようにバイトに向かった。初日は100人入るような店内に10~15人程度しか客がおらず、閑古鳥が鳴いていたが、ガチガチに緊張しながらも演奏を終え、浦和の自宅に帰宅した頃には深夜になっていた。食卓で遅い夕食を取るタケカワの隣りに、まだ起きていた寛海が無言で座る。何か叱られるのでは、とタケカワは不安だったが、寛海は説教がましいことは一切話さず、ずっと無言のままだった。
それ以降も、タケカワが夜の店のバイトで深夜遅くに帰宅するときは、いつも父が自分の書斎で寝ずに起きていたという。寛海は69年2月に55歳で東京放送(TBS)を定年退職し、自身のライフワークであるクラシック音楽、とりわけベートーベンの研究をまとめた著作を多数発表することになるが、夜遅い息子の帰りを待ちながら執筆作業に励んでいたという。
タケカワは父の逝去後に、高校時代の夜のバイトを振り返ってこう語っている。
「父はその頃に僕の事が心配で、僕が帰宅するまで仕事をしていたのだった。そのせいで、仕事が夜型になってしまったのだと僕は父に言われたのである。夜中に帰ってきて、家の戸をそっと開けると必ず、父の書斎に灯がともっているのを見て、うっとおしいけれど、それでいて、安堵するような、複雑な気持ちに駆られたのを覚えている。」
<ビートルズのコピーバンドなのに…?>
金町のサラリーマンコンパや、後述する西川口のゴーゴーホールでは、自分たちのレパートリーであるビートルズの楽曲を演奏してもまったくウケず、終いには店の客がパタッと踊るのを止めてしまったという。ノリのいい「ユー・キャント・ドゥ・ザット」(64年のアルバム『ハード・デイズ・ナイト』収録曲)あたりはまだ踊ってくれたそうだが、その他の曲となるとさっぱり。68年当時はまだまだビートルズも活動中だったが、夜の店の客層にはどうも人気がなかった、とタケカワは述懐している。
「この状況はまずい」と考えたバンドはビートルズ以外の楽曲から選曲し、カバーすることになる。金町のサラコンのマスターから言われて演奏したのは、R&Bグループのテンプテーションズがビルボード1位を飾った大ヒット「マイ・ガール」(1964)と、バブルガムポップ(ティーン向けのポップミュージックのジャンル)の代表曲と評される、1910フルーツガム・カンパニー「サイモン・セッズ」(1968)の2曲。ジャンルが全く異なるこの2曲が、彼らのバンドにとって初めての、ビートルズ以外のライブレパートリーとなる。この2曲は評判が良く、店の客も踊ってくれたが、ビートルズナンバーに代わるとまたもや踊らなくなってしまったという。
さらに翌年にゴーゴーホール等で働く頃には、メンバー達もそれぞれが腕を上げて、ラジオから流れる海外ヒット曲をカバーできるようになる。彼らのレパートリーとしては、クリーム「ホワイト・ルーム」(1968)、ジミ・ヘンドリックス「紫のけむり」(1967)、ドアーズ「タッチ・ミー」(1968)、ヴァニラ・ファッジ「キープ・ミー・ハンギン・オン」(1967)など。とにかく客が踊る曲をヤケクソで取り入れてレパートリーを増やし、最終的にはビートルズの楽曲の数は半分以下になったという。
なお余談だが、タケカワが還暦を迎えた2012年10月のバースデーライブで、ゴダイゴの盟友である浅野孝已とのコンビでこれらの楽曲をカバーしたことがある。そのライブのMCで、浅野がこれらの曲について、「ビートルズの初期は踊れる曲だったけど、だんだんと“聴かせる曲”に変化していったからね」、「エム(浅野が68年より在籍していたバンド)でも『サイモン・セッズ』を演ったことがある。ディスコティークやサパークラブなど、店のスタイルに合わせて演奏できないと、プロとしてやってけないからね。」とコメントしていたという。いみじくも、当時すでにザ・ゴールデン・カップスのメンバーとしてデビューしていた、ミッキー吉野もカップス時代を振り返って「お客さんが踊れない曲はダメだった。スローでもアップテンポでも、お客さんがグルーヴして踊れる音楽をやらないと仕事がもらえない」と、同じような経験を語っていた。
<英語詞ポップス作曲に開眼>
高校2年の4月、英語の授業中にちょっとした “閃き” が起きる。教師の話を聞いていたら、いきなり英語のセンテンスとそれに合うメロディのフレーズを思い付き、その後のメロディが次々と頭に浮かんできた。このメロディを逃してなるものか!とばかりに、五線紙がない代わりに授業ノートの余白部分に自分で5本の線を引き、メロディの音符とその歌詞を書き綴った。授業は上の空で、夢中でスコアを書いていたら英語の授業どころか、次の国語の授業も終わろうとしていることにやっと気付いたという。その初めての曲が「I’LL MAKE YOU SAY YOU LOVE ME, TOO」。いかにも高校英語の文法で学習する、使役動詞「make+目的語+原形不定詞」パターンの構文のタイトルである。現在のタケカワに言わせれば「他愛のないラブソング」だが、中学2年の時と違い、ちゃんとしたポップス調の曲を、ちゃんと韻を踏んだ英語詞も含めて自分の力で書き上げた、初めての曲であり、それは彼にとって大きな自信となった。
2018年に開催されたタケカワのファンミーティングで、高校2年生当時の世界史の授業ノートが展示されたことがある。そこには “エリュトラ海案内記” “プルタルコスの英雄伝” といった授業内容と一緒に、落書きの様に無造作に書き込まれた「PRETTY LITTLE BIRD」(「PRETTY WHITE BIRD」の原曲)と「TELL ME WHY」のスコアが書き込まれていた。楽器を使わず、頭の中に浮かんだメロディをすぐにメモ書きで落とし込むタケカワの作曲スタイルと同時に、"why" "die" "lie" "sigh" といった具合に詞の母音韻を踏むことに徹底的にこだわった当時の作詞法が如実に見て取れる。
※上のプレビューにある「TELL ME WHY」は1995年2月26日、彩の国さいたま芸術劇場でのライブ音源。iTunesでダウンロード購入可(日本国内でのApple Musicでは表示・再生できないため、ブラウザでプレビュー再生推奨)。
CD『アンコール・ベスト 1995-2』でも購入可。
※本文中に登場する人物は、すべて敬称略にて表記しております。ご了承ください
※無断転載禁止
前後のエピソードはコチラから!
