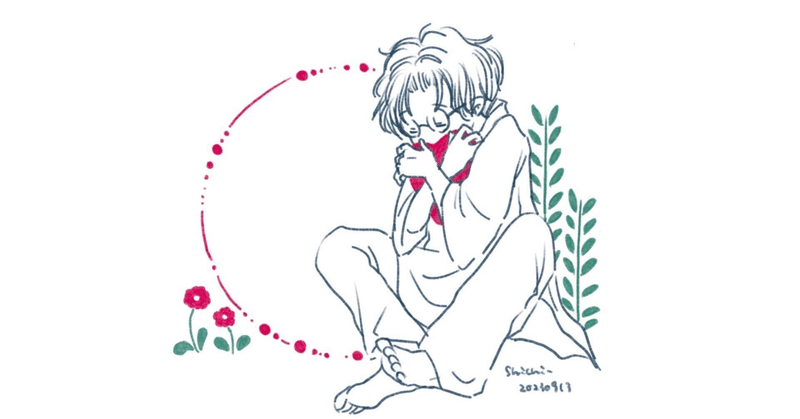
「母性」と「父性」必要な時期が違う。こどもに今「必要な要素」はどっちだろう?
共依存の実態や、自分の「親子関係」からくる
こころの仕組みをまだまだ理解していなかった頃。
わたしは自分の娘や息子に「自分を重ねる」ということができていませんでした。そういう風にみていなかった、というか。「自分の方」に意識が向かずに、ずっと表面的な「相手のこと」ばかりみていたのです。
言い換えると、
相手の反応に対して、「自分の発している言動を振り返る」ということに意識が向かないということ。
過去の自分は「相手の表面的な言動」に一喜一憂してばかりでした。
そして、
今よりもっと精神的に未熟であったことはもちろん、
子育てに関して「気負いすぎる」ところがあり。自分の育児に「客観性」を持ち合わせていませんでした。誰にも「邪魔されたくない」というような感じがありました。
「わたしは、『親みたいな子育て(選択)』はしない」
と、
そんな意思を「前提」として強く持っていたということが
ひとつ大きくあります。
だからこそ、
結婚当時、親に頼らず、
わたしに子育てを任せてくれる(元)夫との家庭はある意味「円満」でした。
わたし自身、小さい子の相手は、そもそも得意で。
保育園の3歳児未満のクラスで数年働いていた経験もあるし、託児所でも数カ所バイトしていたこともあったので当時のわたしにとって「乳幼児との関わり」は「やりたいこと」で「得意なこと」でした。ましてや「我が子」となれば、その気持ちはとても強いものでした。
乳幼児期のこどもの「欲求」というのは、とてもわかりやすいのです。原始的であり、「与える側」というのは比較的「母性」を活かして「愛情を注ぐ」割合が多い。欲しがる乳幼児にとっても、生きるために「純粋にそれらを求める」と。
なので、与える側が
「ようこそ、この世界に!」
という気持ちで迎えている場合、乳幼児の言動は「愛おしいもの」として感じられるというか。わたしにとっては、そうでしかありませんでした。
そういう「愛着を形成する大事な時期」に
わたしは「自分に任せてくれる夫」「経済的な安心のもと子を育てられる環境(夫がサラリーマンだった)」があったことで、自分が「関わりたいように、子育てができた」という状況でした。
元夫には本当に感謝していることが沢山あります。
私の親子問題での紆余曲折のなかで、
こどもたちには保育園を何度も転園させてしまいましたが、どこの保育園でも「愛着がちゃんと出来上がっているので大丈夫です」と言われ。自分の自覚している「不安要素」を先生方に伝えていましたが、先生からは「実際に不安なお子さんは何人もいますけど、Maiさんちのお子さんは大丈夫です。」と言われていて。そのことが、間接的に自分の子育てに対する「安心」として、当時「自分に不安でしかなかった」わたしにとって、わたしの微かな希望になっていました。
「子供達の社会との接点」は、園くらいで。
自分がいかに「子育てへの興味関心」が高かったとしても、実際の「こどもとの関係性」というのは、自分だけではわからず。
いくら「頑張っていた」としても、ただの「親の自己満足」の場合もあるから。そうやって「保育のプロ」たちに、「大丈夫です」と言われてきたことは、わたしの不安を取り除くための「唯一の指針」にもなっていました。
その頃から数年を経てわたしが自ら「児童相談所」にお世話になったときも。
当時は本当にこころが疲弊していて。「不安と焦り」はピークになっている状態でしたが、そこでも「こどもに関するプロ」の方々、長年「問題を抱えている母子」をみてきている所長と「面談」をさせていただき。
「お子さんは、お母さんと愛着がしっかりあるので大丈夫です」
「だから、どうして。。。と思うところはありますが、今お母さんにとって必要なことなのであれば、協力させていただきます」と。
そんな風に言っていただけて。
自分の「偏見を壊す」大きな一歩を踏み出す勇気を持ちました。
「今は、目の前にいる『こどもの事に関するプロ』の人たちを信じて、こどもたちをお願いしよう」「わたしは、わたしでプロに関わってもらっているのだから、『自分の問題』をなんとかしよう」と。
こどもたちを信じて。
他人を信じて。
自分の意思で、こどもたちを「児童擁護施設」に託すことに決めました。苦渋の選択でしたが、わたしにとって「(今の自分では)もう無理」だったので。
人に、頼ることができなかったわたしにとっては、あれが人生で最大の「選択」だったと思います。最大に「辛い選択」でした。
3年半。今振り返ると「あっという間」でしたけど
その間、本当にものすごく沢山の「深く、重要な時間」を過ごしてきました。
毒親育ち。
機能不全家族で「子育てに不安すぎた」自分。
自分の子育ては「大丈夫」だと思っていたのに。
全然「大丈夫じゃなかった」のです。
人に、プロに、
助けてもらえてなかったら。
自分を、受け入れてこなかったら。
わたしはものすごく「重要なこと」に気づかず
こどもたちを「独りよがりな自分」のまま子育てをしていたと思います。
こどもたちの「成長」というのは
やっぱりちゃんと「段階、レベル」があります。
生き物として、きっとそうなのだと思うし。
実際に、我が子と接していてそう感じます。
「乳幼児期」と「学童期」は、全然違います。
こどもたちが学童期、さらに思春期に入ってくる年齢となると
子育ては「全く別モノ」になるというか、別のレベルに突入するので「社会性」や「社会」というものの割合が本当に増えます。
だから「社会性」「社会」というものに
そもそも適用できてなかった、苦手意識やトラウマなんかがある親にとっては、とても「難しい時期」に入ります。
こういう時期に、こどもと関係性を「こじらせてしまう」のは、至極当たり前のように思いますし。
乳幼児期の「難しさ」とは全然「種類が違う」ので。
どうしても「お母さん」では難しいのは、性質上「ある」と思います。
必要になってくるのは「母性」ではなくて「父性」の方だからです。
お母さんでは、そもそも「難しい」こと。
ここで「問題」になりがちなことが
自分は「すぐに変われない」のに
こどもには「すぐに変わって欲しい」という親側の「想い、欲、期待」との葛藤。
以前のわたしのように「気負いすぎている」お母さんにとって、
この時期のこどもとの関係性は、毎日「すごくキツイ」と思います。ましてや「不登校」で一日中「こどもをみている」「こどもとの時間が多い」となると、「早く」なんとかしなければ、と。どんどん自分もこどもも追い込んでしまいます。
負のループは、こんな環境、こんな時期に
特に強く現れてくると思います。
そんなときこそ
「こども」を通じて
「自分の方」にこころを寄せてあげる
ということが大事になってきます。
わたしが学んできた
子育てにおいてとても「大事なこと」の一つです。
今後、母子共に「自分らしい幸せ」を諦めず、希望をもって生きていけるための具体的なサポート活動を拡げていきます。そのための活動資金にしますので、ぜひお気持ちいただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。
