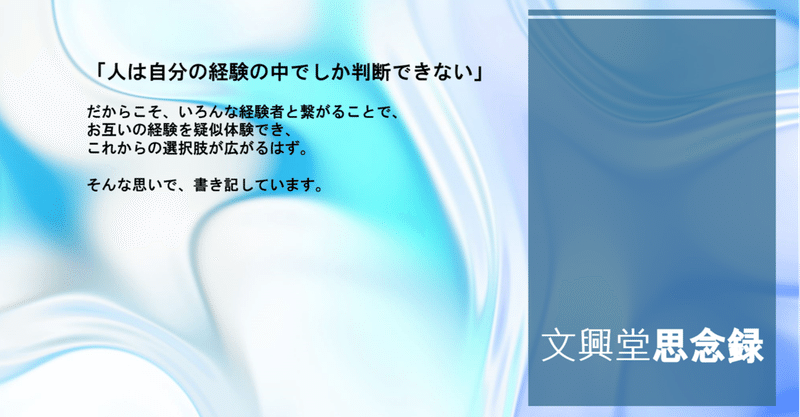
#1)これからについて考えてみた。
2020年5月。未曾有のウイルスが人々の暮らしを大きく揺さぶり続けている。おかげで今までの生活環境が望むと望まざるとに関わわらず大きく変化を遂げてしまった。全くもって寝耳に水。会社員として働いていた自分は、ある日突然休業命令を言い渡されて今は自宅待機という状態が続いている。同じような環境に置かれている方も少なくはないと思う。
これは言い換えれば、ある日突然、今まで手にしたことがない「時間のゆとり」というものを手に入れてしまったということでもある。なんとも会社員とはこんなにも脆いものか、と自分でも驚くほどに、この時間を使って自分の身をどのように社会に活かせばいいのか即座にわからなかった。きっと今まで知らず知らずのうちに、会社という枠組みの中で与えられた目標や義務に没頭してしまって、自分自身が社会に貢献したり還元したりできる事って何なのか?ということに向き合い考えるという時間を持たなかったからだと思う。
とはいっても、時間は刻一刻を刻まれていく。そのうち、今この時間っていうのは、目に見えない何者かに「新しい自分を開拓しなさい」と言われているに違いない、と、なんとなく直感でそう受け止めた。自分に与えられたこの自由な時間をどうしたいの?と自問した。答えは明確だ。少しでも社会の役に立つ時間にしたい!社会とつながる時間にしたい!
それで?そのために何を実践するの?何が自分に出来わけ?そこが大事なところだものね??
猛威を振るうウイルスに有効かつ簡便な対応策・予防策がない中で、未知なる脅威とどう向き合ってこれからの生活を紡いでいくのか、それぞれがいろんな考えを馳せていることだろう。そんな心の中の声や考えを文字という形に表現して誰もが見えるようにしてみたら、ひょっとして未来に通づる解決の扉が開くことがあるんじゃないか?それなら自分にもできる!
そんな思いから、今までの自分の経験値や見聞を含め、徒然なるままに心の中にあるものを形にして残してみようと思ったというわけで。
まず#1はこのライティングを始めるにあたっての動機や思いについて、備忘録として残しておこうと思う。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
■目次■
§1)漠然とした不安が経済活動を鈍らせる?
§2)そもそも「経済」って何だろう?
§3)今、自分たちに本当に必要な情報とは?
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
§1)漠然とした不安が経済活動を鈍らせる?
おおよそ人って生き物は「不安だな・・・」と感じることがあると前へ進む動作が鈍りがち。じゃ、その「不安」っていったい何なんなんだろう?
それはきっと、今ある現状の生活を維持し続けようとする中において、過去に自分自身では経験したことがなかったり、事態を予測したり対策を講じたりすることが極端に難しい「今の当たり前をくつがえすこと」や「未来の自分自身の在り方を想定できないこと」を指すのではないかと思う。だから不安要素は人それぞれ違う。例えば「赤痢」という病が未知なるもので抗生剤もない世の中なら生命維持の不安を感じて活動の活発さが鈍るだろうが、既知の病で抗生剤を持っている世の中なら不安さほど感じず活動量に大きな変化はない、といったようなことかと。
今回のCOVID-19騒動もこれに該当する。世界中のだれもが体験したことも予測したこともないものが現れて、今まで当たり前だった生活をし続けることを脅かしにかかっているもんだから、「不安」を感じて「じっとしている」という選択をし、結果、世界の経済活動を鈍らせた。
でも、本当に経済活動が鈍る原因は「不安」にあるの?
たとえ周りで紛争が起こっていようとも商売を営み日常生活を止めない世の中もある。だれでも簡単に銃を所持でき、いつどこで凶悪犯罪に巻き込まれるかわからなくても、新しい生活様式を開発し続ける世の中もある。こうした要素だって「不安」の一つなわけだけれど、その不安を押してでも経済活動を続ける「必要性」や「目的(在りたいイメージ)」を明確に持っていたとしたら、多少安全が担保されずとも人はその活動を止めないのではないか?とも思う。むしろ今ある不安が踏み台となってより快適な生活を形作っていくことだってあるんじゃないかな?
今の世界の状況でいえば、今まで慣れ親しんだ生活に固執せず、それぞれが考える力を持ってCOVID-19の存在する中でも経済活動をし続ける必要性や将来のより良いイメージを明確に持つことができれば、活動は活発に続いていくはず。
今までの生活を保持し続ける先に未来を描いて甘んじるのではなく、自ら考え周囲の変化を受け入れて行動するという人数の多少が、経済活動を活発にするか鈍らせるかの要素ではないかと。
§2)そもそも「経済」って何だろう?
言葉の成り立ちはギリシャ語の οικονομία(家政術)に由来するそうで、和訳すると「家庭のやりくりにおける財の扱い方」。つまり人間の生活に必要な物を生産・分配・消費する行為についての、一切の社会的関係のことだそう。
個人的には、どのような経済の形であれ、需要と供給のバランスの上に、人がより快適に幸せな生活を送ることができる相互関係性を築いたもの、という印象を持っている。
原始には、最低限の生命維持のためのやりくりで1日24時間が終わるという状況だったのが、徐々に工夫が施されより短時間でより確実に生命維持ができるようになるにつれ、余暇時間が生まれ、余暇時間によって学びや芸術や発明やらが次々発生した。こうした経済活動の中で生まれたものは全て、その時その時における快適な生活のために需要があったものであり、時代を問わず必要とされるものは常に改良されながらその形を変えて現存している。戦時下や独裁下といった経済環境でさえ、元々は人々自らが望んで作ってきた沿線上に現れた経済の形であって、結果としてそれを大多数が良しとしなかった時には経済環境が大きく変化を遂げ新しい経済の環を作り、今に至るというわけで。
「需要と供給が適度に保たれた経済」
この需要というのは実に不思議なものだなぁと思う。自分は全く意識していなかったのに、他から指摘されたり提案されたりすると急に沸々と湧き出てくるものでもあるから。今世界をリードしてきた経済圏の多くが、自己利益を最優先して物を作って儲ける「市場経済」という枠組みにあるけれど、この中の需要の多くは喚起された需要だと考えている。他から喚起された需要であっても、それがより多くの人々に望まれればマジョリティとなり、生活の中の当たり前として溶け込んでいく。
まさに、自分の経験になかったものを、他人と交流してその経験を疑似体験することによって選択肢を増やした結果だと言えるかもしれない。
需要を喚起し、新しい経済圏を創出してきた過去の偉大な事業家たちは、自己利益の前に、公益をまず考えてそこから人々の需要を喚起し、結果巨利を得、地域や国や自身をも豊かにした。私利の前に大きな「理念」や「目的」があった。需要を喚起するには多くの苦労や不安要素もあったろうし、法律や慣習の壁を崩すという現実問題もあっただろう。そんな不安や困難を押してでもやり抜く理念や目的が経済活動を回し続けてきた。
そうして築かれた恩恵の経済圏の中で、きっと現代の私たちの多くが自ら深く考えることなく生活を送ってきたんだろうなって、今回のCOVID-19の一件でようやく本来の市場経済の在り方がズレてきていることに気付き始めた。私自身、先人たちの遺産である経済に甘んじ、自ら考えることをサボっていたことに気付かされたな、と思う。
過去の人々が紡ぎだしてきた経済をどのように受け継いで今あるべき経済を創出していくか、が今を生きる者の課題だと強く思う。需要と供給のバランスの上に、人がより快適に幸せな生活を送ることができる相互関係性をもう一度築き直すときなんだろうと強く思う。
そして何より、新しい経済を創っていくうえで「情報」は欠かせないと考えている。とくに情報の流動性がよい現代においては、個人レベルで様々な情報をやり取りし、取捨選択できる。この強みを生かさない手はない!
§3)今、自分たちに本当に必要な情報とは?
情報爆発の時代、と言われて久しい現代。昔と比べて手にすることができる情報があまたあるという恩恵の反面、色んな所にいろんな答えが転がっている状態でもあるわけで、たまたま見聞した情報(答え)を鵜呑みにする危険性もはらんでいると言える。
経験や体験に元付く情報は非常に手硬い情報の一つ。そうした情報と繋がるためには、自分や経済圏・周辺社会がどうなっていたいの?のいう自分なりのイメージや目的をまずは自分で考えてみて仮設を立ててみること。それからその考えや仮設がズレてるのか真っ当なのかを他の人に投げかけて議論してみること。いろんな情報がどの源流からきているものなのかを知ろうとする姿勢、を大切にしたいなと思っている。周りのいろんな意見や情報に右往左往しないために、まずこの点は意識しておきたい。
次からは各カテゴリーごとに記事を編集していきます。
