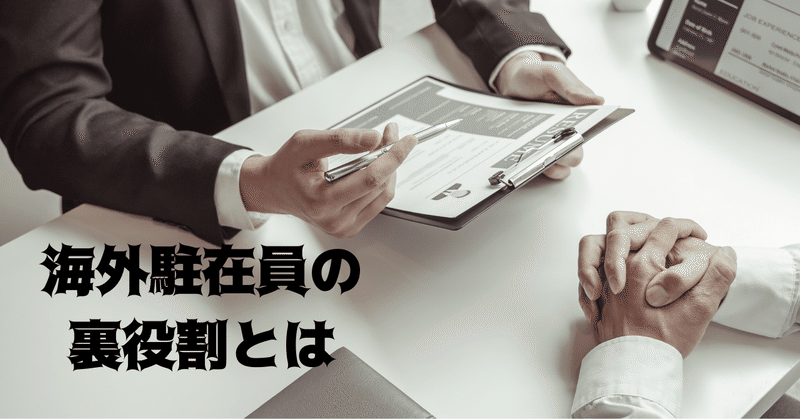
海外駐在員の裏役割とは
自己紹介
ご覧頂きありがとうございます。新卒で食品会社に就職し、営業職を経験したのちにアメリカの子会社に赴任。約10年間海外駐在しています。
自分自身への備忘録も兼ねてアメリカでの体験や自身の考えをnoteに残していきたいと思います。同じ境遇やこれから海外に挑戦したいという方にとって少しでも参考になれば幸いです。
はじめに
少なくないコストをかけて駐在員を他国に派遣するのですから、明確な目的や業務上の役割があり、それらは赴任前に伝達されていることと思います。
ここではそのような個別具体的なものではなく、それらをより高いレベルで遂行していくための裏役割をお伝えしていきたいと思います。
私の10年という駐在経験の中で、駐在員が担うべき裏役割とは以下の4点に集約されると思っています。
中・長期の視点
仕組み作り
カタリスト・語りスト
コーポレートガバナンス
これらを一つ一つ掘り下げていきたいと思います。
中・長期の視点
まず時間軸的な観点です。
人材が流動的なアメリカ社会では現地社員に中・長期的な視野を期待することは困難です。なぜなら彼らにしてみれば同じ会社で働いているかどうかもわからない5年後・10年後のことはそこまで重要ではありません。それよりも短期的にでも結果を出して評価され、昇格することで次なるキャリアアップにつなげていきたいという心理が働きます。
一見、会社のことを考えての提案のように聞こえても、自分のインセンティブ(業績連動)のためだったり、中・長期的に考えると必ずしもプラスにならないこともありますので注意が必要です。ただ提案を断ってばかりだと、現地社員からすると何も決められない人だと思われてしまいますので、見極めなぜそうできないのかを伝えるコミュニケーション(3項目目に繋がってきます)が必要です。
ただ駐在員も通常、任期は3~5年くらいかとは思います。そういう意味では現地社員同様に流動性は高いのかもしれません。
しかしだからといって自分の任期中だけのことを考えて種をまかずに収穫ばかりしていると、世代が変わった時には刈り取るものがなくなってしまいます。
事業ステージにもよるとは思いますが、今刈り取っている成果は数年前にまいたものということも海外事業ではよくあります。逆に今、種をまいていないのだとしたら数年後にそのツケが回ってきます。
次世代により良い事業を引き継ぐために、中・長期的な視点に基づいた日々の活動や判断が求められます。
仕組み作り
次は職務範囲に関連した観点です。
ジョブ型雇用では現地社員はかなり厳密に職務範囲を規定されています。そのため、新たな職務が発生しても日本のように柔軟には人を動かすことが出来ません。
そのため、まず駐在員に新たに生まれた職務を埋めることが求められます。
永遠に自分一人では続けられませんので、仕組みを作っていくことが求められます。
構造を把握して、仮設設計を行い、仕組みを構築したらその原動力になるのも自分自身ということもあります。そうして期待されるアウトプットが得られたら、徐々に人材をあてがっていく(新たに採用)というPDCAが必要になってきます。
もちろん期待されるアウトプットが出なければ、何度も修正を行う必要があります。非常に精神的負担も大きいですが、この仕組み化を繰り返すことがビジネスパーソンとしての成長に大きく繋がってくると感じます。
カタリスト&語りスト
3点目はリーダーシップや相互理解に関する観点となります。
カタリストとは直訳すると「化学反応を起こすための触媒」を意味します。そこから転じて人の行動や意識の向上を促進したり、周りの人の良い刺激となるような人材のことを意味します。
これは私も驚いたのですが、馬鹿にされるのかなと思っていた日本人の仕事に対しての姿勢はアメリカ社会でも評価されます。英語にも”Work Ethic"という仕事に向き合う姿勢を表現する言葉がありますので、一つの美徳なのだろうと思います。
もちろん長時間労働を推奨しているわけではありません。日本とは比較にならないくらいに効率性は求められます。それが担保できた上での姿勢という意味です。
また駐在員は本社と現地社員の板挟みになることも多々有ります。
どちらの言い分が正しい・正しくないということではなく、双方共に相手の視点がわからないことがすれ違いを生みます。
そしてその両方の視点を持つことを許されるのは駐在員のみです。そういう意味で、言葉遊びではありませんが、カタリストでありながら双方の視点を双方に伝えて理解を促す”語りスト”でなければなりません。
そうすることで初めて、双方の理解が深まり思ってもみない”化学反応”が起きるのではないでしょうか。
コーポレートガバナンス
最後はディフェンスの観点です。
この部分は性善説の日本人にとっては特に意識が必要な部分だろうと思います。
アメリカではルール(契約)に書いていないことはやって良いという解釈です。もちろん何でもかんでもやりたい放題ということではないですが、ルールが不十分だったりあいまいだったりすると、それを利用しようとする人が一定数出てきます。
ですので、日本の常識的には「いちいちそんなこと書かなくても、そんなことする奴いないよね」と思っていても、ビックリするようなことが起きる時もあります。
ですので普段から、業務標準化(マニュアル・ルール作り)も重要ですし、現地社員の役割や実務のプロセスについてもしっかりとした関与が必要です。決してブラックボックスを作らせてはいけません。最初はそのつもりがなくても、「これ誰も見てないのでは…」と気付くと人間は低きに流れるものですので。
最後に
私がアメリカに10年駐在して感じてきた、赴任の際には”伝えられない”4つの裏役割を考察してみました。
事業ステージにもよりますが、この4つの役割を現地社員に求めることは酷だと感じています。現地社員にとっては自己矛盾を抱えてしまう(短期的なパフォーマンスが落ちたり、状況によっては自分の解雇リスクにつながる)こともあるだろうと思います。
ただ、あくまで”裏”役割ですのでこの役割を全うせずとも問題はないだろうとは思います。実際、駐在員でも裏役割を実践している人の方が少数派だと
感じます。
ただ実践できている人は例外なくハイパフォーマーであり、駐在期間中のビジネスパーソンとして大きく成長していたと感じます。
新たに駐在し始めた方、これから駐在する方はこれら4つの裏役割を意識して日々の業務にあたってみてはいかがでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
