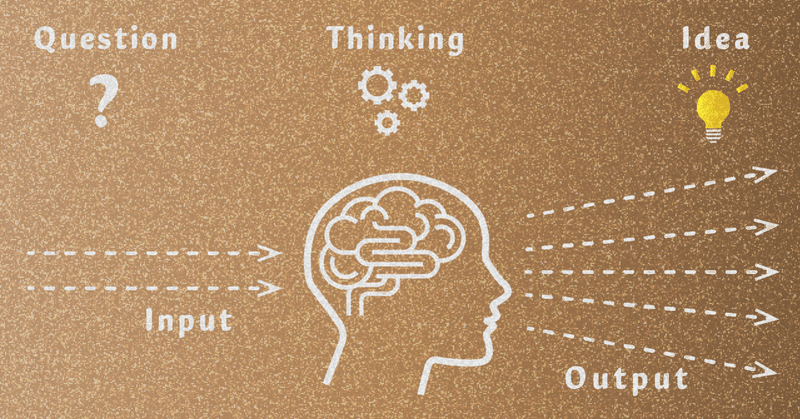
【コンセプチュアル・アート】頭脳警察は誰だ
現代美術研究家であるトニー・ゴドフリー著『コンセプチュアル・アート』木幡和枝訳、岩波書店、2001年。コンセプチュアル・アートの観念について果敢に挑んだ本書を読み解いていく。
内容が多岐に渡る(全448ページ!)ため、章立てごとに区切って進めていく。6回目は第5章『頭脳警察は誰だ コンセプチュアル・アートの多様性』。この章で、コンセプチュアル・アートの方向性(方法)が見えてくる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ベトナム戦争真っ只中の1967年。すでに50万人ものアメリカ兵がベトナムにいた。
戦争で最初の犠牲となるのは真実であり、欺瞞的な言葉-リディブリーフィング(軍属の任務後の情報臨取)、インシデント(出来事)、プルーフ・パケージ(証拠一式)、など-が横行していた。
戦争において大切なのは「真実」ではなく、思い通りの結果を獲得することであった。
第二次世界大戦中の戦争画家のように、日本の戦況を恣意的にゆがめ、あたかも日本軍が活躍しているように情報操作した絵画が描かれていた。戦争画家としては、藤田嗣治などが有名であろう。
1960年代末期のアメリカは広告と広報の時代、大量消費時代であり、資本主義の絶頂期にあった。技術の進歩がよりよい生活を約束していたのだ。
ちなみに本章のタイトル『頭脳警察は誰だ』は、フランク・ザッパの『フリーク・アウト』というアルバムに収録されていた曲であるとのこと。
コンセプチュアル・アートは言語の誤用に対する反動と同時に、消費社会への批判だったと考えることも出来る。
これを説明するものとして、以下の7つを挙げている。
・シリアル(連続的要素からなる作品)
・反形象の彫刻
・言語に基づく作品
・理論的な作品
・モノクローム絵画
・介入的行為
・レディメイドに対する詩的なアプローチ
・アルテ・ポーヴェラ(貧しい芸術)
さらに、1960年代末期の多くのアーティストたちが主要素として(唯一の要素として)言葉を使うようになった理由として、以下を挙げている。
・美術品の脱物質化という企図が依然として継続していた
・より広範囲の人々と交信したいという欲求があった
・「人の頭に入り込みたい」という願望があった(ハラルド・ゼーマンの言葉)
・すべての芸術作品は本質的に言語的だという意見の人々がいた(ジョセフ・コスースの『アート=ラングエージ』を例に)
・アートの意味を理論化する必要があった
・アート市場への嫌悪(脱物質化の傾向を生んだ要因のひとつとして)
資本主義の絶頂期において、アート作品もまた「商品」として趣向品のひとつに加えられた。ギャラリーや美術館など、作品を取り扱う=売買の道具として。この流れに異議を唱えた流れとして、脱物質化、というのが表出してきたのであろう。脱物質化(非物質化、非神秘化など)は以前ルーシー・R・リパードを読んだので以下参照。
ダン・グラハムの広告雑誌のような作品や、アラン・チャールトンのモノクローム絵画などなど。挙げられていた作品は、「中心に、芸術作品の神秘性をはぎとる欲求を秘めていた」ものであった。
美術(絵画や彫刻)がもつ、神秘的なイコン。もっぱらコンセプチュアル・アートの攻撃対象はモダニズム(その後の抽象表現主義も含まれるであろう)であったように、リパードのいう「美術の非物質化」(私は「非具現化」の方がいいと思うが)が合致する。
そして、コンセプチュアル・アートの最終的な現れである「アルテ・ポーヴェラ」へとつながっていく。
「貧しい」、「困窮した」アートを意味し、制作材料がありきたりのものばかりであったことに由来する。
1967年、イタリアの美術批評家・プロデューサーであったジェルマーノ・チェラントは著書で以下のように述べている。
平凡なものがアート界に入ってきたわけだ・・・身体の介在や行為がアートになった。言語がもっていた道具としての源泉は新たな言語学的な分析にさらされた。それは生まれ変わり、それとともに新たな人間主義が台頭した。
リパードのいう「行為としての芸術」、パフォーミング・アートがこの時点でコンセプチュアル・アートに接続される。
さらには常にクールであったデュシャンとは対照的に、イアニス・クネーリスによるレディメイドは事実や素材を「ホット」に、流動的に、かつ不確定にする達人であった。レディメイドを詩的に作りかえており、ほかにもヨーゼフ・ボイスやライナー・ルーテンベックなど、基本的な素材や形態と取り組み、そこから異化されたものを制作していた(このあたりについては、次章で展開される)。
他者にものごとを正確に伝えるのであれば、言葉の方が確実である。現に言葉による作品が作られていることからも、美術の神秘的な観念から脱却し、コンセプトを提示する手段としてアート(芸術)が用いられるようになった。
ここまで読み進めて思うのは、コンセプトといえば聞こえはいいが、それ屁理屈じゃない?という作品も散見された。また、それをアートといえば、アートなのだ、とあったように、多様性というか、異種格闘技戦のように、なんでもかんでもアートにしてしまうところ。
欧米と日本におけるアーティストの本質的な役割(権限)の違いが、アートの存在意義やアート作品を作る意味といった部分が根本的にかけ離れている気がする(現代においては、欧米的なスタイルで制作しているアーティストも存在するため、一概にそうとは言えないのも確かだが)。
さらにはやはり、美術批評家や美術館のキュレーターによる影響が多大である点。キュレーションによってさまざまな解釈ができるため、ゴドフリーが挙げていたアーティストから読み解くと、そうであった(極論を言ってしまえば、挙げた作品しか存在しないほどに)、確かにそうではあるのだが、カテゴライズすることは一種の危険性をはらんでいるのではないか。
○○ブーム、というのが最たる例ではないかと思う。写真新世紀で梅佳代がグランプリを取った次の年、同様のテイスト写真の応募が非常に多かったと聞いたことがある。
火付け役はメディア、といっていいであろう。自身のスタイルや思考など、核となるものがない者は乗っかり、続くはずもないので結果的に辞めていく。また、同調勢力(サークルや方向性の同じ仲間)に浸ってしまうと、居心地がよいため抜け出そうと考えることすらしなくなってしまう。
「今日、明日で結果が出ることはない。地道に、継続的に制作・発表を続けられることが最低条件であり、いつしか誰かが評価してくれる、かもしれない。最低でも10年。アーティストとは生き方である。」とアーティストを志した際に聞いた言葉をふと思い出した。
よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。
