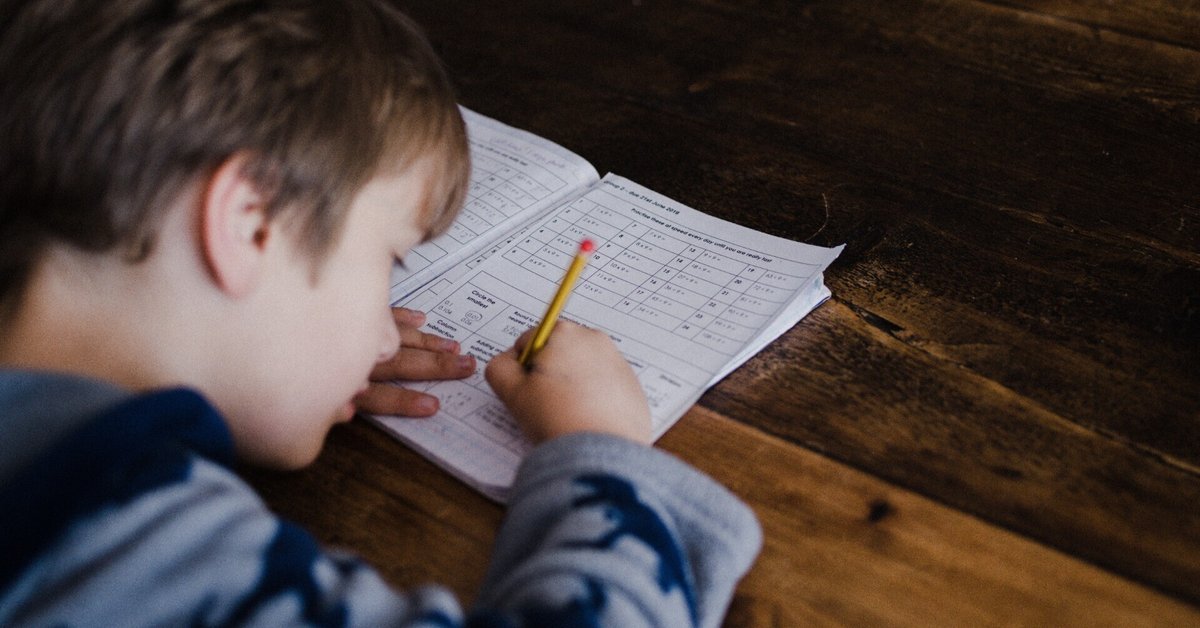
【0から研究計画書を書く】大学院までの道 Part.2
「研究計画書」は私の大学院受験におけるひとつの山場だったと感じます。
それだけ時間がかかったし、労力をかけて1枚の紙を書き上げました。
今回は、大学院受験で多くの学校が提出を求める研究計画書について、私の経験と学びを書いていければと思います。
【もくじ】
1.「研究」って、なに?
2.必要なインプット
3.アウトプットのやりかた
4.まとめ
1.「研究」って、なに?
私のように大学に行かず院を目指す方や、大学には行ったけれ研究というものに当時多くの時間を割けなかった方などは、計画書を書く以前に、ここがスタート地点になるのではないでしょうか。
私は、研究計画書に手を付けようとした時持っていたのは
「興味のあるテーマ」だけでした。
逆に言うと、興味のあるテーマについて論文や専門書を多く読んだ経験や、仕事で取り扱った経験、知識などは皆無に近い。
そこで私が取った行動は、「研究」の全体像を知る事ができる本を読むことでした。本のタイトルは「情報生産者になる」上野千鶴子著。

この本を紹介してくれたのは、私と同じような状況から大学院に進まれたOGの方でした。
著者の上野千鶴子さんは、元東大教授。はっきりとした物言いで常に物議を醸している方なので好き嫌いはあると思いますが、
社会学系、あるいは文系の研究科を目指し、かつ研究とは何かを考えるのには非常にいい教材になったのでお勧めです。
この本では体系的に研究、論文について纏められていますが具体的には
・問の立て方(リサーチクエスチョン)
・先行研究の読み方
・研究計画の立て方
・情報収集と分析の方法
・アウトプットの仕方
が事例も交えながら分かり易く書いてあります。
この本で、「研究とは」という全体像を捉えてから、研究計画書の参考書を読むと、なるほど、こういう事か。と納得感が増します。
ちなみに、参考書はこちらにしました。
具体例が沢山載っている点が、構成の参考になりました。
(具体例ではなく、書き方のコツなどを言語化したものがお好みであれば、違う参考書が良いかもしれません)

2.必要なインプット

研究とはなにか、計画書とは何かを理解したら次のステップとして、先行研究調査を行いました。
ここでの私の「論文経験値」ですが、レベル0.1程度。
正直、2,3しか論文を読んだことが無く、専門書などに関しても「分厚いし難しそう」という理由で1冊も読んだことがありませんでした。
経験も知識もほぼ0の私でしたが、まずは研究計画書を書いてみようと思ってとりあえずやってみたんですね。
すると、自分の経験にしか基づかない、論理的とはかけ離れた
「エッセイ」が完成してしまいました。
なるほど、私はこの程度の知識なのだなと情けないながらも分かり、
このレベルから合格レベルの計画書に到達するには恐らく100本は文献を読むべきだと考えました(それほどにひどい文章でした…)
論文の調べ方から私は調べました。
■主に使用したのは2つのサービス。
・Google Sholar
・CiNii
■4ステップで進めた
①「外国人 労働者 日本」といった興味分野のワードで検索
②5-10件をピックアップして読む
③全体像を掴み少し分野を絞って再検索と参考文献を5-10件ピックアップ
④上記を繰り返し100を目指す
⑤文献はリンク付きでリスト化する(wordやExcel)

上記のようなステップで進めていると、最初の興味から随分絞らるかと思います。自分でも言語化できなかった、自身が持っているリサーチクエスチョンに気づくことができる、自己発見のステップです。
このステップを繰り返すにつれ、私は「良い文献」の見つけ方が少し分かってきました。
■「良い文献」を見つけるコツ
・著者の実績を先に調べてから読み始める
・結論から先に読むことでコスパUP
・文献のランクも考慮しながら読む
文献のランクについては、研究計画書の「引用文献欄」に記載する際にもチェックすると良いと思います。
例えば、ジャーナルに載っている査読済みの論文と、大学内での紀要論文だと質が違う場合があります。(もちろん例外もありますのであくまでも参考としてですが)
いい内容であると自身が判断したならばどんな論文でも引用に記載して良いとは思いますが、一般的にはランクがあるという事を知っておくことが重要だと思いました。
3.アウトプットする

文献等を合計30-50程度読んだあたりで、計画書のペンが進むようになったので、インプットとアウトプットを並行して行いました。
そして、そのころには既に締め切りまで5週間になっていて。
なので私は、第5版までやって提出しようと計画を立てました。
週に1回完成に持って行き、添削に出す。(もしくは自分で添削)
それを5回繰り返せばある程度磨かれた文章になるだろうと思ったんです。
■この段階でのポイント2つ
①添削を誰に頼むか
②違うと思ったら潔く方向転換
①添削を誰に頼むか
これは本当に計画書の完成度を左右するファクターの1つだと思います。
なぜなら、私の書くことができる文章なんてどんなに努力してもたかが知れているからです。
でも、どんな人だって最初はそうだと思います。私と比べたって団栗の背比べ程度の差でしょう。なので手助けが必要です。
私は、先日まで通っていた経営塾の講師の先生方や、大学の先生をしている職場の上司、目指す大学院のOG、自分の家族など、合計で6名ほどにお願いしました。
余談ですが、実は最初、5万円ほど支払って添削サービスのような物にも申し込んでいたんですが、3日でキャンセルしました。
添削サービスは有用だと思うんですが、なんせ私はその時非常にナイーブな精神状況だったんですね。
1人での初めての受験という戦いに、不安で孤独で仕方なかったんです。
そんな時に、私の事を知りもしない業者の方に「これってどういうこと?」
「本当に大学院行きたいの?」というスパルタ指導がなされると、
「私のことなんにも知らないくせに!!(乙女)」
となってしまったんですね(笑)
精神の安定も崩してはならないのが受験であると思うので、合わなければ、辛ければ自分に厳しくしすぎないで手を変え品を変えやってみるといいと思います。
そして、専門家と専門家以外、2つの視点で見てもらうと良いでしょう。
専門家としては、文献に触れる機会がある方にお願いできるのがベストであると感じます。
一方で、友人や家族のよう、専門家以外の添削も入れると、狭くなっていた視野に気づくことができ、より洗礼された文章になっていきます。
②違うと思ったら潔く方向転換

ある程度書き進めていると、
「あれ、私が2年間かけてやりたい研究ってちょっと違うよな?」
と思う瞬間がくるかもしれません。
そんな時は、その直感に従って潔く方向転換しましょう。
どれだけその分野の文献を読んでいても、経験があっても、もったいないと思わずに。
これまで学んだ知識や経験は必ず方向転換先でも役に立ちますし、独自の視点に繋がる。
そして、面接では確実に研究計画書についてプロからのツッコミを受けます。
その時に、熱のこもった本心を語れることが、少なくとも私にとっては捨てがたい要素だったので、第2版を書き終えた後に、大きく方向転換をしました。それに、ある程度構成は完成しているので案外大変じゃなかったりします。
頑丈な張りぼてを作り込んで面接に挑むより、本心であればそこまで作り込む必要もないので、コスト削減にもなると考えて、私はいつもこの「本心ぶつけ法」を採用しています(笑)
緊張すると考えてきたことは飛んでしまいますが、本心はいつも飛ばないので胸を張って話せます。
4.まとめ
研究計画書は1つの受験の山で、結構大変ですよね。
私が今回お話したのは、私の様な、研究そのものについて、研究テーマについてかなり無知な場合の短期的な進め方です。
計画書で大切なのは、常に他人の視点を意識することだと考えています。
というのは、先行研究も、添削も、鍵になるのはいつだって先人、先輩たちの積み上げてきたものです。
冒頭で紹介した上野千鶴子さんの本にこんな一節がありました。
「先人たちの研究に10%だけでも自分なりの視点を入れる事ができたなら、それは立派な研究だ」
山のようにある先行研究を前に、自分のちっぽけさに気づき、その中で私にしか見つけられない課題を見つけようともがくのは苦しくも楽しい作業でした。
今回の記事には、正しい方法もそうでないものも混じっているとは思いますが、これが今のところの私の解でありますのでご容赦ください。
今後も、解を更新していきたいなと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
