
かくも難しきは協働かな
ご無沙汰しています。地方公務員のタケゴンです。
久しぶりの記事は、協働のマネジメントと題し、昨年、1月12日に、管理職対象に研修らしきことをした時のお話について、昨年度末にアップし損ねた下書きをもとに、ご紹介します。
相変わらず、尊敬する仲間や先輩のお話をつないだお話です(笑)
1 協働のマネジメント
茨城県の助川さんは、その著書で、業務内・外と職員・地域のマトリクスからなる4つの場(職場、現場、学場、街場)を提唱されています。

そして、加留部さんは、この中で、一番難しいのが職場(業務内・職員)での協働だと言われています。
一方で、今は縦割り<総合行政(部局横断)の時代、このため、協働のマネジメントの必要性は、ますます高まっていると考えます。
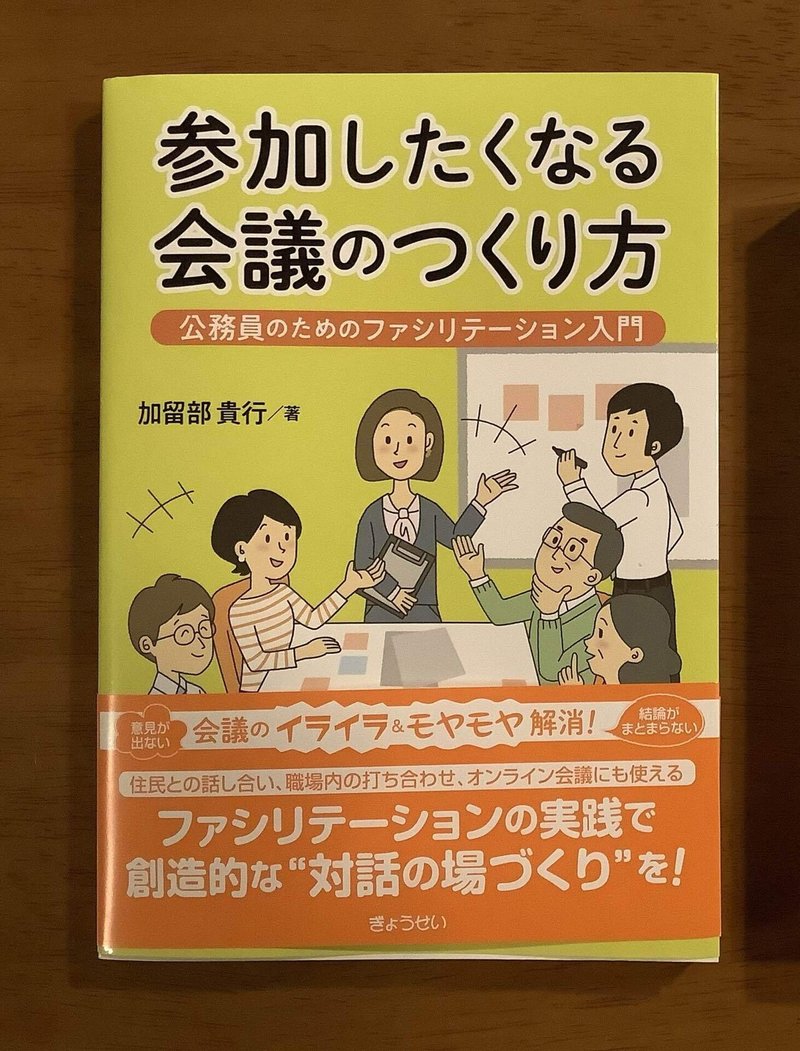
2 合言葉と名言を忘れない
(1)関西広域連合の合言葉
上流は下流をおもいやる。下流は上流をおもいやる(感謝する。)
これは、嘉田元滋賀県知事がさかんに言われていたお言葉で、関西広域連合本部事務局出向当時、道州制や北陸新幹延伸時など、利害調整時の合言葉になっていました。
特に、官房組織と現場において、重要となる協働のマネジメントの原点だと考えています。
(2)多くの方の名言
協働のマネジメントにおいて、意識したいことは、多くの方が多くの名言を残されていますので、以下に紹介します。
・人はどうしても対立構造をつくってしまう。私はこれを脱却して、二項対立から相乗効果をつくりたい。(小紫生駒市長)
・他者の思いや事情はあなたとは違う。特に官房組織等はこのことを意識して、下から振る舞って普通であることを意識してほしい。(後藤吹田市長)
・自分の考えを相手に強要してはいけません。相手のために尽くして見返りを求めない心を持てば争いごとはなくなります。一番大切なものは愛です。(←石の教会神父)
・一万人いれば一万人のストーリーがある。でも、それぞれ違う一万人が、お互いを思い合い、力を合わせて、思いを合わせて、全世界に、第九を発信する。それが、やがて争いのない世界へとつながっていく(←佐渡裕)
・自分の利得よりも相手への貢献。人と人との間には相性が存在します。そのため、貢献しても報われないこともあります。しかし、自分の利得だけ考えていては、良い人間関係は構築できません。そして、そのことは組織横断的な取組にもいえることです。共感=信頼+魅力。信頼を得る方法=周りへの貢献。(←山形市後藤課長)


3 悩む人は協働できる人
私は、尊敬する人を見て、いろんな人のお話を聞いて、次のように考えています。
相手の話を傾聴できる人、相手のことを思いやることができる人は、それゆえに悩むことは多い。でも、だからこそ尊い。自分のことしか考えない人、周りの言うことを聞かない人は悩まない。自分がそうだとも気が付かない。
相手のことを思いやり、その上で、ローカルルールに迎合するのではなく、真理を構築し、これに基づき、柔軟に、守るべきことを守り、必要なことは改善できる人が、協働のマネジメントできる人ではないでしょうか。
4 くじけないために唱えよう
最後に、時にくじけそうになる時に唱える魔法の言葉とも言える公務員仲間の師匠たちのお話をご紹介して、今回のまとめとします。
・問題はなくならない。もしなくなったと思っても氷山の一角。おおらかにしなやかに。一喜一憂しないで、まだ機が熟していないと考えたらいいし、やり方がまずかったと思うなら変えて、追い風になるのに備えて、また、時が来たら、やったらええんちゃうん。(←神山町大南さん)
・雨の日も晴れの日もある、どんな時もあせらず、あきらめず、じわっと臨む。ささやかな営みが、時間をかけて、大きな環境を生み出し、その下で人が育つ。(←加留部さん)
・死を恐れるより、死を受け入れたうえでよりよく生きることを意識する方が自分らしく生きることができて死を恐れなくなる。だから一分一秒、今を大切に、正直でなくとも誠実に生きる(FTA竹本会長)
・今日すべきことは今日する。困難の先には必ず光があふれる日々がある。(←後藤吹田市長)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
