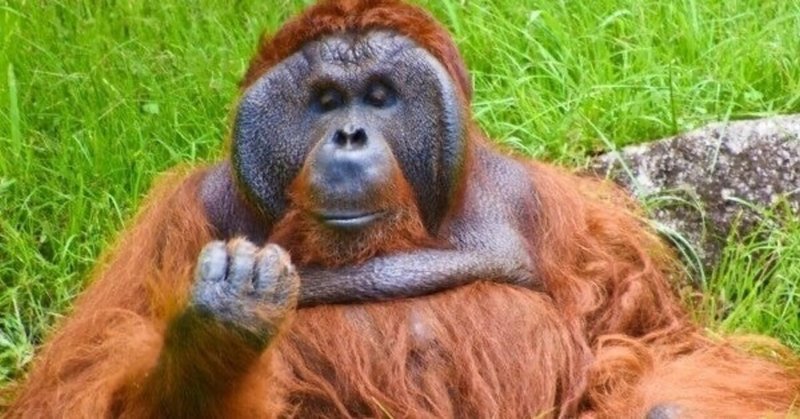
オランザピンの使い方
精神科の薬の使い方シリーズ、今回は抗精神病薬のオランザピンを取り上げてみたいと思います。このシリーズはあくまで薬剤師向けに書いておりますが、精神科の薬のことをもっと勉強してみたいその他精神科領域の医療職や、私が精神科医の先生方に処方提案させてもらう時の考え方や根拠も述べている点で一般の医師や若手精神科医の先生方にも学ぶところがあるよう意識して書いています。ただし、一般の方や当事者向けではないことにご注意下さい。
オランザピンは、先発品である「ジプレキサ」のインタビューフォームを参照すると、米国イーライリリー社において開発されたチエノベンゾジアゼピン系の非定型抗精神病薬です。オランザピンは、リスペリドンに代表されるSDA(serotonin-dopamine antagonist)にカテゴライズされる薬剤が特徴としている、5-HT2A/D2受容体親和性比が高い(つまり、抗精神病薬としての主要なターゲットであるドパミン受容体よりもセロトニン2A受容体を強力にブロックする。そのような作用の意義は拙著『リスペリドンの使い方』をご参照ください)という特徴も持ちつつも、アセチルコリン、ヒスタミン、ノルアドレナリン等をリガンドにする多数の受容体に対しても比較的高い親和性を有しています。
さらに、インタビューフォームには次のように書いてあります。
このように多数の神経伝達物質受容体に対する作用を介して統合失調症の様々な症状(陽性症状のみならず、陰性症状、認知障害、不安症状、うつ症状など)に対する薬効が発現し(多元作用型:multi-acting)、また多くの受容体に対する作用が脳内作用部位への選択性につながる(受容体標的化:receptor-targeting)MARTA(Multi-Acting Receptor Targeted Antipsychotic)という概念の元に、ジプレキサの開発が進められた。
はい、抗精神病薬の歴史においてMARTA(マルタ)という新しいカテゴリーを提唱した薬剤なんですね。後で述べますが、統合失調症治療でMARTAが何かアドバンテージになるかというと微妙なところがあるのですが、米国を初めとする諸外国では統合失調症のみならず、双極性障害の躁状態の急性期治療(単剤またはリチウムやバルプロ酸との併用療法として)、さらに、双極性障害のうつ状態の治療や維持療法としても広く適応症が承認されており、適応外使用なら認知症のBPSDや不安障害圏、知的障害などに伴う不穏症状や行動障害などにも幅広く使われることがあります。もちろん、精神科以外ではシスプラチン治療の際の制吐剤としては公知申請通ってるぐらいですよね。
そのように、色んな場面でよく使われるオランザピン。特に精神科領域で「こういう使い方だけは覚えとけ!」とか「こういう点に改めて注意!」というのを、エビデンスを自分の経験を元にまとめてみたいと思います。
オランザピンとクロザピン
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
