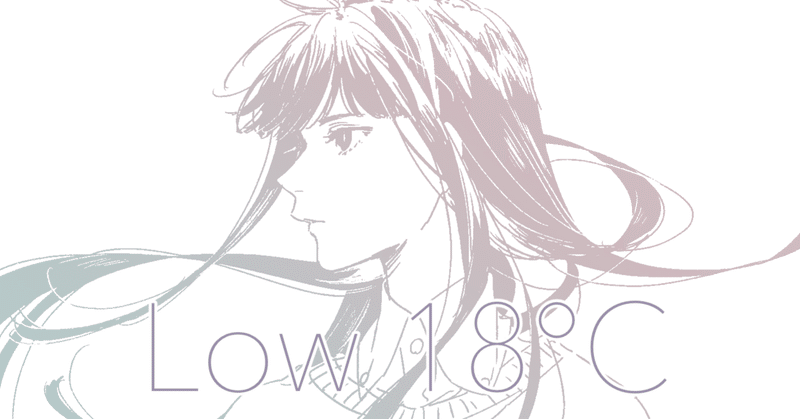
【短編小説】low 18℃
三ヶ月前、三年間付き合った彼氏と別れた。
大学二年生の夏から付き合ってたから、その報告をすると必ず「どうして?」と吃驚される。私も吃驚してる。どうしてだろう。
気が合わなかった? ──だったら三年間も付き合ってない。
遠距離になった? ──二人とも東京で就職した。
他に好きな相手ができた? ──別れるとき、私も彼も泣いていた。
どうして、だろう。星も見えない夜空に向かって溜息を吐いた。
永遠なんて、言葉にすれば陳腐なものを、私は凡俗にも信じていた。否、私が思う永遠というのは私が死ぬまでという意味だから、本来的な意味での永遠とは違うのかもしれない。それでも私は、彼のことを──彼のことだけを──永遠に愛して、永遠を共にするのだと思っていた。
それが永遠でなくなってしまった理由は、どこにあったのだろう。
『結婚するんでしょ?』
『え?』
大学生当時、彼の仲の良い女の子にそう言われた。言われたというか、念押しされたというか──揶揄われたというか。
『だってラブラブじゃん』
『……、まぁ、』
『結婚式、呼んでよね』
『……そうだね』
『そしたらアタシがスピーチしてー、』
その女の子は、彼の仲の良い女の子だった。彼と彼女は同じ学部で別のサークルだった。私と彼女は同じサークルで同じ学部だった。でも私の仲の良い女の子ではなかった。
『お前さぁ、何でアイツと一緒にいんの? 絶対アイツと気ィ合わないじゃん』
私の仲の良い友達は、彼女と私との仲をそう評した。そんなとき私はいつも、えー、と困った顔をして逃げていた。
確かに、私と彼女は気が合わなかった。
真面目にサークルに打ち込むことを、私は当たり前だと言って、彼女はダサイと言った。仲の良い先輩に誕生日プレゼントを渡すことを、私は当たり前だと言って、彼女は媚びだと言った。彼氏とデートに出掛けた話をしないことを、私は当たり前だと言って、彼女はつまらないと言った。
何もかも気が合わなかった。その差は、当初はただの差だった。それがやがて亀裂になった。そして、彼と彼女が仲良くなった頃、彼女は私と話すようになった。
『だって、さぁ。気は合わないけど、だからって嫌いだって顔に出すのって違うじゃん。もう子供じゃないんだからさ……』
彼女との仲を疑問視する声はサークル内で複数あった。きっと誰もがそう思っていて、何人かは冗談半分で私に訊ねて、仲の良い友達に私はそう零《こぼ》した。
『必要以上に仲良くはしないよ。線を引く、っていうのかな。敵意なんて向けないし、ただ心を開かないでおくだけだよ』
彼女は、よく喋る人だった。友達が多くて、コミュニティが広くて、何でも喋る人だった。
彼も、よく喋る人だった。友達が多いわけではなかったし、コミュニティが広いわけでもなかったけれど、わりと何でも喋る人だった。
化学反応は、最悪だ。私と彼との会話は彼女に筒抜けで、彼女に筒抜けということはサークル内のみんなに筒抜けだった。勿論彼にも良識はあって、プライベートなこと──要は恋人同士の行為──まで喋りはしなかった。それは彼女に訊ねられてもなんとかかんとか躱していたようだ。
ただ、残念ながら、私と彼の良識は合わなかった。サークル内で誰と誰との間でいざこざがあったとか、誰と誰とがいい感じだとか、誰と誰が付き合ったとか、私にとっては、そんなことはプレイベートだった。他人が口を挟むべきものでも口を出すべきものでも口にすべきものでもなかった。知ったなら知ったで、そこまでだ。せいぜい恋人という名の身内に世間話でしたらそこで終わりだ。そう思っていた。
でも彼は違った。そんなことは他愛ない世間話だった。誰に喋ってもいいものだった。当人達にさえ伝わらなければ問題のないものだった。だからよく喋る彼女によく喋るのを厭うことはなかった。彼女もよく喋ることを厭うことはなかった。
大学生活もとうの昔に折り返し、就職活動を少しずつ意識し始め、その準備期間みたいなものが始まって、本格化し始めた頃。私の頭の中も、少しずつ将来の希望のようなビジョンで占められるようになった。女の私が働きやすい場所、男と同質の仕事を同質に評価してもらえる場所、私が働きたいと思う場所を探した。そのうち、私がしたいこと、私がなりたいもの、私がほしいものを思い描いた。
『お前、将来、どうすんの?』
就職活動の真っ只中、彼が口にしたその言葉に、私は詰まった。
どうしたいかは、決まってる。ううん、決まってないけど、分かってる。理路整然と説明できるものではないけれど、輪郭だけはぼんやりと分かってる。私にはほしいものがある。
彼はよく喋る人だった。彼女もよく喋る人だった。彼と彼女は仲が良かった。私と彼女は仲が良くなかった。
知られたくない、と感じた。私がほしいものは私の全てで、私のルーツを覗き見られるような気がして、心を許した人以外には知られたくなかった。でも彼にとっての“それ”はどうなのだろう。
他愛ない世間話だろうか?
他人に喋って構わないものだろうか?
彼女に喋ってしまうものだろうか?
『……就活してる内に、決まればいいかなぁって感じ』
私は、彼に線を引いた。
どうして彼と別れたの? スクランブル交差点手前で立ち止まると同時に、ゆっくりと答えを出す。
将来も語れない人と、一緒にいることはできない。
私は神経質に過ぎたのかもしれない。もしかしたら、自分がどうしたいか、どうなりたいかなんて、知られたらちょっと気恥ずかしいだけで、誰に知られてもいいものだというのが世間的な価値観なのかもしれない。
私は大人の定義を間違えたのかもしれない。もしかしたら、大人になるということは、嫌いな人に感情を見せないとか精神的な距離を置くとかそういうことではなくて、物理的な距離を積極的に置くことから始めるべきことなのかもしれない。
私は彼を信用しなかったのかもしれない。もしかしたら、彼は私の将来を彼女に語ることはしなかったのかもしれない。それは他人に無暗に喋りたいことではないから、私が他人には知られたくないと察しているから。
それでも──私が神経質に過ぎていて、大人の定義を間違えていて、彼を信用しなかったのだとしても──私はそれが不満で彼と別れた。私が“将来を語りたくない”と感じた人と一緒にいることはできないと感じたから。
もし、一生大学生だったら、彼とはずっと一緒にいたのかもしれない。働くとか結婚するとか老いるとかそんなことは考えないで、ずっと同じ部屋で、寝転がって、今日あった楽しい話をして、一日を終えて。そんな毎日を繰り返すことができるたなら、彼とはずっと一緒にいれたのかもしれない。
でも現実は違った。わざわざ日めくりカレンダーを捲らなくても日々は過ぎ去り、私達には働くべき時が来た。きっとそのうち結婚を執拗に勧められる時が来て、否が応でも老いを感じる時が来る。そんなことは、ずっと前から分かってた。
だから、終わった。
スクランブル交差点の信号が青に代わり、人は示し合わせたように足を踏み出す。少し疲れた息を吐いた。デスクワークばかりとはいえ、足早に家へと急ぐ人達に合せて歩みを早くすればヒールを履いた足も弱音を吐くというものだ。フレアスカートを翻し、バッグのせいで少しずれた白いブラウスを整えて、周囲の人達と同じように歩き続ける。
朝も昼も夜も、名前も知らない人なんて没個性的だ。髪を七三に整えてスーツを着ている人も、耳から口までピアスを通している人も、頭から爪先まで真っ白な重苦しいドレスとタイツと厚底ヒールで固めている人も、誰も彼もが珍しくなくて、いても不思議じゃなくて、いなくてもおかしくない人。その中にすっかり溶け込んで交差点を渡り終え、駅へと歩き続ける。
その途中。
ぴたりと足を止める。二、三人が、急に立ち止まった私を迷惑そうに避けいった。でもそんなことは私の意識の外だ。
彼だ。きっと彼だ。間違いなく彼だ。見間違えるはずがない。ずっとずっと好きだった人。唯一好きだった人。永遠に好きだと想えた人。
彼がいる。私がコンマ秒前に通り過ぎたそこに彼がいる。
振り返ろう。そう誰かが言った。振り返れば彼に会える。三ヶ月会ってない彼に会える。大好きだった彼に会える。
こくん、と生唾を飲み込んだ。まるで告白の前のように心臓は高鳴った。
そっと、振り返った。
彼は、いなかった。
擦れ違ったのは彼だったのだろうか。彼は私を見つけてくれたのだろうか。彼は振り向いてくれたのだろうか。
何も分からなかった。確かめる術もなかった。
喉の奥が急に締め付けられて、苦しくなった。
好きだ。今すぐにでもそう叫びたかった。
今でも好きだ。そう伝えたかった。
君のことが大好きだ。そう泣きたかった。
永遠だと思った。彼となら永遠に一緒にいることができると思っていた。
それなのに、君との未来がないことを知った。
永遠なのは、私が彼を愛する気持ちだけだった。
それだけでやっていけるほど、私は強くなかった。
だから、私達は終わった。
ほんの少しだけ零れた涙は、冷たい風に攫われた。見上げた高層ビルに埋め込まれた電子パネルが、本日の最低気温一八度を示していた。
──あぁ。どうりで、寒いはずだ。
そっと、バッグの中から取り出した濃紺のカーディガンを羽織る。
また今年も、君を好きになった季節が終わる。
前作は恋を忘れた話、今作は恋を忘れられない話。どちらも夏の終わりらしいお話。
表紙は雨沫さん(https://twitter.com/ama_mt_)の画像をお借りしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
