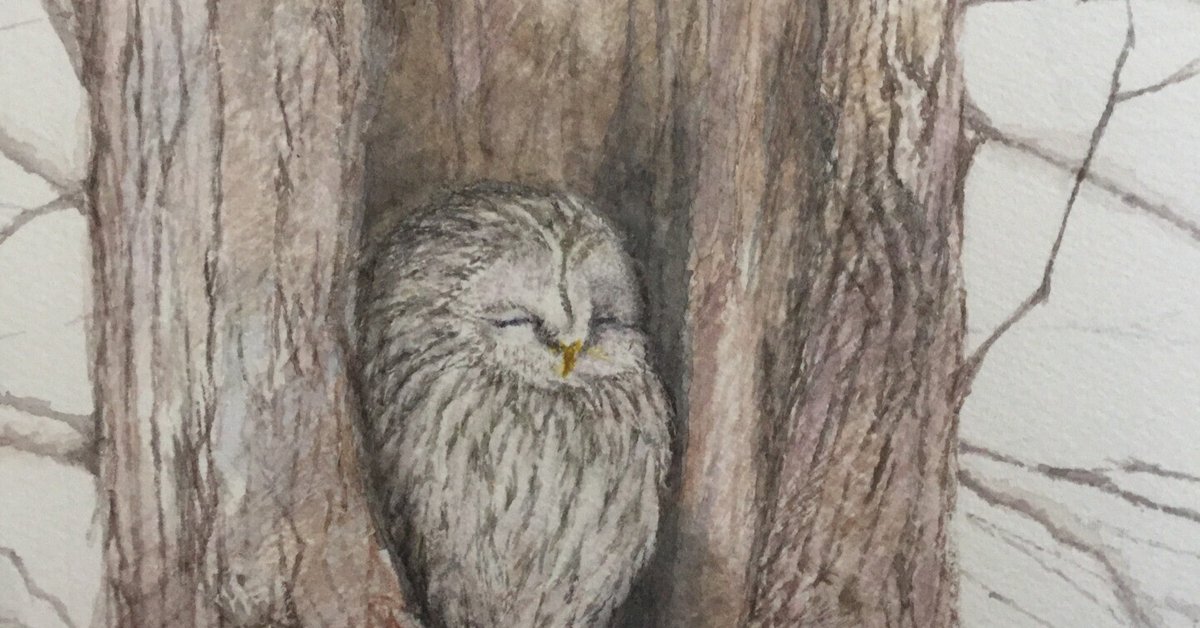
幸田露伴の随筆「古革籠⑥」
古革籠⑥
帯妻蓄妾
僧侶が妻帯するのは、あってならないことである。戒律は厳存している。戒律を破ってはならないのは明らかである。しかし国の法律で禁じられていないので、今は宗祖の仏制に背いて妻帯する者が多い。真宗の人は僧では無く優婆塞(うばそく)なので妻帯することもあろうが、他の仏教各宗の人の中には、「僧である以上は仏制を守るが善い。」と主張する人も少しは有るハズである。であるのに今は堅固に仏制を主張する人はいない。儒教では妾を蓄えることを禁じていない。妾や側室を置くことを許すことが見える。支那(中国)二十余朝の天子の中で明の一帝だけが皇后以外の婦人に接することなく、歴代の高官貴族の中にあっては趙子昂(ちょうすごう)が妻の詞(うた)に感じて妾を蓄えなかった話を残す。儒教では家の断絶によって祠が絶えることを非とする。妾を置くことをキリスト教のようには禁じてはいない。世には回教やモルモン教のようなものも有るのである。儒教を信じる者の中で妾を蓄えて何処に非があると主張する者も少しはあるハズだが、今は誰も蓄妾のことを云わない。国法で妾の存在を認めなくなってからは、実際は蓄妾していても之を隠している。まことに我が国の人民ほど国法を重んじる人民は無いだろう。仏の十大弟子で誰が妻帯したか、先聖や孔子に妾は居なかったか、思うに国法の力の大であるだけでなく、自然の力の大きいことを思う、自然に人は人の赴(おもむ)くところへ赴くのだろう。
注解
・優婆塞:出家することなく在家のままで、仏道修行にはげんでいる人。
・趙子昂:中国・南宋から元にかけての政治家・書家・画家。
・趙子昂の妻の詞:趙子昂の妻の管道昇が、子昂に側妾を置きたいと云われた時に返した泥人の詞(うた)。
爾儂(なんじ)・我儂(われ)、
忒煞(はなはだ) 情多し。
情多き処 熱きこと火の如し。
一塊の泥を把(と)って、
一箇の爾(なんじ)を捻(ひね)り、
一箇の我を塑(つく)り、
咱(わが)両箇(りょうか)を将(い)て 一斉に打破し、
水を以って調和し、
再び一箇の爾を捻り
再び一箇の我を塑るに、
我が泥の中に爾あり、
爾の泥の中に我あり。
爾と 生きては一箇の衾(ふすま)を同じうし、
死しては一箇の槨(ひつぎ)を同じうせん。
(貴方と私、甚だ愛が深い。愛の深い処は火のように熱い。 一塊の泥を把(と)って、一箇の貴方を捻(ひね)り出し、一箇の私を塑(つく)り出して、 その二箇を一緒に砕いて水で練って、再び一箇の貴方を捻り一箇の私を塑れば、私の泥の中に貴方が在り貴方の泥の中に私が在る。貴方と私、生きては衾(ふすま)を同じくし、死んでは槨(ひつぎ)を一緒にしよう。)
若き言と老いての評
私は三十二才の年に思った。
年の若い時は心が浅いものである。善いと思えば善いとだけ思い、悪いと思えば悪いとだけ思って、善い中にも悪いことはあるだろうし、悪い中にも善いことのあることを思わない。この為、人を評価すれば或いは過酷になり、或いは寛大になり過ぎる。事を論じれば或いは理屈に偏り、或いは情に傾く。しかし、自分を欺かないで、そして人を悪く云うことも無く、ただ自分の思うことが正しいと信じ、それ以外を知らないことで大きな間違いを起こすことが少なく無い。これは皆、心の浅いところから出る間違いである。年の若い時はヨクヨク用心して、自分は心の深くない若者であると自覚するのが当然である。
年の若い者と老いた者では、ともすれば心持ちが相反するものである。若い者と老いた者では身体の様子も違い、心の働きも違い、趣味も判断も皆違い勝ちで、老人が東に行こうとすれば若者は西に行くと云い、若者が南に行くと云えば老人は北に行こうとするようなことが多いものである。それで、ともすれば若者は老人を罵り、老人は若者を謗(そし)る。その愚かなことは何れとも云い難い。しかし、若者は未だ老人の心身の状態を知らないが、老人は自分の若かった時の心身の状態を覚えているので、老人の意見に若者が従う方が好いようだ、若者が老人の意見を妄(みだ)りに拒絶するのは、自分を通し過ぎると云えよう。ただし、これも時と場合によることで一概に云うのも馬鹿げている。
若者は老人を愚かと思って居るようだ。若者の眼には老人の云うこと為すこと、その多くが愚かに聞こえ愚かに見える。しかしこれは若者が愚かな証拠でもある。人の賢いところを見ること無くして人の賢くないところを見るのは、その人が賢くないからである。
若者は心身共に盛んなので、間違っても物に屈服するような癖を付けてはいけない。物に屈服する癖が身に沁み心に浸みるのは甚だ忌むべきことで、そうなると英気もやがて日々に衰えて行き、思うことも為せない男に成り果ててしまう。取るに足らない遊びや戯れでも成功しないうちは止めない習慣を付けるが善い。物に屈服しないで事を成し遂げた経験を一ツ二ツ身につけると、次第に自分の心も強くなって行き、その人は常に胸中に勇気の有る眼前に望みの有る人になることが出来るであろう。
若鶏が闘っては勝ち、闘っては勝つ時は、勝つと云うことを知って負けると云うことを知らないまま、堪え難いほどの痛い思いにも能く堪え忍んで、終(つい)には強敵にも勝つものである。また若い時から屡々(しばしば)戦って屡々負けた者は、負け癖が付いて、痛みを忍ぶ勇気も持てず、実際は自分の力よりを劣る者にも勝てないものである。鶏でも負け癖が付いたものを下鳥と云って世間は甚だ嫌う。人に負け癖が付いた者をどうして喜べよう。
若い人が自ら克つ工夫を知らないことほど頼もしくないことは無い。自ら克たない人は、自分で自分を新しくすることを知らない人である。自分を新しくすることを知らない人は、やがて日に日に垢付き汚れて塵埃の中で古び腐るだけである。
若い学生などは、自分の先生に渾名などを付けて侮り軽んじているものである。愚かな振る舞いであることは云うまでも無いが、これはまた許しがたい事でもある。又、自分の父や兄などを、友達同士の会話の中で甚だしく罵って世にも類の無い堅物のように云う者もいて、これ等の輩は、自分が心ある人から爪はじきを受けているのも気づかずに、自分をどれほど偉い者と思い上がっているのか、まことに馬鹿げた至りである。天が見て居(お)られるのも畏れず、人が見ているのも憚らないようになっては、愚もまた極まると云える。
若い人の将来は今直ぐに予測はできない。しかし虚飾することの少ない者は堕落することが少ないと或る人が云っている。また或る人が云う、「私は、学生が不注意と粗暴な挙動とによって空しく棄てられた一寸若しくは二寸三寸の鉛筆が多いのを見るにつけ、将来の国家に取って無用の人物がこの教室から出ること、これ等鉛筆の数に比例すると想わずにはいられない」と。今や私は老いた、しかし私は老いを知らない、今猶盛んである。ただ、今は昔の老人に接するような気持で先人に対するだけである。
観音経と提婆品
観音経に云う、「呪詛諸毒薬(じゅそしょどくやく)、所欲害身者(しょよくがいしんしゃ)、念被観音力(ねんびかんのんりき)、還着于本人(がんじゃくおほんにん)、(私を害そうと呪うのなら、その呪いを観音の力で本人に還着させる)」と。蘇東坡が之を改めようとしたが、蘇東坡は実によく解っている。「還着于本人(本人に呪いを還す)とあっては、普門品(観音経)は提婆品(最勝王経)に及ばないこと遠い」と云う。
注解
・観音経:仏教の教典
・蘇東坡:中国・北宋の政治家、詩人、書家、画家。宋代随一の文豪として多分野で業績を残した。
・最勝王経:仏教の教典
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
