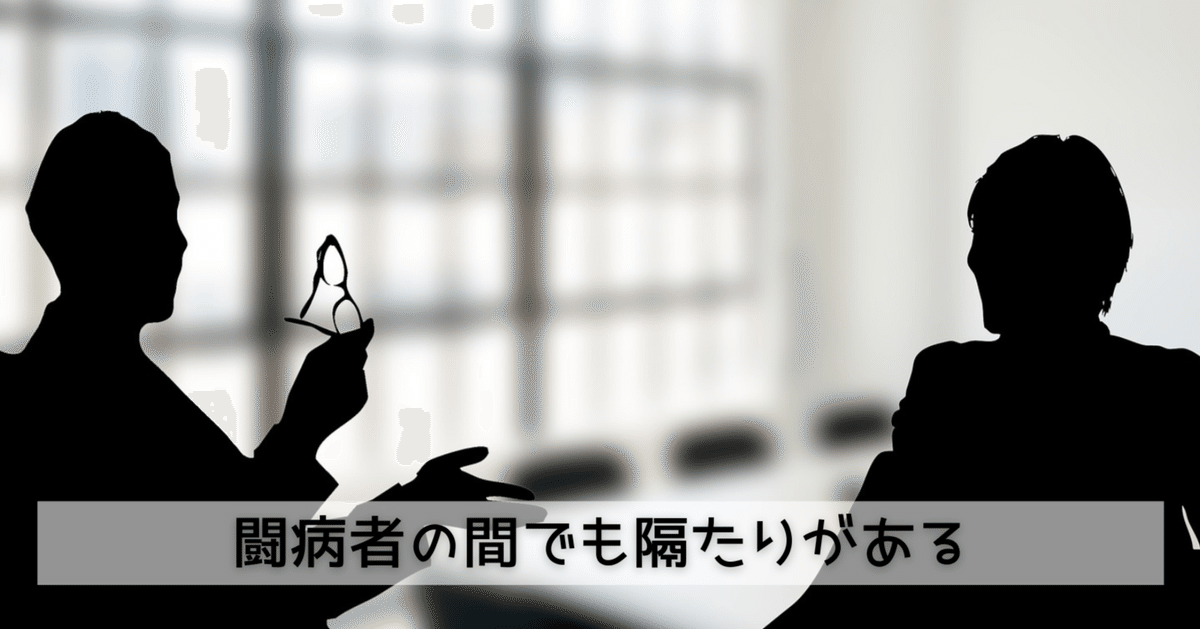
~『闘病者の孤独』を客観的に見つめる~
Twitterを始めて約2ヶ月が経ちました。
様々な情報と共に、色々な想いが巡ってきています。
『感情』を基にして色々考えると、どうしても体調に響いてしまう自分の状況から、ここは一旦冷静に、客観的に『状況記録』としてまとめておこうと思います。
※この記事は約6,200字 7~8分で読めます。

今回は要点をある程度絞って、闘病者の括りの中で『初発者』と『再発者』の観点で物事を見ていきます。
下の表の様にざっくりと抽象化をしていくと、個人的には比較的頭の中を整理しやすいのではないかと考えています。

【抽象化】
線引きするポイントを絞り、細かい部分を無視してざっくりとしたグループ分けをすること。
例えばある図形の特徴に『色(赤)・形(三角)・大きさ(小)』等があったとき、『形』にのみ着目してグループ分けする(色や大きさは無視)様なイメージ
がんに罹患したか否か?という抽象化を行うと、いわゆる健常者か罹患者かという観点で物事を見ることになります。
※ここでの健常者は『がん』にのみ焦点を当てています
この観点からは、健常者、罹患者お互いの考え方等には『ある程度の隔たりは当然生じるであろう』という結論に至りそうなのは、想像に容易いでしょう。
がんという病気の経験者と非経験者ですから、がんに対する考え方や感じ方は当然異なる可能性が高いわけです。
一方で、健常者もさらに抽象化していくと、自分ではなくとも家族や友人ががんを罹患しているケースも当然あります。実際、その様な方々のツイートもとても多く見受けられます。
このことは自分自身が健常者というグループの中にいたとしても『がん罹患者が周りに居ない人との隔たりは生じやすい』ということを示しています。
『自分はがん患者ではないが子供が闘病している健常者』の気持ちを、『周囲にがん罹患者がいない健常者』が汲み取る…ということは、想像するになかなか難しいでしょう。
★
この様に各人の背景を細やかなポイントで抽象化をしていくと、現在闘病している罹患者との隔たりは各所で見受けられる可能性が高いと考えられます。
これを全ての事例で客観、考察を行うと多大な労力も必要になります。
※存命か既に死別してしまったか等の抽象化も…
そのため今回のNoteでは繰り返しになりますが、がん罹患者であっても初発なのか?再発(それ以後も含む)なのか?という抽象化によって話題を展開していきます。
この抽象化を選んだ大きな理由として「考え方や病気の捉え方が想像以上に大きく異なりそう」ということが、ここしばらくTwitterを眺めながら感じてきたことだからです。
ここから先は出来る限り客観性を担保しつつ、論理を展開していこうと思いますのでお付き合いください。
▼ さらに『前提』を定める
ごくごく当たり前ですが、再発者は必ず初発を経験しています。そして初発者はまだ再発を経験していません。
つまり、再発者の方が経験値としては上(あくまで経験の差)であるという事実は、変えることが出来ません。
追々記載していきますが、この『経験』の差が初発者と再発者の隔たりの一因となっていることは、可能性として十二分にあるかと思われます。
もう一つの前提として、その人の置かれている状況や環境によって物事の受け止め方や考え方は大きく異なるということです。
この後にも何度も出てくる記載になりますが、がん闘病に感じる感性に正解はありません。感じたものこそが全てであり、その人その人の正解です。
他人に強要したり、論破して否定するものでもありません。
・年齢
・病状
・性別
・就業環境
・金銭面
・家族状況
こういった点が人によって千差万別である限り、治療や経過、物事の捉え方を完全に同一のモノとして比較することは出来ません。
★
これらの前提があって然るべきなのに、この前提を無視して正解を見つけようとすることに苦しみが生まれているように感じます。
誰かの「正しさ」を押し付けられて、自分自身の心の声とのギャップに胸を痛めてしまっていては、病気に集中して向きあうことも難しくなってしまいます。
あくまでも今回の観点は「正解」を見つけ出すのではなく、現実をできる限り客観視して今後の闘病生活に活かすというところにあると考えています。
▼ 経験という大きな差
先ほども書きましたが、経験の差は非常に大きいと感じています。
「再発者は初発者の気持ちがわかるかもしれない」という立場にありますが、逆に「初発者は再発の気持ちが理解できないかもしれない」という立場にあります。
この前提をしっかりと理解しておかないと、「どうせ言ったところでわからないだろう」という気持ちを根底に持ってしまうことになってしまいます。
そうなると、残念ながら相互理解は確実に破断していきます。実際そのようなツイートをいくつか目にしました(明らかな経験の差による『呆れ』とマウントによるもの)。
罹患者と健常者との間で生じがちな隔たりが、実際には初発者と再発者との間でも生じる可能性が十二分にあるということを、事前にしっかり理解しておかなければいけません。
▼ 時間軸による整理
私を例に致しますと『再々発』という状況でありますので
① 初発時
② 再発時
③ 再々発時
という時間軸を分けて、その時々の心境を比較して考察をすることが出来ます。
これは再発者の特有の視点であり、初発者の方に持つことが出来ません。
となると、再発者としては初発時の感情と再発時の感情をしっかりと分けた上で物事を考える必要が出てきそうです。
初発者の方は再発者の感情を経験していませんので、比較して物事を検討することが出来ません。
初発と再発にそこに本来優劣の差はなく、どちらがツラくて、どちらがツラくないと議論は生まれないはず…と考えています。
▼ 初発者の心理と自分の記憶
私の初発時の感情を、参考として整理してここに記載します。
初発時の自分自身の記憶としては、大きく分けて3つではなかったかと記憶しています。
① 自分の病気や状況に理解が追い付いていない
② 漠然とした不安を抱えている
③「がん」という言葉の重みがすぐ「死」に直結する
もし初発者の方が読まれていたらいかがでしょうか?
再発者の方はこういった心境ではなかったでしょうか?
そして、治療の必要性が眼前に迫られた時に『抗がん剤』についてひたすらに情報を集めていた記憶があります。
① 抗がん剤の効果
② 抗がん剤の可能性
③ 日々抗がん剤は進化していて、生存率が改善している
④ 副作用を抑える薬も以前より随分と開発されている
⑤ 多くの人が通院しながら治療している現実
様々なことをこの時点で知ることになります。
他にも「人は生きている人のうちの50%はがんになる」などという言葉を強く理解するのも、この頃ではなかったかなと思います。
※この言葉の持つ真意が、未だに私には分かりません…
この辺を総合して解釈をすると「がんは誰でもなりうるし、薬は日々進歩しているからきっと大丈夫だよ!」などという少し安直に思えるような結論を当事者(初発者)へ不用意に発して傷つける健常者が出てくることも、想像に容易いかと思います。
悪気はないのかもしれませんが、調べると簡単に出てきてしまう安い情報を良いカタチへと加工して「励まし」というラベリングで初発者へ送る。
ただ、それを初発者の心境としてまだどのように受け止めたらいいかが分からずに困惑している。
そういった状況を示唆するツイートも、日々目にしています。
▼ 隔たりの要因の根本的な考えの違い
長々と前置きと前提の整理をしてきましたが、本題となっている『初発者と再発者の隔たりの大きな要因』が私はここにあると考えています。
それは『悩みの観点』が、初発者と再発者では大きく異なるということです。
・ そもそも癌が治るのだろうか?
・ いつまで生きられるのだろうか?
・ 副作用は大丈夫なのだろうか?
・ また趣味の○○ができるんだろうか?
・ 髪の毛は生えてくるのだろうか?
・ 仕事に復帰できるのだろうか?
こういった悩みがはどちらかというと(もちろん再発者の中にも一定数はあるが)初発者の方のツイートに多いように感じます。
一方で再発者の方の心境としては
・ 次の治療がダメだった場合、他に選択肢はあるのだろうか?
・ またあの辛い治療に自分は体力・精神的に耐えられるのだろうか?
・ 元気になったとして、社会に自分の居場所は存在しているのだろうか?
・ 家族にまた負担を掛けてしまわないだろうか?
・ 再発の恐怖と闘うことがツラい
こういった苦悩のツイートを見かけることが比較的多い様に感じます。
普段は明るくツイートされている再発者の方でも、ふとご自身の心の隙間を吐露されてツイートされた時には、特にこの様なツイートが目立ちます。
繰り返しになりますが、もちろん初発者の方が再発者の方のような悩みを持つこともあるでしょうし、その逆も然り…とは考えています。
そこに『優劣』も『正誤』もありません。
ただ、総じて悩みどころのポイントが、初発者の方と再発者の方では。少し違いそうというのはお分かり頂けたのではないかと思います。
これは当然のことなのかもしれませんが、再発者にとって既に考えたことのある部分での悩み(もしかすると考え終わった悩み)が、初発者の方にとっては初めてであるわけです。
この考え方の違い、持っている悩みの違いがTwitter上で誤解を生み、結果的に大きな隔たりへと繋がってしまっているように感じます。
私なりに抽象化を進めていくと、初発者と再発者の希望を2つの形に分けてることが出来るかと思います。
初発者の方は
今回のがんが『治る』ことを望んでいる
まあ、これは当たり前で「生きたい」という気持ちからがんを治したいに繋がっています。
同様のことが再発者の方にももちろん言えるのですが、少しだけ考えの方向性が違っていて
今後『再発をしない』ことを望んでいる
になるのかなと思います。
「生きたい」という生への感情の根本に違いは無いのかもしれませんが、再発によって1度手に入れた希望(初発を一度乗り越えた)を再び失うことを、初発者と違って強く恐れている様に感じます。
私も一番ツラかったのは再発時かもしれません…。
再発によって人生の選択肢が減ってしまうわけであり、今後可能な治療の数も減ります。人生がもう一度狂わされるのです。
そういった経験をしてきている再発者の視点としては、『治る』というよりかは『再発をしないで欲しい』という気持ちの方が強く出ている様に感じます。
治ると信じて治療を続けてきた気持ちがもう1度折られて、再び立ち上がって前を向く辛さを再発者は知っているからなのかもしれません。
▼ 私からの1つ所見
ここまで長々と読んで頂き、ありがとうございます。
このNoteをまとめるにあたって一つ大きく省略している部分があります。
まだ正式にまとめきれておらず、言葉として表現するには心もとない部分はあるのですが…
『生きる』と『善く生きる』
この部分の考え方をしっかり整理して表現しなければ、正直本件についてもなかなか具体的な結論に至らないのではないか…と考えています。
ただ、この部分はかなりセンシティブな部分も含まれているため表現として難しいのが事実です。そのため、まとめるのに時間を要しているので、次回以降のまとめを期待していて頂ければと思います。
(一部抜粋)
「生きる」>>「善く生きる」の不等式がまかり通っているのが現代社会で、例えば 自分の命を繋ぐこと(生きる) >> 妊孕性の保存(善く生きる)の構図が本当に簡単に生まれてしまっている(ほかにも例は多々ある)。そしてそれを罹患者は受け止めさせられている。
命を繋ぐことを優先する外野(医師・家族・友人等)の意見はいわゆる「正しい」ものではあるが、本人の意志である「善く生きる」という望みがなぜここまで蔑ろにされなければいけないのか?という疑問と問答である。
健常者が自身を高めたり、改善して努力すること(美容に投資したり、給与アップに向けて資格勉強をしたり)も「善く生きる」ことに変わりないのに、なぜ罹患者は「生きる」>>「善く生きる」の不等式をここまで「正しさ」として受け止めさせられるのだろうか?
その省略部分も絡んでくる問題ですが、相手の考えに「正しさ」を押しつけることが結果的にどれほど人を苦しめるのかというところを今回のNoteを通じて理解して頂ければと思います。
健常者と罹患者との間に隔たりが生まれるのは、やはり起こりうる可能性の高いことです。人は経験していないことに疎く、安易に自分の考えを述べることで相手を傷つけてしまうことが起こりがちです。
本件では客観的に初発者と再発者の違いを今回のNoteでまとめてきましたが、初発者の方の悩みが、再発者の方ににとってはすでに考え終わっていることが多いという点が伝われば何よりです。
相手の立場や状況、年齢や性別等においてその時に抱えている悩みには違いがあります。もし、大きな悩みとして抱えている方がいるのであれば、むしろそこにアドバイス(あくまで寄り添い)を渡して、闘病生活を共に歩んでいく必要があるのではないでしょうか?
人間の『承認欲求』は罹患者の中でも当然の様に生じている様で
・ 自分の病気の方が大変だ
・ なに小さなことにウダウダ言っているんだ
・ そんな悩みなんて自分に比べたら贅沢なものだ
そんな風に自分をより一層悲観的に捉えて相手を制して自分を保っている…としても、私個人としてはあまり気分のいいものではなかったです。
もちろんそのツイート主の方々の状況を完全に把握しているわけではなく、「気分が良くない」というのはただの私の感想になるのですが…
※ 一方で他者との比較で自己を保つという考え方は、人間にとって本能でもあるので否定できないことも事実です。この辺りも執筆に向けて準備を進めていますが、いつになることやら…(^^;)
世間一般で言う「マウントを取る」というのを「上から」ではなく、なぜか「下から」取る様な表現をされている人たちも、少なからずいるということをこの数ヶ月間のTwitterで学ぶことになりました。
▼ さいごに

客観的な事実を抽象化して一つのまとめとしました。抽象化の仕方によっては、また別の結論になるかと思われます。
・考え方の違いの可能性
・持っている悩みの違い
・現在の状況、環境下
全てを理解することは出来ませんが、様々な方と触れていく中で今後も自分の感性や知見の糧としていければと思っています。
表題の意としては『闘病者の背景には一つとして同じものはなく、それを理解してもらえない(特に罹患者同士)と感じた時に「孤独」を感じてしまう』ということでつけさせて頂きました。
ただでさえ健常者と罹患者の認識の違いは生まれやすいです。そこに加えて、罹患者同士でも認識のズレが生じてしまうと…あまり良いカタチではないかなと感じてしまいます。
誰しもが歩み寄り、全てを理解できないとしても寄り添う姿勢でツラい闘病生活を乗り越えていければと願っております。
ろくさん
