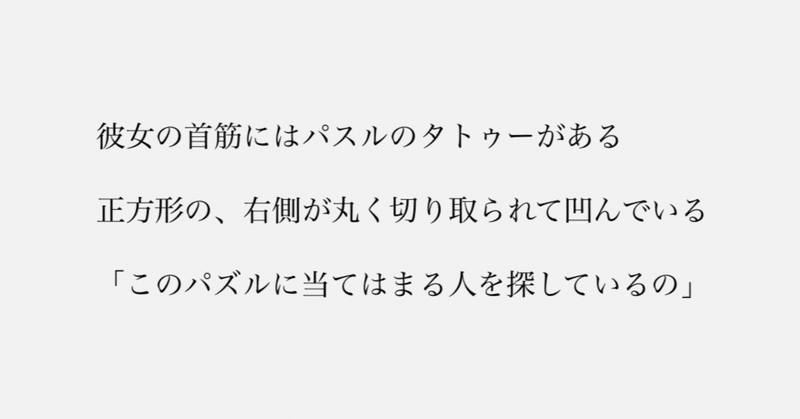
きっと僕らはこのままで
彼女の首筋にはパズルのタトゥーがある。
正方形の、右側が丸く切り取られて凹んでいる。
「このパズルに当てはまる人を探しているの」
夜の八時頃。街の中心で食事を済ませた後、静かな場所を求め行く先を決めないまま歩いていた時、彼女はそう呟いた。
僕の視線に気が付いたのだろう。その欠けている穴に見惚れていたのが恐らくわかったのだ。それは彼女の白く透き通った肌の上では違和感がある、いびつなデザイン。
欠けている穴が、どこか深淵へと続いているような、三日月のその先を見るように吸い込まれていた。
「それは、誰かと一緒に彫ったものなの?」
「ううん、そういう事では無いよ。私が一人でいれたもの。けれどそうして本当に出会えたら、運命ってあるって信じられそうな気がするの」
少し前を歩いていた彼女は、振り返りながら笑顔でそう言った。彼女の濁りのない黒い艶やかな髪の毛がふわっとなびいた時、同時に桜の花がひらりと落ちた。
僕が写真を撮る人間だったなら、間違いなくシャッターを切らなかった事を後悔するような、そんな一瞬。
「詩奈子さんは、運命を信じていない?」
「あらら、清吾君は運命を信じているみたいな言い方ね」
「信じているというか…。訪れる人には訪れるし、訪れない人には訪れないというか。いや、これも違う気がするな」
「いいよ、ゆっくりで」
「うん」
彼女は僕と違って多くの事を話さない。僕は話ながら思っている事を組み立てる。そんな僕の組み立てを、彼女はいつも待っていてくれて、そんな彼女が僕は好きだった。
「運命って、意識していても、意識していなくても求めていた出来事が訪れるって事なんじゃないかな。昔の友人とたまたまホームで再会するとか。それが只のクラスメイトだったなら、それは偶然になるんだろうけど、かつての未練ある恋人だったなら、ああこれは出会うべくして出会ったんだって、運命だって、そう解釈しそうなものじゃない?」
「ふむふむ。君の例えはいつもわかりやすくてお姉さんは助かるよ。要は捉え方次第って事かな?」
「まぁ、物凄く短く言うと、そうだね」
「うんうん、わかる気がするよ」
彼女は僕よりも三つ年上だった。お姉さんらしくといって、いつも少しだけ背伸びをしながら後ろ手を組んで歩いている。
桜の花が風で散る様子を眺めながら、こちらを振り返らずに彼女は続けた。
「わかるな~、わかっちゃうな。私ももう大人だからさ。突き詰めればそういう事だろうなってさ。でもさ、そういう理屈を度外視するような、圧倒的な見えない出会いを、私は探しちゃってる」
ひらりと落ちた桜の花弁の先に彼女は手のひらを構えていた。
花弁を受け止める事が出来たのか、するりと抜けてしまったのか。
僕の距離からはわからない。
「だからなんとなく、本当に勢いで、こんなタトゥーを彫っちゃったのよ」
「ふうん。まぁ、詩奈子さんには逆に似合っていると思うよ、素敵だと思う。でもその運命的な出会いを求めるようになったのはいつからなの?」
「さあ~、いつからでしょうね」
彼女は先に近くのベンチに腰掛けていて、コンビ二で買っておいた缶ビールを開けていた。
彼女の昔の話はあまり聞いた事が無かった。話すタイミングも無かったし、何故か知りたいとも思わなかった。
出会った頃から既に僕の中の彼女は完成してしまっていて、その不透明さを背負っている彼女が魅力的に感じられていたからだろう。
だから僕はまた、これ以上追及するのを辞めた。
「ところで清吾君、展示会の方は順調なの?」
「あぁ。明日陸男達と会場の下見。置き方とか、照明とか諸々。服はまぁ、間に合うよ」
「へぇ~、かっこいいじゃん。やっぱりそういう物作り?している人って私の周りにはいないから、すごいね」
「すごくなんか無いよ、打ち込んでいるベクトルが違うだけ。僕は詩奈子さんみたいにエクセルとかプログラムとかわけかわらないし」
「そんなもんか、じゃあどっちもすごいね」
「そう、どっちもすごい」
僕も彼女の隣りで缶ビールを開けて一口飲んだ。相変わらずビールのおいしさはわからない。けれどレモンサワーでは無くビールを選ぶという小さな事でさえ、最低限年上の彼女との差を少しでも縮めたいという思いから始めた事だった。
彼女は所謂会社勤めをしている。旅行の予約に関するなんやかんやだとか。アイティーという響きだけで、僕の歩んできた道とはかけ離れている人だとわからされる。
僕はと言えば服飾の専門学校を中退してもうすぐ半年になる。中退の理由はなんとも言えない、これ以上学費が払えないからという理由だった。
何か表現がしたかった。この世の中になのか、自分に対してなのか、誰かに向けてなのか。
心の陰に陽が当たるような、暗い夜に火が灯るような、そんなささやかでいいから救われるような。
それがなんなのかわからずに、ただぐるぐるとそのまま洋服を作り続けている。来週に控えている展示会も決してそれらの想いが昇華出来たような完成品では無く、何にも慣れていない自分が、何かをしているという錯覚の安心を求めて開くものだった。
彼女はそんな僕を褒めてくれるのだった。それが嬉しく、そしてまるで僕自身では無く、そんな珍しい存在として見られている気がして、たまにひどく虚しくなる。
「詩奈子さんは、明日は仕事?」
「そうね、いつも通り。明日はでも午前は有給取ってある」
「じゃあ、どうしよっか」
缶の傾け方から、最後の一口なのがわかった。
「それじゃあ、ね。いこっか」
「ん、行く」
僕らはそのまま、いつも通り、ホテルへと向かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
