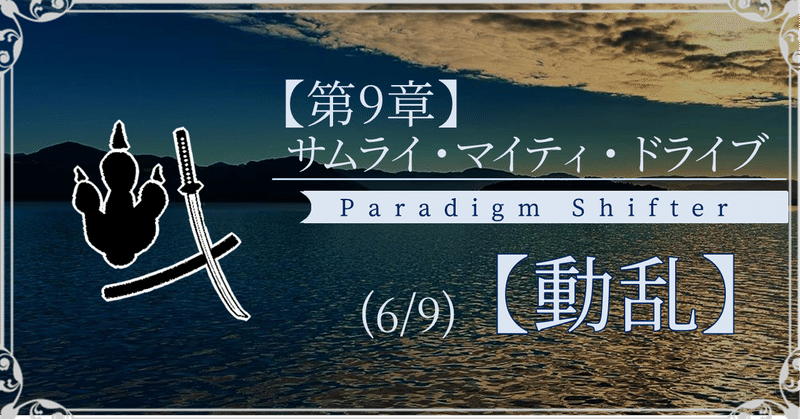
【第9章】サムライ・マイティ・ドライブ (6/9)【動乱】
【単騎】←
「……なにか、起こったのか?」
砦のなかに響きわたる警鐘の音で、アサイラは目を覚ます。床をともにしたはずの女領主の姿は、すでにない。
身なりを整えて、あてがわれた部屋の外に出れば、城内の兵士はおろか、女たちや子供たちも慌ただしく行き交っている。
「あ、土左衛門の旦那ッ!」
「土左衛門は、勘弁してくれないか……」
廊下を走る女衆の一人が、アサイラに気がつき、声をかける。
「それより、なにがあった?」
「なにをのんきな顔をしているのさ……賊が出たんだよッ!」
「……賊?」
アサイラは、いぶかしむ。小規模とは言え、ここは立派な城塞だ。山賊のたぐいが現れた程度で、これほどまでうろたえるものだろうか。
「それで、ナオミさまが討伐に向かったんだけど……ああ、もう! 説明している時間も惜しい……気になるんだったら、ついて来なッ!!」
女は、一通りまくし立てると、廊下を駆けはじめる。アサイラも、そのあとを追う。
すぐにアサイラは、女が砦の城門に向かっていることに気がつく。城内のほとんどの人間が慌ただしく右往左往しているが、その中心地は正門の方角だ。
「……よぉし、扉はあまり大きく開けるなッ! いつ、どこから賊が飛び出してくるか、わからねぇぞ!!」
「ああ、かわいそうに『薙鳥<ちどり>』……いま、なかに入れてやるよ」
男どもが城門を支えているすきに、女衆がなにかを砦の敷地へと引き入れる。騒ぎの中心が、満身創痍で倒れこんだ小型恐竜であることに気がつく。
鞍と手綱を装備した騎乗恐竜の回収が終わると、男たちは急いで城門を閉めて、かんぬきをかける。女たちが、止血用の布と薬草を持って、集まってくる。
「おう、土左衛門の旦那かい」
「土左衛門は、よしくれないか……それよりも、なにがどうなっている?」
城門を開閉する力仕事を終え、一息ついた男が、アサイラに話しかける。
「賊の討伐にいった御前さまが、戻ってこねえ……帰ってきたのは、騎竜の『薙鳥<ちどり>』だけだ」
「篝火の進軍速度、遅くならねえぞ! どんどんこっちに来る!!」
会話するアサイラたちの頭上で、見張り台の兵士が声を張りあげる。目前の男の顔色が青ざめ、周囲に同様が広がっていく。
「……おい、『薙鳥<ちどり>』! そんな身体でどこに行くつもりだい!?」
閉ざされた城門のまえで、別の騒ぎが起こる。人だかりが割れたかと思うと、騎竜がよろめきながら立ち上がり、アサイラのほうへゆっくり近づいてくる。
見慣れぬ肉食恐竜をまえにして、一瞬、異邦人の青年は息を呑む。だが、相手に敵意がないことは、すぐにわかる。
ナオミの騎竜は、アサイラの服のすそをかみ、引っ張ろうとして、ふたたび倒れこむ。小型恐竜の手当てをしようと、女衆が寄ってくる。
「……賊が来たってのは、湖岸側の方角でいいのか?」
「ああ、そうだが……旦那、なにをするつもりだ?」
「俺が、賊とやらを止めにいく」
「なに言ってるんだ! それに、いま、城門を開くわけにはいかねえぞ!?」
「……必要ない」
アサイラは、見張りやぐらのうえにつながるはしごに手をかける。そのまま、ぐいぐい登っていく。
「旦那、武器はどうするんだ! 刀や槍はぁ!?」
「それも、必要ない」
足下から聞こえる男の怒鳴り声に、アサイラは小さく返事をする。
「……ヒイッ!?」
すでに士気が砕けかかっている見張り台の哨戒兵は、アサイラの姿を見ただけで腰を抜かしそうになる。
異邦人の青年は、櫓のうえから自分が溺れた湖の方角を見やる。松明らしき、複数の光点が森の入り口あたりにさしかかっている。
「ウラア──ッ!」
雄叫びをあげつつ、アサイラは見張り台から跳躍する。わずかな対空のあとに、青年は難なく地面に着地する。
衝撃を吸収するために曲げたひざを伸ばしつつ、闇のなかにたたずむ森の方角に視線を向ける。夜空をおおう厚い雲の端から、月光がこぼれている。
「土左衛門の旦那ァ!!」
櫓のほうから、女衆の頭目の声が聞こえて、アサイラは振り仰ぐ。
「土左衛門は……」
「刀や槍はいらないそうだけど、こいつは持っていきな! 役に立つよッ!!」
文句を言おうとしたアサイラに向けて、束ねた縄のようなものが投げよこされる。青年は、見慣れない道具を受け取ると、身を翻して駆けだした。
───────────────
「砦には、ナオミ御前のほかにまっとうな戦力は無し。そうだな──ン?」
暴威竜の鼻先が、ばきばきと梢の枝をへし折るなか、武将ツバタが泰然と口にする。
この土地が戦場になることを前提としていないなど、大御所陣営どころか、ほかの勢力の武将ですら知っていることだ。
使うあてのない兵力など、穀潰しに等しい。ゆえに、配備される理由もない。
「仮に、幾ばくかの兵がいたとしても、身どもの忠臣たるこなたらと『跋虎<ばっこ>』のまえには問題とならぬ。違うか──ン?」
「御意にッ!」
暴威竜のすぐ横を走る迅脚竜の背にまたがった副官の武将が、律儀に声をあげる。
ナオミ御前の奇襲には驚かさせられたが、それも退けたいま、予測される障害は微々たるものだ。ツバタは、巨竜のうえでほくそ笑む。
「──止まれ」
そのとき、一行の頭上から男の声が森に響きわたる。サムライたちは、迅脚竜の脚を止め、槍や弓をかまえる。
「何者だ! 名乗れッ!!」
「この次元世界<パラダイム>では、盗賊相手にも名乗らなきゃならないのか?」
ツバタは、身構えつつ、闇のなかに目を凝らす。家臣たちの篝火が、わずかに樹上を照らし、視界の確保の助けとなる。
大樹から伸びた野太い枝のうえ、見慣れぬ装束に身を包む一人の男が立っていた。
───────────────
(バッド……これはまずいだろ。身体が動かない)
ナオミは、真夜中の黒い水のなかをゆっくりと沈んでいく自分を自覚する。巨竜の尾の衝撃が重かったためか、もがくことすらままならない。
あるいは、いままさに、自分は死後の世界に向けて落下しているのかもしれない。赤毛の女の脳裏に、そんな考えがよぎる。
天地が逆転した状態で、足下の水面がわずかに明るくなる。雲に隠れていた月が、顔を出したか。ナオミは、幻想的な湖中の光景を、どこか他人事のように眺める。
(そういえば──)
女衆が子供たちに話していた、おとぎ話を思い出す。イクサヶ原の中央に鎮座する巨大な湖、その底には竜宮城があって、この世の楽園が広がっているという。
このまま自分も、この世ならざる場所へと召されていくのだろうか。ナオミは、ぼんやりと考える。
(──それは、嫌だろ)
赤毛の娘の口元から、気泡がこぼれて、足の先へ向かって登っていく。たとえ、楽園だとしても、ひとつところに捕らえられたくはなかった。
ただ、どこか遠くへ行きたかった。ひたすらに、自由になりたかった。あのときだって、そう思って、どこまでも蒸気バイクを走らせた。
(ああ、そうだ……)
この世界──イクサヶ原にやってきたときも、いまと同じような状態だった。
蒸気都市郊外の濃霧のなか、舗装されてすらいない地面のうえを走り続けていると、ふと、足下がなくなった。
白煙のような霞に包まれていたせいで、最初、なにが起こったのかわからなかった。正直なところを言えば、いまだって、あれがなんだったのか理解できない。
気がついたとき、赤毛のバイクライダーは、蒼天のうえから自由落下していた。遙か上空から、巨大な恐竜の足跡のような湖と、その周囲に広がる緑が見えた。
そのまま、湖面に着水した。衝撃で意識を失い、そこから先のことは覚えていない。漁師に救出されたときには、蒸気バイクは行方知れずになっていた。
(……んん)
なにかに、呼ばれたような気がする。ナオミは、わずかに動く首をうえに向けて、湖底を見やる。赤毛の娘の背を押すように、月の光条が差しこんでくる。
湖の底が、見える。明らかに人工物とわかるものが、水没している。黄金比の曲線を描くフォルム、真鍮色の輝きを放つ高純度のオリハルコンフレーム……
(よう、相棒。迎えに来てくれたのか?)
ナオミは、目を細める。そこにいたのは、あの日、自分のまたがっていた蒸気バイクだった。どれだけ水没していたかわからないというのに、錆ひとつ、ついていない。
相棒の周囲を守るように、湖底には巨大な全身骨格が横たわっている。恐竜のものではない、正真正銘の真龍──ドラゴンの白骨死体だ。
(ウチの死に様としては、まあ、悪くないところだろ)
末期の幻覚だと思いながら、赤毛の娘は手を伸ばす。口元に、安らかな笑みが浮かぶ。蒸気バイクのハンドルに、指が触れる。
しっくりと、手になじむ感触が伝わってくる。まるで、失われた自分の半身を取り戻したような感覚を、ナオミは味わう。
フルオリハルコンフレームの相棒を抱きしめて、赤毛の娘はまぶたを閉じた。
→【再動】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
