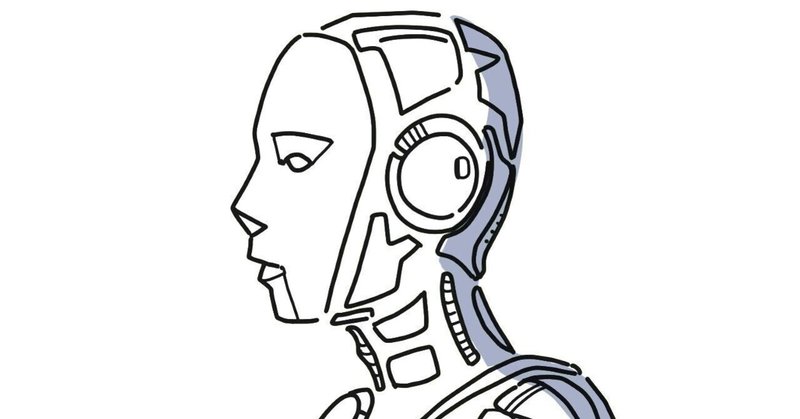
アイの物語①ー序説ー
山本弘さんの長篇『アイの物語』は、昨今フィクションから遠ざかっていた私(彷蜃斎)が、久しぶりに熱中できた、いや舌を巻いた小説でした。 今、フィクションから遠ざかっていたと言いましたが、正確には全く小説等を読んでいなかったわけではありません。読んではいましたが、以前ほど面白いと思えなくなっていたというのが正確なところです。
いつものように、図書館で偶然手にした本が『アイの物語』でした。作者の山本弘さんが、1997年から2005年にかけて断続的に発表した5つの短篇小説に、2つの中篇小説を書き下ろすことと同時に7つの物語を巧みにつなぐ「インターミッション」と呼ばれるショート・ストーリーならびに「プロローグ」と「エピローグ」書き加えることで、2006年に長篇小説あるいは短篇連作集に仕立て直した労作です。
読みながら、まず気がついたのは、この作品はアメリカのテレビドラマ「スタートレック・シリーズ」の影響をうけて書かれたのだろうということでした。
「スタートレック」は映画「スターウォーズ」の影に隠れて、日本ではいささかマイナーな印象のあるテレビ・シリーズですが、何を隠そう彷蜃斎はその大ファンでして、その影響下に書かれた小説を、これまで知らなかったことに恥じ入った次第です。
その「スタートレック」ですが、詳細は ウィキペディア等に譲りますが、とにかく極めて先進的なコンセプトで作られた作品なのです。物語の時間軸は22世紀から24世紀で、光速を超えるテクノロジーを獲得した人類が、地球を盟主とする惑星連邦を樹立し、多くの宇宙人たちと交流しているという設定で、現在のところ全部でテレビドラマシリーズが7本、2本のテレビアニメ、13本の映画が制作されています。
最初の「スタートレック」は1966年に放送されました。日本では確かフジテレビだったと思いますが、「宇宙大作戦」(響きがなんとも昭和ですが)というタイトルで日曜日のお昼過ぎに放送されていたことを記憶しています。
当時、テレビのスピーカーの前にマイクを置いて、音声のみをソニーのテープレコーダーで録音して、何度も聴いていました。いうまでもなく、当時のテープレコーダーのテープはカセットテープの前の形であるオープンリールですが、若い方にはわかりますでしょうか?
昔話が多くて、なかなか本題に入れませんが、『アイの物語』の第1話「宇宙をぼくの手の上に」はインターネット上で、「スター・トレック」さながらの物語(冒険活劇)をリレー形式で紡ぎ出していく同好会「セレストリアル」のお話で、初出は「SF Japan」(おそらく雑誌)の2003年冬号の発表されています。
2003年といえば、邦題「宇宙大作戦」(いわゆるオリジナルでTOSと呼称されています。)が1969年に終了し、新たに邦題でいえば「新スタートレック」(TNG)が1987年に始まり、おそらくは好評だったので、スピンアウトの「ディープスペースナイン」(DS9)、ついで「ヴォイジャー」(VOY)と同じ世界観でシリーズ化され、最後に「TOS」の前の時代を描いた「エンタープライズ」(ENT)が放送中だった頃です。
第2話「ときめきの仮想空間(ヴァーチャル・スペース)」は初出が「ゲームクエスト」に1997年5月で、タイトルから容易に類推できるように、インターネット上の仮想空間で繰り広げられる恋愛譚、第3話「ミラーガール」は一時期流行した「たまごっち」の究極の発展型である〈ミラーガール〉をめぐる物語で、初出が「SFオンライン」1999年3月29日号、一話飛んで第5話「正義が正義である世界」は「ザ・スニーカー」2005年6月号発表で、ゲーム内のキャラクターであるスーパーヒーローを主人公にした物語です。
これら全ては、個人的には新スタートレック以降採用された「ホロデッキ」と呼ばれる「仮想空間」の未来的進化形態の影響下にあると想像されます。「ホロデッキ」とは、現在の二次元的仮想空間が三次元で体験できるというもので、登場するキャラクターは一種の自意識を持つに至っており、「ヴォイジャー」では、人間を治療するホロドクターまで現れています。
さらに、「新スター・トレック」では、アンドロイドのデータというキャラクターも登場し、彼が単なる機械から人間として成長する、あるいは人間から同じ生物として認知されるまでが描かれています。
山本弘さんは、このアンドロイド・ストーリーとホロデッキキャラクター譚を巧妙に結合させることで、新しいドラマを紡ぎ出したといえるでしょう。
頂戴したサポートは、活きた形で使いたいと思っています。是非、よろしくお願い致します。
