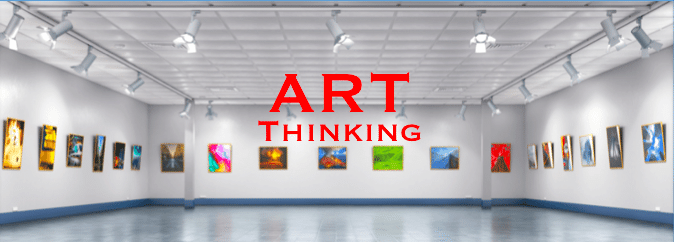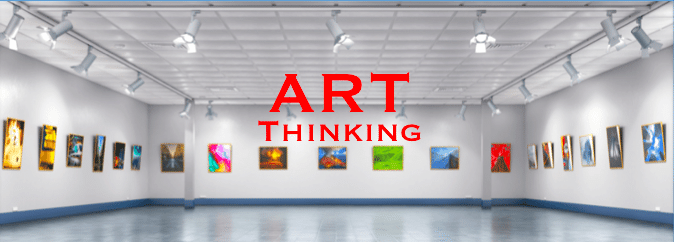【AIの衝撃、、冷や汗が出た】
2040年に来ると言われていた「シンギュラリティ」が2025年頃に始まる?!話題の人工知能の創造性をチェックしてみたら大変なことに、、
シンギュラリティとは、AIが人間の能力を超える時点 や、それにより人間の生活に大きな変化が起こるという概念のことですが、2015年にコンピュータ囲碁プログラムAlphaGoがプロ棋士を破った頃は、AIというよりコンピューター(電子計算機)の賢い仕事というイメージでした。ところが、今話題になっているChatGPT(https://chat.op