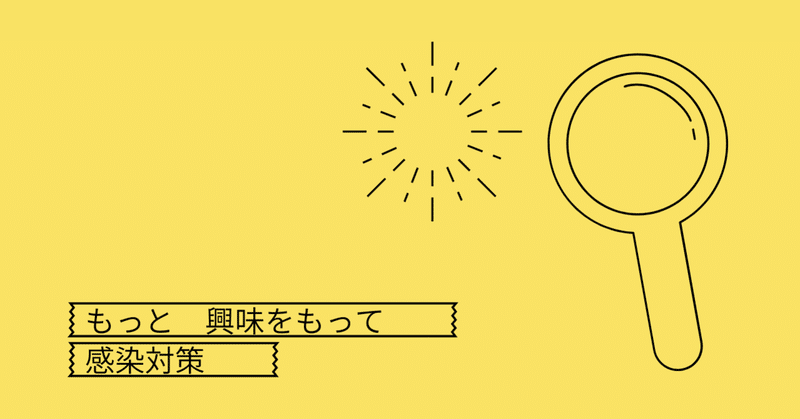
感染に対する意識のギャップ
ステルスオミクロンまで出てきて
コロナウイルスが猛威をふるっている現状で
病院とは違う
高齢者施設での感染対策
如何に、施設に持ち込まないか、広めないか
予防するのが感染対策
基本的なところからだと
スタンダードプリコーション
看護師に説明すれば、根拠が分かっているので
1~10の「1」だけを説明すれば「10」まで理解してくれる
いわゆる、「普通」。
でも、介護士は医療を含めた「感染」というモノを
かじる程度しかカリキュラムに無いようで
入職してから、勉強会や経験で習得していく
1~10の説明を「0.5」刻みで説明しないと分からない
「そこまでやるの?」
「めんどくさい。」
最初は、介護士が発しているその言葉を聞いて、結構傷ついていたが
最近は慣れた
根拠が分かれば、無駄なエプロンは使わなくて良いし
場面場面で必要なPPEを着用すれば良い
「根拠が分からないから無駄な手技が増えてめんどくさくなるんだ」
と、爆発したくなるときがある
その中でも感染に意識の高い介護士もいる
そういう人は、「めんどくさい」という気持ちがないので
説明すると理解力もあり実践力もある
とても、頼もしい人材
感染対策をしていて思うことは
病院よりも高齢者施設の感染対策の方が大変だ。ということ
建物の構造が全然違うので、ゾーニング含めた対策が難しい
そして、病院は、治療をする場なので、徘徊する方やマスクができない方は殆どいないでしょうが、高齢者施設は集団生活の場で殆どの方の現病歴には認知症の文字がある。しかも、大部屋が多く、個室はかなり少ない。さらに、居室の出入口は扉ではなくカーテンだけの所もある。
以上のことを考えると
施設の構造や利用者の現病歴は変更することはできないので
介護福祉士のカリキュラムに感染を充分に組み込まなければいけないのでは?と考える。
力を持っている方達。
是非、考えてみていただきたい。
認められた感があって やる気が出てきます
