2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集1: Juu & G. Jee, Francesco Tristano, Benny Sings, Caroline Shaw, Lena Andersson, Deerhunter, OGRE YOU ASSHOLE
2019年ベストアルバム1: 100位〜76位、2019年ベストアルバム2: 75位〜51位で取り上げたアルバムから前提の説明にある程度文字数を要する等して、やや長めの文章になったが1記事にするほどでは無い、という文字数で落ち着いたレビュー集。最初からお目通し頂きますと有り難く存じます。
99. Juu & G. Jee - New Luk Thung (นิวลูกทุ่ง)
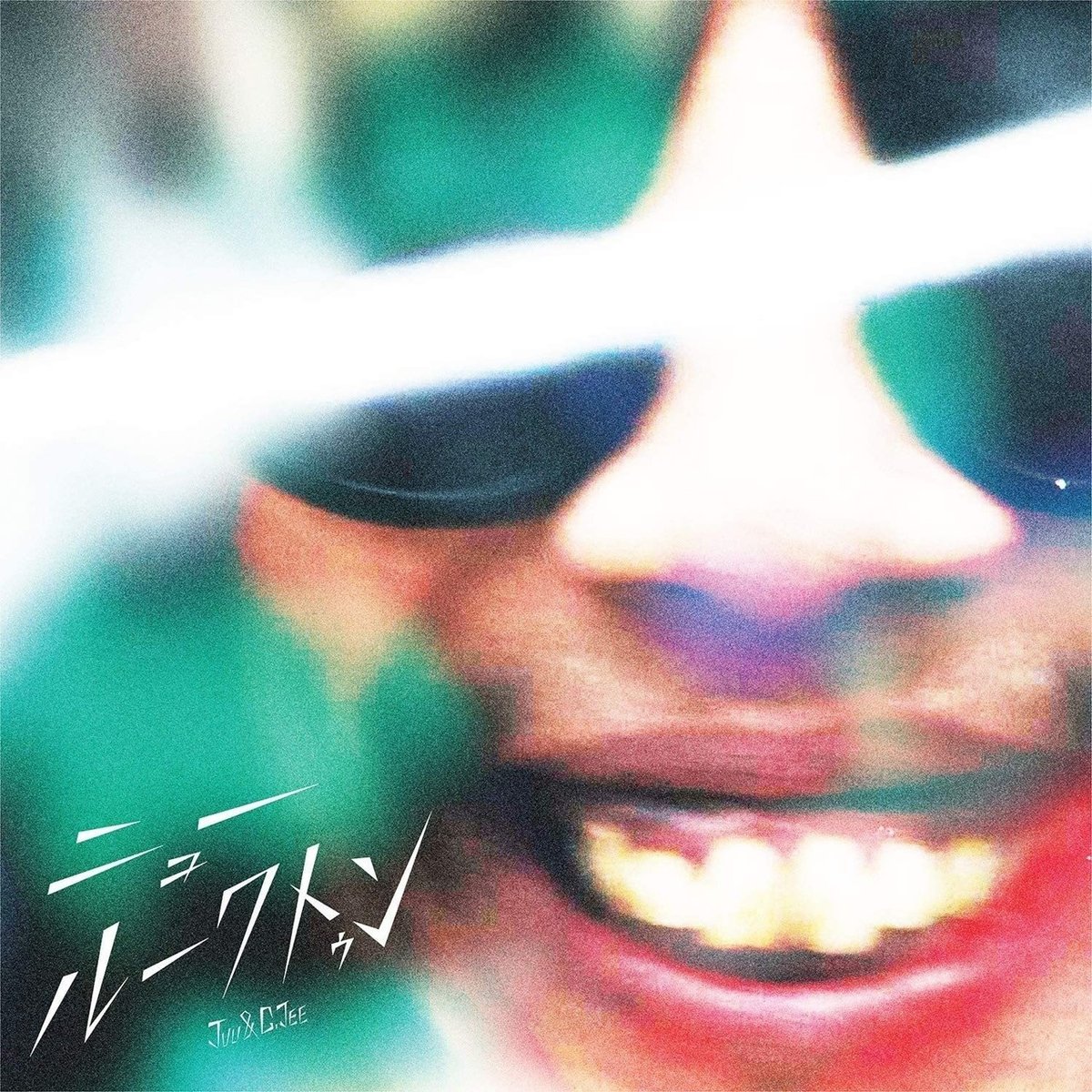
タイの男声ラッパーJuuとその弟子(タイではポップ・ミュージックの世界でも師弟制度が一般的)である女声シンガーG. Jeeの連名作。stillichimiyaのYoung-Gが全面参加でstillichimiya全員のマイクリレーが聴ける曲もあり。
リリースは日本のレーベルEm Recordsから。これまでにも東南アジアの音源は古い歌謡曲等を出してきたほか、日本の弓神楽や木崎音頭も伝統音楽リスナーの範囲を超えて話題になった。その他西洋的なものもミニマルやインダストリアルと先鋭的な作品が多く、いわばグローバルに対してのローカルな音楽の紹介に徹してきたレーベルだ。それが本作は、国籍こそ日本でも英語圏でも決してリスナー数が多いとは言えないタイのアーティストであるし、ラップ自体もタイ語と日本語が中心ではあるが、概ねその他のYoung-G仕事からも想像できる、(一部古いタイ音源のサンプリングや伝統楽器がメインリフのトラックもあるにせよ)USヒップホップからの影響を前提としたどちらかといえばグローバルなサウンドのビートが主だ。
では何故Em Recordsがそんな作品を出すのか。それはLP封入のライナーにあるように、ルークトゥン(Luk Thung)という音楽は楽器編成や作編曲のスタイルでは無く、田舎の生活を歌う歌詞によって定義されるからだ。つまりヒップホップだろうがヘヴィメタルだろうが歌詞さえルークトゥンの様式に則っていれば良い。欧米のポップ・ミュージックとその強い影響下にある音楽だけを聴いていればわからない価値観が、欧米の音楽をなぞったサウンドの元で尚アイデンティティを失わずに鳴る。こういった”ガワ”の部分だけでも本作は十分に面白い。
シンプルにヒップホップとして聴いても良質。大麻解禁を訴える歌詞からしても実際に影響もあるのだろう、レゲエ的でもあるJuuの塩辛い声が時にかなり大胆なヴォーカルエフェクトを伴って演出されるストーン感に酔う。
93. Francesco Tristano - Tokyo Stories (2LP)

この異端のピアニストについて皆が皆知っているわけでも無いと思うが、彼のキャリアを思い入れ込みで紹介するとそれだけで文字数を食ってしまうので、ここまでの過程については八木皓平によるMikikiのこの記事を参照されたい。キャリアの事実関係について素晴らしく整理されているのみならず、過去作に触れる際度々苦めの評価になりつつもそのスタイルに期待を持って追っているあたりが個人的に共感出来る。
が、肝心の本作の重要点をどこに置くかに関しては少々解釈が違う。八木がフォーカスする過去作から連なるクラシカルとテクノの融合アプローチの延長よりも、私にはこと前半における誤解を恐れずに言えば俗っぽくもあるポップな映画音楽めいた叙情表現、ここに本作のキモがあるのではないかと思えるのだ。
言わずもがなタイトルは小津安二郎の代表作『東京物語』を意識したものであろうし、東京に慣れぬ者の戸惑いという意味で大きく出れば同一テーマとさえ言える(?)ソフィア・コッポラ『ロスト・イン・トランスレーション』が描いた情緒とも似ている(実際にはトリスターノは本作制作以前から何度となく東京を訪れているのでこれら映画の主人公とは全く感覚が違うだろう)。
より具体的に言えば共演経験もある坂本龍一のリリカルなピアノ路線とも近いし、久石譲やひいては久石が種を撒いて広がったクラシカルとかアートとは遠いイメージを持たれそうな深夜TVものなんかも含めたアニメ劇伴すらちらほら思い浮かべる。この辺を意図したとは断言し難いが、結果的にLo-fi Hip Hopサンプリングソースの宝庫として評価される未来もありえそう。それでいて解釈が違うとは書いたが当然Mikiki記事八木の指摘も全く間違いでは無い。こういった味わいが混じった世界観はなかなか貴重。
90. Benny Sings - City Pop

Spotify (別ver。下記参照) / Bandcamp / LP / LP+7"
“シティポップ・リバイバル”が始まる前、諸外国での評価が起きる前から日本人アーティストとも親交を持っていたオランダの男声SSW。
元々は2018年に『City Melody』として日本でのみCD及び配信が出ており、本来日本先行で後にワールドワイドにも展開されるはずだったのだが、ジャケと一部の内容、さらに『City Pop』というど真ん中なタイトルに改題されて2019年にリリースされたのが本作。日本のSpotifyには未だ『City Melody』版のみ。"シティポップ”の発祥国だと言うのに…!
そんな経緯にタイトル、そしてCorneliusをフィーチャーした楽曲や日本人のみのバンドによる日本録音もあり、更には音楽で参加した日本のアニメ『キャロル&チューズデイ』配信中のリリース、とあらば、直球な日本のシティポップ・オマージュかと思ってしまうが、実情は結構”いつものベニー・シングス”である。
というのも、そもそも日本人と親交があったベニー、いつ頃からどれほど強く意識していたのかは不明なれど少なくともソロ・キャリアの初期にはある程度日本のポップスに対する目配せがあり、あるいはThe CardigansやSwing Out Sisterといったともすればビッグ・イン・ジャパンと揶揄される欧州ポップに自然な馴染みがあった事もそれを加速させただろう、元々シティポップとの親和性は高かったのだ。つまり、”よし、流行っているシティポップとやらをやってみよう”というよりも、”ついに私の時代が来た!”というような視線で欧米のシティポップ評価を見ており、本作を作るに至ったのではないか。
その心持は確実に制作にポジティヴな勢いを与えただろう、"幾重にも重なるミルフィーユのあま〜いクリーム”の如し極上甘々ポップ「Softly (Tokyo)」*を筆頭に、もとより安定した職人的作家であるベニーのディスコグラフィにおいても屈指の優れた楽曲が揃っている。2010年代後半を彩った形としてのシティポップ・リバイバルはいよいよ終焉に向かいそうな2020年、最後の打ち上げ花火を見る感覚でこれを聴くのはいかがだろうか。
* : (初出は0円からDL出来る2015年のレーベルコンピで、2018年にオリジナルとも本作とも違うver.の7"を出している。それだけ気に入っているのだろうが、それも納得な極上の傑作曲。是非コンピのDLと上のLP+7"セットの購入でコンプリートして欲しい)
83. Caroline Shaw / Attacca Quartet - Orange

Kanye Westのオフィシャル・リミックスも手掛けるなどヒップホップシーンにも顔を出すピューリッツァー賞受賞のインディ・クラシカル作曲家。日本人メンバーも含む人種混成楽団Attacca Quartetの演奏に書き下ろし曲の全てを委ねた作品。
楽曲自体が示すクラシカルの枠を超えた要素は、他ジャンルリスナーから最も知られているであろうカニエ・ウェスト仕事から想像できるヒップホップのものというよりロック文脈的で、The NationalのBryce Dessnerがバンド外で行っているような、ブルースやカントリー等ロックから見たルーツ・ミュージックとクラシカルを接続する試みと言える。
その曲自体の出来も非常に素晴らしくその観点から深堀りして語る事も可能だろうが、ここではAttacca Quartetの演奏にフォーカスしたい。
私的体験で恐縮だが、ロック中心リスナーであった10代の私は、恐らく同世代から60年代リアルタイマーの諸先輩方にかけて少なくない人数が抱いていたであろうものと同じように、どこかクラシカルに対する敵視も持っていた。それが徐々に氷解していった中で、特に重要な体験の一つだったのがAlban Berg Quartetが演奏するドビュッシーを聴いた事だ。それは当時の私のような浅はかな知識で他ジャンルリスナーが想像する「譜面に起こされた楽曲を忠実に演奏するという行為のお行儀の良さ」とはかけ離れており、まるで互いをジャックナイフで苛み合うかのような鋭い緊張感にKing Crimsonの名盤『Red』すら思い起こした10年前を今もありありと覚えている。
ここでのAttacca Quartetには往時のABQと比べて全く引けを取らぬ凄まじい緊張感がある。譜面を大前提としたクラシカル文脈の演奏であっても、時にジャズやロックが持つものと同等かそれ以上の”演奏による緊張感”が生まれるのだという事を他ジャンルリスナーにも把握してもらうため、本作ほど良い材料は無いだろう。
79. Lena Andersson - Söder Mälarstrand
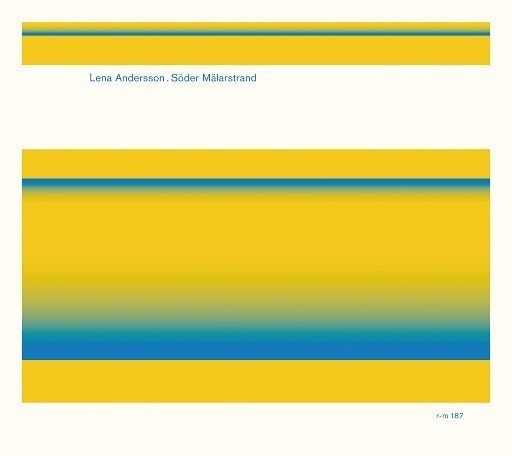
なんだか人名のような名義だが日本のKyokaとアイルランドのEomacによる国籍を超えたプロデューサー・デュオ。
旧Raster-Notonとその所属アーティストにとって10年代とは、幅広いジャンルのリスナーやアーティストから「自分のメインのジャンルはどうあれ”最先端”の音楽とはそこにある」と見做されるようなブランドを築いていった00年代から転じて徐々に他ジャンルからの求心力を失っていった苦難の時代だったと言えるかもしれない。それは極端な複雑さや逆に徹底したミニマルさといった、装いから前衛をアピールするような振る舞いへの不信でもあっただろう。ではそんなディケイドも終わろうとする時代に提示された本作はどのような装いか。
冒頭の「Middle Of Everywhere」を聴くと、00年代前半であらばRaster-NotonというよりNinja Tune (AutechreやAmon Tobinのような)的あるいはWarp的と見做されたかもしれないが、何にせよ00年代的なIDM〜エレクトロニカのその先をまだ試みようとする音楽と聴こえるかもしれない。実際、複雑なリズムのレイヤーは十二分にそういった路線の実験もまだまだ挑戦の意義があると示すものでもあるが、アプローチ自体に不信や飽食感を抱いたリスナーをこの1曲で決定的に引き戻せるかというと怪しい。しかし、アルバムを聴き進めてから振り返れば、この冒頭曲も作品コンセプトとしては00年代的な複雑さよりも、上を彩るシンセの鋭い暴力性にこそあったと気付くはずだ。何せ中盤にはダンスに対するアンチテーゼどころか、まるでNine Inch Nailsのアッパーな曲のようにヘッドバンギングで盛り上がるノリさえ許容するような流れもあるのだから。
一方でRasterから出る音楽にある種の明白なインテリジェンスを求める向きも裏切られる事は無い磨き上げられたサウンドがある。言ってみればロースクールを主席で出た経験豊富な検事に徹底したアリバイ工作を用意された上で密室に閉じ込められ六法全書で殴られているようなもので、これはちょっと諦めて殺されるしかない。
64. Deerhunter - Why Hasn’t Everything Already Disappeared?

前回のディケイドの変わり目にドリーム・ポップやシューゲイザーのファンを賑わせて登場したこのロックバンドは、4年ぶりの新作でジャンルのトレードマークたる空間系エフェクトを排したストイックかつミニマルなサウンドによって「何故まだ全てが消え去ってはいないのか?」とポスト・アポカリプスを歌っている。
このサウンドの変化はThe Boo Radleys等シューゲイザーやドリーム・ポップと呼ばれるサウンドからキャリアを経て変遷させた過去のバンドに類例を求める事も難しい。The Strokes『Is This It』のミニマルさをジャーマン・プロッグ等70年代の実験的なアプローチを念頭に違うルートから再構築しようとしたもの、とでも聴こえ、サウンド面はほぼほぼ別のバンドだ。
作曲面においてはどうか。ここは繋がりを見いだせる。オルタナティヴ・ロック以降の感覚を当然の前提として持ちつつ、The Beatlesらパンク以前のクラシック・ロック代表格への愛着も隠さない。ただし空間系エフェクトが無くともそれなりにポップに聴こえたはずの、派手なフックも甘いコーラスも本作には置かれていない。端的に言って地味になっている。
それでもロック・バンドとしての体裁は崩していないため、現代音楽としてのミニマルやミニマル・テクノのような削ぎ落とした反復の快楽が産まれているわけでも無い。前述The StrokesやThe XXあるいは日本のゆらゆら帝国『空洞です』といった00年代以降の優れたミニマルなバンドサウンドの前例が既に数多くある中で、決定的に革新的と言える部分も無い。
それなのに不思議と取り憑かれたように聴いてしまう… 取り憑かれたと言えば、本作のジャケット・アートはドイツの画家Peter Ackermannの作品をフィーチャーしたものだが、それについてフロントマンBradford Coxはインタビューにて”書店の棚から落ちてきた本がたまたまこの絵のページを開いていた(要約)"という旨を語っている。これはいかにもいにしえから連なるロックスターのオカルトめいているが、実はそこそこ信憑性がある。何せこのPeter Ackermannなる人物、ネット上でも日本語はおろか英語でさえ非常に情報が少ない。ドイツ語に精通していればともかく(Bradfordは自称ドイツ語はわからない)コンセプトやアイディアから辿り着くのはなかなかに難しい部類のアーティストだろう。
そんな偶然は大枠のコンセプトのみならずサウンドとも異様なマッチングを見せている…いや、ひょっとしたらこの絵が発見された後にこのモノクロのトーンに合わせてミックスを行ったというのもありえるか?なんにせよ、このアートワークとサウンドのどちらが先にあったものかわからないような不思議な一致。これは流石にアートワークが決まってからそれに合わせたものと断定して良いと思うが、絵のトーンに合わせたシルヴァーのヴァイナルも加わり総合芸術としてあらゆる要素が隙無く一つのコンセプトを描いている。
「何故全てが消えてしまったんだ?」ではなく「何故まだ全てが消え去ってはいないのか?」と表現される事の奇妙なリアリティは、冷戦時の東側諸国におけるシンセサイザー・ミュージック的サウンドや本作中随一にポップな楽曲を唐突にぶつ切れさせる事によって奇妙なままで補強され、通勤中に思い出した悪夢のように聴き手の背後に取り憑いてくる。
62. OGRE YOU ASSHOLE - 新しい人 (及び2018年の12インチシングル「動物的/人間的」)

日本のサイケデリック・ロック・バンド、スタジオ・アルバムとしては3年ぶり8作目。
聴かれる価値があると思うからこそこのベストに入れている。間違いなく一定の水準はクリアした良盤だ。しかし彼らのディスコグラフィを以前から知る者として本作を語るならば、少々辛めの言葉が混じらざるを得ない。
プロデューサー石原洋、エンジニア中村宗一郎というゆらゆら帝国第4・第5のメンバーといえる布陣をバックに、バンド本隊も少なからずゆらゆら帝国への憧れを感じさせるサウンドを演じてきた事で、彼らはしばしば「ゆら帝のコピーバンドだ」「パクリだ」というような揶揄にも晒されてきた。
が、その一人石原洋とは決別し、初のセルフ・プロデュース『ハンドルを放す前に』では一部が予想していた極端なサウンド変化は無かったものの、幾つかの部分では”脱・ゆら帝チルドレン”を試みたようにも聴こえた。そんなアルバム(とライヴ・アルバム1枚)を挟んで、本作にも別ヴァージョンが収められた「動物的/人間的」という12インチシングルが2018年に出ている。
それは途轍もない名曲だった。以前からキーとなる楽曲で頻出していたメロトロンやおそらくそれのオーバーダブでは無いほかのシンセ・ストリングスも重ねられ、ディレイやリヴァーブもいつになく厚く主張するそれはシューゲイザーにも近いオウガ流ウォール・オブ・サウンドで、歌詞が描く瑞々しい若さが跳ね返す夏の乱反射と、裏腹に貼りつき続けるデヴィッド・リンチ的不穏さが途方も無いコントラストを生んでいる類例が思いつかぬ世界観。これは彼らが”脱・ゆら帝チルドレン”を果たしたと言える決定的な1曲だった。
そしてB面では同じ曲がまったく別録音によって長尺チルアウト向きダウンテンポに仕立てられている。序盤の形こそゆら帝に結び付けられるこれまでのオウガの形ではあるが、そこから反復を重ねるにおいて、ゆら帝が反復を軸としたオリジナル曲では立ち上がりこそメロウでも常にどこかジャーマン・プロッグの影響下にある棘が顔を覗かせたのに対し、ここでのオウガは棘や毒、攻撃的な要素を排して最後までメロウなチルアウトという機能性に徹した演奏になっている。これはそれらの手法自体の優劣を語る訳では無いが、オウガの歴史を思えばこれを”(ある一点において)ゆら帝を超えた”ものだとしても良いだろう。
しかしそんな変遷を経ての今作は大雑把に言えば石原洋最後の参加作、スタジオ・アルバムとして前々作にあたる『ペーパークラフト』のアップデートという印象だ。
確かに非常に質は良い。何度も引き合いに出している後期ゆらゆら帝国や、CANのようなジャーマン・プロッグ、The Sea And Cake等の音響派といった音楽が好きだがこのバンドの作品を聴いていなかったら、本作から聴いても後悔する事は無いと断言できる。
だがやはりその変遷から見れば、その手に掴んだ決定的変化/進化を何故自ら手放してしまったのかという思いが拭えない。本作における「動物的/人間的」のアレンジはメロウなエレピを主としたものでそれなりに新鮮さはあるが、同時に12インチ両面のテイクと比べ過去からの連続性も意識しすぎている感もあって、それは『ハンドルを放す前に』で試みた可能性から前進も後退もしていない。
繰り返すがこれは非常に質の高い作品ではある。しかし、より大きな何かを掴めそうな感覚を受け取っていたいちファンからすれば、手放しの称賛で文を締め括る事は出来ない。
結構ギリギリでやってます。もしもっとこいつの文章が読みたいぞ、と思って頂けるなら是非ともサポートを…!評文/選曲・選盤等のお仕事依頼もお待ちしてます!
