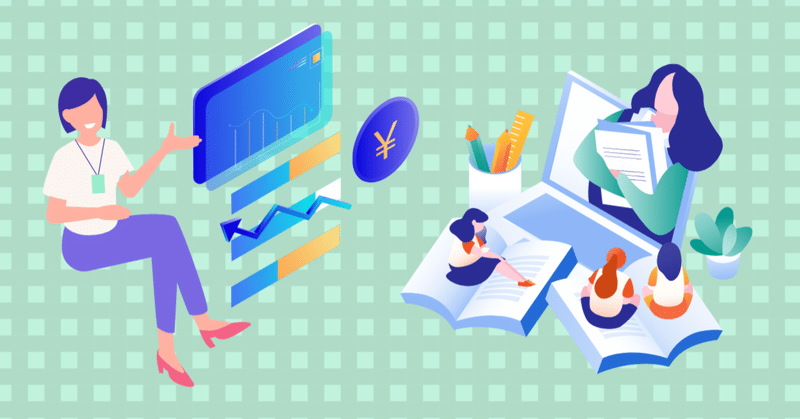
私がためらいなく「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」と言えるまで
4人のお子さんを育てながら大学院で研究を行っている、さおりさんという方がTwitterにいます。現在は就業しておらず専業主婦ということです。
さおりさんの現在の選択は、ツイートから推察する限りは「自然の流れ」という感じです。夫君と対等な協力の上に現在の家庭が形成され、現在の最適な役割分担として夫君が稼ぎ手という形になっています。今後については家族メンバーそれぞれの幸福を実現する形で自然に変化するかもしれないけれど、「かくあるべき」という理想に沿って何かをすること(たとえば、さおりさんが近未来に稼ぎ手になるなど)は予定されていません。
私自身は結婚も出産も子育ても専業主婦経験もない50代ですが、さおりさんの存在を知って、嬉しくなりました。言葉通りに「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」と言える日が、やっと来た。そう思ったのです。
私が生まれる前に始まった「主婦論争」(1955-現在)
1955年、評論家の石垣綾子さんが主婦を第二の職業とした「主婦第二職業論」にはじまる「主婦論争」が始まっていたようです。伝聞型なのは、私はまだ生まれていなかったからです。ここでいう「第二」は「第一」に対するもので、「劣る」「正統ではない」という意味合いです。流れをざっとつかむには、こちらの村上潔さんの論考がよいと思います。
「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」(10歳まで、1963-1972)
私が「モノカキになろう」と考えたのは、4歳の時でした。自分が就けそうで、女性が既に就いていた実績があって、16歳より前に稼げる可能性のある仕事を他に見つけられなかったからです。目的は、船を買って家出すること。当時住んでいた家は漁港のすぐそばにあり、大小さまざまな船の出入りを毎日見ていました。
私が「お嫁さん」志向を持っていないようすは、数年のうちに周囲の大人たち、具体的には母親や近隣の専業主婦の方々に何となく知られることとなりました。さらに「私たちをバカにしている」という話になっていきました。でも私には、専業主婦をバカにしたり見下したりするつもりは全くありませんでした。自分はまだ10歳にも達していない子どもで、相手の専業主婦の方々は20歳代や30歳代の大人です。ご機嫌を損ねたり批判材料を与えたりすることを恐れなくてはならない方々、大なり小なり自分の生殺与奪を握っている方々を、どうしてバカにして見下すことができるでしょうか?
子どもである自分に許された、知や発達へのちっぽけなアクセスを奪われないために、私は「専業主婦は立派な職業、それを選ぶことは立派な選択」と言い始めました。小3くらいで大人向けの本や雑誌を読めるようになった私は、かなり遅れて「主婦第二職業論」に触れていたのかなあと思います。はっきり覚えていませんが、専業主婦がそういう視線を非常に恐れているということを本で読んで知ったという、漠然とした記憶があります。
私には、専業主婦であるあなたがたを軽蔑したいという思いはありません。私が他の職業を選ぶ選択を褒めてほしいとは思わないけど、とにかく妨害しないでください、お願い。
「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」(10歳代、1973-1982)
10歳代になると、この言葉を口にする相手は2通りになりました。私自身の母親と、高校のクラスメートです。
母親は、私の将来について具体的に想像して期待するようになりました。いつものように外で遊んで日焼けして帰ると、いきなり平手打ちが飛んできたこともありました。母親が怒りながら語ったところによれば、その時の母親は、私の大学進学と就職と結婚退職と結婚式について想像していました。ちょうど結婚式のウエディングドレスのデザインについて考えていたとき、私が日焼けして帰ってきました。そのウエディングドレスに日焼けは似合わないので、怒りを抱いたということでした。
中高一貫女子校に入ると、「高校は外部受験して県立の共学校へ」という希望が多様な形で打ち砕かれました。今から考えると、母親の思い描く私の未来像、すなわち「専業主婦」という将来に、「県立共学校に行く」という選択肢はありえないということだったのでしょう。とにかく高校を卒業すれば大学受験資格が得られるのだから、妥協することにしました。
高校時代、母親は私と接触する機会のある大人に依頼して「あなたの将来は専業主婦」と刷り込むように工作したりしていたようですが、簡単に私にバレました。その高校からは当時めったに出なかった国公立理系への進学者が出るかもしれないことへの期待のせいか、高校の先生方は、母親のその作戦に動員されませんでした。母親の思い通りのコースに乗らない私が口で何を言おうが、母親は「自分をバカにした」「親をないがしろにする」と怒るだけだったので、母親に対して「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」と言うことはなくなりました。
高校3年の時に最も大変だったのは、クラスメートたちです。もちろん、彼女たちも受験学年であり、受験勉強をして志望校を研究していました。彼女たちの志望校の検討は、「有利な結婚とは」「自分が有利な結婚によって実現したい専業主婦としての暮らしとは」「有利な結婚を引き寄せやすい経歴とは」「そのために必要な大学(短大)進学とは」というものでした。高校3年でそこまで具体的に考える彼女たちのことは、当時も今も「すごい」と思っています。問題は、彼女たちが「女の幸せは結婚よ」「大学に進学しても就職しても、結婚して主婦になりたくなるに決まっている。その時に理系は不利」などと私を口説きにかかってきたことです。
私は毎日のように、彼女たちに対して「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」と言わなくてはなりませんでした。あなた方がそれを選ぶことはあなた方の権利。私はそれを尊重する。だから私が別の選択をすることを妨げないで。お願い。
「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」(20歳代、1983-1992)
20歳代の私は、実家を離れて大学夜間部に進学した後に大学院に進学し、同時に職業生活の切れ目がほぼない生活を送っていました。両親からの結婚へのプレッシャーは激化しましたが、26歳になると急激に止みました。当時の実家方面では、その年まで結婚できないとなると、キズモノとして諦められたわけです。
大学の同級生や先輩後輩の中には、専業主婦になるという選択をした人もいます。特に価値判断することなく、「ああ、彼女はそうするんだ、お幸せに」というだけのことでした。
問題は、周囲の大多数を占める男子学生たちでした。中には、「身近にいる少ない女子学生の中から付き合う相手を確保し、自分の作りたい家庭を作るためのパートナーにしなくては」という熱でいっぱいの人もいました。彼らは、ありとあらゆる手段を講じて自分と付き合わなくてはならない罠に私を追い込み、私が応じないと嫌がらせに転じるのでした。私は彼らに対して、「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」と言わなくてはなりませんでした。そういう選択をする女性もいるでしょう。あなたが専業主婦の妻のいる家庭を作りたいのなら、そういう女性をどこかで見つけてください。それは、私じゃありません。
「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」(30歳代、1993-2002)
この時期は、あまり悩ましくありませんでした。というのは、30歳代になった私とお付き合いが続いている友人知人女性の中に、専業主婦が一人もいなかったからです。「妻の稼ぎで夫が大学院に行き、夫が修了して再就職した後にその稼ぎで妻が医学部再受験」というパターンならありましたけど。
当時は、バブル崩壊後の10年間でもありました。結婚していようが独身であろうが、本人あるいは配偶者がどういう職業に就いていようが、とにかく今日を生きて近未来につなぐだけで精一杯。専業主婦という選択の是非についての話が出る幕はありませんでした。もしも「夫が自分の友人で、その妻が専業主婦」というパターンがあっても、同様に「夫一人の収入で、妻と子どもの生活と未来を支えるには」という悩みがあっただけだろうと思います。
両親やきょうだい(特に妹)との間では、それなりに悩ましかったです。この時期、母親は電話をかけてきては「親に孫の顔を見せてやりたいと思わんとねえ(親に孫の顔を見せたいと思わないのか)」「ウチだけ孫がいない、親の顔に泥を塗ってどうしてくれるとねえ」などと博多弁で泣き叫び、父親は「この歳になって子どもが誰も結婚していなくて孫がいないのは」と同様のことを冷静に言い、妹は「お姉ちゃんはウエディングドレスを着たいと思わんと?(思わないの?)」と言ってきていました。まことに困惑することではありましたが、それ以前の時期に比べれば若干は気楽でした。その時期の両親は、私が結婚することや子どもを持つことについて「私自身の幸せのために」と取り繕うことすら放棄し、ただ「結婚している子どものいる自分がほしい」「孫のいる自分がほしい」という欲求をあからさまにしていたからです。そういう欲求を私が向けられるべきであるかどうか、私がその欲求を満たすべきであるかどうかは、「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」であるかどうかとは関係なくなっていました。
この時期、事実婚と解消を経験していますが、それは専業主婦が職業であるかどうかとは無関係な出来事なので省略します。
「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」(40歳代、2003-2012)
この時期は、私が中途障害者になり、最初の大学院博士課程で失敗した時期です。私が専業主婦にならなかったことは、「自己責任で勝手なことをしたから失敗した」という形で両親から突き刺さってきました。同時に、弟妹が次々に結婚して子どもたちに恵まれたので、単身の私に介護プレッシャーがかかってくることになりました(母親が私に介護プレッシャーをかけはじめたのは、私が小学生で母親がまだ30歳代だった1970年代前半からですが、それはさておきます)。私が障害者になっても両親は諦めませんでしたが、障害者運動家の介入によって断念しました。次に起こったのは、私を血縁関係から切り離すことでした。両親が2006年ごろから具体的に何をどのようにしたのか、いずれ書く機会もあるでしょう。
妹は結婚後、専業主婦になりました。疎遠なので多くを知りませんが、妹の家庭状況は、専業主婦または専業主夫がいないと回らなさそうなものでした。夫が稼ぎ手なら、自動的に妻が専業主婦になるでしょう。私は、妹の持っている「私自身の数倍の年収と高い社会的ステータスがある夫+子どもたち」という価値と自分の価値を比べて、どのような基準によっても自分の方が低く、したがって自分は両親に何を言われたりされたりしても文句が言えないという結論に達し(その結論は人権というものを無視している点が誤りですが)、悶々と苦しんでいました。「不要動物の殺処分」という用語を見たら、自分がそこに行って殺処分してもらわなくてはならないような衝動に駆られたほどです。「女は産む機械」論でいえば、私は機械ですらないわけです。
はい、専業主婦は立派な職業で選択肢の一つです。その選択をして成功した妹は素晴らしくて、私はクズです。生きている価値がありません。
「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」(50歳代、2013-2022)
50歳になるのと概ね同時に、私は職業生活を立て直し、2回目の大学院博士課程チャレンジに入りました。修士課程から数えると、3つ目の大学院です。「なんとかなるだろう」と思っていたのですが、とんでもない誤算がありました。女性院生、それも40歳代50歳代の女性院生が多いということです。私は「自分以外全員男」といった環境には慣れているし、そういう場での処世術もなんとかこなしてきました。でも「女もたくさん」という環境は高校以来です。もちろん、専業主婦経験がある方もいますし、現在進行形で専業主婦という方もいます。
人生中盤にさしかかると、「専業主婦だから」「専業主婦だったから」といったことの意味は相対的に小さくなります。「専業主婦」という肩書よりも、「どのように専業主婦である(あった)か」という個別各論の方が効いてきます。「専業主婦だから(だったから)付き合えない」という方がいるわけではありません。専業主婦どうこうが問題になるとすれば、「あなたには、私が専業主婦であること(あったこと)の価値を認める義務がある」と内心のどこかで考えている感じの方に接近を図られた時に、どう逃げたりかわしたりするか。正直なところ、苦戦しました。苦戦の果てに「接近を許した時点で終わってる、無理」と判断しました。同じ大学院の院生を接近させないというのは、それはそれで難事なのですが、接近させたらトラブルにしかならないのは目に見えています。こちらは一方的に障害者でありマイノリティですから、トラブルになったら圧倒的に不利です。こういう場面では、「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」なんだから、専業主婦の(専業主婦だった)あなたは、他の誰にでも評価されるでしょう? 私に求めなくていいでしょう? しつこく私に求めるのはなぜ? ということになります。
一方で、掛け値なく「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」と言える方々との出会いもあります。リアルで出会えないのであれば、あるいは、リアルで出会えても接近されたくない専業主婦の方とセットでしか出会えないのであれば、リアルで見つけなくていいんです。SNSには、さおりさんのような方もいます。
おそらく「主婦第二職業論」から半世紀以上の時を経て、掛け値なく「専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ」と言うこと”も”できる時代がやってきたのでしょう。そこに、私自身が生きてきたことによる学びや変化が重なったのでしょう。
専業主婦は立派な職業で選択肢の一つ。もしもその人が、そういう方だったらね。私はその選択をしなかった。それが何か?
おまけ:専業主夫は?
さおりさんは、ときどきツイッターで批判されています。批判の多くは、「その価値基準で計れば、そうなるでしょうね」という内容です。そして私は、同じ価値基準で彼女を計ってみる気がしません。彼女にとっての合理性や選択肢や選好に基づかない評価に、どういう意味があるのだろうかと疑問を覚えます。
さおりさんを批判する方々は、
「もしも夫が4人の子どもを育てながら大学院に通い、妻が主要な稼ぎ手という夫妻だったら、夫に同じ批判をしますか?」
という私の問いに、どう答えるのでしょうか。聞いてみたい気はします。でも、かなりどうでもいいです。
どんな現在も、どんな選択も、その人なりに限界の中で「少しでもマシ」を目指してきた結果。それを互いに認めあえるような社会を、まずは自分の周囲に作りたいものです。
ノンフィクション中心のフリーランスライターです。サポートは、取材・調査費用に充てさせていただきます。
