
【小説】「顔の無い身体と心無き触れ合い」
夜の路地。車一台分くらいの道の両サイドには、アパートや古い木造建築が立ち並ぶ。忙し過ぎた仕事の日々が一段落し、背中に鉛のごとく張り付いていた疲れも取れて来た。電柱やアスファルトを照らす月が若干眩しく感じるのは、上を向いて歩くことが増えたからだろうか。
数か月の早朝から深夜に渡る繁忙期。家と会社(と時々コンビニ)を行き来するだけの日々。ほとんどの友人とは疎遠になり、そもそも恋人は作りづらい状況で、実家はもう昔に……
つまりは社会的孤立状態に、仕事があることを除けば近い訳だ。
突き当りのT字路に着く。右に曲がる。左側は新築一軒家が並び、右側は緑のフェンスで、フェンスの向こうは崖で、崖の下には、古いアパートや商店、町工場等が密集している「旧市街」と呼ばれているエリアが広がっている。「旧市街」の向こう側は丘になっていて、野原があり、小さな工場の銀の煙突が月に照らされ、控えめに光っている。
一軒家の並びが途切れ、木々が巨大な影のように並んでいる。木々の中に、外灯に照らされた傾斜の緩い階段があり、私はそこを登る。ここに来るのも久しぶりだ。公園。全体で300㎡はあるだろうか。公園は三つのスペースに分けられていて、今私がいる遊具のあるスペースと、右奥には木々以外何も無いが「旧市街」が一望できる見晴らしのいいスペースがあり、左奥には複数の大木に囲まれたベンチが並ぶスペースがある。
滑り台の前に黒猫がうずくまり、じっと私を見ている。夜の闇より黒い猫。私は落ち葉を蹴りながらベンチへ向かう。
ベンチ同士の間に、小さな黒い人型の影が見える。恐る恐るベンチに近づく、電灯に照らされる、身体のサイズより一回り大きい薄緑のコートを着た子供。子供は下を向いていて顔が見えず、よく見るとコートの複数個所が破れて黄色い綿が出ている。
目を離したくても離せない。典型的な「ホラー映画ぽい」光景。
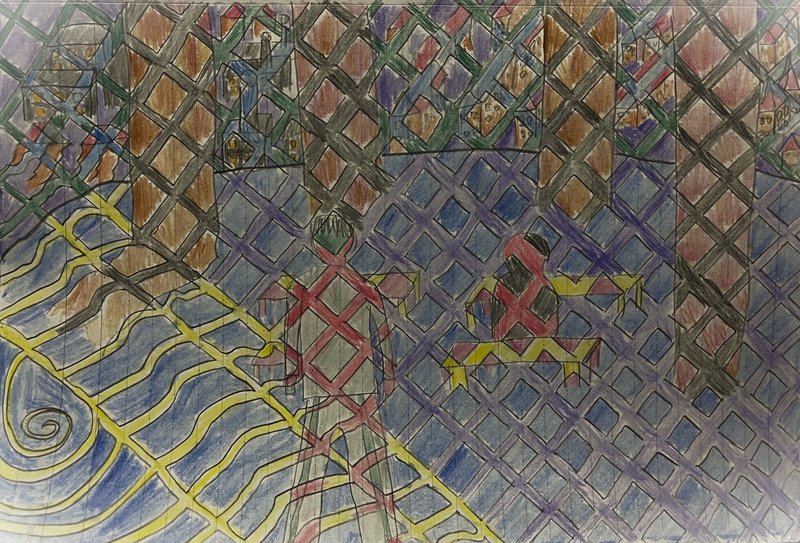
「おにいさん」
ポツリと聴こえた高めの声。いよいよホラーだ。嫌だなあ。こういう時こそ逃げたいのに身体から力が抜けたりする。子供は顔を上げる。コートのフードを脱ぐ。短いがボサボサの黒髪とパッチリとした二重の大きな目。(猫に目が似てる気がする)電灯に照らされ青白く光る肌。猫のような目はただただ大きく見開かれ私の目を捉えているが、悪意は無さそうで少し安心した。
「おにいさんには、さがしものはないの」
無いよそんなの。謎の少年が唐突な問いを投げるのもどこかホラーぽい。無視するのもかわいそうな気がして私はありのままを優しい口調を意識して答えた。
「無いかなあ。うん、無いね」
「ぼくもないかな」
無いんかい。しかし次の瞬間、少年は早口かつ呟くように次々と喋った。それは機械的な感じがした。
「もうすべてみつかったんだ。ものもつながりも。あさはあっちのほうにあるふるいきのいえにいくとおばあちゃんがげんかんからでてきてぱんとすーぷをくれる。ひるはこのこうえんのあっちのほうでいつもすべりだいのまえにおんなのこがいておべんとうをはんぶんくらいくれる。よるはきゅうしがいのほうでえんとつのついたいえのおじいさんがなべをたべさせてくれる。つんとするにおいをいつもおじいちゃんはただよわせてる。ちなみにあさおばあちゃんちにいくまえとゆうがたきゅうしがいのみちではあいさつしてくれるこたちがいる。べんきょうはここのべんちでおしえてくれるひとがいて、そのあとはあそんでくれるこたちがいて、たまにぷれぜんとをくれるこもあらわれる」
最初に感じた恐怖は消えていたが、違和感が膨らんだ。
「たくさん人との繋がりがあるのは良いことだし凄いと思うけど、逆に多過ぎて疲れない? 何だろう。親とか兄弟、よく一緒にいる友達や親友と上手くやった方が楽なんじゃ……」
言ったそばから後悔で顔が熱くなった。子供も含め、人には色々事情があり、単純化した「こうすべき」を当てはめるような質問やアドバイスはするべきじゃない。昔私がされて嫌だったことを、つい言ってしまった。それに今の私にだって繋がりは……
「うんでくれたひと、がっこうできまってるつながりとかだとしても、とにかくすくないひとによりかかられぼくもよりかかるとこわいがうまれてしまう。しはい、ふくじゅう、こわいのいらない。おとなはおみせでものをうってもらうだけのひと、しごとだけわけあうひと、げーむだけするひととか、すこしずつのつながりたくさんもってる。ぼくもそうする」
相変わらず機械的な早口。寒い風が吹き、自分を抱きしめながら足踏みをする。少年はずっとここにいるつもりだろうか。事情が分からないが、何となく気の毒でここを離れられない。
「ありがとう。おにいさんはぼくのはなしをきいてくれた。ぼくはぼくをふりかえられた。おやすみなさい」
そう言ってゆっくり私に背中を向け、フードを被り下を向き動かなくなった。
「わ、分かった。おやすみ」
私は最初は少年を見ながら後ずさるように、そして最後は速足で家へ帰った。(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
