
作品の考察とは、作品である
作品の考察って、なんか気持ち悪いものもある。
考察というより、単なる書き手の妄想のような気がしてならないものもあるから。
有名な話だと、トトロの少女たちはすでに死んでいる、というものがある。
こういった内容がいかに筋が通ったものであれ、『トトロ』の作品価値やテーマには一切関りがないものであるのは確かであって、
その考察を眺めている人も、まさかそれが公式見解だと信じる人は(中にはいるだろうが)ほとんどいないだろう。
では、どういうふうに眺めているのか。

ある程度、人それぞれだと思うが、あくまでそれはよく考えられた作り話(根拠があっても)であって、一種のエンタメだと考えられている。
じゃあ無価値なのかというと、そういうわけでもない。
考察というのは優れたものであればあるほど、作品を丹念にチェックしているわけであるし、また筋の通った根拠を眺めるのは、作品理解の助けにもなって丁度いい。
また怪談や都市伝説などを思い出してほしいが、あれも実は創作であるという事実を半分受け入れられたうえで存在している、一種の協定物であると言える。

もちろんそれを公に明言するのは、都市伝説のルールを破ることになる(しらける)が、お化け屋敷などと同じで、体験者はあるルールに同意したうえでスリルを楽しんでいるわけである。
「これが本当なわけがない。しかし、本当であったらどうしよう」という葛藤を(その矛盾性を)楽しんでいるのである。
それは立派なエンタメであると言えるし、ある種の幕のかかった人工的な神秘なのだ。
俗に作品の考察というのも、その派生作品である(しかしこれは俗用であって、正式の語義ではないが)。

考察といえば、学術的な問題を正当な論拠をもって考えていくことであるが、エンタメ作品の考察といえば、ほぼ間違いなくこの「都市伝説性」を帯びる。
その「都市伝説性」を楽しむべきなのであって、とやかく言うべきではない(なぜならその人の作品なのだから)。
ただ、あまりにもその「作品」としての考察がまずかったら、文句は言われるだろう。

しかし、ここで不思議なことが起こる。「考察」は半分、事実からの推論と言える。
もう半分は作者の理想(妄想ともいえる)、性格が混じる。
考察のおもしろさは、事実量の多さとは関係がない。
たとえ内容の1%程度しか事実に即していないとしても、素晴らしい考察は存在する。
それは何なのかというと、考察の面白さは、すべて「考察」というストーリーの構成力、考察者の共通感覚の鋭さ(人情を理解する心)、また「語り」の上手さで決まってくる。
都市伝説の名作の書き手は、一流の作家にも匹敵する力を持っている。
「きさらぎ駅」や「カンカンダラ」、「リゾートバイト」などは名作の都市伝説である。
話を戻すが、
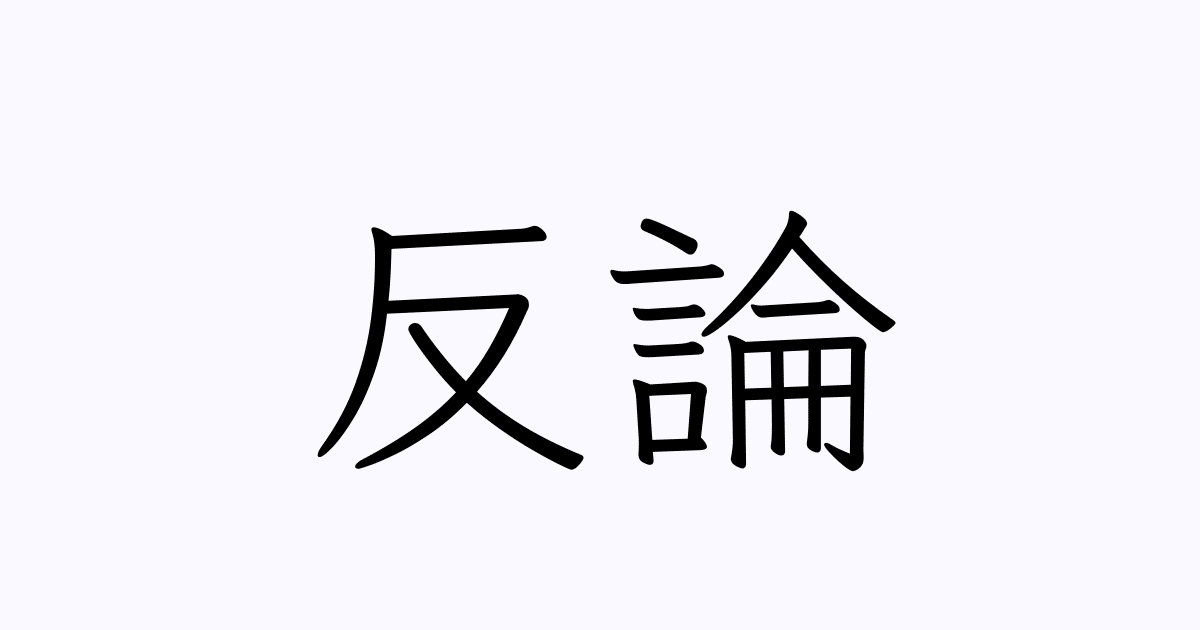
考察の批判に対する反論は、その点容易になってくる。
なぜなら論拠は「事実」であり、それは絶対に動かせないからである。
そこに考察が「気持ち悪い」と感じる根源がある。
それは作品であって作品でない。創作性と事実性の、責任の所在が不明確なところがある。
事実は確かに動かしがたいが、「考察」には解釈の恣意性が多少存在する。
「解釈」といっても、共通感覚の鋭いひとの解釈ならば、多くの賛同を得るだろう。ただ、よく問題視されるのは理想家の、よく言えばロマンティストの(それもニッチなロマンの)考察である。
その根源は紛れもなく「性格」にあるし、その人個人の「作家性」とも言っていいが、それを「事実」的なものであるとする言明に、論理不一致の気持ち悪さが生まれるのだと思う。

ただし、それが1%であったとしても、事実に立脚したものであるから、反論が容易である。また解釈は自由であるから、解釈を責められる謂れはない、との反論も可能だ。
しかし、そうではなくて、共通感覚(人間のこころを理解する感覚)の欠如を、自分の「性格」を「事実」に浸食させる杜撰さを、「作品」としての考察が人を惹きつけるために押さえるべきポイントを無視していることが、責められているのだ。
しかし考察というのは、事実が何パーセントなのか、想像が何パーセントなのか、はっきりとは分からない。作者でさえも分かっていないだろう。そういうものである。
しかし、ある程度「事実」に立脚している以上、批判があれば作者も納得しづらいものがある。

人は見えているものが間違いと言われると、納得できないものである。
なぜならそれは今「見えている」からである。
そういう人には見る角度を変えたらどうか、と言わなければならない。
本来、考察はやはり「作品」である。
なぜなら事実は事実でしかない。簡易的なレポートで済む。
不確定な情報に対する考えがあるから「考察」なのである。
しかしその考察の論理に、どれだけあなたの「性格」が混じっていますよ、と言うのはなかなか難しい。だから「もどかしさ」が生まれ、「気持ち悪さ」に変わっていくのである。

「事実」という論拠があるから、考察全体を「事実」とみなしたがる作者と、
そこに「性格」が混じっているのを見てとる体験者(読者)の会話のズレが、起こってしまっている。
ただし、こういうことは、作品の良し悪しを語る際にも、よく起こる。
いろいろな意見があっていい、というのは現実的な妥協点だが、それで納得するかどうかは、言ってみなければ分からない。個人的には、分かり合えないのを無理に綺麗ごととして片付けるより、言いたい放題言ってしまって、考えを戦わせるほうが双方に利益があると思っている。
ただし共通感覚というのは、一種の才能のようなものなので、良い書き手の立場に成り代われるものでは、そうそうない。
いい漫才師に「人の感情を読み取る方法」を教わっても、いまいち分からないのと同じである。その共通感覚は、伝えることができない。

以上です。
それが「作品」であるとはっきりわかれば納得できる話も、「考察」という名目がつくと、ひどい物でもはっきりそうとは言えないのは何故か、と考えてみました。
事実に立脚しているから、作者も言葉に熱がこもっています。しかしきちんとふり返っているでしょうか?
事実をどう解釈するのかは、作者の恣意に委ねられています。しかしそここそ、作者の腕の見せ所です。
「事実」なんだから、認めないのはおかしい、という前に、その解釈は自分の中からどうやって来たのだろう、という思いに至ってみるのは、逆に面白いことなのではないでしょうか。
自分の作品を「事実の考察」というアーマーで固める前に、これは「作品」だから、自分の手でいくらでも面白くできるんだ、という矜持を持つことで、面白い考察が書けるのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
