
軽薄嘲笑に埋もれるビジュアル系
朝からすっきりしない倦怠で、書く気も起きないのですが、奮起ふるいたたせて、やっと椅子に付いたというのが実態です。ですから、先に云っておきますが、この記事は駄文の雑記です、ただの愚痴です、夫婦喧嘩みたいなもので犬も猫も猿も食わない、とうぜん皆さんもくわない、を前提でだらだら書きます。
だからなに、という理由は、とりたててありませんが、いや、ないこともなくて昨日のアレですが、ここで再度ソレ云っても夫婦喧嘩ネタですから辞めておきましょう。
最近の記事(全般)を読んでいると情景描写がないと感じます。なにかというと語るべき内容のシチュエーションがなくて、いきなり本題の前戯なしというやつです。
一昔前の小説は、それが前提の原稿になっていて、2.3行読んだだけで、その場面が想像できます。云ってみれば映画監督が、作品構想をねっている時期の絵コンテみたいなものです。
だから今のは、それがない。じゃ理由は何かといったら、やっぱり写真(ai合成も)とかYouTubeとか、ビジュアル系が整っていて、それを文で書く必要がない、とおもったからです。
その逆もあるようで、こんな動画がありました。
ある著名な建築家ゲストを招いてインタビーをやっていて、それをみて感じたことですが、ゲスト紹介するのに、いろいろ方法がありますが、同席コメント女子がその世界的ゲストの頭髪を話題にして髪型云々しましたが、その髪と当建築テーマと、どう関係するのか意味不明で、まあよくある「テレビワイドショー」の一部と、勘違いしていたのでしょう。
じゃ何か、そこにアンシュタインがいたら「その下の長さは何センチありますか、」と質問するかという話しです。(まないことはないです日本のテレビ界)
先日、宇宙の法則について書きました。さすがに難解で、閲覧はすくなかったです。
音声解説 音声FILE
https://dotup.org/uploda/dotup.org3005529.mp3_wJEmTeilXPKAvrOV1pAL/dotup.org3005529.mp3
まあ書くにあたっては時世を考慮してタイムリーな記事をかくようにしてますが、昨日のように、そうであっても反社会的(下ネタオンリー)な文言が並ぶと、拒否され、ワイドショー的な軽薄嘲笑スタイルが好まれる、という現実に抗うことは無理なんでしょうか。
云ってみれば宇宙物理も建築家のヘアスタイルとかガーシー逮捕とか、ワグネル謀反とかね、庶民平民クラスとして横一線でしかなく、深堀も浅堀もないわけです。
スサノオ、オオノヤスマロ、とはだれなのか?2022-07-25 07:00:39 表示を確認 | 記事
豊葦原瑞穂国「春夢」 春の世の夢の如し・・・《神意によって稲が豊かに実り、栄える国の意》日本国の美称。
「此の―を挙(のたまひあげ)て我が天祖(あまつみおや)彦火の瓊々杵尊(ににぎのみこと)に授へり」〈神武紀〉
豊葦原中国(旧字体:豐葦原中國、とよあしはらのなかつくに)とも呼ばれ、単に中国、もしくは中津国(中つ国)とも言う。日本書紀には、豊葦原千五百秋瑞穂國(とよあしはらのちいほあきのみずほのくに)という記載がある。神々の住む天上世界である高天原と対比して、人間の住む日本の国土を指すと考えられる。
日本神話によれば、スサノオの粗暴に心を痛めた姉の天照大神は天岩戸に隠れてしまい世の中が混乱してしまった。
このため、八百万の神々は協議の結果、スサノオに千位置戸(通説では財物、異説では拷問道具)を納めさせ、鬚を切り、手足の爪を抜いて葦原中国に放逐し、高天原から追放したとされる(『古事記』では神逐(かんやらい)、『日本書紀』では逐降(かんやらひやらひ)と称する)。
スサノオの息子である大国主(オホナムチ)が、スクナビコナと協力して天下を経営し、禁厭(まじない)、医薬などの道を教え、葦原中国の国作りを完成させたといわれる(日本書紀)。
大国主はのち、国土を天孫ニニギに譲って杵築(きづき)の地に隠退、後に出雲大社の祭神となっている。
なお、安房の国については、養老2年(718)に上総国から分かれ、その後、一時、上総国に合併されますが、天平勝宝元年(757)に再び独立、上総・下総・安房国が成立しました。名前の由来は、『古語拾遺』では四国の阿波国の忌部が移住したことによるとされています。
こちらは、四国と房総の黒潮を通じた交流を物語る地名と言えるでしょう。
古社叢の「聖地」の構造(1)※参照記事引用
東関東の場合
神社、正確にいうと日本の古社叢は、拝むところ、つまり拝所は一つではない。だれでも本殿には参るが、それ以外に摂社、末社がある。さらにご神木、神池、磐いわくら座あるいは神ひもろぎ籬などがある。本論ではそういう点に着目して、日本の古社叢の拝所、すなわち聖地の構造についてのべる。聖地についてはいろいろな説があるが、ここでは「一の宮研究の方法」(『社叢学研究第8号』上田篤)にしたがって論をすすめたい。
そこで「日本の聖地」である古い社叢の信仰を、そのまつられる祭神の種類からそれをもたらした者が「天孫族」「出雲族」「先住族」、いいかえると古墳人、弥生人、縄文人とする視点から事例調査した。事例調査対象として、東関東に鎮座する一の宮をとりあげる。県でいうと、千葉県と茨城県の海岸地帯であり、昔の 国 名 で いう と、南から 北へ安あわ房国・上かずさ総国・下しもうさ総国・常ひたち陸国である。部分引用
以上みぐるしい雑文の羅列でした。 <(_ _)>
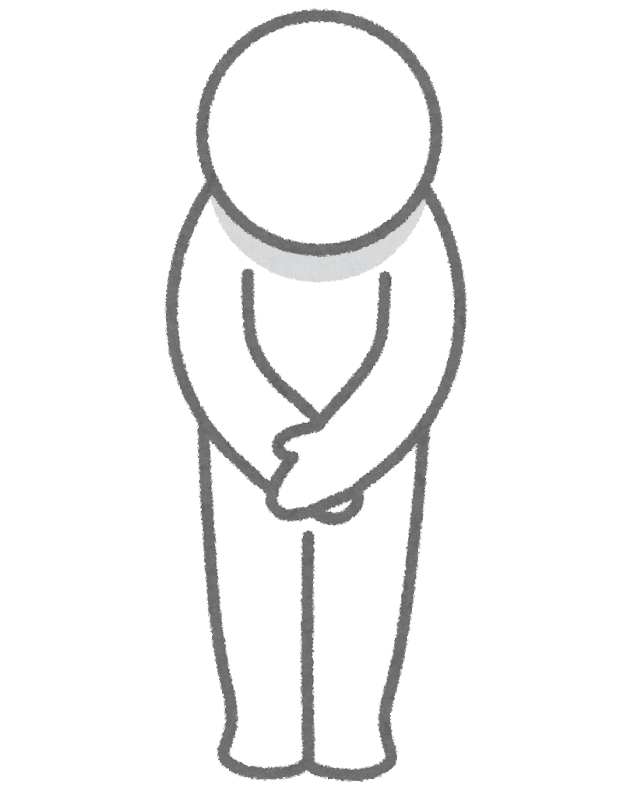
続編「ヤマトタケル 八咫烏ガイド 東征」は、社会ニュースが先行して、進みませんが、何れ本格的に執筆する予定です。
きょうのところは「武田徹 立花隆」「泥濘(でいねい) 梶井基次郎 著」二編を後ほどインポートします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
