
虹の色彩論/虹彩法(虹の贈りもの)
自然界の色彩に虹の色が浸透していることを発見して以来、自然の色彩の観察とスケッチを通して思う、現場の立場からの色彩論です。
〈 出逢い 〉
1996年10月28日、北海道スケッチ旅行をしていた霧多布岬でのこと。
その日は未明から、海に映った月明かりに見とれて、ながいあいだ夜の海の景色をたのしんでいた。
それは、天の高いところにあった月が、西の地平線へとしずみ、東の水平線あたりが仄かに白みはじめたそのころであったと記憶している。
海も陸も360度が真っ平らにみわたせるその場所で、境界線にそって天球をつつみこむ虹を見た。
……虹は、空の一番高いところまでを淡い紫色に染めあげて、気がつくと、自分も風景もすべてが虹につつまれていた。
『あー、これが自然をあらわす色なんだ‼』
そのときわたしは、虹につつまれたこの星を見ていた。
〈 虹彩法 〉
絵を描くといえば、通常、デッサンからはじめてその後に色を塗る、と考えるのが普通のことであり、色から描いて形をあらわす。と言えば、なにか奇異に感じられるかもしれません。
〝虹彩法〟と名づけたこの描法は、通常おこわれる描法とは違った観点に立ち、まず色を描くことからはじめてゆきます。
なぜ色から描くのか? と問われたら、それは、自然界の色彩には、線というものが存在していないから。と、答えることができます。
なぜなら――、観察している意識を物の形から色彩へと移行したとたん、線と見えていたそこにさまざまな色が現れる。……ということになるからです。
線とは、物を捉えようとする人間の意識が作りだす概念であり、デッサンとは、
「わたしは、物を、このように捉えている」と、表明することに他なりません。
つまり、『線』と『色』は、対照的な関係にあるものなのです。
そこでこの描法は、その色彩の方に意識の目を向けることで、今までおこなわれてきた絵画の方法に、新たな視点を提示できるのではないか。と考えています。
*
雨上がりの大空に架かる虹は、なぜ人の気持ちを捉えて美しいのでしょう。
それは、『人の内面を表す色だから』と考えることは、夢物語の絵空事なのでしょうか。
自然界の中には、この鮮やかに輝く虹の色が、お互いを損なうことなく浸透し合い充ちている様子を観察することができます。
ここでいう〝虹の色〟とは、物質に着色した、あるいは定着した色を言うのではなくて、物質から自由になろうとする色を指して言います。
通常色といえば、物質に定着したものをいい、ここで使用するクレヨン(オイルクレヨン゠オイルパステル)も物質の色であるため、自然界に浸透したこの〝光の描く色〟を描き現すことはできません。
描いたものは、あくまでも物質的な色に過ぎません。
しかしこの物質の色が、人間の意識を介して、物質性を越え出て精神性へと高まってゆくことができる。と、言うことができます。
ここでいう精神性とは、自然の物を観賞したり、芸術作品に触れて感動を覚えた経験をお持ちの方であれば、どなたにもご理解いただけるのではないかと思うのですが、敢えて言わせていただくならば、
人は、目にした物に、物質では到底表現できないような事象を発見したときに、思いもしなかった感情が、心の奥底から湧き上がってくるのを覚えます。
……つまり、心の震え(感動)を。
そしてその感動が、物自体によって引き起こされたのではなくて、その物の物質性を、「なにものか」が、精神的な高みへと引き上げたことで惹き起こされたのだ。と気付くことができます。
つまりそれは、取りも直さず、《自分の意識の働きかけが、精神的な力(なにものか)の働きを、そこに見出したのだ》――ということを。
そして、この「働きかけ」が、〝光の描く色〟に触れてゆくときに、見えないベールが取り払われて、物質界に縛られない色彩世界が開かれてゆきます。
〝虹彩法〟は、この自然界にある、〝光の描く虹の色〟の一色、一色を、分けて観てゆくことからはじめてゆきます。
それは、自然界にある光の描く色が、絵の具のように混ざった状態で見えるのではなくて、一つ一つの色が、独立した状態で、重なり合い浸透し合う姿になって見えてくる(和音のように)。という理由によります。
それは、自然界のありのままの現れであり、混ざってしまう色とは(混色した状態から元の独立した色として取りだせなくなるのは)、絵の具の持つ特性である。と言うことができます。
そして、この絵の具のもつ特性が、人の認識を高みへと導いてくれるのです。
つまり、自然界にある〝光の描く虹の色〟が、あらゆるところに重なり合った姿で現れるために、先ずは、その一色一色を識別することからはじめて、観察を進めながら、色を重ねることから進めてゆきましょう。というわけです。
*
こうして、自然の色彩の方に目を向けてゆくと、普段何気なく見ている風景の中には、実に様々な状態の色があることに気がつきます。
つまり、そこに、奥行きや運動といった、通常の色には現れてこない、違った要素が現れているのが観察できます。
(色の観察は、うんと目を細めて、物の輪郭を見ないようにすると観やすくなります)
それは、遠近法的に表現される奥行きではなく、筆の捌きによる動きでもなく……、
たとえば、一枚の葉っぱの中には、葉っぱの厚さをはるかにしのぐ色の深さが観察できますし、大気の中に、移ろい、変化する、色彩の様子を観察することができます。
……つまり、写真に写した生物と、実際の生物との違いのように。
また、人工の照明によって作られる影の中には、太陽光線の影の中に現れる、美しくバランスのとれた虹の色とは逆に、色と色の浸食とも思える、バランスを欠いた混ぜ合わさったような色が観察されます。
*
自然界の色彩からは、実に多くのことを学ぶことができます。しかし、そのすがたを描き現そうとしても、観察の当初は、それら虹の色が、沈黙したまま、何も語りかけてはくれない。と、感じられるに違いありません。
それは、自然界の色彩が、シンプルに見えながらも複雑に重なり合い、しかも移ろいやすく、わたしたちの目が、その動きについてゆくことに全く慣れていないから……、という理由によります。
空を見上げてじっと観察をつづけていると、この自然界に見る色の深さとは、個々の色たちの個性によって表される表現であり、動きとは、それら色と色とが触れ合い、ぶつかり合い、高揚し、衰退し、生成し、壊れゆく、瞬間瞬間に繰り広げられてゆくドラマなのだ。
と認識するとき、
やがて、肉眼で見る物質よりももっともっと緻密で繊細な粒子が見えはじめて……
自然界とは、このような出来事に満ち満ちていて、そこに触れたときに、わたしたちは感動を覚えるのではないか! ……との思いが、
翼を広げ――、大空に舞い上がるのを覚えるのであります。
このように、神秘に包まれた自然界の色彩に思いを馳せながら、観察と描写を繰り返し試みて、色彩の本質であるものに近づいてゆきたいと考えます。
〈 自然界の色彩 -1〉
自然界の色彩は観察する者によっても見え方が異なる。――という事実を、スケッチ会の現場を通して教えられます。
また、止まることなく活動する自然界の色彩は、移ろいやすい自分自身の内面(意識)にも似ている。
――と、観察が進むにつれ、そのように感じられてもきます。
だからといって、そのことで、描くことが容易になるわけではありません。
逆に慣れは、自分の思い込みに走り、画面上の色彩がにっちもさっちも行き場を失って濁らせてしまったり、あるいは、それまで壁であったものが突然取り払われたような気分になり、まったく違った世界観に逸(はし)り、それまでの手法を一新して、自分の今いる地点が分からなくなって、行き詰まる。といったことにもなりかねません。
そのため、制作しながら惹き寄せてしまうそのような囚われを、一一吟味しながら排除してゆく、注意力と判断力が、厳密に求められることになります。
自然界の虹の色は、自分が青を欲すれば青が現れ、黄色を欲すれば黄色が現れ、赤を欲すれば赤が現れる。
といった具合に、自分の内面に依存するかたちで表れてきます。
そのため、描き手が自分の考えでもって、空は青以外の色であってはならない。とか、太陽は黄色以外の色であってはならない。とか、
いやいや、太陽は赤でなければならない。
などと、決めつけてしまうと、人と人とのコミュニケーション自体が悪くなり、
自然の姿とはべつものの、人間関係の方に頭を悩まさなければならなくなってしまいます。
実際、こんな話を聞いたことがあります。
昔、小学校の絵の授業の最中に、空を見ていたら、そこに黄色を発見して、空全体に黄色を描いたのだそうです。
すると先生から、空の色は青色である。と、みんなの前で注意を受けてしまい、そのときから、絵を描くことに大変な苦手意識を持つようになってしまった。ということでした。
同じような経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないかと思います。
そしてこのことは、まったくもって由々しき問題であります。
しかし……もしもそのときに、その方の観察が空だけに止まらず、風景全体にまで及んで――、
『黄色ばかりか、青も、赤も、紫も……、ピンクやオレンジや、いや、もっともっとたくさんの色たちが、空や、海や、山や、そして野の草花や虫や鳥や月や星々までも照らして、輝いている!』ことが発見されていたら、
苦手意識は、密やかな楽しみへと変わっていけたかもしれません。
空を例にあげて言えば、日中の、青く輝く空全体であったり、あるいは、白くはっきりと浮かんだ雲であったり、霞がかったグレーの雲の中であったりと、様々ではありますが、
普段見慣れた、青や、白や、灰色といった空や雲の中に、……身を潜める、黄色や、紫や、ピンクや、オレンジといった色たちが、ところにより鮮やかに、ところにより緩やかに輝いている様子が観察できます。
(先述したように、うんと目を細めて観察してみてください)
その現れ方は実に捉えようがなく、時間帯や季節、大気の状態にもよりますが、観察している、その人のそのときのこころもちによっても変わる。
……としか言いようがないほど、まるで生き物のように変化しているそれらの色たちを観察することができます。
日の出前……、夜の帳が白みはじめて一日の幕が開かれてゆきます。
明るさは、黄色味を帯びながら、徐々に夜の帳の中へと浸入し、同時に、退潮する暗がりの中から鮮やかな青が姿を現します。
明るさは、空全体を包み込むように広がりながら、一日のその清らかなはじまりが、喜びに溢れるエネルギーに充たされてゆく……、と感じることができます。
みるみる高まりゆく明るさは、やがて昇りくるものを称えるように……、
水平線辺りを赤みがかった色に染め上げながら、
すると、訪れる者に道を譲るかのように、
あるいは、生まれくる者を息を潜めて待つかのように……、 突然静まる。
と、静寂を割る轟きと共に、遂に、色彩の根本である放射する光が……、厳かにそのすがたを現しはじめる。
このときの風景と、夕暮れどきの風景を写真に撮って見比べても、大した違いは感じられないかもしれません。
しかし、この両方を、じっくり観察しながら絵を描くとき、その違いは歴然となります。
朝の風景を描くと元気を貰う。「もう一枚描きたい」という気分になれる。
しかし、夕陽の風景を描いた後は、ぐったりと疲れる。
そしてそのときに、朝を染め上げてゆく黄色と、夕暮れを染めてゆく紫色を、視ることになります。
しかしこの色は、普段わたしたちが見ている色や、写真で捉えることのできる色とは性質が異なります。
言うならば、〝生命感覚〟で見ている(感じている)というような性質のもので、
朝の清々しい気分。
夕の物憂げな気分。
そのように、内的に感じられる色なのです。
……つまり、朝の色、夕の色という〝時〟に応じた〝基調となる色〟のあることを体験します。
これを仮に、〝時の色〟と呼ぶことにします。
この〝時の色〟の一日の変化に注目すると、オレンジ色に染められてゆく朝焼けの色は、背後に黄色という基調の色を持ち、
その明るさによって、朝が導かれてゆくのが感じられます。
やがて明るさは、徐々に強さを増し……、その基調をオレンジ色に変えながら、日中の一番陽の高くなる頃には、焼けるような輝き(明るさ)の中に、〝赤〟本来のすがたである、〝最大の生成と最大の破壊〟を持つエネルギーを感じることができます。
こうして、一日の移り変わりの中で最高潮に達した〝時の色〟は、その強い陽射しの中に徐々に影の色を交えながら、黄昏時には、哀しみにも似た慈しみにあふれるパープル(赤紫色)に包まれて――、日没の頃には、西の空を染め上げてゆく茜色の中に、懐深い紫の浸透を感じることができます。
こうして、陽の光が退潮してゆくなか、やがてどこまでも深い群青に導かれて、時の色は、夜の帳の中に隠れるように、青く深く沈み、夜特有の活動に入ってゆきます。
やがて、闇の深さが満ちて夜の活動も終わりに近づくころ、
閉じゆく闇の中から、身を沈めていた緑がすがたを現し、
時は、新たな朝に迎えられてゆきます――
このように、それぞれの基調の色が、それぞれの気分、つまり人間の感情と深く関わっていることを、自然界の色彩を観察しながら感じとることができます。
(しかも、その時々の〝時の色〟の中には、更なる虹色の変化があって、その中にも更に……と、幾重にも重なって感じられます)
<自然界の色彩 -2>
さて、自然の光の中でのスケッチが進むにつれ、徐々に、大気に充ちている虹の色の様子が観察されるようになり、影の中で輝いている色の様子を観察できるようになります。
自然界の色彩は、明るい場所であっても暗い影の中であっても、緻密で透明な輝きに満ちています。
そして、このときの色は、先述したように、肉眼の奥にある〝生命感覚〟で感じているような見えかたで、肉眼よりもはるかに実感を伴います。
このように書くと、何か、如何わしい話しではないのか? と、疑われるかもしれません。
しかしスケッチの現場に来て、物の形に意識を向けることを止めて、意識の焦点を風景全体に広げるように観察をはじめると、概ねそのうちの何色かは直ちに観察できる。……ことを、スケッチ会の現場で確認しています。
特に、先にも例として挙げた、小学校低学年からそれ以下の年頃には、既成概念で固まった大人の頭とは違い、はるかに柔軟な感性で、それらの色を観察することができる。
ことも、確認しています。
例えば、ある観光名所に向かっていたとします。
そこで突然、目の前に広がる光景に一瞬息を呑む瞬間のあったときのことを、
(観光名所に限らず散歩の途中であったり)思い起こしていただきたいのですが、
この瞬間には、囚われのない自然の色彩が、肉眼を通り越して心の奥まで届いていた。
ことが考えられるのです……が、
しかし、この〝光に溢れる色彩〟は、先にも触れたように、留めて観察することができません。
掴もうとした瞬間にはすでに取り逃がしてしまい、……もぬけの殻となった場所に、どこからか持ってきた、あるいは自分の作り上げたイメージでもって埋め合わせる。
という状況になり、感動はたちまち別のものに変化してしまいます。
そしてそのとき、もし、
『緑の色は黄色と青によって作られる』という概念でもって絵を描きだしたとすると、
自然界にある〝光のすがた〟が、
絵の具という素材によって、
どのように変化しているのかが、……解らなくなる。
つまり、自然界にある光のすがたを人間の頭でもって〝概念化〟しようとした瞬間から、
絵の具の色彩の持ち得る〝光〟の要素が見失われ、その事実も一緒に見逃されてしまう。
ことになる。
これは勿論、ここで述べている内容を含んでのことです。
だからこそ、〝概念化〟してゆくことで失われる〝ひかり〟を、
再び見出す試みが必要である。
――と、強く感じるのです。
人は、大人になりながら、出来事を概念化する方法を身につけてゆきます。
なぜなら、現実社会がそのようである。ことを知るからで、そしてそれが、社会を形成してゆく上で、必要なことである。と学ぶからです。
しかし……、そのことによって、失われてゆくもののあることも識ることになる。
これは、大人になりながら学んでゆく、人間にとって必要な課題であり、取りも直さず、自らの人生を通して負うことになる課題。――なのではないのだろうか。
光の要素を失う――、という、観念的にのみ関わっていたら気づかれなかったであろう出来事に、〝生命感覚〟をもって関わってゆく……ことで、描くという行為は、どこまでも内面化されてゆくことになります。
つまり、そのことによって、〝生きる〟という、辛苦を伴う内的な出来事に出くわしてゆくことになる。
このときに――、
『光であったものが光を失う――とは、どういうことなのだ?』という問いが発せられ、問いは、自分自身の内面に向かって突き進む自問自答する牙を持つ。――ことになる。
一方、このような内的な問いを持つことなく、観念的に否生命的に、あるいは無感覚的にこの問いの前を通り過ぎるときには、問いの吟味は為されないまま、素材は絵の具のまま乗せられてゆくことになる。――ということになる。
このときの絵と、幼児の描く絵を混同することは見方の誤りとなる。ので、その点に触れたいと思います。
幼児を含む子供の思考は、脳を経由して営まれる大人の思考とは異なり、はるかに直に素材に触れている。
ことが考えられるのであり、
子供の思考は、そこに素材の持つ〝光〟を見るからこそ、
あるときに見て感じた記憶が、心の核に止まったまま、大人になってもなお消えことなく遺り続ける。――のであろう、と。
子供の絵が天才であると言われる所以は、
感じたものを、感じたままに現している。
ところに見出されるのであって、
子供にとってそれはなにより自然なことであり、生きるための必要なのだ。
すると子供に、大人の喜ぶような絵を描かせようとすることは、この天才を阻害し、創造の芽を摘んでしまう。ことになりはしまいか。
子供が、本当に喜んで描くものを理解してゆくことではじめて、創造の芽は育まれ、成長を、発展する姿を、見届けることになる。のではないか、――と。
思考という、脳の活性化でもって世界を見るようなってゆく大人になってはじめて、
「光であったものから失われてゆく〝ひかり〟とは、一体何であるのか?」という問いが発せられ、
そこに〝生きる〟という問題が生じ、
……辛苦が生まれる。
(このときの辛苦は、飢餓やいじめといった外的要因による辛苦を指すのではなくて、勿論そのことも含むが、どのような状況にあっても生ずる、自分自身の中からやってくる内的要因のもたらす辛苦を指す)
ことを考えるとき、
人間の生命そのものが、
〝生きる〟という問題に、〝ひかり〟を求めてくるのではないか。
その答えとなるものを、
宗教が、
芸術が、
哲学が、
求めてゆくのではないか?
――が、しかし、この問いを見失うとき、〝生きる〟という問題は、外的要因に渡され、自分の外側に問題を抱えるような格好になる。
……そして、この外的要因となされた問題が、人間に対して様々な悪戯をする。
ことになる。
外的要因に渡された〝生きる〟という問題が、本人に基づかない様々な幻影に姿を変えて、本人自らの姿をも変身させる。そして、様々な事件、事故、紛争などの社会的問題と結びついてゆく。ことになる。
(このことは、メディアの報道によって嫌というほど報されるので、敢えて、取り上げることはしない。ことにします)
他方、内的要因のまま取り残された〝生きる〟という問題は、そこに問題を抱えるから、内的な牙で噛み砕くことで、問題の核心にある〝こたえ(すがた)〟も、解き明かされる可能性を残す。ことになる。
そして、この、内的な作業の過程で、大人になって既成概念化されて見えなくなってしまった、
幼児の頃に見ていた世界観が……、
輝きを取り戻すかたちで、現実世界を照らし得る光となって育ってゆける。
――のではないか。
このようにして、〝生きる〟という問題は、その人の努力の成果として、辛苦という〝影〟の要素の中にある〝光〟の要素を見つけだすことになる。――のだと思う。
つまり、光である自然界の色彩を、光を失った絵の具という素材で描き現そうとする試みは、
外的要因でない〝自分〟の中に、
〝ひかり〟となる要素を見つけだそうと試みる、
どこまでも意識的な作業なのだ。
そして、この意識的な作業を通して克服されてゆく過程が、目には見えないが、素材を通して明かされるからこそ、
人は、そこに、感動を覚える。――のではないのだろうか。
自然の光は、人間によって一旦その〝ひかり〟を失う。
……しかし、人の内的営みを通して再び〝内的な光〟へと変換され得る。
という事実を、自然界の色彩は教えてくれる。
いや、そこへと導いてくれる。
<自然界の色彩 -3>
もし絵の具が、下にある色を損ねることなく重なり合うことができたとしたら、見た目には、自然に近い輝きを描き現せるのかもしれない。
それは、テレビやPCやスマホのモニターのように、光線を利用した重なりとなって――。
しかしそのように便利な絵の具ができたとしたら、
先に述べたように、表現の内容となる意識的な作業が失われ、
人は、〝絵の具という素材を通して意識を高めてゆく道〟を、
見失うことになりはしまいか……と、以前より危惧はしていたのだが、
近年のテクノロジーのもたらす限りなく視覚的な映像は、
網膜の刺激を直接的に脳に伝達させるだけで、人間の内的な作業を阻害し、得られる収穫物を奪っているようにしか見えない。
……のは、わたしの眼の誤りだろうか、
網膜に受ける、外的要因が作りだす刺激は、人間の中から生じる内的なパワーを消費させるだけで、増やすことをしてくれない。
人は、外的要因の作りだす強烈な刺激に曝されると、自分の中に作り上げる内的イメージを見失うことになる。
つまりそれが、〝生きる〟というイメージ。
〝生きる〟というどこまでも内的な問題が、外的な要因に隠れて見えなくなる。
イメージとは、何かの大容量の情報を得たときに働くものではない。
限られた素材を、他の素材と組み合わせたり、合体させたり、反発させたり……と、
その情報を弄り回しているときに湧き出す内的なパワーだ。
では、〝感動〟とは、〝内的な光〟とは、〝生きるイメージ〟とは、一体……どこからやって来るのか?
自然界の色彩に目を向けるとき、そこには、前述したような内的な輝きを持つ色彩を観察することができます。
その姿は美しく、バランスが取れていて、その美しさやバランスが、見る人の心の中に〝喜び〟という明るさを作りだしてくれる。
……と、考えられます。
(もちろん、その人の感じる程度に応じて)。
つまり人は、自らの内的な喜びに明るさを感じるのであって、それは外的な光の持つ明るさよりも、はるかに親しいものです。
現代において人は、過去にあったような、偉大なる明るさにではなくて、より親密な明るさに〝ひかり〟を求めるのではないのだろうか。
自然が……、人間の内的な作業によって、汲み取ることのできる喜びを無限大に持つ存在であるからこそ、人は、その出来事の中に、〝生きている〟という喜びを感じ、〝光〟という認識を得ることができるのではないか――
そして、この自然界の〝光〟に、自らの内面にある〝ひかり〟が応えるかたちで、感動が惹き起こされてゆくことになる。のではない。
そして……、
この自己の〝ひかり〟の自覚とともに、
人間であることの、『生きる意味』の理解が、はじまってゆくのではないか。
こうして、闇の中から現れ出てくる〝自分〟という内的なひかりの認識の度合いに応じて、
日々の、日常の中に生起してくる闇(不安)の正体が、
実は〝自分自身〟であることを……、
〝自分〟を認識する深さこそが
〝光〟の正体であることを、
そして――、
それが自分の力によってのみしか達成され得ないことを……自覚するときに、
日々の日常の戦いは、
それまでとは違う、
〝内的ひかり〟を強化する機会と捉えて、
〝生きる〟、積極的な意志に置き換えてゆくことができる。
のではないでしょうか。
――がしかし、
その成果(実り)を、日常の中に直ちに得ようとすることは、理想ではあるが、
認識の際おこなわれる自問自答の牙が――諸刃となり、
自分自身を、
相手を、
深く傷つけてしまうことにもなる。
つまり、このような意識的な作業を、
日常の多忙な中に直ちに持ち込むことは、
猛暑荒天の只中に裸のまま身を曝すことと一緒で、
日常の中で早速そのことを実践しようとしても、
無理が生じるのは、火を見るより明らか。なのです。
そこで、まずは、
日常から離れた、意識の集中できる場所を見つけて
(外的刺激……たとえばゲームやPCなどではなく、自然あるいは、自分自身の内証に赴けることがらに集中して)、そこでの探求を進めながら、
獲得された認識を、――忍耐と共に、
徐々に、日常の中へと持ち込み拡げてゆくことが、現実的な成果に繋げてゆける良い方法になるのではないかと考えます。(わたし自身、その途上なのですが・・・)
〝虹彩法〟は、スケッチという非日常の場所に身を置くことで、
日常の雑多な問題から一旦意識を切り離し、
囚われのない目で自然を観察することで、
自然の持つ美しさとエネルギーに触れ、英気を養い、
本来の自分に立ち返り、
そうすることで、
日常の出来事の雑多な絡み合いの中にも、
必ず、解ける糸口のあることを、自ずと理解できるようになってゆける。
その切っ掛けにして頂けるのではないか。と、考えています。
〈 虹の贈り物 〉
自然の色彩を観察しているとき、自然界の色彩は、全体性の中にその個性を現している。ということに気づかされます。
絵の具を用いると、
虹の色は、赤色・青色・黄色の三つの色で現すことができるのですが、
〈 下図A―1 〉

このとき例えば、黄色を隠した……赤と青の関係。〈 下図A―2 〉

あるいは、赤を隠したときの……黄色と青の関係。〈 下図A―3 〉

更に、青を隠したときの……黄色と赤の関係。〈 下図A―4 〉

と観てゆくと、三つの色が揃っているときに感じるそれぞれの色が、どれかの色を隠したときには、その性質が変わったように見える。
もっと適切に言うなら、固有の輝きを失う。ことに気付かれないでしょうか。
(※ここで取り上げるはなしは、飽くまでも絵の具の色のことについてです)
実はこの図、ドイツの詩人ゲーテが考えた『色相環』という色の配置図を、自分流にアレンジして作った「虹の太陽」なのですが、
ゲーテは、プリズムを使った実験を通して、自然界の色彩の調和する姿を『色相環』という図にして示しました。
〝虹彩法〟を紹介したビデオ、そして拙著「スケッチに行こう」に述べさせていただいているのですが、この『色相環』にまだ出会う前、
主催させていただいていた子供スケッチ会に、お兄ちゃんだったかお姉ちゃんにくっついてきていた小さなお子さんの真似て描いていた絵が、まさに、このようだったのです。
そのころのわたしは、〝虹彩法〟の説明を虹の形を模して説明していたのですが、
その絵を見た瞬間、
『これこそ、求めていた、自然界の色彩だ!』と、直感しました。
その後に、ゲーテの〝色彩論〟に示された『色相環』を知り、それが〝虹の太陽〟に発展して、現在のわたしのイメージする、色とことばの橋渡しになっています。
この三つの色の性質の違いは、探求するほどに明らかとなります。
この虹の輪に、緑から紫に至る対角線を引いたとします。このとき右下の部分を隠すと、(左図)黄色からオレンジ色を経て赤に至る明るい色が現れ、
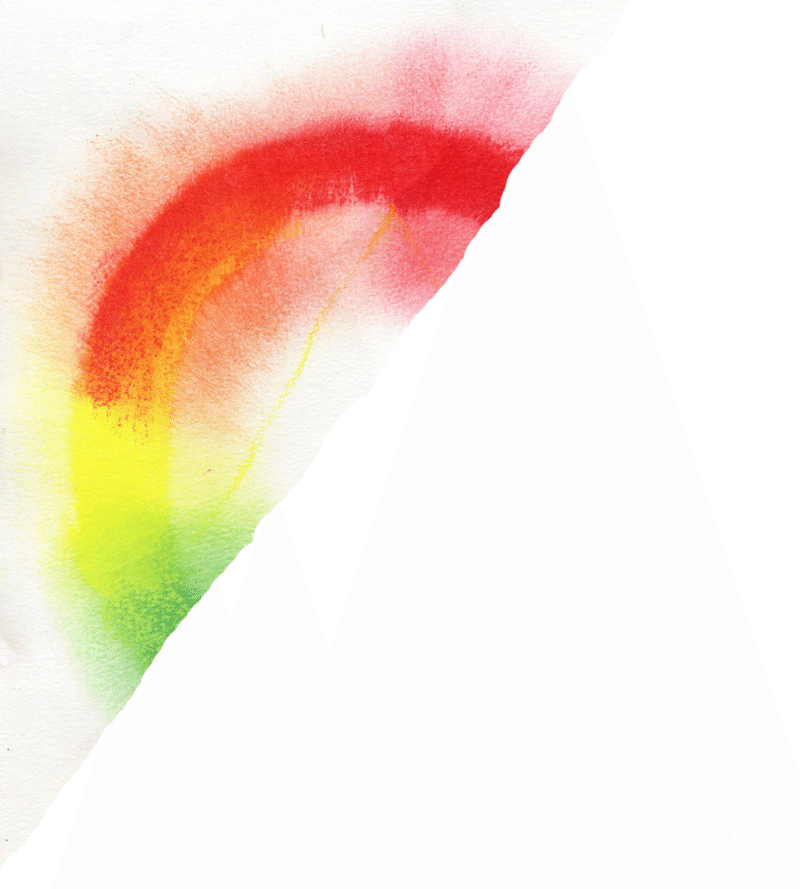

反対に、左上の部分を隠すと(右図)、紫色から青を経て緑に至る暗い色が現れるのがお分かりいただけると思います。
そしてこの図に、先述した〝時の色〟の黄色からはじまる一日の色の移り変わりと、
更にそこに、四季の変化をなぞらえてみると――、
一日の目覚めとなる〝時の色〟は……、
新しいいのちのはじまる若葉の芽吹く輝く春の色に、
やがて木々の若葉は、活発となる夏の強い陽射しにふくまれる〝赤〟を吸収して、
ぐんぐんとその緑の色を深め……、
秋、懐深い〝紫〟の光の浸透の中に実を結び、〝緑〟は、星々の煌めく宇宙の深さの〝群青〟に導かれて〝青〟く沈む冬の眠りへと向かい、新たな命としての目覚めを待つ。
このときの、春に芽吹く木々の若葉の色とは……、
光の表現である黄色と、水の表現である青との共働の成果であり、
夏の太陽に焼かれてゆく若葉は、
その中に熱の表現である赤を吸い込んで、いよいよその緑の深さを増し、
秋、三つの色は互いに結び合い、実りと成し、
冬、実りは種を遺して、土(実りを育てる土)の表現となって還ってゆく――。
それはまるで、人生の巡りのようにも見えてきます。
このように、ゲーテの考えた(発見した)色相環を通して表れてくるイメージを拡大解釈してゆくならば、
この虹のすがたとは、太陽の内的な顕れを暗示しているのではないか……、
と見ても、差し支えはないのではなかろうか。と、勝手に考えています。
そして――、ゲーテの考えた色相環を絵の具に置き換えてみれば、
黄色は、青と混ざることで緑という新たな姿を得るのであり、
赤は、青と混ざることで紫の姿を得、
そして、赤と黄色が混ざることでオレンジ色の姿を得るのである。……から、
これは、自分とは、違う個性を得たことによって、豊かな変化を得る。のである。
と見ることができる。
……しかし、このことは、
相手の個性を奪った。
と見ることもできる。
つまり、絵の具によって、
虹の色は、
互いに、個性を失いながら、新たな個性を得る。
――それはちょうど、人が、今までの認識を棄てることによって、新たな認識を得る。
ことに似ている。
このように、人は、絵の具という素材(物質)を用いることで、高い認識に至る道を開いて行くことができる。……と、言うことができる。と思う。
更に――、黄色という色は、赤色という色は、青色という色は、先述したように単独で成り立つことができない。
つまり、他の二つの色との関係性においてはじめて、固有の色としての自立性を持つ。
――ことを考えれば、
前述したことも踏まえて、このことが、個性をなすために必要な関係性なのであり、
個から全体性(宇宙)へ到る、唯一の認識を与えてくれる関係になるのではあるまいか。
つまり……、〝感動〟の、秘密なのではあるまいか。と。
さらに更に――、赤紫(パープル)という色は、この虹の構成体全体を包み込む性質を有していて(拙著、「スケッチに行こう」に叙述)、
この色が、赤・青・黄色という色の中から現れることで、虹の色の関係性は、更なる高み(深さ)へと導かれてゆくのです。
自然の力は、この構成体を保持することを行うのではないか――‼
※ここに示した内容は、あくまで、わたしの、内的要因に基づく話しであります。
ところで、闇の色とされる〝黒〟は、この三つの要素が最大限に濃縮された姿である。とは考えられないでしょうか?
そのこともあって、わたしの主催させていただくスケッチ会では、「なるだけ黒を遣わないように」、進めさせていただいております。
*
自然界の色彩は美しい調和に貫かれており、人は、自己の思考と感情という内的な力を通して、
この調和の中に意識的に関わり、
その体験で得た実りを携え、
ふたたび何度でも、
現実である日常の中に出ていって、
内的な戦いに臨みながら、
その本来の目的である〝自己の強化〟を、行ってゆける。
――のではないか、と、信じます。
日常こそは、自己の偏見や囚われの渦巻く、内的な世界の表れであり、
僅かずつしか進んでゆけない〝試練の場〟であります。
そして……、
この、色彩体験を通して、
『自然界に輝く色彩とは、外なる自然ばかりを照らしているのではなくて、それは、自分の内面へ向けられた〝ひかり〟である‼』
という認識が、
日常を取り巻く闇(不安)を、
確実に照らす〝ひかり〟になり得る。――と、
堅く信ずるのであります。
青空の秘密は、緑の葉っぱの秘密は、その色彩の中にのみ記されてあり、
人は、その内的な営みを通して、
その神秘の扉の向こうにある〝ひかり〟を証ししながら、
自己の内面を強化しつつ、
全体に関わる者へと成長してゆけるのだ、――と。
2005年3月初版・2011年3月改訂~2022年第三版、2023年6月第4・10月第5版 2023年10月9日 著者 瀬﨑 正人
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
