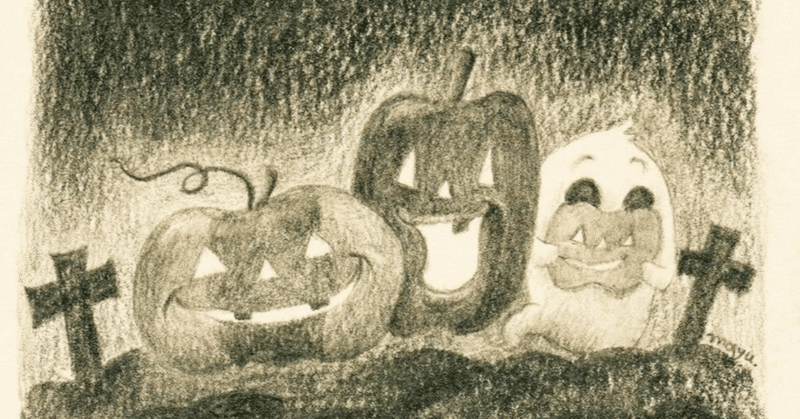
【短編】魔の祭日(3000字程度)
月の見えない重苦しく心地よい闇の下、庭先のカボチャの火が足元を照らす。
彼の命がゆらゆらと庭を見つめている。口は歪んだ笑みを表し、目は恍惚とした虚ろである。このカボチャとなった者の生前に、私は想いを馳せた。
きっとカボチャのようにからっぽで、なんにでも興味を示す、危機感の一切がくり抜かれたおつむをしていたことだろう。そんな生物はどこを探しても人間以外に他はないのかもしれない。あるいは飼い慣らされた愚かな犬が稀に当てはまるか。
まったく、犬を好く人間というものが理解できない。
それに、猫と対等のように扱われているのも気に食わない。猫があんな舌を常にさらし続けるアホ面をと対等なわけがないのだ。あんな人間に従順な生物が、思い上がりの人間を陰で嘲笑うことの悦びを知る猫と同じように扱われているのに腹が立つ。人間など、猫の生活を潤す下僕であるべきなのだ。
あるいは、彼の命となってもらうべきだ。
人間の存在価値は、彼のためにカボチャとなる以外にあるわけがない。
庭に面した通りを照らすカボチャの火は、この足元の一つきりとなってしまった。そろそろこの場所ともお別れだ。私は、最後まで残しておいた、そのとっておきのカボチャの隣にかがみ、溜め息を漏らす。彼のためとはいえ、お菓子を作るのはなかなか面倒なのだ。儀を執り行うための祝祭、最後の晩餐を人間に設けなくてはならない。
霧の立ち込める大通りの向こうから、黒猫が私の方へ歩いてきた。人間がつけるような呼称はなく、黒猫は私にとって黒猫であり、それ以上でもそれ以下でもない。しかし、美しい漆黒の毛並みは気に入っている。
黒猫は私の横に落ち着くと、ただ前を見据えるのみであった。目的は私と同じで、その時を待っている。黒猫がやってきたということは、いよいよ時間ということだ。
黒猫は、私に媚びようなどとはしない。もっと明確に言うならば、媚びる風を装わない。私がその対象に含まれないことを黒猫はよく知っているのだ。
ふっと、火が揺らめいて明滅したと思ったら、そこには彼がいた。
「いやぁ、待たせたようだね」
ジャック・オー・ランタンが、軽快な調子で口から漏れ出す灯りを揺らめかせた。しかしその灯りは弱々しく、今にも沈黙してしまいそうだった。
「遅いわよ。埃にでもなった気分だったわ」
狼男のように睨みを利かせたつもりだったが、その伽藍洞の瞳をみると、ジャックには通じていないみたいだった。隣で黒猫がニャーと鳴いた。
「十三人の子どもと、十四人の大人が住む地域を探すのは中々大変だったよ」
もしくは二十六人の子どもと二十八人の大人、とジャックは黒猫を持ち上げ、続けた。いつもより口数が少ない。黒猫は媚びる必要がないジャックを煩わしく思ったのか、引っ掻いた。脆くなっていたジャックの頭にヒビが入る。
あ、とジャックの開きっぱなしの口の中で火が萎縮した。
「もうこの頭もダメか。いやはや、短命の不死も辛いものだね。明日まで保つかな」
黒猫を下ろしてジャックが呟く。
「そのカボチャは子どもだから今日まで。今日で十三日でしょう。辛いのは貴方でなく、私の方よ、ジャック」
私は、怪しげに輝く、足元のとっておきのカボチャを撫でた。とても落ち着く灯りだ。
「開催場所を探すのにこんなに待たされる身にもなってほしいわ。探す手間を省くために、死神に間引いてもらえないかしら」
「彼は毎日忙しいからね。とても難しいよ」
そういえばこんな話は去年の今頃もしていたような気がした。
「じゃあフランケンの怪物は?吸血鬼も、狼男だっているでしょう」
これから忙しくなることを思うと誰かに頼りたくなってくる。私とジャックの仕事を少しでも引き受けてくれる怪人はいないものか。
「彼はネジの調子が悪いらしくてね、博士に直してもらっている最中だよ。吸血鬼は、あいつは今は、彼女を仲間に引き込もうと奮闘中だ。狼男は人を間引くほど人前に出ようとはしないやつだよ。月が出てないとどうしようもないよ」
そう言ってジャックは月も星も見えない空を見上げた。
怪人も各々都合があるようだ。しかしフランケンの怪物はいつもそんな調子だから、博士が哀れである。
「そもそも、誰かに間引いてもらっても、結局は死神の仕事を増やすことに繋がるから、心苦しいものだよ」
だから人数の揃っている地域を探すのがいいのさ。
最早理解していることなので、この話をグダグダ続ける意味はなかった。しかし、理解はしていても納得しているわけではないので、こうして、私はいつもジャックに不平を漏らすのだった。
「ともかく、今はその頭を取り替えましょう」
「おお、そうだったね」
そう言うとジャックは、最後のカボチャを持ち上げ、まじまじと見つめた。
「このカボチャでこの地域も最期と思うと、なんだか感慨深いものだね。どうだろう。このカボチャは僕に似合うだろうか?」
「カボチャなんてどれも同じよ。それに似合ってなかったら取り替えないつもりかしら?」
いつも通りの会話だ。ジャックの唯一のお洒落と言えるのがカボチャ頭の取り替えである。服は細身の黒のタキシードで定着している。服といっても脱ぐことはなく、それが彼の体の一部のようなものなのだ。これを服というのであれば、肌が剥きだしている部位はどこにもない。手は白の手袋をはめているし、首もない。カボチャが人でいう頭の場所に据えられるだけである。
「そうも言っていられないから取り替えるけど、ハロウィンには皆が来るだろう?」
カボチャの火が一段と弱弱しくなる。「一番似合っているカボチャ頭でいたいのさ」
私はそれを聞いて笑みを浮かべた。
「大丈夫よ。それはとっておきのカボチャ。一番似合うと思って今日までとっておいたのでしょう?」
ジャックの瞳が、心の内までも見透かすかのようにこちらを見つめてくる。本当に心を読まれている気がした。
ハロウィンに一番似合っているカボチャがそのカボチャだと、貴方が言ったのよ。だから大丈夫。よく似合うと思うわ。
私は心の内でそう言った。
さっきよりも密やかな彼の命がちろちろと揺らめいて、消えた。とっておきのカボチャの火もそれに続いて消えた。
一瞬の闇の中、私はハロウィンがやってくることが楽しみに思えていた。いつもそうだ。お菓子を作るのは面倒で嫌気がさすが、ジャックが年に一度、最もその火を激しく燃やす夜が、すぐそこまで近づいていることを思うと、私の瞳は、暗闇の中で猫娘のようならんらんとした輝きを宿らせていた。
ミイラの眠りのような沈黙がしばらく続いた。瞬間、私の瞳の輝きは更に増し、沈黙は引き裂かれた。カボチャの灼熱が天空に火柱を立て、辺り一面をあぶり出した。火柱はしばらくの間天空を焼き焦がし、暗雲に風穴を開けた。満たされない月が、ひっそりとした青白い光で魔の祭日を求める。スポットライトのような月の欲求を受け止めるのが、ジャック・オー・ランタンである。カボチャの火が、彼の中で月の光よりも怪しげに青く揺らめいた。
ハロウィンがやってくる。天空を焼いた火柱が招待状だ。多忙の死神や、いつも神妙な狼男、フランケンとその怪物、吸血鬼、その他の怪人もこれを見ていたはずである。
虚ろな瞳にいつになくやる気を滾らせた彼が怪しげに青い炎を吐いた。
「愉快で仕方ないねえ。さあ、ハロウィンの夜を催そうか」
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
大学生のときに書いたやつなんで、10年くらい前の文章です。
ハロウィンということで久々に思い出したので、載せてみます。
魔女の視点で書いたからか、だいぶ気取って書いたのを覚えています。
この続きは、いつか書いてみたいんですけどねぇ……。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
