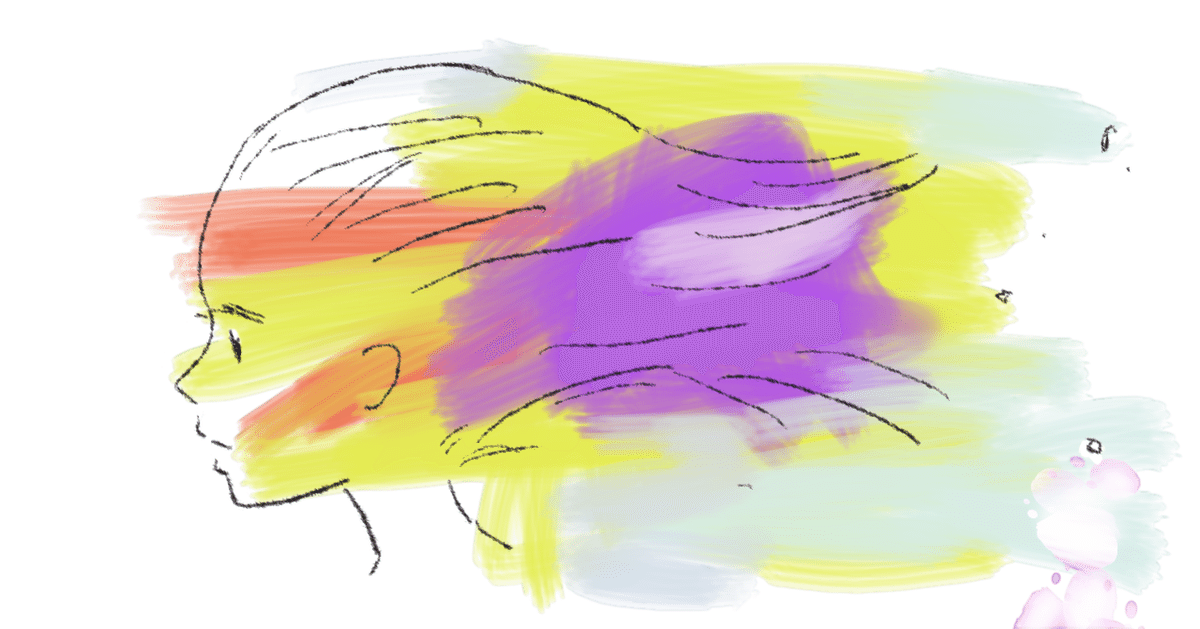
1___君の彼氏になりたい。 / SnowMan
———高嶺の花。
そう表現するのが一番正しい。初めて会った時から、君の笑った顔が僕だけに向けられてたらいいのにと思った。一度も面と向かって好きだとは言ったことはないし、言うつもりもない。・・・まあ、そんな状況には一生ならないと思うけど。
「あの。お風呂、ありがとうございました」
そんな彼女がなぜ、俺の家で、シャワーを浴びている????????
——————数時間前。
「え〜、本日は親睦会に参加いただきありがとうございます!楽しみましょう!かんぱーい!」
カチンと爽やかな音が店内に響き渡る。もう赤ら顔の社員がちらほらと見える。
20人以上が参加するこの”親睦会”と言う名の合同コンパは、会社で年に一回行われる”慣例行事”になっている。会社のお金で酒が飲める、他の部署の人間と交流できるため参加。各々、参加する名目がある。
「おい、お前の狙ってる子、向こうで上司に絡まれてるぞ、いいのかよ?俺はあの子の隣の子がいい〜から行こう!」
有無を言わさず連れていかれ、そのまま、女子2人と上司の間に割って入る。勝手に自己紹介を始める同期を横目に俺も着席し、目を合わせないように自己紹介をする。
「初めまして、だよね、初めまして。俺は」
「・・・初めまして・・・?」
「え?・・・あ〜〜〜、ごめん、俺トイレ行くわ!」
誰が反応するわけでもなく、席を立つ。戸惑った顔が俺を見つめていた。
トイレに入った瞬間、顔が熱くなる。あの反応はなんだ?話したことあるのか?
確かに、彼女は社内でも可愛いと多部署からも噂されるほどのルックスの持ち主で、入社してまだ半年しか経っていないが、散っていった男は数しれず。そんな彼女と。俺が。初めましてじゃないのか???
それはもちろん、俺も廊下ですれ違った時に一目惚れしたが。え、いつ。どこで?
いくら考えても思い出せないため、諦めてトイレを出る。
戻ると、座っていたところにまたあの上司が座っていて、俺の同期は女子と2人でどこかへ消えていたので、端っこの方に座って終わるまでやり過ごすことにした。
「はい!じゃあ二次会行く人〜〜!ついてきて〜〜」
うちの営業部エースと部長が先頭を歩く。
静かに、一礼をして、軍団に背を向けて歩き出す、と。
「あの」
「はい?・・・あ」
振り向くと高嶺の花がこちらを見つめていた。
「え、なに〜〜?いかないの?」
さっきまで彼女の隣にいた課長が彼女に話しかけにくる。
「え、あ、はい。ちょっと明日、予定があるので」
「そうなんだ、じゃあね、お疲れ様」
さっと身を翻して軍団に溶け込んでいくのを自然と2人で見送る。
「えっと、じゃあ」
「あ、私もこっちなので一緒に帰ってもいいですか?」
「・・・はい、どうぞ」
とは言ったものの、歩き始めて10分ほど沈黙が2人を包む。口を開こうとしたのを阻止するかのように、冷たいものが首筋に当たる。
「冷たっ、え、マジ?」
見上げると顔に当たる、雨。小雨ならまだしも、激しく降る雨。今日の天気予報では雨マークはなかったはず。
「あの、俺んち、走ればすぐなので、そこまで走れます?」
「え?あ、はい、大丈夫です!」
激しくなる雨に内心感謝しながら、2人で走って俺の家へ。
「本当にすぐでしたね」
「はい、今日飲み会近くで良かったです。あ、ちょっと待っててくださいね」
着いてすぐに我に返る。え。俺、何大胆なことしてんの?と自分を責めようと思ったが、玄関先からくしゃみが聞こえたので大急ぎでタオルを持っていった。
「すすすすすみません!!すぐ拭いてください!あ、玄関じゃ冷えますよね!あ、洗面所使ってください!俺、大丈夫なんで!!あ、風呂、あっため・・・」
そこまで言って、また自分をぶん殴りたくなる。考えないで出てくる言葉ってなんだよ。
「ふふふ、ありがとうございます。洗面所使っちゃっても大丈夫ですか?」
「っ、はい!どどうぞ!お風呂もよかったらどうぞ!」
驚いた顔の後、失礼します、と靴を脱いで洗面所に消える彼女。少し経った後、顔だけ出しながら、
「やっぱり服が乾くまでお風呂はいってもいいですか?」
「どうぞ!!!!!」
そう言ったのはいいものの、濡れたヒールの靴に新聞紙を入れながら自分が何をしたか思い出して恥ずかしくなる。
「お風呂ありがとうございました」
後ろから声が聞こえ、すぐ立ち上がる。
「あ。これは決して、変な意味ではなく、濡れた靴には新聞紙を入れると乾きやすいので、」
俺のよりもはるかに小さい靴を持ちながら弁明する。
「あはは、大丈夫ですよ。ありがとうございます」
「い、いえ、あ、コーヒーでも飲まれます?」
顔を上げると俺のスウェットを着た彼女。あ、やばいわ、これ。
すぐに目をそらす。服が乾くまでの間。乾くまでの間だけだから。
「いただいてもいいんですか?服も貸していただいたのに。あ、でもお風呂」
「あ、大丈夫ですよ、乾きましたし、服も替えたので。それに、乾くまでも少し時間ありますし」
「じゃあ、いただきます」
そういって微笑む彼女に、俺は、やはり、恋をしている。
単純だけど、仕方ない。彼女の笑顔が俺のものになればいいのに。
「どうしました?」
「あ、いや、ミルクは入れますか?」
「ん〜〜〜、ください!苦いの少し苦手なんです」
と肩を竦める。嗚呼、くそ。このまま帰したくない。帰らないでほしい。
時計の針を確認しながら、コーヒーを淹れる。気を紛らわすために、テレビをつけると、今話題のアイドルが新曲を披露するところだった。
「知ってます?この人たち、ダンスすごく上手なんですよ!」
「へえ、初めて聞きました、好きなんですか?」
「最近、よく聞きます!」
そうなんですね、と相槌を打ちながら自然と趣味の話になる。彼女は休日はショッピングすることが多いこと。海外映画は字幕で見ること。本は表紙で決めて買うこと。知らない彼女が垣間見えて、コーヒーが冷めても気にならなかった。
「あ、じゃあ今度おすすめの」
——ピピピピッ
彼女の話を遮るように、現実に引き戻すかのように、乾いた音が鳴る。
「あ、乾きましたね、それに、もう12時近いですし」
時計を見ると11時半を指そうとしていた。
「そ、うですね、雨もおさまってきましたし、今日はありがとうございました」
そう言って立ち上がり、洗面所の方へ行く彼女の腕をつかもうと空を切る。
「え?」
「あ、ゴミが、」
「ありがとうございます」
無理だ。絶対無理だ。そんなことできるわけがない。『帰るな』なんて言えるはずがない。こんなに終電が来ることを恨んだことはない。
彼女を玄関まで見送る。
「今日は本当にありがとうございました。あの、傘、必ず返しますね」
「いや、ビニールなんでどっちでもいいですよ」
「いえ、必ず返します・・・じゃあ、ありがとうございました、おやすみなさい」
「本当に駅まで行かなくていいんですか?」
「すぐそこなんで、大丈夫です。ありがとうございました」
一礼して出て行く彼女を引きと目ようか何度も考えたけど、俺にはそんな勇気なかった。扉が閉まってからも新聞紙を握りしめたまま扉を見つめていた。
そんな次の日、風邪を引いたのは言うまでもない。
『遅くまで昨日はありがとうございました。帰れましたか?』
昨日のスウェット姿を思い出してしまう。昨日の余韻が冷めない。熱も下がらないい。返事が来ることを見届けず、また深い眠りにつく。休みでよかった。深い闇に吸い込まれるかのように、体がどんどん沈んでいく。体が重い。
夢を見た。彼女が知らない人と街を歩いている。俺の知らない服、昨日とは違う靴を履いて。笑っている。誰に笑いかけているの?それを見ているだけの俺。ただ、それだけの夢。
目が覚めると陽は傾いていて、熱もだいぶ下がっていた。夢見が悪く、頭がぼーっとする。返事は来ていなかった。意気地なしな自分に嫌気がさす。
昨日の彼女の濡れた髪の毛も、笑った時に糸目になるところも、確実に俺に向けられていた。でも、俺のものではなかった。想像しても泡のように彼女は消えて行く。彼女は誰のものでもない。
「美容院行こうか、な」
彼女はどんな服装が好きなのかな。髪の毛は短い方が好きなのだろうか。彼女に会えることを考えると自然と笑みがこぼれる。
次、もし会えたらなんて言おう。2人で会えるなら、言ってもいいかもしれない。
———ピロン
『昨日はありがとうございました。今度の休日、傘返しにお家お伺いしますね』
「お邪魔します」
「どうぞ、散らかってますが」
「ふふ、散らかってなんかないですよ、あ、髪の毛切りました?」
「あ、はい、あ、そう、なんです」
「似合ってます」
告白なんて絶対無理だ。可憐に笑う彼女は俺の隣にふさわしくない。
冗談でも言えることと言えないことがある。
彼女の用事のついでに寄ってもらったため、時間は限られている。時計の針はもう8時を指そうとしている。カフェオレを机に置きながら彼女の今日は濡れていない髪の毛を見る。
「遅くにすみません、本屋寄ったら、遅くなっちゃって」
「いえ、大丈夫ですよ」
「それで、これ、」
彼女は紙袋から一冊の本を出す。
「え?あ、これ、え?」
戸惑いながら受けとった一冊の本は俺の好きな作家の最終巻だった。前はそんな話してないのに。
「思い出せませんか?」
上目遣いで見つめる彼女の目が潤んでくる。頭をフル回転させ、彼女と本を結びつける。
一つの衝撃的な出会いを思い出す。
「・・・・・・もしかして、”表紙買いして失敗してた子?”」
「・・・っ、はい!思い出してくれましたか?」
嗚呼、彼女の笑顔を見て、全て思い出した。
それは、桜が咲いて、新入社員の心が浮ついている時。俺も浮ついていてあまり入社式のことは覚えていない。うちの会社の入社式は部署別ではなく、早めに来た人から詰めて座る形式で、俺は同期とは別の場所に座っていて、周りは知らない人だらけだった。
「ハズレかよ・・・」
「ですよね!私もそう思います!」
「え?」
隣から、俺の独り言に反応する声が聞こえた。
「え?あ、すみません。私、さっき本屋寄って表紙で決めて買ったんですけど、今読んでたら全然面白くなくて」
「はあ」
「もしよかったらいりますか?」
「これ、俺は好きですよ?人間が生々しく描かれているし、歯に衣着せぬ台詞の数々で」
「私はもう少しライトな恋愛小説だと思ったのに、しかも表紙なんてザラブストーリーみたいなものだったのに、しかも3巻目だし、あげます」
「あ、ありがとうございます」
「いえ!でもお隣に座ったのが貴方でよかったです」
笑った顔が可愛いのと積極的すぎるギャップに圧倒されて、もらった本の記憶しかなかった。入社式の感じと違ったから。廊下ですれ違った時はもうそんなことすっかり忘れていた。
「ごめん、飲み会で初めましてなんて言って」
「そうですよ!私はあれから会社中探して、あの時の貴方だって気づいてました。でも全然話すタイミングなかったし、本の内容語り合うような関係でもないし、だからこの前は気づいてもらえるかなと思っていたのに、全然気づいてもらえないし」
「ごめんって、思い出した、最終巻持ってなかったんだよ、ありがとう」
「いえ、思い出してもらえてよかったです!」
涙目になりながら嬉しそうに話す彼女が愛おしくて如何しようも無い。
時計の針はそろそろ11時を指そうとしている。彼女はあと30分もしたら帰ってしまう。帰していいのか?傘も返してもらってもう会う口実は無くなってしまった。
でも、俺にとっては高嶺の花の彼女と、釣り合うのか。
心臓がドクドクと大きく胸を打つ。
テレビから彼女の好きなアイドルがまた歌唱していた。
「好きです」
「え?」
「・・・このアイドル!俺も、なんか好きです!」
「ふふふ、ありがとうございます」
俺の阿保。馬鹿。意気地無し。
でも言えるわけない。絶対無理だ。時計はそんな俺を焦せらせるかのように止まることはない。
11時半を指そうとする。
「あのもうそろそろ、出ますか?」
「あ・・・、そうですね、そろそろ、行こうかな」
腰をあげ俺の横を通り過ぎる彼女。
考えなしで動く俺はマジでどうかしてる。
気づいたら腕を取っていた。驚く彼女を見ないで、早口で伝えようとする。
「あの、今日は、帰らなくても、いいんじゃないでしょうか?」
「・・・え?」
「・・・・・・いや、嘘です、すみません」
「嘘なんですか?」
「え?」
「私は、帰りたくないです」
俺の意気地なし。女性に言わせるのかよ。
「今日は帰らないで」
次はちゃんと目を合わせて。彼女の目が潤む。嫌だったのだろうか。
「12時過ぎても、おうちにいていいんですか?」
「好きなだけいてください」
そう笑うと、彼女は少し意地悪な顔をする。
「でも、私たちの関係に名前がないなら、今日は2時に帰ります。タクシーもあると思うし」
意地悪な笑みを浮かべて俺に少しづつ近づいてくる。
「2時に帰っていいですか?」
不敵な笑みの彼女に勝るものはない。気づいたときにはもう遅い。
彼女の耳元に口を寄せ、簡潔に今思っていることを呟く。
彼女は一瞬驚いた後に大きく頷きながら俺に抱きつく。
嗚呼、きっと本をもらったあの時から、俺は彼女に恋をしているのではなく、彼女の笑顔に囚われているのだ。逃げ出せない。彼女の笑顔からはもう逃げられない。
気づいたときにはもう俺は彼女のもの。
『君が好き。君の彼氏になりたい。』
Fin
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
