
方程式【もしかして(日本+イタリ ア)÷2=理想郷?】の解きかた
男はだまって大いにしゃべる

昔、日本には、三船敏郎が演じる「男は黙ってサッポロビール」というコマーシャルがありました。あのキャッチフレーズは、沈黙を美徳とする日本文化の中においてのみ意味を持ちます。
一方ここ欧米では、男はしゃべることが大切です。
特に紳士たる者は、パーティーや食事会などのあらゆる社交の場で、 自己主張や表現のために、そして社交仲間、特に女性を楽しませるために、一生懸命にしゃべらなければなりません。
「男はだまって、しゃべりまくる」のが美徳なのです。
例えばここイタリアには人を判断するのに「シンパーティコ⇔アンティパーティコ」という基準がありますが、これは直訳すると「面白い人⇔面白くない人」という意味です。
そして面白いと面白くないの分かれ目は、要するにおしゃべりかそうでないかということです。
ことほど左様にイタリアではしゃべりが重要視されます。
イタリアに限らず、西洋社会の人間関係の基本には「おしゃべり」つまり会話がドンと居座っています。社交の場はもちろん、日常生活でも人々はぺちゃくちゃとしゃべりまくる。

社交とは「おしゃべり」の別名であり、日常とは「会話」の異名にほかなりません。
言葉を換えれば、それはつまりコミュニケーションの重大、ということです。
コミュニケーションのできない者は意見を持たない者のことであり、意見を持たないのは、要するに思考しないからだ、と見なされます。
つまり西洋では、沈黙は「バカ」と同じ意味合いを帯びて見られ、語られることも多い怖いコンセプトなのです。
西洋人のコミュニケーション能力は、子供の頃から徹底して培われます。
家庭では、例えば食事の際、子供たちはおしゃべりを奨励されます。楽しく会話を交わしながら食べることを教えられるのです。
日本の食卓で良く見られるように、子供に向かって「黙って食べなさい」とは親は決して言いません。せいぜい「まず食べ物を飲みこんで、それからお話しなさい」と言われるくらいです。
学校に行けば、子供たちはディベート(討論)中心の授業で対話力を鍛えられ、口頭試問の洗礼を受け続けます。
そうやって彼らはコミュニケーション力を育てられ、弁論に長けるようになり、自己主張の方法を磨き上げていきます。
社交の場の「おしゃべり」の背景にはそんな歴史があります。それが西洋社会なのです。
沈黙を美徳と考える東洋の国で育った筆者は、会話力を教えられた覚えはありません。
おしゃべりな男はむしろ軽蔑されるのが、いかに西洋化されたとはいえ日本の歴とした現実です。
男は黙ってサッポロビールを飲んでいるべき存在なのです。自己表現やコミュニケーションを重視する西洋文化とは対極にあります。

筆者は日本の風習とは逆のコンセプト、つまり「‘おしゃべり’がコミュニケーション手段として最重要視される」西洋社会に生きています。
そこで筆者は、仕事や日常生活を含むあらゆる対人関係の場面で、懸命に会話術の習得を心がけようと努力してきたつもりです。
おかげで日本人としては、パーティーや食事会などでも人見知りをせず、割合リラックスしてしゃべることができる部類の男になったのではないか、と思っています。
ところがそれは、西洋人の男に比べると、お話にもならない程度のしゃべりに過ぎないのです。
子供時代から会話力を叩き込まれてきた彼らに対抗するには、筆者は酒の力でも借りないと歯が立たない。
ワインの2、3杯も飲んで、さらに盃を重ねた場合のみ、筆者はようやく男たちのおしゃべりの末席を汚すか汚さないか、くらいの饒舌を獲得するだけです。
その後は知りません。彼らのしゃべりに圧倒されて、負けないゾと頑張って、頑張るために杯を重ねます。重ねるうちに絶対にやってはいけないことをやります。
つまり「酔いに呑まれて」しまって、やがて人々のヒンシュクを買う羽目に陥ったりもするのです。
ベニスを見てから死ね

ベニスは街の全体が巨大な芸術作品と形容しても良い場所です。
その意味では、街じゅうが博物館のようなものだと言われる、ローマやフィレンツェよりもはるかに魅力的な街です。
なぜなら博物館は芸術作品を集めて陳列する重要な場所ではありますが、博物館そのものは芸術作品ではないからです。
博物館、つまり街の全体も芸術作品であるベニスとは一線を画すのです。
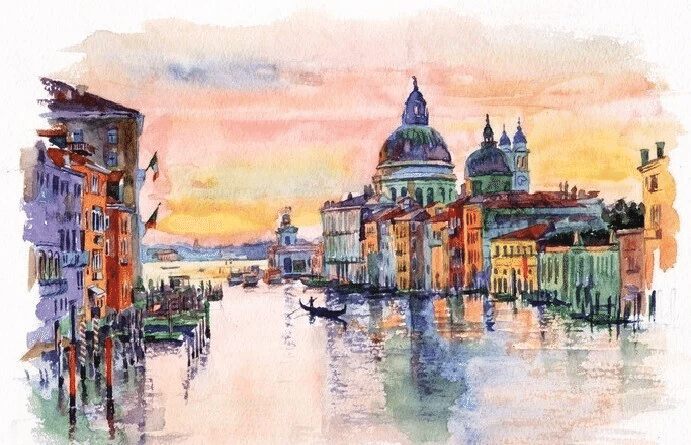
ベニスは周知のように、何もない海中に人間が杭を打ちこみ石を積み上げて作った街です。
そこには基本的に道路は存在しません。その代わりに運河や水路や航路が街じゅうに張り巡らされて、大小四百を越える石橋が架かっています。
水の都とは、また橋の都のことでもあるのです。
ベニスの中心部には自動車は一台も存在せず、ゴンドラや水上バスやボートや船が人々の交通手段となります。

そこは車社会が出現する以前の都市の静寂と、人々の生活のリズムを追体験できる、世界で唯一の都会でもあります。
道路の、いや、水路の両脇に浮かぶように建ち並んでいる建物群は、ベニス様式の洗練された古い建築物ばかり。
特にベニスの中心カナルグランデ、つまり大運河沿いの建物はその一つ一つがい謂(いわ)れのある建物群。全てが歴史的建造物。
それぞれの建物は、隅々にまで美と緊張が塗りこめられて大運河の全景を引き立て、それはひるがえって個別の建築物の美を高揚する、という稀有(けう)な街並みです。
しかしこう書いてきても、ベニス独特の美しさと雰囲気はおそらく読む人には伝わりません。

ローマなら、たとえばロンドンやプラハに比較して、人は何かを語ることができます。
またフィレンツェならパリや京都に、あるいはミラノなら東京やニューヨークに比較して、人はやはり何かを語ることができます。
ベニスはなにものにも比較することができない、世界で唯一無二の都会なのです。
唯一無二の場所を知るには、人はそこに足を運ぶしか方法がありません。
足を運べば、人は誰でもすぐに筆者の拙(つたな)い文章などではとうてい表現し切れないベニスの美しさを知ります。

ナポリを見てから死ね、と良く人は言います。
しかし、ナポリを見ることなく死んでもそれほど悔やむことはありません。
ナポリはそこが西洋の街並みを持つ都市であることを別にすれば、雰囲気や景観や人々の心意気といったものが、たとえば大阪とか香港などにも似ています。
つまり、ナポリもまた世界のどこかの街と比較して語ることのできる場所なのです。
見るに越したことはないが、見なくても既に何かが分かります。
ベニスはそうはいかない。
ベニスを見ることなく死ぬのは、世界がこれほど狭くなった今を生きている人間としては、いかにも淋しいことです。
‘違うこと’は美しい

筆者はここイタリアではミラノにある自分の事務所を基点にテレビの仕事をして来ましたが、これまでの人生ではイギリスやアメリカにも住まい、あちこちの国を旅し、学び、葛藤し、そしてもちろん大いに仕事もこなして来ました。そんな外国暮らしの日々は、いつの間にか筆者が大学卒業まで暮らした故国日本での年月よりも長くなってしまいました。長い外国暮らしを通して筆者はいろいろなことを学びましたが、その中で一つだけ大切なものを挙げてみろといわれたら、それは”違い”を認める思考方法と態度を、自分なりに身につけることができたことだと思っています。
国が違えば、人種が違い言葉が違い文化も習慣も何もかも違う。当たり前の話です。ある人は、人間は全ての違いがあるにもかかわらず、結局は誰も皆同じであると言います。またある人は逆に、人間は人種や言葉や文化や習慣などが違うために、お互いに本当に理解し合うことはできないと主張します。それはどちらも正しく且つどちらも間違っています。なぜなら人種や言葉や文化や習慣の違う外国の人々は、決してわれわれと同じではあり得ず、しかもお互いに分かり合うことが可能だからです。
世界中のそれぞれの国の人々は他の国の人々とは皆違う。その「違う」という事実を、素直にありのままに認め合うところから真の理解が始まります。これは当たり前のように見えて実は簡単なことではありません。なぜなら人は自分とは違う国や人間を見るとき、知らず知らずのうちに自らと比較して、自分より優れているとか、逆に劣っているなどと判断を下しがちだからです。

他者が自分よりも優れていると考えると人は卑屈になり、逆に劣っていると見ると相手に対してとたんに傲慢になります。たとえばわれわれ日本人は今でもなお、欧米人に対するときには前者の罠に陥り、近隣のアジア人などに対するときには、後者の罠に陥ってしまう傾向があることは、誰にも否定できないのではないでしょうか。
人種や国籍や文化が違うというときの”違い”を、決して優劣で捉えてはなりません。”違い”は優劣ではありません。”違い”は違う者同士が対等であることの証しであり、楽しいものであり、面白いものであり、美しいものです。
筆者は今、日本とは非常に違う国イタリアに住んでいます。イタリアを「マンジャーレ、カンターレ、アモーレ」の国と語呂合わせに呼ぶ人々がいます。三つのイタリア語は周知のように「食べ、歌い、愛する」という意味ですが、筆者なりにもう少し意訳をすると「イタリア人はスパゲティーやピザをたらふく食って、日がな一日カンツォーネにうつつを抜かし、女のケツばかりを追いかけているノーテンキな国民」ということになります。それらは、イタリアブームが起こって、この国がかなり日本に知れ渡るようになった現在でも、なおかつ日本人の頭の中のどこかに固定化しているイメージではないでしょうか。
ステレオタイプそのものに見えるそれらのイタリア人像には、たくさんの真実とそれと同じくらいに多くの虚偽が含まれていますが、実はそこには「イタリア人はこうであって欲しい」というわれわれ日本人の願望も強く込められているように思います。つまり人生を楽しく歌い、食べ、愛して終えるというおおらかな生き方は、イタリア人のイメージに名を借りたわれわれ自身の願望にほかならないのです。
そして、当のイタリア人は、実は誰よりもそういう生き方を願っている人々です。願うばかりではなく、彼らはそれを実践しようとします。実践しようと日々努力をする彼らの態度が、われわれには新鮮に映るのです。
筆者はそんな面白い国イタリアに住んでイタリア人を妻にし、肉体的にもまた心のあり方でも、明らかに日伊双方の質を持つ二人の息子を家族にしています。それはとても不思議な体験ですが、同時に家族同士のつき合いという意味では、世界中のどこの家族とも寸分違わない普通の体験でもあります。
日本に帰ると「奥さんが外国人だといろいろ大変でしょうね」と筆者は良く人に聞かれます。そこで言う大変とは「夫婦の国籍が違い、言葉も、文化も、習慣も、思考法も、何もかも違い過ぎて分かり合うのが大変でしょうね」という意味だと考えられます。しかし、それは少しも大変ではないのです。私たちはそれらの違いをお互いに認め合い、受け入れて夫婦になりました。違いを素直に認め合えばそれは大変などではなく、むしろ面白い、楽しいものにさえなります。
日本人の筆者とイタリア人の妻の間にある真の大変さは、われわれ夫婦が持っているそれぞれの人間性の違いの中にあります。ということはつまり、私たちの大変さは、日本人同士の夫婦が、同じ屋根の下で生活を共にしていく大変さと何も変わらないのです。なぜなら、日本人同士でもお互いに人間性が違うのが当たり前であり、その違う二人が生活を共にするところに「大変」が生じます。
われわれはお互いの国籍や言葉や文化や習慣や何もかもが違うことを素直に認め合う延長で、人間性の違う者同志がうまくやって行くには、無理に“違い”を矯正するよりも「違うのが当然」と割り切って、お互いを認め合うことが肝心だと考え、あえてそう行動しようとします。
それは一筋縄ではいかない、あちこちに落とし穴のある油断のならない作業です。が、私たちは挫折や失敗を繰り返しつつ“違い”を認める努力を続け、同時に日本人の筆者とイタリア人の妻との間の、違いも共通点も全て受け継いで、親の欲目で見る限り中々良い子に育ってくれた息子二人を慈しみながら、日常的に寄せる喜怒哀楽の波にもまれて平凡に生きています。
そして、その平凡な日常の中で筆者は良く独(ひと)りごちるのです。
――日本とイタリアは、この地球上にたくさんある国のなかでも、たとえて言えば一方が南極で一方が北極というくらいに違う国だが、北極と南極は文字通り両極端にある遠い大違いの場所ながら、両方とも寒いという、これまた大きな共通点もあるんだよなぁ・・・――
と。
名車という名の欠陥車たち

イタリアには名車がたくさんあります。古くはOMという車に始まり、現在はフェラーリ、ランボルギーニ、マセラッティ、アルファロメロ、ランチァなどとつづきます。これらの車はどれをとってみても、非常にカラフルで新鮮な印象を人に与えます。なんとも美しく個性的です。
ドイツにもイギリスにもアメリカにも名車はあります。しかし、人それぞれの好みというものを別にしても、筆者が知る限りではイタリアのそれほど個性的でカラフルな感じはしないように思います。
なぜそうなのかと考えてみると、どうもこれはイタリアの車が完全無欠というにはほど遠いせいであるらしいことがわかります。典型的な例はアルファロメオです。この車はスポーツカータイプの、日本で言えば高級車の部類に入る車の一つですが、イタリアではごく一般的に街を走っています。筆者もかつて乗り回したことがあります。
アルファロメオはバカバカしいくらいに足が速くて、スタートダッシュから時速100キロメートルに至るまでにわずかな時間しかかかりません。まるでレース カーのような抜群の加速性です。ボディーの形もそれらしくスマートで格好がいい。ところがこの車には、古くて新しく且つ陳腐だが人を不安にさせる、笑い 話のような悪評がいつもついてまわります。
いわく、少し雨が降るとたちまち雨もりがする。いわく、車体のそこかしこがあっという間にサビつく。いわく、走っている時間よりも修理屋に入っている時間のほうが長い・・・云々。アルファロメオの名誉のために言っておきますが、それらは大げさな陰口です。
しかし、火のないところに煙は立ちません。アルファロメオはドイツ車や日本車はもとより、イタリアの他の車種と比べても、故障が多く燃費も悪い上に排気音も カミナリみたいにすさまじい。スマートで足が速い点を除けば、車そのものが不安定のカタマリようなマシンです。つまり「欠陥車」ですね。

ところがイタリア人にとっては、アルファロメオはそれでいいのです。スマートで格好が良くてハチャメチャにスピードが出る。それがアルファロメオのアル ファロメオたるゆえんであって、燃費や排気音や故障の多い少ないなどという「些細な事柄」は、ことこの車に関するかぎり彼らにとってはどうでもいいことな のです。
そんなバカな、とおどろくにはあたリません。イタリア人というのは、何事につけ、ある一つのことが秀でていればそれを徹底して高く評価し理解しようとする傾 向があります。長所をさらに良くのばすことで、欠点は帳消しになると信じているようでもあります。だから欠点をあげつらってそれを改善しようとする動きは、いつも 二の次三の次になってしまいます。
人間に対しても彼らは車と同じように考えます。というよりも、人間に対するそういう基本的な見方がまずあって、それが車づくりや評価にも反映している、という方が正しいと思います。分かりやすい例を一つ挙げればベルルスコーニ元首相です。
醜聞まみれのデタラメなこの男をイタリア人が許し続けたのは、デタラメだが一代で巨財を築いた能力と、人当たりの良い親しみやすい性格が彼を評価する場合には何よりも大事、という視点が優先されたからです。そうしたイタリア的評価法の真骨頂は子供の教育にも如実に現れます。
この国の人々は、極端に言えば、全科目の平均点が80点の秀才よりも、一科目の成績が100点で残りの科目はゼロの子供の方が好ましい、と考えます。そして どんな子供でも必ず一つや二つは100点の部分(試験の成績という意味だけではなく)があるから、その100点の部分を120点にも150点にものばして やるのが教育の役割だと信じ、またそれを実践しているように見えます。
たとえば算数の成績がゼロで体育の得意な子がいるならば、親も兄弟も先生も知人も親戚も誰もが、その子の体育の成績をほめちぎり心から高く評価して、体育の力をもっともっと高めるように努力しなさい、と子供を鼓舞します。
日本人ならばこういう場合、体育を少しおさえて算数の成績をせめて30点くらいに引き上げなさい、と言いたくなるところだと思いますが、イタリア人はあまりそういう発想をしません。要するに良くいう“個性重視の教育”の典型なのです。
子供の得意な分野をまず認めてこれを見守る、というのは非常に人間的であたたかく、しかも楽観的な態度です。同時に厳しい態度でもあります。なぜなら一人一 人の子供は、平均点をのばして偏差値を気にするだけの画一的な勉強をしなくても良い代りに、長所と認められた部分を徹底して伸ばす努力をしなければならな いからです。
長所とは言うまでもなく個性のことです。そして個性とは、ただ黙ってぼんやりと生きていては輝かない代物なのです。
かくしてアルファロメオは、社会通念になっているイタリア国民一人一人の前述の物の見方に支えられて、第一号車ができて以来ずっと、速さとカッコ良さだけ にせっせと磨きをかけてきました。一日や二日で達成したものではないからその部分では他のどんな車種にも負けません。
同時に雨もりや故障という欠陥部分の強い印象も健在です。突出しているが抜けている。だから憎めない。それがアルファロメオであり、名車の名車たるゆえんです。なんともイタリア的というべきか。はたまた人間的と言うべきか・・陳腐な結論かもしれませんがそれ以上の言葉はみつかりません。
日伊さかな料理談義

「世界には3大料理がある。フランス料理、中華料理、そしてイタリア料理である。その3大料理の中で一番おいしいのは日本料理だ」
これは筆者がイタリアの友人たちを相手に良く口にするジョークです。半分は本気でもあるそのジョークのあとには、筆者はかならず少し大げさな次の一言もつけ加えます。
「日本人は魚のことを良く知っているが肉のことはほとんど知らない。逆にイタリア人は肉を誰よりも良く知っているが、魚については日本料理における肉料理程度にしか知らない。つまりゼロだ」
3大料理のジョークには笑っていた友人たちも、イタリア人は魚を知らない、と筆者が断言したとたんに口角沫を飛ばして反論を始めます。でも筆者は引き下がりません。
スパゲティなどのパスタ料理にからめた魚介類のおいしさは間違いなくイタメシが世界一であり、その種類は肉料理の豊富さにも匹敵します。

しかしそれを別にすれば、イタリア料理における魚は肉に比べるとはるかに貧しい。料理法が単純なのです。
この国の魚料理の基本は、大ざっぱに言って、フライかオーブン焼きかボイルと相場が決まっています。海際の地方に行くと目先を変えた魚料理に出会うこともあります。それでも基本的な作り方は前述の三つの域を出ませんから、やはりどうしても単調な味になります。
一度食べる分にはそれで構いません。素材は日本と同じように新鮮ですから味はとても豊かです。しかし二度三度とつづけて食べると飽きがきます。何しろもっとも活きのいい高級魚はボイルにする、というのがイタリア人の一般的な考え方です。
家庭料理、特に上流階級の伝統的な家庭レシピなどの場合はそうです。ボイルと言えば聞こえはいいが、要するに熱湯でゆでるだけの話です。刺身や煮物やたたきや天ぷらや汁物などにする発想がほとんどないのです。
最近は日本食の影響で、刺身やそれに近いマリネなどの鮮魚料理、またそれらにクリームやヨーグルトやマヨネーズなどを絡ませた珍奇な“造り”系料理も増えてはいます。だがそれらはいわば発展途上のレシピであって、名実ともにイタメシになっているとは言い難い。

筆者は友人らと日伊双方の料理の素材や、調理法や、盛り付けや、味覚などにはじまる様々な要素をよく議論します。そのとき、魚に関してはたいてい筆者に言い負かされる友人らがくやしまぎれに悪態をつきます。
「そうは言っても日本料理における最高の魚料理はサシミというじゃないか。あれは生魚だ。生の魚肉を食べるのは魚を知らないからだ。」
それには筆者はこう反論します。
「日本料理に生魚は存在しない。イタリアのことは知らないが、日本では生魚を食べるのは猫と相場が決まっている。人間が食べるのはサシミだけだ。サシミは漢字で書くと刺身と表記する(筆者はここで実際に漢字を紙に書いて友人らに見せます)。刺身とは刺刀(さしがたな)で身を刺し通したものという意味だ。つまり“包丁(刺刀)で調理された魚”が刺身なのだ。ただの生魚とはわけが違う」
と煙(けむ)に巻いておいて、筆者はさらに言います。
「イタリア人が魚を知らないというのは調理法が単純で刺身やたたきを知らないというだけじゃないね。イタリア料理では魚の頭や皮を全て捨ててしまう。もったいないというよりも僕はあきれて悲しくなる。魚は頭と皮が一番おいしいんだ。特に煮付けなどにすれば最高だ。
たしかに魚の頭は食べづらいし、それを食べるときの人の姿もあまり美しいとは言えない。なにしろ脳ミソとか目玉をずるずるとすすって食べるからね。要するに君らが牛や豚の脳ミソを美味しいおいしい、といって食べまくるのと同じさ。

あ、それからイタリア人は ― というか、西洋人は皆そうだが ― 魚も貝もイカもエビもタコも何もかもひっくるめて、よく“魚”という言い方をするだろう? これも僕に言わせると魚介類との付き合いが浅いことからくる乱暴な言葉だ。魚と貝はまるで違うものだ。イカやエビやタコもそうだ。なんでもかんでもひっくるめて“魚”と言ってしまうようじゃ料理法にもおのずと限界が出てくるというものさ」
筆者は最後にたたみかけます。
「イタリアには釣り人口が少ない。せいぜい百万人から多く見つもっても2百万人と言われる。日本には逆に少なく見つもっても2千万人の釣り愛好家がいるとされる。この事実も両国民の魚への理解度を知る一つの指標になる。
なぜかというと、釣り愛好家というのは魚料理のグルメである場合が多い。彼らは「スポーツや趣味として釣りを楽しんでいます」という顔をしているが、実は釣った魚を食べたい一心で海や川に繰り出すのだ。釣った魚を自分でさばき、自分の好きなように料理をして食う。この行為によって彼らは魚に対する理解度を深め、理解度が深まるにつれて舌が肥えていく。つまり究極の魚料理のグルメになって行くんだ。
ところが話はそれだけでは済まない。一人ひとりがグルメである釣り師のまわりには、少なくとも 10人の「連れグルメ」の輪ができると考えられる。釣り人の家族はもちろん、友人知人や時には隣近所の人たちが、釣ってきた魚のおすそ分けにあずかって、釣り師と同じグルメになるという寸法さ。
これを単純に計算すると、それだけで日本には2億人の魚料理のグルメがいることになる。これは日本の人口より多い数字だよ。ところがイタリアはたったの1千万から2千万人。人口の1/6から1/3だ。これだけを見ても、魚や魚料理に対する日本人とイタリア人の理解度には、おのずと大差が出てくるというものだ」
友人たちは筆者のはったり交じりの論法にあきれて、皆一様に黙っています。釣りどころか、魚を食べるのも週に一度あるかないかという生活がほとんどである彼らにとっては、「魚料理は日本食が世界一」と思い込んでいる“釣りキチ”の筆者の主張は、かなり不可解なものに映るようです。
北斎・広重に見る近代的自我あるいはその欠如

先ごろ、イタリア・ミラノで大きな北斎展が開かれました。その催し物は世界最古の大学がある学生の街、ボローニャにも移動して開催されました。
ミラノでは1999年に大規模な北斎展が行われて以来、かなり頻繁に江戸浮世絵版画展が開かれます。浮世絵への理解と関心が高いミラノの感興はイタリア全土へと広がっています。
展覧会では葛飾北斎のほかに歌川(安藤)広重と喜多川歌麿の作品も展示されました。合計の展示数は200余り。
3巨匠の作品がそれだけの規模で一堂に会する展覧会を見るのは、筆者にとってはミラノでの体験が初めてでした。
展示作品は全て素晴らしいものでしたが、筆者はそこでは特に、北斎の風景画3シリーズ「富嶽三十六景」「諸国滝廻り」「諸国名橋奇覧」と、広重の「東海道五十三次」が並ぶように展示されているのを楽しみました。
北斎と広重をほぼ同時並行に鑑賞しながらあらためて感じたことがあります。それは広重をはるかに凌駕する北斎の力量です。北斎はドライで造形的、広重は叙情的で湿っぽい、とよく言われますが、北斎は精密とダイナミズムで広重に勝り、人物造形でも広重より現代的だと感じました。
作品群の圧倒的な美しさに酔いしれながら、人の顔の描写にも強く気を引かれました。北斎は遠くに見える小さな人物の顔の造作も丁寧に描いていますが、広重はほとんどそこには興味を抱いていません。そのために描き方も雑で、まるで子供が描く「へのへのもへじ」と同じレベルにさえ見えます。\

多くの絵で確認できますが、特に人物が多数描かれているケースでそれは顕著です。例えば「嶋田・大井川」の川越人足の顔は、ほとんど全員が同じ造作で描かれています。子供の落書きじみた文字遊戯の顔のほうが、まだ個性的に見えるほどの、淡白な描き方なのです。
東海道五十三次は全て遠景、つまり”ヒキあるいはロング”の絵です。大写し又はクローズアップの絵は一枚もありません。そこでは人物は常に景観の一部として描かれます。これは当たり前のようですが、実は少しも当たり前ではありません。そこには日本的精神風土の真髄が塗り込まれています。
つまり、人間は大いなる自然の一部に過ぎない、という日本人にとってはごく当たり前のコンセプトが、当たり前に提示されているのです。そこでは、個性や自我というものは、自然の中に溶け込んで形がなくなる。あるいは形がなくなると考えられるほどに自然と一体になります。

その流れで個性や自我の発現機能であるヒトの表情は無意味になり、その結果が広重の人物の表情の「どうでもよい」感満載の表現だと思います。のっぺらぼうより少しましなだけの、「へのへのもへじ」程度の顔の造作を「とりあえず」描き付けたのが、広重の遠景の人物の表情なのです。
それらの顔の造作は「東海道五十三次画」全体の精密と緊張、考究され尽くされた構図、躍動感を捉えて描き付けた動きやタッチ、等々に比べると呆気ないほどに粗略で拙いものです。作品の隅々にまで用いられた精緻な技法は、人物の表情には適応されていないのです。
厳密な意味では北斎の表情の描き方も広重と大差はありません。が、北斎は恐らく画家としての高い力量からくる自恃と精密へのこだわりから、これを無視しないで表情を描き加えています。だがそれとて自我の反映としての表情、つまり感情の露出した顔としてではなく、単なる描画テクニック上の必要性から描き加えたもの、というふうに筆者には見えます。
従って、広重よりはましとはいうものの、北斎もやはり人物の顔の描写をそれほど重視してはいません。たとえば彼の漫画などの人物の表情の豊かさに比べると、たとえ遠景の人物の表情とはいえ、どう見ても驚くほどにシンプルです。表情の描写には、彼の作者としての熱意や思い入れ、といった精神性がほとんど見られないのです。筆者はそこに近代精神の要である“自我”の欠落のようなものを発見して、一人でちょっと面白がりました。
“私”という個人の自我意識によって世界を見、判断して、人生を切り開いていく、という現代人の我々にとって当然過ぎるほど当然の価値観は、西洋近代哲学の巨人デカルトが“我思う、故に我あり”というシンプルな命題に託して、それまでの支配観念であった「スコラ哲学」の縛りを破壊した“近代的自我”の確立によって初めて可能になりました。

スコラ哲学支配下の西洋社会では、「個人」と「個人の所属する集団と宗教」は『不可分のもの』であり、そこから独立した個人の存在はあり得ませんでした。デカルトが発見した“近代的自我”がそのくび木を外し、コペルニクス的転回ともいえる価値観の変化をもたらしたのです。自我の確立によって、西洋は中世的価値観から抜け出し、近代に足を踏み入れたのでした。
日本は明治維新以降の西洋文明習得に伴って、遅ればせながら「自我の意識」も学習し、封建社会の精神風土とムラ社会メンタリティーに執拗に悩まされながらも、どうにか西洋と同じ近代化の道を進んできました。欧米を手本にして進み始めて以降の精神世界の変化は、政治・経済はもとより国民の生活スタイルや行動様式など、あらゆる局面で日本と日本人を強く規定しています。
しかし、西洋が自らの身を削り、苦悶し、過去の亡霊や因習と戦い続けてようやく獲得した“近代的自我”と、それを易々と模倣した日本的自我の間には越えられない壁があります。模倣は所詮模倣に過ぎないのです。それは自我と密接に結びついている、「個人主義」という語にまつわる次の一点を考察するだけでも十分に証明ができるように思います。
「個人主義」という言葉は日本では利己主義とほぼ同じ意味であり、それをポジティブな文脈の中で使う場合には、たとえば『いい意味での個人主義』のように枕詞を添えて説明しなければなりません。その事実ひとつを見ても、日本的自我はデカルトの発見した西洋近代の自我とそっくり同じものではないことが分かります。デカルトの自我が確立した世界では、「個人主義」は徹頭徹尾ポジティブな概念です。「いい意味での~」などと枕詞を付ける必要はないのです。

自我の確立を遅らせている、あるいは自我を別物に作り変えている日本的な大きな要素の一つが、多様性の欠落です。「単一民族」という極く最近認識された歴史の虚妄に支配されている日本的メンタリティーの中では、他者と違う考えや行動様式を取ることは、21世紀の現在でさえ依然として難しく、人々は右へ倣えの行動様式を取ることが多くなります。
それは集団での活動をし易くし、集団での活動がし易い故に人々は常にそうした動きを好み、結果、画一的な社会がより先鋭化してさらなる画一化が進みます。そこでは「赤信号も皆で渡れば怖くなく」なり「ヘイトスピーチや行動もつるんで拡大」しやすくなります。その上に多様性が欠落している分それらの流れに待ったをかける力が弱く、社会の排外志向と不寛容性がさらに拡大するという悪循環になります。
多様性の欠落は「集団の力」を醸成しますが、力を得たその集団の暴走も誘発し、且つ、前述したように、まさに多様性の貧困故にそれを抑える反対勢力が発生し難く、暴走が暴走を呼ぶ事態に陥って一気に破滅にまで進みます。その典型例が太平洋戦争に突き進んだ日本の過去の姿です。
江戸時代の北斎や広重にはもちろん近代的な自我の確立はありませんでした。しかし、彼らは優れた芸術家でした。芸術家としての誇りや矜持や哲学や思想があったはずです。つまり芸術家の「独創を生み出す個性」です。それは近代的自我に酷似した個人の自由意識であり、冒険心であり、独立心であり、批判精神です。
しかし、社会通念から乖離した個性、あるいは“近代的自我”に似た自由な精神を謳歌していた彼らでさえ、自らの作品の人物に「個性」を付与する顔の造作には無頓着でした。筆者は日本を代表する2人の芸術家が提示した美の中に、“近代的自我”を夢見たことさえないかつての日本の天真爛漫の片鱗を垣間見て、くり返しため息をついたり面白がったりしたのでした。
十字架に祈る盆の清廉

10月末から11月初めにかけてのイタリアの祝祭の日々が、2021年のコロナ禍中でもめぐってきました。
10月31日はハロウィン。ケルト族発祥のその祭りを最近、遅ればせながらイタリアでも祝う人が多くなりました。
翌11月1日はカトリック教会の祝日の一つ「諸聖人の日」。日本では万聖節(ばんせいせつ)」とも呼ばれるイタリアの旗日です。
続く11月2日は「万霊節」 。一般に「死者の日」と呼ばれます。
「死者の日」..日本語ではちょっとひっかかる響きの言葉ですが、その意味は「亡くなった人をしのび霊魂を慰める日」ということです。日本の盆や彼岸に当たります。

カトリックの教えでは、人間は死後、煉獄の火で責められて罪を浄化され、天国に昇ります。その際に親類縁者が教会のミサなどで祈りを捧げれば、煉獄の責め苦の期間が短くなる、とされます。
それは仏教のいわゆる中陰で、死者が良い世界に転生できるように生者が真摯な祈りを捧げる行事、つまり法要によく似ています。
万霊節には死者の魂が地上に戻り、家を訪ねるという考えもあります。イタリアでは帰ってくる死者のために夜通し明かりを灯し薪を焚く風習さえあります。
また死者のためにテーブルを1人分空けて、そこに無人の椅子を置く家庭もあります。食事も準備します。むろん死者と生者が共に食べるのが目的です。
イタリア各地にはこの日のために作るスイーツもあります。甘い菓子には「死の苦味」を消す、という人々の思いが込められています。
それらの習慣から見ても、カトリック教徒の各家庭の表現法と人々の心の中にある「死者の日」は、日本の盆によく似ていると感じます。
10月31日から11月2日までの3日間、という時間も偶然ながら盆に似ています。盆は元々は20日以上に渡って続くものですが、周知のように昨今は迎え火から送り火までの3日間が一般的です。
3つの祭礼のうちハロウィンは、キリスト教本来の祭りではないため教会はこれを認知しません。しかし、一部のキリスト教徒の心の中では、彼らの信教と不可分の行事になっていると考えられます。

人々は各家庭で死者をもてなすばかりではなく、教会に集まって厳かに祈り、墓地に足を運んでそれぞれの大切な亡き人をしのびます。
ところで11月1日の「諸聖人の日」は、カトリックでは文字通り全ての聖人を称え祈る日ですが、プロテスタントでは聖人ではなく「亡くなった全ての信徒」を称えて祈る日のことです。
プロテスタントでは周知のように聖人や聖母や聖女を認めず、「聖なるものは神のみ」と考えます。聖母マリアでさえプロテスタントは懐疑的に見ます。処女懐胎を信じないからです。
聖人を認めないプロテスタントはまた、聖人のいる教会を通して神に祈ることをせず、神と直接に対話をします。権威主義的ではないのがプロテスタント、と筆者には感じられます。
一方カトリックは教会を通して、つまり神父や聖人などの聖職者を介して神と対話をします。そこに教会や聖人や聖職者全般の権威が生まれます。
カトリック教会はこの権威を守るために古来、さまざまな工作や策謀や知恵をめぐらしました。それは宗教改革を呼びプロテスタントが誕生し、両者の対立も顕在化していきました。
ところが「死者の日」には、既述のようにカトリックの信者は教会で祈るばかりではなく、墓地にも詣でます。
あらゆる宗教儀式が教会と聖職者を介して行われるのがカトリック教ですが、この日ばかりは人々は墓地に出向いて直接に霊魂と向かい合うのです。
カトリックは慈悲深い宗教です。懐も深く、寛容と博愛主義にも富んでいます。プロテスタントもそうです。
キリスト教徒ではない筆者は、両教義を等しく尊崇しつつも、11月1日の「諸聖人の日」には、聖人よりも一般信徒を第一義に考えるプロテスタントにより共感を覚えます。
また、教会の権威によるのではなく、自らの意思と責任で神と直接に対話をする、という教義にも魅力を感じます。
それでは筆者は反カトリックの男なのかといいますと、断じてそうではありません。
筆者は全員がカトリック信者である家族と共に生き、カトリックとプロテスタントがそろって崇めるイエス・キリストを敬慕する、自称「仏教系無心論者」です。
「仏教系無心論者」である筆者は、教会で祈る時などにはキリスト教徒のように胸で十字を切ることはしません。胸中で日本風に合掌します。実際に手を合わせる時もあります。

例えば筆者は2018年、亡くなった義母を偲んで万霊節に墓参りをした際は、十字架に守られた墓標の前に花を供え、カトリック教徒の妻が胸の前で十字を切って祈りを捧げる脇で、日本風に合掌しました。
そのことにはなんの違和感もありませんでした。義母はカトリック教徒ですが、墓参のあいだ筆者はずっと「義母の新盆」ということを意識していました。
死して墓場の一角に埋葬された義母は、十字架に守られつつ筆者を介して、仏教思念に触れ盆の徳にも抱かれている、と素直に思いました。
何らの引っかかりもなく筆者がそう感じるのは、恐らく筆者が前述のように自称「仏教系の無心論者」だからです。
筆者は宗教のあらゆる儀式やしきたりや法則には興味がありません。心だけを重要と考えます。
心には仏教もキリスト教もイスラム教もアニミズムも神道も何もありません。すなわち心は汎なるものであり、各宗教がそれぞれの施設と教義と準則で縛ることのできないものです。
死者となった義母を思う筆者の心も汎なるものです。カトリックも仏教も等しく彼女を抱擁する、と筆者は信じます。その信じる心はイエス・キリストにも仏陀にも必ず受け入れられる、と思うのです。
カトリックの宗徒は、あるいは義母が盆の徳で洗われることを認めないかもしれません。いや恐らく認めないでしょう。
仏教系無心論者の筆者は、何の問題もなく義母が仏教に抱かれ、イエス・キリストに赦され、イスラム教に受容され、神道にも愛される、と考えます。
それを「精神の欠けた無節操な不信心者の考え」と捉える者は、自身の信教だけが正義だというドグマに縛られている、例えば窮屈な 一神教の信者、というふうに見えなくもありません。
‘建物語り‘は‘人物語り’~ミラノ中央駅とムッソリーニ~

イタリアにある膨大な数の歴史的建築物の中で、最も新しいものの一つがミラノの中央駅舎です。
1931年にオープンしたミラノ中央駅は、イタリアの国鉄駅の中ではずば抜けて威厳のある外観を持つ建物。
世界で一番美しい駅舎と呼ぶ建築評論家もいます。
駅舎は1925年に工事が始まって6年後に完成しました。
イタリアの国家的大プロジェクトは、何百年も工事が続いたものも少なくありません。たとえば同じミラノの大聖堂ドゥオーモは、およそ500年もかかって完成しました。
竣工まで長い時間がかかった歴史的建造物はほかにもたくさんあります。その伝統は今も残っていてイタリアの建築工事の進捗は遅い。
大事業だったミラノ中央駅の駅舎がわずか6年で完成したのは、横暴で険しいファシズム政権が工事関係者の尻をたたき続けたからです。
駅舎を規定する正式な建築様式名はありません。

リバティやアールデコの混合様式とされますが、「リットリア様式」とも呼ばれます。リットリアとはムッソリーニが権力を握っていた時代の建築群の総称。つまりファシスト様式。
古代ローマ帝国に倣って質実剛健を目指したと言われています。
筆者が知る限り、ミラノを訪れる多くの日本人は駅の堂々としたたたずまいに感動します。筆者も嫌いではありません。
ところが、実は、この駅の建物を多くのイタリア人は毛嫌いします。
理由はただひと言、「威張っている」です。
要するに洗練されていない、ということです。
筆者はイタリア人のそのセンスや見識に感嘆します。
例えばベニスの中心、大運河沿いに立ち並ぶ建築群は、その一つひとつが洗練を極めた美しいものばかりです。
それに比較するとミラノ駅舎のシンプルな力強さは、硬い印象があり繊細とは言えないかもしれません。
ベニスでは当時の貴族や大商人が、東方貿易で得た莫大な富を惜しみなく注ぎ込んで、優美な建築物を作りました。
大運河沿いに家を持つのは名誉なことだと考えられましたから、彼らは競ってより美しいものを創ろうとしました。
そのために建築群はさらに洗練を極めることになりました。彼らには「そういう家」が必要だったのです。
一方独裁者のムッソリーニは、自らの威厳を示すために大上段に構えた威圧的な印象を持つ建物を創る必要がありました。

要するに彼もまた彼なりの必要に迫られたのです。
歴史的建造物は、それが巨大だったり威厳があったり古色蒼然としているからすごいのではありません。「誰かがその建物を必要とした」という点がもっとさらにすごいのです。
「建物とは人」のことにほかなりません。
ムッソリーニの時代には、彼と追随するファシストらが必要としたためにファシズムを象徴するリットリア様式の建築物が多く造られ、中でも目立つものがミラノ中央駅舎です。
目の肥えたイタリア人は、駅舎の威風にムッソリーニの野心やごう慢や民主主義への冒涜などを嗅ぎ取って、まゆをひそめます。
それは洗練を極めた建物群で街を埋め尽くして、ついには全体が芸術作品と言っても過言ではないベニスのような都市を造ってきた、イタリア人ならではの厳しい批評だと筆者には見えます。
建築が彼らに受け入れられるためには、ムッソリーニの負の記憶がなくなって、駅舎が建物自体の生命を宿し始める、恐らく何世紀もの時間が必要に違いありません。
長い時を経ても駅舎がなおそこに立っているなら、それはつまり人々が、「存続させるに値する建物」と見なしたからです。

誰かが必要としたために生まれた建物は、その後の人々の要求に支えられて生き続けます。
建物は時代の要望やニーズによってさらに長生きをし、短い命しか与えられていない我々人間から見れば、ほとんど永遠にも見える年月をさえ生き抜きます。
駅舎が将来そんな運命をたどったまさにその時にこそ、人々は建物を美しいと感じることでしょう。
美の正体は、先に触れたところの、長い時間を生き延びた建築物に宿る独自の生命です。
つまり建物を必要とした古人の意図と、時間と、建物そのものが分かちがたく融合した強い生気。
人々は溢れ出る生気の豊かさに心を撃たれて、恍惚としてそこに立ち尽くすことになるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
