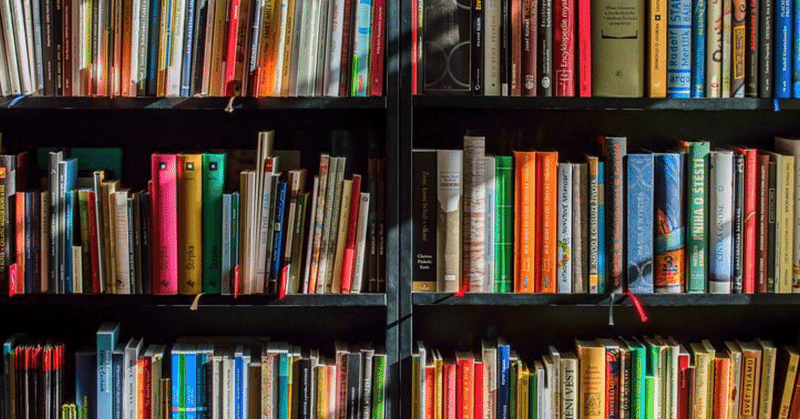
20221022 よくわかる双極性障害(書籍・備忘録)
よくわかる双極性障害(躁うつ病)
著者:貝谷久宣
ページ数:128ページ
発売日: 2013/03/15
出版社:主婦の友社
先日図書館で借りた本。
じっくり読めないまま返却期限となって
しまったため、また後日借り直したい。
出版されてから10年近く経っていたが
それ程古い内容とは感じなかった。
イラストが多く、文字が大きいため
読みやすかった。
病気や薬の説明も詳しく書いてあったが
今まで読んだ関連の本にはあまり見られ
なかった「心理社会的治療」というもの
についても詳しく触れていた。
〜以下はメモ〜
躁状態は7つの基準で判断する
①自尊心の誇大
②睡眠欲求の現象
③多弁
④観念奔逸
⑤注意散漫
⑥活動の増加
⑦痛ましい結果
(快楽行動に没頭など)
〔双極性障害II型の場合〕
症状のある期間は54%
症状の出ている期間のうち
うつ状態 93%
混合状態 4%
躁状態 2%
ほとんど鬱
心理教育について(精神療法)
・病気についての知識を得る
・再発のサインを把握する
・服薬の大切さを知る
・症状への対処法を学ぶ
・ストレスへの対処法を学ぶ
対人関係療法
社会リズム療法
家族療法
日常生活についての注意点
体内時計のリズムを整える
・就寝、起床は決まった時間に
・食事は規則正しく
・昼間はできるだけ外出する機会をつくる
・毎日、できるだけ人とふれ合う
・生活の記録をつける
運動には薬と同じくらいの効果があると
言われている。
適しているのは有酸素運動。
(まずは掃除などから少しずつ
動くことを始めてみる)
非定形抗精神薬には体重増加の副作用あり
(オランザピンやクエチアピン)
マインドフルネス瞑想
(朝晩10分ずつが良い)
・瞑想中に湧き上がる思いに対して
「良い・悪い」の評価をしない
・湧き上がる思いから「逃げようとしない」
・感じた感覚は「心を開いて受け止める」
・不安な気持ちは
「自分そのものだと思わずに自分を信じる」
・不安な気持ちに対して
「どうにかしようと考えない」
・不安な気持ちでも
「あるがままに受け止める」
・自分の気持ちや習慣に
「とらわれない、固執しない」
【目次】
第1章 双極性障害とはどんな病気なのか
第2章 双極性障害の「躁」と「うつ」の
症状を理解する
第3章 なぜ、双極性障害になるのでしょうか
第4章 双極性障害の治療は、薬物療法と
心理社会的に治療が柱です
第5章 日常生活のメンタルケアと
家族の接し方
第6章 体験集・回復への道
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
