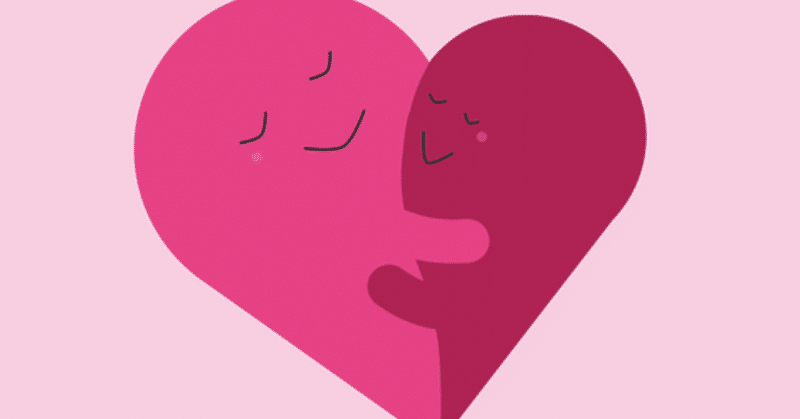
20221109 障害受容とは
今日の調子(10段階評価)
身体→7
心→5
昨晩珍しく寝付けなくて寝不足のまま
朝を迎えた。
日中も眠気が来なくて少し不気味だ。
かと言ってやる気がみなぎっていたり
イライラはしていないから、躁みたいな
感じとは違うのかも。
今朝、鬱とはまた違う感情で
落ち込んで少し泣いた。
ひとことで言うと
今まで自分がやってきたことは
一体、何だったのか。
そんな気持ちが溢れてしまったからだ。
自分が双極性障害だということ。
過去を振り返るとそういう気配はきっと
ずっとあり、やり過ごせている間は良かった。
けれど仕事を通じて、それができなくなって
始まりは双極性ではなく鬱を発症した。
一旦は良くなっても度々そこに
引き戻されてしまい、3回程休職をした。
途中からは、そうなってしまうことに
自分の気質がとても関係していると知った。
原因かと思われていた、仕事を退職しても
治らなかったからである。
薬や通院だけでは寛解は難しい。
そう思ってカウンセリングやセラピー
心理学の勉強をして自分と頑張って
向き合ってきたつもりだった。
鬱以前に、ずっと感じていた
生きづらさの正体も知りたかった。
そうやって勉強していくうちに
ひとつの原因とも思われる
幼少期の母親との関係が大きく影響
していることが理解できた。
そして最近では、現在の母親に対して
やっと楽な気持ちを持てるところまで
来ていた。
鬱を患ってから15年くらいだろうか
ずっと何とか普通の生活を送りたい
気持ちで頑張っていた。
ずっと寛解状態であったし、順調に快復を
感じていたはずなのに、再び鬱状態になり
2か月ほど前に10年ぶりに病院を受診した。
そして、医師に双極性障害を告げられた。
治ることはないので
薬は一生服薬が必要です。
受診直後は、やっぱりかと思いながらも
病院に何とか行けて良かった
これで鬱状態から少しは解放されるはず。
という気持ちの方が強かった。
でも、時間が経ってきて何故か
病気を受け入れられない
という、自分が出てきてしまった。
それは冒頭に書いた
今まで自分がやってきたことは
一体、何だったのか。
という気持ちがあったからだ。
じゃあ、そんなに頑張って回り道せずに
病気であることを速やかに受け入れて
生きて行けていれば、良かったのでは。
そう思ってしまうと、それが出来なかった
自分は馬鹿ではないか、とさえ思ってしまう。
誰と競っていたわけでも無いのに
勝手に病気に負けたと思うのだ。
そして全てを病気のせいにしたくなって
しまう。
白黒思考に陥る。
それでも、得た知識は無駄では無いし
だからこそ軽めな症状で済んでいる
という見方もできる。
普通の暮らしがしたかった。
みんなと同じじゃない。
自分は病気だから普通の人たちが
できることが出来ない。
そんな気持ちばかりがグルグルまわる。
私にとっての普通それは
仕事にちゃんと行けることそれが大きかった。
このままではそれが出来ないし。
そして、これからも普通の人たちと
同じような頑張りは鬱や躁を招くことを
意識して行動しなければならないという
制限がかかるわけで。
いや、それを言うなら今までだって
病院に行ってなかっただけ。
状態は変わってないだけなんだけど
やはりはっきり認めると認めないとじゃ
違うのだ。
今はまだ受け入れ切れないだけなんだ
とは思っている。
頭がずっと混乱しているような気がする。
でも、少しずつ前に進んでいるような
そんな気はしている。
カメの歩みだけれど。
障害...とまで言ってしまうことが私の程度では
申し訳ないような気持ちがある。
けれど、受容することについて少し調べて
みた。
そうしたところ、こちらのページが出てきた。
障害受容を考えるうえで需要は大きく5つに分かれた段階的な過程で進むという理論が一般的に言われています。
1.ショック期
2.否認期
3.混乱期
4.適応への努力期
5.適応期
障害を受容(受け入れる)までには
5つのステップがあるとのこと。
これは1から5まで順々に進むわけではなく
何度か戻りつつ、最後には5に辿り着ける。
(全ての障害者に当てはまるわけではない)
今の自分は
3.混乱期にいると思われる。
そんな中でも情報収集してはいるから
4.適応への努力期も少しは出来つつある。
最終的に5.適応期を迎えられるように
自分のペースで歩んで行きたいと思う。
こうやって指針のようなものがあるのは
ありがたい。
きっと私だけじゃなく、いろいろな方々が
同じ悩みを持って乗り越えているのだなと
励みになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
