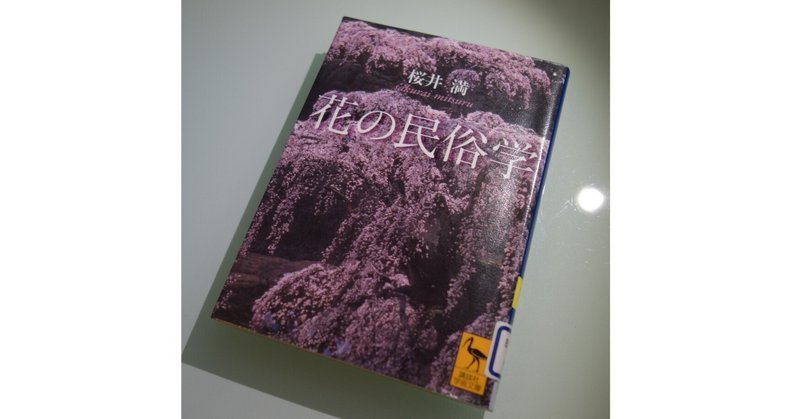
難易度高めな読書にのんびり取組中
日付が変わってしまったが、今日は、仕事が入らないのを良いことに、のんびりと過ごした。昼寝もたくさんした。あまり進まないが読書もした。
給食が始まっておらず、早い下校をしてきた子どもに、抜歯による頬の腫れが少し減ったことを指摘された。鏡を見て、確かに頬骨辺りからの腫れが、少し下から腫れていることに気づいた。
ただ、痛みはそこそこあるので、朝から痛み止めを飲んでいる。ロキソプロフェン3錠は、1日の上限だろう。
先日、図書館で何となく借りてきた、民俗学の文庫本を読んでいる。桜井満・著「花の民俗学」。
新しめの本を選んだつもりだったが、かなり古い本だった。大本になっているのは、1974年初版と目次の後に書かれていた。講談社学術文庫の初版が2008年というだけで、なかなかの古さ。
古いと悪いという話ではないのだが、言葉の面で難易度が高い。一種の古典だと思いながら読んでいる。
実際に、著者は万葉学者とのことで、古典や和歌の引用も多いのだが、それにはふりがながあったり、解説があったりする。どことなく説明不足に感じてしまうところはあるが、過去の読書から知っている話もあるので、大きくは困らない。
ただ、通常の文章の中も読みにくい。
2ページくらいで一区切りする文章を読んでは、さっきのは何だったんだ、と一つ検索して調べるような状況。
「被衣」も調べた。「かつぎ」と読むのだったか、とは思ったがイメージが湧かない。変換候補にも出てこなかった。
図書館で、真っ先に行こうとしたのは新着図書コーナーだったので、古い本を読む気分ではなかったのだが、のんびり読んでいる。亡き祖父母の時代の感覚を知る感じを楽しんでいる。
この本のテーマは「日本人にとっての花とは」。植物学ではないが、花と人との歴史のようだ。華道以前の話が書かれている。
まだ大して読み進められていないが、花といっても、桜だけでもない。
日常に飾る花というよりは、お祭りなど、特別な日のことが取り上げられているように思うが、花へのアプローチもいろいろ。飽きずに読んでいる。
花は人のこころを豊かにするが、豊かな人のこころによって花は豊かになるのである。
蔵書にしている夢枕獏・著の陰陽師シリーズにも、そんな話は出てきたが、改めて、そういうものだよな、と思った。
その陰陽師の本では、桜を美しいと思う人(博雅)がいるから、桜は美しい。誰も思う人がいない場所の桜は?というような場面があった。
上の引用に続く文。
信仰心と芸術意識との間には大きな溝があるように考えられているが、決してそうではなく、文学・芸能・絵画・音楽等々伝統的なすべての芸術は、呪術宗教的な場から生れたものであった。華道もまた例外ではないのである。これが日本の芸道の一つとして成立し定着したところに、日本的なこころを見出すべきであろう。
話題にされている時代は古いが、書かれた頃からも、かなりの年数が経っている。感染症の影響で、お祭り自体も減っている。なので、今の日本人感覚と同じとは思われない。が、今がそうである理由が、引用箇所からだけではなく、いろいろと感じられて興味深い。
重陽(菊の節供)の話に、「お供日」という言葉が出てきた。
かなり前の、子どもへのいただき物に、ドラえもんすごろくがあり、今でも遊ぶ。日本地図の中に、土地に因んだマスがあり、九州に「おくんち」というマスがある。きっとそれは繋がりのある言葉だと思った。
お祭りと、お供えをする日は、少なくともセットだろう。
重陽ということは9月9日なのだから、9日を「くんち」と発音するようにも思ったが。
最後まで読み切れるかは不明だが、面白い学問だった頃の、民俗学の流れを汲んだ本なのだろうと思いながら読んでいる。
奥付の次ページに、『「講談社学術文庫」の刊行に当たって』という文章があった。刊行の挨拶のページを読み、面白いと思ったことはなかったが、何だか面白いと思った。
これは、学術をポケットに入れることをモットーとして生まれた文庫である。学術は少年の心を養い、成年の心を満たす。その学術がポケットにはいる形で、万人のものになることは、生涯教育をうたう現代の理想である。
続く文章も抜粋する。
「学術は、まず魔術への挑戦から始まった。」
「学術の権威は、幾百年、幾千年にわたる、苦しい戦いの成果である。」
「その生成のあとをかえりみれば、その根は常に人々の生活の中にあった。学術が大きな力たりうるのはそのためであって、生活をはなれた学術は、どこにもない。」
「生活と学術との間に、もし距離があるとすれば、何をおいてもこれを埋めねばならない。」
古典のような文章を読んでから読んだせいか、やや古さのある文体にも違和感なく読んでしまった。
読み終えてみると、書かれた時期が古く、1976年だった。
そんな頃から生涯教育がうたわれていたのかと思った。
学術の権威が、今でも城のようなイメージなのかは知らないが、今の時代でも違和感のない内容が書かれていることに驚いた。
