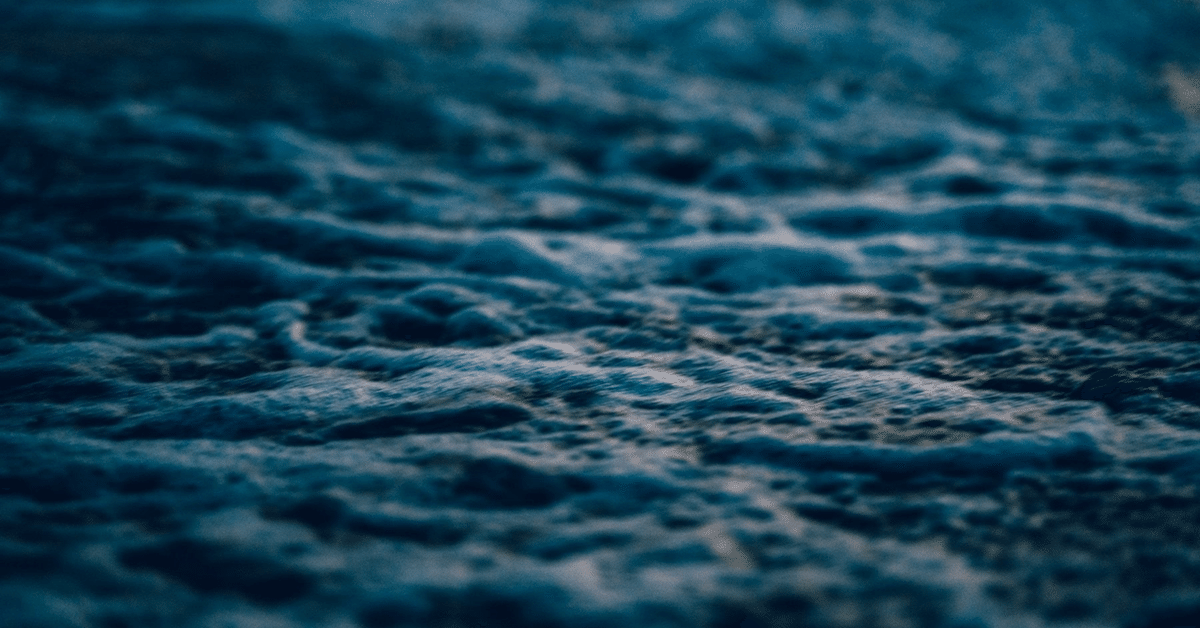
唾棄すべき世界【再掲】
やっぱりやめないか、と僕は小さい声で言った。彼女は震える手でミルクティーを飲み、睡眠薬を流し込んでいた。潮風が強く吹き、荒々しい波の音が断続的に聞こえた。
「急にどうして?」
「やっぱり死ぬのは怖いし、もう少し生きてもいい気がしてさ」
「あなたも嫌気がさしてたじゃない」
「うん、さしてた、今だってそうだ。でも君ともう少し一緒にいたくなった」
「私も同じだよ。だから一緒に死にたい」
彼女はポケットのホッカイロを僕の手に握らせる。
「でも別に無理強いはしない。あなたの人生はあなたが選ぶべきよ。でも私は死なせて。あなたの手で死なせて。」
彼女は僕の手を取って、真っ白な頬に当てた。
「私、この手が大好きなのよ。だっていつもとても暖かいでしょ?この手に触れると、まるであなたの心に触れてるみたいで」
「僕にはできないよ。わがままかもしれないけど、君にも生きてほしい。君がいるからこそ僕はもう少し生きてみようって思ったんだよ」
「ありがとう、でももう終わった話だよ。」
彼女は僕のすぐ前に近づく。
「もう無理なのよ。だってひどいじゃない。勝手に私の周りを歩き回ってとても無邪気に傷つける。致命的に痛めつける。ずっとずっとそうだった。お父さんだってお母さんだって、他の人間もみんなそう。私はこの世界であとどれだけ頑張ったらいいの?」
彼女の目は酷く赤らんでいて、唇はかすかに震えていた。
「抱きしめてもいいかな?」
「もちろん」
僕は彼女をちぎれるくらいに強く抱きしめた。そこに存在があって、触れることができる、それ以上に価値のあるものなんてこの世界にはなかった。長い間そうしていた。空が明るみ始めた頃、彼女は眠くなってきた、と言い僕を離した。
「ねえ、私の最後のお願いを聞いて。ずっとずっと人のわがままに耐えたんだから。」
彼女は僕の右手を掴み、崖の淵まで連れて行った。そして、その手のひらを彼女の胸に当てた。お願い、と彼女は弱々しい声でいった。僕は僅かな力で彼女を押した。彼女は穏やかに微笑んで僕の視界から消えていった。彼女と水の触れる音が波の音に紛れて微かに聞こえた。少し響いてすぐに消えていった。空は明け方の夕日で赤く染まり、涙で濡れた頬がやけに冷たかった。唾棄すべき世界は、今日もまた静かに始まろうとしていた。僕ではない誰かのために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
